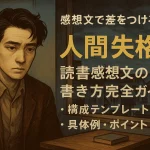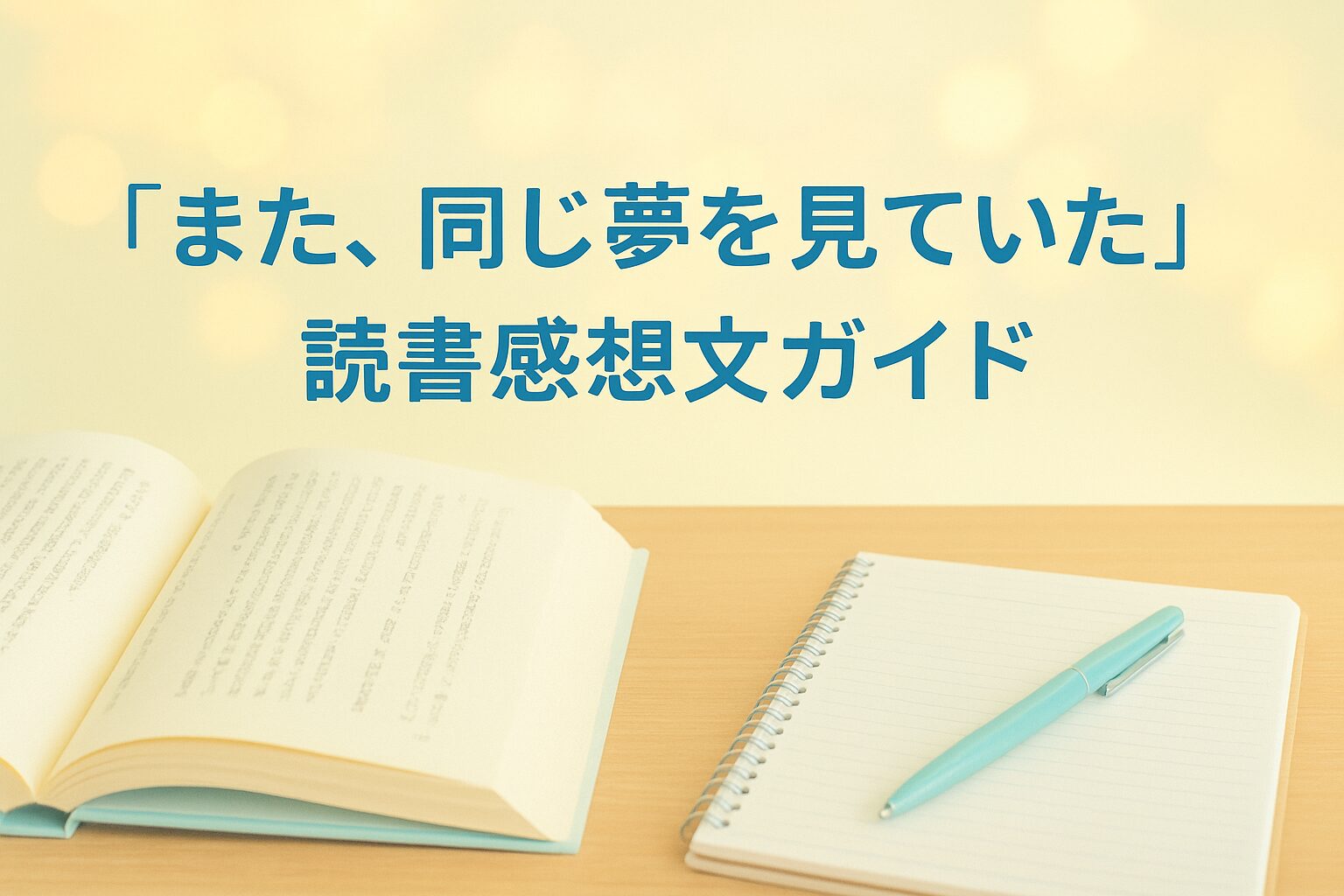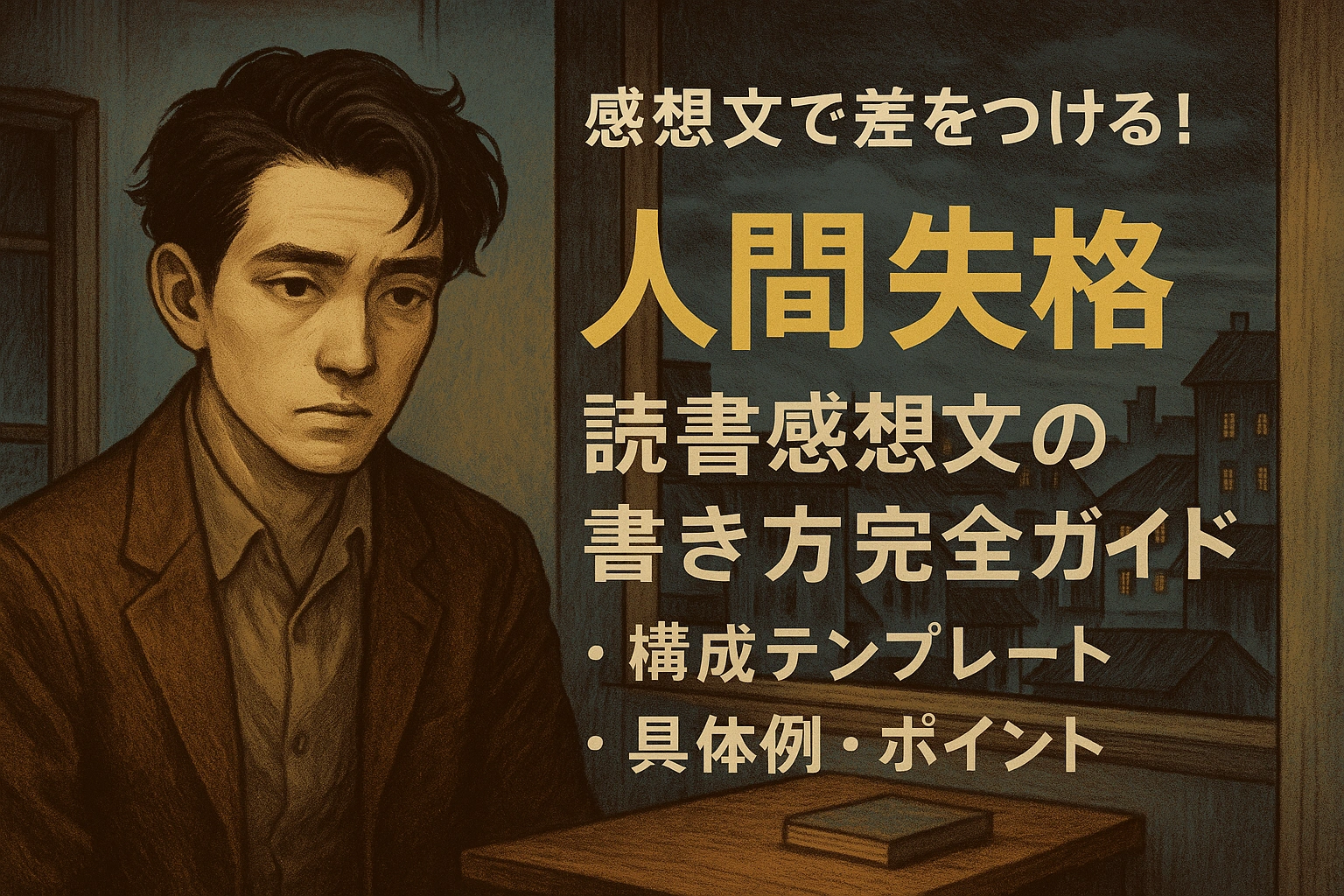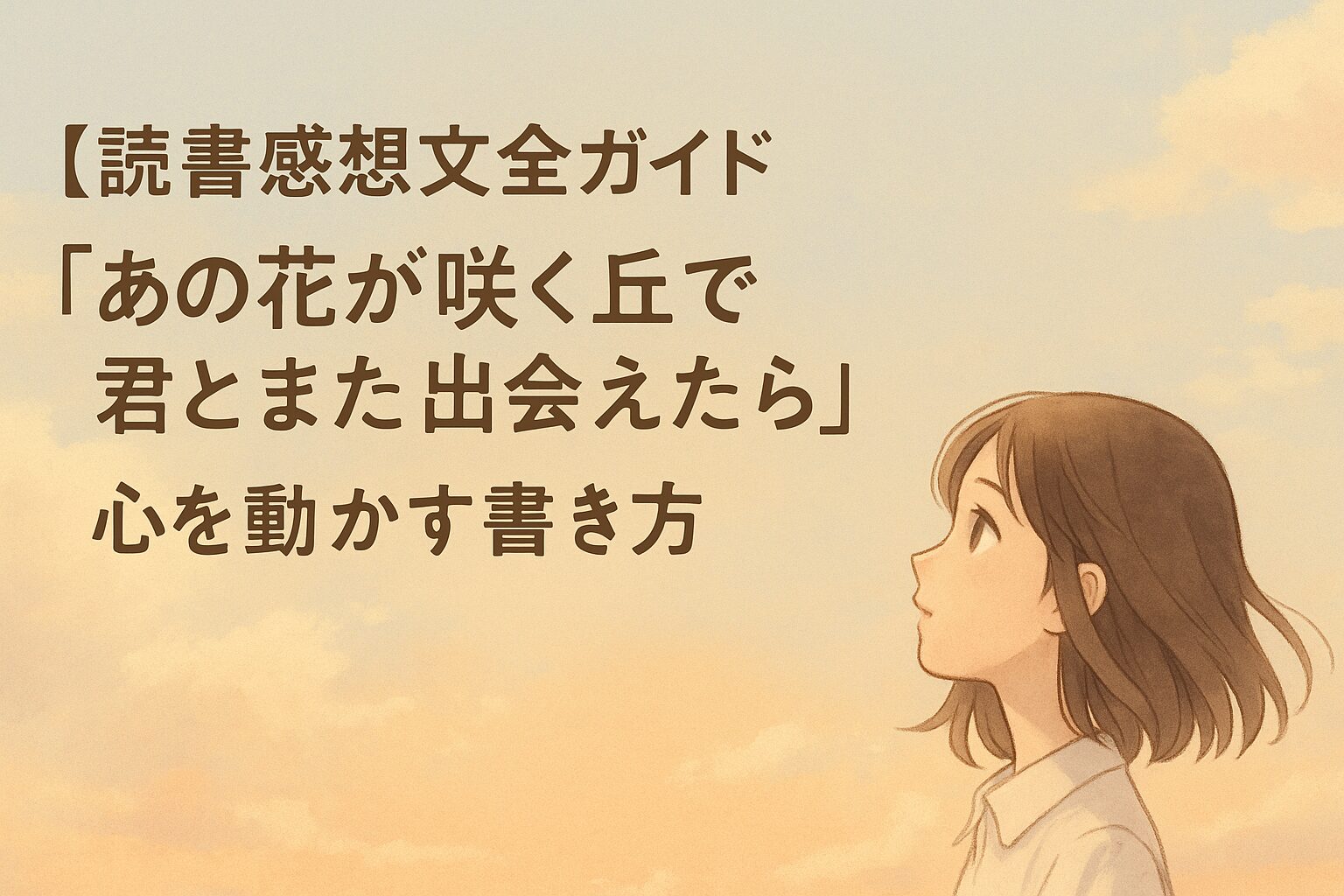高校の夏休みや冬休みの課題といえば、読書感想文。でも「どの本を選べばいいのかわからない…」「読みやすくて感想が書きやすい本ってある?」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
この記事では、そんな高校生に向けて、感想文にぴったりのおすすめ本を厳選してご紹介!さらに、本の選び方から、書き方のコツ、失敗しがちなポイントまでしっかり解説します。
読書が苦手な人でも安心して取り組めるように、ジャンル別で読みやすい作品も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
スポンサーリンク
高校生の読書感想文で本を選ぶときのポイント5つ
興味を持てるテーマがあるかどうか
読書感想文の本選びでまず大切なのは、「自分が興味を持てるかどうか」です。どれだけ名作でも、自分の関心がないテーマだと読むのが苦痛になってしまいます。
例えば恋愛に興味がある人なら青春小説を、ミステリーが好きなら推理小説を選ぶと自然に物語に入り込めます。テーマに共感できると、感想も自然にわいてくるので、書くのがぐっと楽になります。「これ、ちょっと気になるかも」と思える本に出会えると、それだけで読書が前向きなものになります。
おすすめは、書店や図書館でタイトルやあらすじをパラパラと見て、「おもしろそう」と感じたものを選ぶ方法。教師や友達に「面白かった本ある?」と聞いてみるのも、意外な出会いにつながることがありますよ。
ページ数が多すぎないか
高校生向けの読書感想文では、無理のないページ数の本を選ぶことが重要です。長編すぎると読むのに時間がかかり、内容を整理するのも一苦労。特にテスト期間や部活で忙しい時期に読むなら、200〜300ページ程度の中編小説が最適です。
これくらいの長さなら読み切りやすく、内容もしっかり頭に残ります。また、ページ数が短いからといって内容が薄いわけではありません。むしろ短編でも心を打つ作品は多く、感想文として書きやすいテーマも多いです。
はじめて読む作家の作品などは、短めのものから入って、その作家の文体や世界観に慣れるのも良い方法です。
感情移入できる登場人物がいるか
感情移入できる登場人物が出てくる本は、読書感想文に最適です。物語の中の誰かに共感できると、「この人の気持ち、わかる」「もし自分だったら…」という視点で考えることができ、感想が深まります。
たとえば、自分と同じ高校生が主人公の話なら、日常生活や人間関係に共通点が多く、感情の流れを追いやすいです。また、困難に立ち向かう人物や、成長していく姿を見ると、「自分も頑張ろう」と勇気をもらえることもあります。
感想文では、登場人物の言動に対して「自分ならどうしたか」「この人の気持ちはどうだったか」を書くことで、具体的で説得力のある文章になります。
メッセージ性が明確かどうか
読書感想文を書く上で、本のメッセージが分かりやすいかどうかは大切なポイントです。作品には「命の大切さ」「家族の絆」「友情の力」など、伝えたいテーマや教訓が込められています。
そのメッセージを自分なりにどう受け取ったかを書くことで、感想文に個性が出ます。たとえば『君の膵臓をたべたい』なら、「生きる意味とは何か」がテーマになりますし、『夜のピクニック』なら「日常の中にある青春の価値」が浮かび上がります。
どんなメッセージが自分の心に残ったかを意識すると、読み終えた後に自然と筆が進むようになります。
映画化・アニメ化されているかチェック
感想文を書くときに「本の世界観をイメージしやすい」という意味で、映画化・アニメ化されている作品を選ぶのも一つの手です。原作を読む前に映像でざっくりストーリーを知っておくと、場面のイメージがしやすく、理解もスムーズになります。
ただし、感想文はあくまで「本を読んだ上での自分の感想」が重要なので、映像だけで済ませるのはNGです。読書の補助として映画を活用するのはOKですが、最終的には「原作の言葉」から何を感じたかを書きましょう。
映像と原作で違う部分を見つけて、その違いについて自分なりに考えるのも、立派な感想になります。
感想文が書きやすい!高校生に人気の小説ベスト5
『君の膵臓をたべたい』/住野よる
『君の膵臓をたべたい』は、感動的なストーリーとわかりやすいメッセージで、高校生の読書感想文に非常に向いている小説です。物語は、重い病を抱えながら明るく生きようとする少女と、彼女と心を通わせるクラスメイトの少年の交流を描いています。タイトルのインパクトとは裏腹に、中身は非常に繊細で深い人間ドラマです。読み進めるうちに「生きるって何だろう」と自然と考えさせられます。
また、主人公たちが高校生という点でも共感しやすく、自分自身と重ねながら読めるのも魅力です。読後に心がじんわり温かくなり、感想も書きやすくなります。短すぎず長すぎないページ数も、読書が苦手な人にとってちょうど良いバランスです。
スポンサーリンク
『ビブリア古書堂の事件手帖』/三上延
『ビブリア古書堂の事件手帖』は、本好きにはたまらないミステリー小説で、読書感想文にも非常に適しています。物語の舞台は鎌倉にある古書店「ビブリア古書堂」。一見おとなしい女性店主・栞子が、本にまつわるさまざまな謎を解き明かしていくという構成です。
この本の面白いところは、「本が鍵になる謎解き」がテーマになっている点です。ただのミステリーではなく、登場する古書の内容や背景がストーリーに深く関わってきます。読むうちに「本ってこんなにもドラマがあるんだ」と驚かされるでしょう。
読書感想文では、「なぜ人は本に惹かれるのか」や、「物語の中で描かれる人間関係や秘密」について、自分の感じたことを掘り下げやすいです。登場人物それぞれに過去があり、それが本を通して明かされていく展開には、どこか切なさや懐かしさもあります。
また、文章が読みやすく、情景描写も豊かなので、読書が苦手な人にも入りやすい構成です。シリーズ化されているため、「1冊目が面白かったら続きを読む楽しみがある」のもポイント。感想文としては「この作品を読んで本に対する見方が変わった」といった気づきを書きやすい1冊です。
『夜のピクニック』/恩田陸
『夜のピクニック』は、高校生活の一大イベント「24時間歩行祭」をテーマにした青春小説です。クラスメイトたちが夜通し歩く中で、それぞれの思いや秘密が少しずつ明かされ、物語が進んでいきます。
特に注目すべきは、「ごく普通の高校生活の中にある、かけがえのない瞬間」を切り取っている点です。大きな事件が起きるわけではないのに、読む者の心を動かす力があります。
この作品は「特別な日常」が描かれているため、自分の学校生活と重ねて考えることができ、読書感想文にも向いています。登場人物たちの悩みや葛藤もリアルで、「もし自分だったらどうするか」と考えながら読み進められるのが魅力。文章もすっきりしていて読みやすく、舞台となるイベントの描写も丁寧なので、情景が頭に浮かびやすいです。
感想文では、「仲間との関係」や「青春の意味」「変わりゆく自分」をテーマに書くと、自分なりの考察を展開しやすくなります。自分の経験とつなげて「自分も文化祭でこんな気持ちになった」と書くと、説得力のある文章になります。青春の一瞬を描いたこの作品は、多くの高校生の心に響く一冊です。
『そして、バトンは渡された』/瀬尾まいこ
『そして、バトンは渡された』は、家族の形や人とのつながりをテーマにした、優しく温かい物語です。血のつながらない親たちに育てられながら成長していく主人公・森宮優子の人生が、穏やかで丁寧な筆致で描かれています。家族の形が複雑であるにもかかわらず、そこにあるのは「愛情」や「信頼」であり、読み終えたときに「家族とは何か」という問いが胸に残ります。
この本の魅力は、登場人物がどれも個性的でありながら、自然と読者の心に入ってくること。どんな境遇でも人との絆があれば前に進めるというメッセージが、多くの人の共感を呼びます。読書感想文では、「自分にとっての家族」「人との関わりで変わった経験」などをもとに、自分の人生と照らし合わせた内容を書くのに向いています。
文章は非常に読みやすく、優しい語り口で描かれているため、読書が苦手な人にもおすすめです。2020年には本屋大賞も受賞しており、評価も高く、先生や親からのウケも良い本といえます。感想文を書くうえで、考えやすいテーマがたくさん詰まった、安心して選べる1冊です。
『塩の街』/有川浩
『塩の街』は、有川浩のデビュー作であり、SF的な要素とヒューマンドラマが融合した作品です。ある日突然「人が塩になってしまう奇病」が世界中に広がるという異常事態の中で、人々がどう生きるかを描いています。設定は非日常的ですが、登場人物の感情や行動はとてもリアルで、「極限状態で人は何を守るのか」という問いが胸に迫ります。
感想文では、「もし自分が同じ状況に置かれたらどうするか」「大切な人を守るとはどういうことか」などをテーマに深く掘り下げることができます。登場人物の選択に対して、自分の考えを重ねながら書くと説得力のある文章になります。また、短編集のように複数の視点で物語が描かれているため、特に印象に残ったエピソードを中心に感想を書くのも効果的です。
文章のテンポがよく、一気に読める構成なので、読書が得意でない高校生でも最後まで楽しめます。有川浩作品に共通する「やさしさ」と「強さ」がバランスよく描かれており、読後に考えさせられる余韻が残る1冊です。
スポンサーリンク
感想文で差がつく!考えさせられる名作文学5選
『こころ』/夏目漱石
『こころ』は、日本近代文学の代表作として知られ、多くの高校の教科書にも掲載される名作です。物語は「先生」と「私」という二人の人物の関係を通じて、「孤独」や「罪悪感」、「人間関係の複雑さ」といったテーマが描かれています。
この作品が優れているのは、時代を超えても人の心の深層に迫ってくる普遍的な問いが込められている点です。登場人物の行動や心理を追っていくうちに、「人を信じるとはどういうことか」「本当の友情とは何か」など、自分の考えを深く掘り下げたくなります。
読書感想文では、「なぜ先生はあのような選択をしたのか」という視点から考察するのが一つの方法です。あるいは、「もし自分が『私』の立場だったらどう接したか」と自分の価値観と重ねて考えることで、内容の濃い感想文に仕上がります。
文章はやや古めかしい表現もありますが、現代語訳付きの文庫本や、注釈がある版を選べば理解しやすくなります。深く考えることが求められる内容のため、感想文の評価も上がりやすく、他の生徒と差をつけたいときにぴったりの1冊です。
『人間失格』/太宰治
『人間失格』は、太宰治の代表作であり、戦後文学の金字塔とも言える作品です。自己否定と苦悩に満ちた主人公・葉蔵の語りは、読む人の心を激しく揺さぶります。全体的に暗い雰囲気の物語ですが、「自分は社会にうまくなじめない」「他人の目が気になる」といった悩みを抱える高校生にとっては、意外と共感できる部分が多い作品でもあります。
感想文では、「なぜ葉蔵は生きづらさを感じ続けたのか」や、「現代社会にも通じる孤独や不安」について考察を深めることができます。太宰の独特の文体に最初は戸惑うかもしれませんが、その一文一文には鋭い感情や哲学が込められており、読み進めるうちにその魅力に気づくでしょう。特に「自分が悩んでいたことと重なる」と感じた人は、それを素直に書くことで、感情のこもった感想文になります。
文学作品としての評価も高く、先生からの印象も良いため、「文学作品にしっかり向き合って書いた」という姿勢が伝わりやすいのもポイントです。重いテーマではありますが、だからこそ読後に心に残るものがあり、「自分がどう生きるか」を考えるきっかけになります。
『注文の多い料理店』/宮沢賢治
『注文の多い料理店』は、宮沢賢治が書いた短編集の一編であり、幻想的な世界観と風刺の効いたストーリーで多くの読者を魅了してきました。物語は、山奥の不思議なレストランに迷い込んだ二人の紳士が、次第に恐ろしい目に遭うというシンプルながら強烈な展開です。一見子ども向けの童話のようですが、実は人間の欲望や傲慢さを鋭く批判した、深いメッセージを持った作品です。
読書感想文では、「自分の中にもこうした傲慢さがあるかもしれない」と内省したり、「自然や他者に対する敬意」について考えるきっかけとして書くことができます。短編のため読みやすく、文章もリズム感があり親しみやすいですが、その奥にあるテーマは非常に深く、大人でも考えさせられる内容です。作品の背景にある時代の価値観や、宮沢賢治の生き方についても少し触れると、より内容に厚みが出ます。
短くてもインパクトのある物語は、読後の印象が強く残るため、印象的な読書感想文が書きやすいです。また、何度読んでも新たな発見があるのもこの作品の魅力。時間が限られている中でも、質の高い感想文が書ける1冊としておすすめです。
『羅生門』/芥川龍之介
『羅生門』は、芥川龍之介の代表作であり、日本文学を語る上で欠かせない短編小説のひとつです。荒れ果てた羅生門を舞台に、職を失った下人が、生きるためにある決断を下すという非常にシンプルな構成ながら、「善と悪」「人間の本質とは何か」という深いテーマが込められています。この作品の面白さは、たった十数ページの短編でありながら、読む人の心をざわつかせる力を持っているところにあります。
読書感想文では、「人は追い詰められたときに何を選ぶか」という普遍的な問いに対して、自分なりの意見を述べることができます。「正しい行いとは何か?」「状況が違えば自分も同じことをするのか?」というように、自分の価値観を深掘りするきっかけになるのです。また、芥川の文章は古風ながら美しく、漢字や語彙が豊富なので、文学的な表現に触れる良い機会でもあります。
文章量が少ないため短時間で読み終えられますが、感想文を書くときには、一度読んだだけではなく、何度か読み返して「なぜこのラストなのか」「作者は何を伝えたかったのか」と考えることで、より深い感想を書くことができます。自分の中の「モラル」と向き合うことになる作品です。
『檸檬』/梶井基次郎
『檸檬』は、たった10ページほどの短編ながら、日本の近代文学の中でも非常に人気のある作品です。語り手の青年が、日々の倦怠感や不安を抱えながら街をさまよい、最終的に丸善(本屋)で見つけた一個のレモンを爆弾に見立てて置いて去るという不思議なストーリーです。現実離れした展開でありながら、どこか共感してしまう空気感が魅力です。
読書感想文では、「なぜ青年はレモンを置いたのか」「檸檬が象徴しているものは何か」という問いを軸に考察することで、独自の視点を展開できます。たとえば、現代の若者が感じる「生きづらさ」や「現実からの逃避」といったテーマと絡めて、自分の気持ちや体験を交えて書くと、深みのある文章になります。
文章は詩的で、非常に美しい表現が多く、読んでいて印象に残る言葉がたくさんあります。感情や景色を「色」や「匂い」で描写する力が秀逸で、感性が豊かな高校生には特におすすめです。
レモンという一つのモチーフを通して、人生や感情の機微を表現しているこの作品は、読むたびに新しい発見がある奥深い文学です。短編なので時間がない時期でも取り組みやすく、密度の高い感想文が書ける優良作品です。
スポンサーリンク
読書が苦手でも安心!読みやすくて面白い短編・エッセイ
『ツナグ』/辻村深月
『ツナグ』は、「死者と一度だけ会える使者」という設定で描かれた感動の連作短編集です。物語は1話ごとに登場人物が変わり、亡くなった大切な人と再会する依頼人たちの思いや後悔、希望が描かれます。それぞれの話は独立していますが、「ツナグ」という使者と、死者との再会という共通テーマによって、深い感動が読者に届けられます。
この本の魅力は、登場人物の気持ちがとても丁寧に描かれているところです。「もし自分が死んだ家族に一度だけ会えるなら、何を話すだろう?」と、読みながら自然と自分に重ねてしまうほど。感想文では、「命の大切さ」「後悔しない生き方」「誰かと向き合うことの意味」といったテーマに触れることができ、自分の体験や気持ちと結びつけやすいです。
文章は平易で読みやすく、1話ごとに完結しているため、途中で読むのをやめても再開しやすいのも嬉しいポイント。感動的な話が多いので、心が温かくなる読書体験ができ、読書感想文としても非常に書きやすい構成になっています。人とのつながりに価値を感じる高校生に、ぜひ読んでほしい一冊です。
『さよならを待つふたりのために』/ジョン・グリーン
原題『The Fault in Our Stars』としても知られるこの作品は、がんを患う少女と少年の恋を描いたアメリカ発のベストセラー小説です。内容は重く感じるかもしれませんが、登場人物たちはとてもユーモラスで、ユニークなやり取りがテンポよく進むため、読んでいて暗くならないのが特徴です。
主人公のヘイゼルとガスは、死を目前にしながらも、互いに愛し、支え合い、人生を前向きに生きていこうとする姿を見せてくれます。感想文では、「限られた時間をどう生きるか」「本当の幸せとは何か」について考察することができます。また、若者らしい鋭い言葉や気持ちの動きもリアルに描かれており、高校生の心にも自然に響く内容です。
洋書が原作ですが、日本語訳はとても自然で読みやすく、感情移入しやすい表現になっています。物語のクライマックスでは涙なしには読めない展開もあり、感動をそのまま言葉にして感想文に落とし込むのにぴったりです。シリアスなテーマでも、登場人物たちの明るさと前向きな姿勢が、読者に「自分も頑張ろう」と思わせてくれる素晴らしい一冊です。
『女子高生サヤカが学んだ「1万人に1人の勉強法」』/碓井孝介
この本は、勉強が苦手だった女子高生・サヤカが、ある一人の塾講師に出会い、「勉強法の本質」を学ぶことで劇的に成績を上げていくという、ノンフィクション風のストーリーです。勉強法のハウツー本でありながら、読み物としても面白く、高校生にとってはまさに「実用的かつ読みやすい」一冊となっています。
読書感想文では、「自分の勉強への向き合い方が変わった」「やってみたい学習法が見つかった」といった、自分の成長や気づきを中心にまとめると書きやすいです。特に、サヤカが成績アップを通じて自己肯定感を取り戻していく様子は、多くの高校生に共感を与えるでしょう。実話に基づいたリアルな内容なので、嘘っぽさがなく、読み手の気持ちにストレートに届きます。
また、文章が平易でテンポよく進むため、「本が苦手」「読書感想文で困っている」という人でも無理なく読み切れます。読書と勉強、両方のモチベーションを上げてくれるこの作品は、「読んで得をした」と感じられるタイプの一冊です。自分の実生活に役立てられる本として、強くおすすめできます。
『天才のノート術』/美崎栄一郎
『天才のノート術』は、誰もが知っている偉人や有名人が、どのようにノートを使ってアイデアを生み出したのかを紹介する一冊です。アップルの創業者・スティーブ・ジョブズや、エジソン、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、時代も分野も異なる「天才たち」が、自分なりの方法でノートを活用し、思考を深めていたことがわかります。内容は堅苦しくなく、図解や写真も多く、読みやすさは抜群です。
この本の面白いところは、単に知識を得るだけでなく、「自分もこんなふうにノートを使ってみたい」と感じさせてくれる実用性にあります。感想文では、「自分が普段どのようにメモを取っているか」「この本を読んで試したいと思ったノートの取り方」などを軸に、自分の学びのスタイルを振り返る内容が書きやすいでしょう。読書感想文というより「実用書の体験記」に近い形でも説得力があり、ユニークな内容に仕上がります。
また、ノート術という身近なテーマを扱っているため、日々の生活や学習と結びつけやすく、読書が苦手な人でも「読んでよかった!」と思えるはず。難しい言葉も使われていないので、ストレスなく読み進められます。知的好奇心をくすぐりながら、感想文に個性を出したい人にぴったりの一冊です。
『置かれた場所で咲きなさい』/渡辺和子
『置かれた場所で咲きなさい』は、カトリック修道女であり教育者でもあった渡辺和子さんによるエッセイ集です。「どんな場所でも、自分の役割を見つけて前向きに生きていこう」というメッセージが込められており、多くの人に勇気を与えてきました。シンプルな言葉で綴られているため、中学生や高校生でもすっと心に入ってくる内容です。
この本の良いところは、一つひとつの話が短くまとまっていること。忙しい時でも数ページ読むだけで心に残る言葉や考え方に出会えます。感想文では、自分が過去に悩んだことや、思うようにいかなかった時の経験と結びつけて、「あのときこの本を読んでいたら、どう感じただろう」と書くと、共感を呼ぶ内容に仕上がります。
「人と比べないこと」「結果より過程を大切にすること」「感謝の心を忘れないこと」など、人生に役立つヒントが詰まっていて、読むだけで心が整います。感想文としては、「自分の考え方がどう変わったか」「これからどんな行動をしていきたいか」を具体的に書くと良いでしょう。
読書が苦手な人でも読みやすく、内容がしっかりしているため、安心して選べる感動の一冊です。
スポンサーリンク
読書感想文の書き方完全ガイド|構成・コツ・NG例も紹介
読書感想文の基本構成とは?
読書感想文には、わかりやすく伝えるための基本的な構成があります。いきなり思いつくまま書くと、内容がバラバラになったり、読み手に伝わりにくくなってしまいます。そこでおすすめなのが「起承転結」に近い、以下の4段階構成です。
- その本を選んだ理由やきっかけ(導入)
- 印象に残った場面やセリフの紹介(内容)
- その部分から考えたことや感じたこと(感想)
- 読後に変わった自分の考え・これからどうしたいか(まとめ)
例えば、「病気の主人公の本を読んで命の大切さを考えた」という感想文なら、「自分が病気になったときどう考えるか」「周囲の人とどう接するか」など、個人の経験や思いを加えることで、内容に深みが出ます。また、最初と最後に自分の変化を書くと、文章に一貫性が出て、読み手にもしっかり伝わる感想文になります。
感想文に決まりきった正解はありませんが、こうした流れを意識することで、自然にスムーズな文章が書けるようになります。読み手に「その本を読んでみたい」と思ってもらえるような構成を目指しましょう。
まずは「印象に残った場面」から書こう
読書感想文が書きにくいと感じる人の多くは、「何から書けばいいかわからない」と悩んでいます。そんなときにおすすめなのが、「一番印象に残った場面」から書き始めることです。心が動いたシーンを思い出し、なぜその場面が印象的だったのかを言葉にしていくと、不思議と自然に文章がつながっていきます。
たとえば、登場人物が思い切った決断をしたシーン、誰かのセリフに救われた瞬間、景色や描写が美しかった場面など、「なぜ心に残ったのか」を考えることで、自分の感情や価値観が見えてきます。そして、それを軸にして他の考察を広げていけば、感想文がより深みのある内容になります。
「なぜそのシーンが印象に残ったのか?」
「自分だったらどう感じただろうか?」
「それは今の自分の生活にどう関係するのか?」
こうした問いを自分に投げかけながら書いていくと、オリジナリティのある感想文が完成します。本を読んだ直後の感情を大切にしながら書くことが、一番のコツです。
「あらすじだけ」にならないためのコツ
読書感想文でよくある失敗のひとつが、「あらすじ紹介だけで終わってしまう」ことです。物語の流れを詳しく説明しすぎると、それだけで原稿用紙が埋まってしまい、「感想はどこ?」と疑問に思われてしまいます。読書感想文は、あくまで「あなたの考え」が主役です。
あらすじは、読者に内容を伝えるために必要最低限にとどめましょう。できれば2~3行で簡単にまとめ、そこから「自分はどこで心を動かされたか」「何を感じたか」にフォーカスしてください。たとえば、「主人公が勇気を出して告白するシーンが心に残った」と書いたあとに、「自分も悩んでいたけど、この本を読んで一歩踏み出してみようと思えた」と続けると、内容にオリジナリティが生まれます。
物語全体を説明するよりも、「印象的な1場面に絞る」ことがポイントです。その場面に対する自分の感情や意見を具体的に書けば、読み手にも伝わりやすく、共感を得やすくなります。
自分の体験と本の内容をつなげるテクニック
読書感想文をぐっと魅力的にするためのテクニックが、「自分の体験と作品の内容を結びつけること」です。たとえば、登場人物が失敗から学ぶシーンを読んだとき、自分が過去に似たような経験をしたことを思い出す…そんな瞬間を文章にすることで、作品への理解がより深くなり、感想文にも説得力が生まれます。
体験と結びつけるときは、無理に感動的な話にする必要はありません。たとえば、「登場人物が友達とすれ違って悩む姿に、自分の友達関係を重ねた」など、日常の中で感じたこととリンクさせるだけで十分です。実際の出来事と登場人物の感情が重なったとき、自分だけの感想が生まれます。
この書き方のメリットは、「あなただけの物語」が感想文に生まれること。他の人とかぶることが少なく、読み手にも強い印象を与えられます。「作品がくれた気づき」と「自分の人生」が交差する場所を見つけましょう。
やりがちなNG例とその改善方法
読書感想文でありがちな失敗には、いくつかのパターンがあります。まず一つ目は、「ただのあらすじ紹介」で終わってしまうこと。これは前述の通り、感想文ではなく説明文になってしまいます。二つ目は、「感動した」「面白かった」だけで終わってしまうこと。感情の説明がないため、なぜそう思ったのかが読み手に伝わりません。
また、「話が飛びすぎて論理的でない」というのもよくあるミスです。話の流れがつながっていないと、読みにくくなってしまいます。これを防ぐには、「一文一文に意味を持たせて、前の文とつなげる意識」を持つことが大切です。
改善方法としては、「印象に残った場面→その理由→自分の考え→今後どうしたいか」という順番を意識すること。これだけでグッと説得力のある感想文になります。完成後は、必ず一度声に出して読んでみましょう。読みやすいか、意味が伝わるかを確認するだけでも、大きな改善になります。
スポンサーリンク
よくある質問(FAQ)
Q1. 読書感想文におすすめの本ってどう選べばいいの?
A. 自分が「ちょっと面白そう」と思えるかどうかが一番大切です。ページ数が多すぎない、登場人物に共感できる、感情が動くシーンがあるなど、書きやすい本を選びましょう。学校の推薦図書リストや、話題になった本も参考になります。
Q2. すでに映画やアニメで見たことのある作品でもいいの?
A. 映像作品で内容を知っている本でもOKですが、必ず実際に原作を読みましょう。映画と本では描写が異なることも多いので、原作にしかない気づきや感想を大切にしてください。
Q3. 感想文の長さってどのくらいが理想?
A. 多くの学校では原稿用紙3〜5枚(1200〜2000字程度)が一般的です。課題に応じて確認しましょう。短くまとめすぎず、自分の考えをしっかり書くことが大事です。
Q4. あらすじだけになってしまいます。どうすればいい?
A. あらすじではなく、自分がどこに感動したのか、どんなことを考えたかに焦点を当てましょう。印象に残った場面を取り上げて、自分の経験や感情とリンクさせると自然な感想になります。
Q5. 本を全部読まずに感想文を書いてもバレない?
A. バレる可能性は高いです。特に感想に深みが出ず、薄っぺらい内容になることが多いので、できるだけ最初から最後まで読みましょう。短編や読みやすい作品を選べば、負担も少なくすみます。
まとめ
読書感想文は「本を読んでどう感じたか」「何を考えたか」を自分の言葉で表現する、自由度の高い作文です。今回ご紹介したように、本の選び方ひとつで、感想文の書きやすさは大きく変わります。小説、名作文学、エッセイ、実用書など、ジャンルにこだわらず、「自分が興味を持てる本」を見つけることが第一歩です。
また、感想文を書くときは、印象に残った場面からスタートし、自分の体験や価値観と重ねてみることがポイントです。あらすじだけに終始せず、自分の感情や気づきをしっかり書くことで、読み手の心に残る文章になります。文章に自信がない人も、構成や書き方のコツをつかめば、しっかりとした感想文が書けます。
今回の記事が、「何を読もうか迷っている」「読書感想文が苦手」という高校生の参考になれば嬉しいです。読書はあなたの人生を豊かにするツール。感想文を書くことは、その読書をもっと深めるチャンスでもあります。ぜひ、自分にぴったりの一冊を見つけてくださいね。