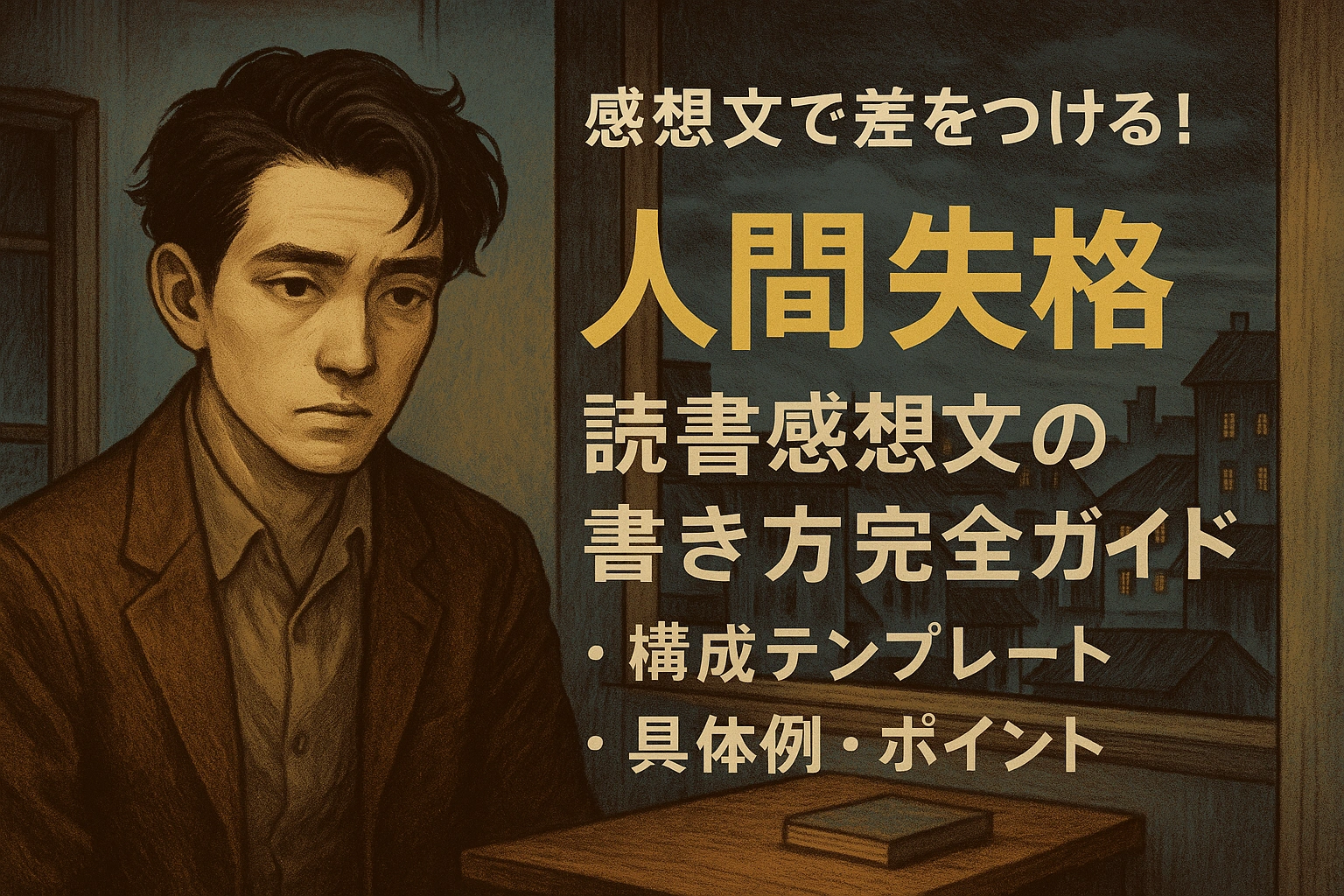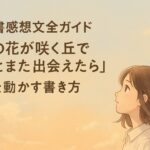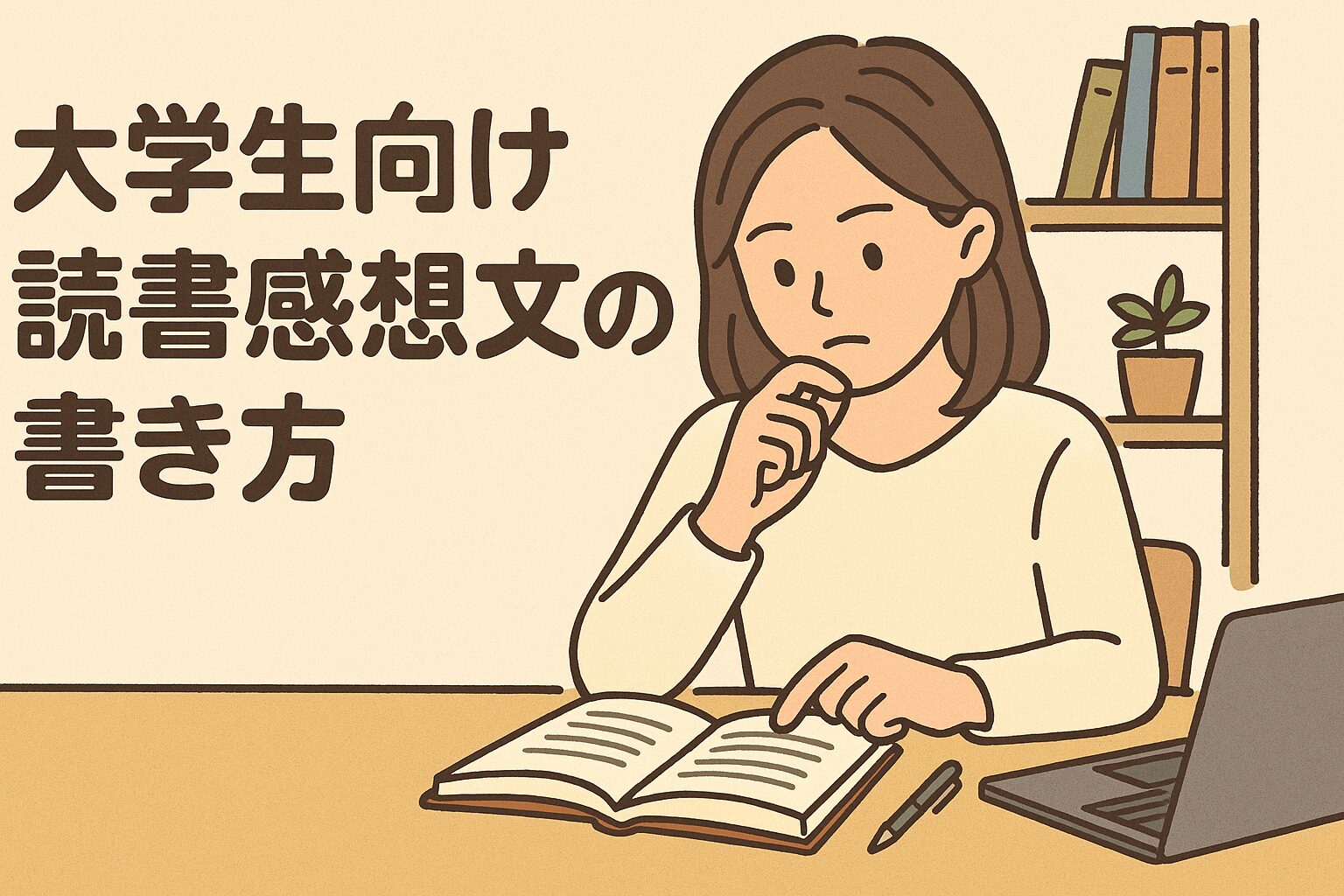学校の読書感想文の課題で『人間失格』を選んだけれど、「難しそう」「何を書けばいいかわからない」と悩んでいませんか?
この記事では、太宰治の名作『人間失格』を中学生でもわかりやすく解説しながら、感想文を書くためのポイントや構成、さらには例文までを徹底紹介します。
初めて読む人にも安心な内容になっているので、「感想文がうまく書けない…」という人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
小説版『人間失格』はこちらから購入できます。
スポンサーリンク
『人間失格』ってどんな小説?背景とあらすじをやさしく解説
太宰治のプロフィールと時代背景
太宰治(だざい おさむ)は、1909年(明治42年)に青森県で生まれました。彼は裕福な家庭に育ちましたが、幼い頃から心の中に深い孤独感や不安を抱えていたと言われています。
彼は東京大学に進学するも中退し、その後は作家として活躍しました。代表作には『走れメロス』『斜陽』などがありますが、『人間失格』は彼の晩年の作品であり、最も暗く、最も深い内面が描かれた小説です。
昭和の戦後という時代背景も重要です。日本が戦争に負け、多くの人が生きる意味を見失っていた時代でした。そんな混乱の中で、「生きづらさ」や「人との関わりの難しさ」を感じていた人たちの心に響いたのがこの作品です。この小説を通じて、太宰は自分の弱さと向き合い、それを言葉にして伝えようとしました。
つまり、『人間失格』はただの悲しい話ではなく、「人間って何だろう?」と私たちに問いかけてくる深い作品なのです。
主人公・葉蔵の生い立ちと苦悩
物語の主人公・葉蔵(ようぞう)は、子どもの頃から人との関係が苦手でした。家では「いい子」を演じ、学校では道化のようにふるまって周りの人に合わせていました。本当の自分を誰にも見せられず、常に仮面をかぶっているような生活を続けていたのです。
大人になってからもその苦しみは消えませんでした。人間関係がうまくいかず、アルコールや薬に頼るようになり、自分が「人間として失格だ」と感じてしまいます。葉蔵の苦悩は、現代の私たちにも通じる「本当の自分を出せないつらさ」や「孤独」のような気持ちを描いています。
葉蔵のように苦しんでいる人は、きっと今の時代にもたくさんいるはずです。だからこそ、この小説は時代を超えて多くの人に読まれているのです。自分を理解してもらえないという苦しさは、誰にとっても身近なテーマですよね。
小説の3つの「手記」と構成の特徴
『人間失格』は、冒頭の「まえがき」、主人公・葉蔵が書いたとされる3つの「手記」、そして最後の「あとがき」という構成で成り立っています。この形式は少し特殊で、まるでドキュメンタリーや実話のように感じさせる効果があります。
まえがきでは「私」が古本屋で葉蔵の手記を見つけたという設定で始まります。その後、葉蔵の一人称で書かれた3つの手記が続きます。手記では彼の子ども時代から大人になるまでの出来事、心の中の苦しみが赤裸々に語られます。そして、最後のあとがきで、葉蔵の手記を読んだ「知人」がその後の彼について語ることで物語は終わります。
この構成により、読者は葉蔵の人生をまるで自分がその場にいたかのように追体験できます。特に手記部分では、葉蔵の内面がリアルに描かれていて、感情移入しやすくなっています。小説全体が一人の人間の告白のようになっていて、その分だけ心に強く響くのです。
社会とのズレと「人間失格」という言葉の意味
「人間失格」という言葉はとても強烈です。まるで、「自分はもう人間として価値がない」と断言してしまうような印象がありますよね。葉蔵はなぜ、こんな言葉を自分に向けたのでしょうか?
彼はずっと、人と本当の気持ちでつながれずに苦しんでいました。誰にも自分を理解してもらえないと感じ、自分で自分を責めてしまいます。そしてついには、「自分は人間として失格なんだ」と思い込んでしまうのです。
でも、この言葉の本当の意味は、「本当は人とつながりたかったのに、それができなかった」という悲しみが込められているのだと思います。だからこそ、読む人によっては「自分も同じ気持ちになったことがある」と共感できるのです。
この言葉に触れたとき、「自分はどうだろう?」と考えるきっかけになるのも、この小説の大きな魅力です。
読者に訴えかけるメッセージとは?
『人間失格』は、ただの悲しい人生を描いた話ではありません。そこには、「本音で生きることの難しさ」や「自分自身との向き合い方」というテーマがあります。太宰治は、心の奥底にある苦しみを隠さずに文章にしました。だからこそ、読んでいて胸が痛くなるのです。
しかし、それは同時に「自分も苦しんでいいんだ」「完璧じゃなくていいんだ」と教えてくれる作品でもあります。誰もが心に不安や寂しさを抱えて生きている。それを言葉にしてもいいんだという勇気をくれるのです。
この小説を読み終わったあと、自分の中にある小さな声に耳を傾けてみたくなる。そんな気持ちにさせてくれるのが『人間失格』なのです。
スポンサーリンク
読書感想文を書く前に考えたい5つのポイント
読みながら気になった場面をメモしよう
読書感想文を書くとき、いちばん大切なのは「自分の感じたこと」をしっかり思い出すことです。そのためにおすすめしたいのが、読んでいる最中に「気になった場面」や「心に残った言葉」にメモを取っておくことです。メモは小さな紙やスマホのメモアプリ、付箋など何でもOKです。
たとえば、『人間失格』で葉蔵が「笑ってごまかすことしかできなかった」と語る場面。この言葉に「自分もそんなふうに感じたことがある」と思ったら、それをメモしておくと、あとで感想文を書くときにすぐ使えます。どんな場面で何を感じたのか、できれば「なぜそう思ったのか」も書いておくと、より深い感想文になります。
また、「この表現がきれいだった」「このときの主人公の気持ちが切ない」といった直感的な感情も大切です。読書感想文は、正しい答えを書くものではなく、自分の心の動きを素直に書くものなので、どんな感情も価値があります。
読んでいる間はストーリーを追うことに集中しがちですが、ちょっと手を止めて「これは大事」と思ったらメモするだけで、後の作業がグッと楽になります。これは、プロの書評家やブックレビュアーもやっている基本テクニックです。読書を深める意味でも、ぜひ取り入れてみてください。
自分が共感した部分を深掘りする方法
感想文の中でいちばん印象に残るのは、「自分の体験や考え」と物語の内容を結びつけた部分です。特に、登場人物に共感したポイントがあるなら、それをしっかり深掘りして書くと説得力が出ます。
たとえば、葉蔵が「他人に本音を言えない」と感じていた場面に共感したとします。ただ「共感しました」と書くだけでなく、「なぜ共感したのか」「どんな体験と重なったのか」を掘り下げてみましょう。たとえば、「私も学校で本当の気持ちを言えずに、無理して笑ってしまうことがある」といった具体的なエピソードを加えると、読む人にしっかり伝わります。
深掘りするときのコツは、「自分に置き換えて考える」ことと、「そのときの気持ち」を細かく思い出すことです。また、できるだけ五感(見た・聞いた・感じた)を使って書くと、感情がよりリアルになります。
感想文は、自分の考えを伝える場なので、正解や正しさを気にする必要はありません。「自分はどう思ったか」に自信を持って、自分だけの視点で書くことが一番大切です。
どんな気持ちになったかを素直に書くコツ
「感想文って何を書けばいいかわからない」という人に多いのが、「うまくまとめよう」としすぎてしまうことです。でも、本当に大事なのは、自分が読んで感じたことを素直に書くことです。
たとえば、『人間失格』を読んで「怖かった」「悲しかった」「よくわからなかった」など、どんな感情でも構いません。その気持ちを正直に書くことで、読む人にあなたのリアルな心の動きが伝わります。逆に、難しい言葉を使って無理にカッコよく書こうとすると、気持ちが伝わりにくくなってしまいます。
コツは、「最初に出てきた気持ちを信じる」ことです。読みながら「なんでこんなこと言うんだろう」「かわいそう」と思ったら、それがあなたの感じた本音です。そこから広げて、「どうしてそう思ったのか」「自分ならどう感じるか」と自問自答していけば、自然と文章も深くなっていきます。
感想文は、うまくまとめる必要はありません。むしろ、少し言葉が乱れていても、その分だけ本気の気持ちが伝わるものです。「感じたことをそのまま書いていいんだ」と思って、気楽に書いてみてくださいね。
登場人物の心情を想像してみよう
感想文でおすすめなのが、「登場人物の気持ちになって考えてみる」ことです。特に『人間失格』のような作品では、主人公・葉蔵の行動や発言の裏にある気持ちを想像すると、感想に深みが出ます。
たとえば、葉蔵が「何をしても人に嫌われる気がする」と書いている場面。これを読んで、「そんなことないよ」と思うだけでなく、「どうして彼はそんなふうに思ったのか」「もし自分が同じ立場だったらどう感じるか」と考えてみましょう。
葉蔵はいつも人の顔色をうかがって生きていて、本当の自分を見せるのが怖かったのかもしれません。そんな彼の気持ちに寄り添って、「彼が安心して本音を言える人がいたら、人生は変わったのかもしれない」と書けば、読み手にも強く響く文章になります。
登場人物を「他人」として見るのではなく、「もし自分だったら」と置き換えることで、より具体的でリアルな感想になります。これは文章力よりも、想像力が大切な部分。自分の心を少しだけ開いて、葉蔵と対話する気持ちで読んでみてください。
「なぜこの作品が今も読まれているのか」を考える
最後に、感想文の締めくくりとしておすすめなのが、「なぜ『人間失格』は今でも読まれ続けているのか?」という視点を持つことです。1948年に発表された小説が、今の時代でも多くの人に読まれているのはなぜでしょう?
その答えの一つは、「心の孤独」や「生きづらさ」というテーマが、今の私たちにも当てはまるからです。SNSでつながっていても本音が言えない、周りに合わせて自分を押し殺してしまう…そんな現代の悩みと、葉蔵の苦しみは重なる部分があります。
また、「完璧でなければいけない」というプレッシャーが強い現代において、「弱さをさらけ出してもいいんだ」と教えてくれるこの作品は、読む人に安心感を与えてくれるのです。読書感想文では、このように自分なりの「時代とのつながり」や「現代へのメッセージ」を見つけて書くと、説得力と深さが出ます。
つまり、今も読み継がれているのは、「この小説が必要とされているから」なのです。
スポンサーリンク
実際に使える読書感想文の構成テンプレート
①はじめに:読む前の印象や選んだ理由
読書感想文の書き出しで重要なのは、「なぜこの本を読んだのか」「読む前にどんな印象を持っていたか」を書くことです。これによって、読者は「この人はどういう気持ちでこの本に向き合ったのか」が分かり、感想文に自然な流れが生まれます。
たとえば、『人間失格』というタイトルを見て「ちょっと怖そう」「暗い話かな」と感じた人も多いでしょう。そんな第一印象や、「学校の課題で読まなければならなかった」「太宰治の名前は知っていたけど読んだことがなかった」という理由でもOKです。大切なのは、自分の気持ちを素直に書くことです。
「初めて聞いたタイトルで、不安な気持ちで読み始めました」とか「昔から有名な作品なので、一度は読んでみたいと思っていました」といった形で、自分の言葉で書くと、読者にぐっと伝わります。また、「太宰治ってどんな人なんだろう?」「人間失格って、どんな話なんだろう?」という疑問を書いておくと、後の感想部分につなげやすくなります。
このように「読む前の自分」を描いておくと、最後の「読み終えた自分」との対比ができ、感想文全体にまとまりが出るのです。
②あらすじ:自分の言葉で短くまとめる
感想文の中にあらすじを入れると、読む人にとって内容が分かりやすくなります。ただし、あらすじは短く、自分の言葉でまとめるのがポイントです。本の内容を細かく書きすぎると、感想ではなく「要約」になってしまいます。
たとえば、次のようにまとめると良いでしょう:
「この物語は、葉蔵という青年が自分の人生を3つの手記で振り返る形で語られています。人とうまく付き合えず、仮面をかぶって生きる彼は、やがて心を病み、人間としての価値を見失っていきます。最終的には『人間失格』という言葉を残して人生を終える、悲しくも深い物語です。」
このように、自分が読んでどう感じたかを交えながらまとめると、内容紹介としてだけでなく「感想文の一部」として機能します。自分の理解した範囲で書けばOKなので、無理に正確さを追求する必要はありません。
また、葉蔵の気持ちや変化を中心に書くと、感想とのつながりがスムーズになります。文章の長さはだいたい5〜7行程度を目安にするとバランスが良くなります。
③心に残った場面:その理由と自分の気持ち
感想文の中で一番大切ともいえるのが、「心に残った場面」とその理由を書く部分です。これは読み手にとって、あなたがこの作品をどう受け取ったかを知る一番のポイントになります。
たとえば、「葉蔵が人に本音を言えず、いつも笑ってごまかしていた場面が心に残った」としましょう。その場面がなぜ印象的だったのか、自分の気持ちや体験と結びつけて書いてみてください。
「私も友達の前ではつい明るくふるまってしまい、悩みを話せないことがある。葉蔵と同じように、本当は誰かに助けてほしいと思っていても、それを言えないことがある。だからこの場面はとても共感できて、心が痛くなった」といった形にすれば、読む人にも強く伝わります。
また、「この場面を読んで、自分ももっと正直に気持ちを伝えてみたいと思った」と続けることで、作品からの学びが自然に表れます。ポイントは、「なぜその場面が印象に残ったのか」「そのとき自分はどう感じたのか」を具体的に書くことです。
④考えたこと・学んだこと
物語を読みながら、自分の中で何かが変わったと感じることがあると思います。ここでは、そうした「気づき」や「学び」をまとめましょう。作品を読んで終わりにするのではなく、そこから何を得たのかを書くことで、感想文がぐっと深くなります。
たとえば、「人間関係がうまくいかなくても、自分を責めすぎないことが大切だと思った」「自分の弱さを受け入れる勇気を持ちたいと思った」といった学びでも十分です。大きなテーマでなくても、自分の中で少しでも変化があれば、それが学びです。
また、「他人の気持ちをもっと想像して行動したい」「本音を言い合える友達の大切さを感じた」といった、行動につながる気づきが書けると、感想文の締めくくりとしてとても良い印象を与えます。
自分自身と向き合い、少しでも成長したと感じたことを素直に書けば、それだけで立派な感想文になります。
⑤まとめ:読み終わった後の自分の変化
最後のまとめでは、読書を通じて自分がどう変わったか、どんな気持ちで読み終えたかを書きましょう。この部分は、感想文全体を締めくくる大切な部分です。
「読んでよかった」「重たい話だったけれど、自分のことを見つめ直すきっかけになった」といった感想が自然です。最初の「読む前の気持ち」と比べて、どんなふうに自分が変わったかを書くと、感想文として完成度が高くなります。
また、「今後はもっと自分の気持ちに正直に生きてみたい」「人との関わりについてもっと考えたい」など、未来への前向きな言葉で締めくくると、感想文全体の印象が明るくなります。
読書とは、自分の中の価値観を広げてくれるものです。その効果を素直に言葉にして、自分だけの読書体験としてしっかり書き出してみてください。
スポンサーリンク
読書感想文の具体例をまるっと紹介!
中学生向け:共感を中心に書いた例
中学生が『人間失格』の読書感想文を書くときは、難しい言葉や時代背景よりも、自分が共感した部分を中心に素直に書くことが大切です。特に、葉蔵の「本当の気持ちを人に言えない」という心の葛藤は、多くの中学生にも共通する部分ではないでしょうか。
例えば、以下のような感想文の一部が考えられます:
私は『人間失格』を読んで、一番心に残ったのは、葉蔵が人に嫌われないように無理して笑っていた場面です。私も学校で友達と話すとき、相手に嫌われたくなくて本音を言えずに笑ってごまかしてしまうことがあります。だからこの場面を読んだとき、「葉蔵の気持ちが少し分かる」と思いました。
また、「自分は人間として失格なんだ」と葉蔵が感じるシーンでは、とても悲しい気持ちになりました。私はそこまで思ったことはないけれど、うまく人と関われないと「自分はダメなんじゃないか」と思うことがあります。この本を読んで、自分を責めすぎないようにしようと思いました。
このように、自分の体験とリンクさせて書くことで、読み手にも「この子はちゃんと作品を受け止めているな」と感じてもらえます。言葉はシンプルでも、感情を丁寧に書くことが一番大切です。
高校生向け:社会や時代背景に触れた例
高校生になると、感想文の中に時代背景や作者の意図を考察した内容を取り入れることで、より深みのある文章になります。『人間失格』は昭和の戦後という混乱の時代に書かれた小説であり、その背景を踏まえて読むことで、葉蔵の苦しみがより立体的に見えてきます。
以下はその一例です:
太宰治の『人間失格』は、戦後の混乱期に発表された作品である。日本が戦争に負け、多くの人が生きる意味を見失っていた時代に、太宰自身の孤独や絶望が強く反映されていると感じた。
葉蔵が「人と関われない」と苦しんでいる姿は、ただの個人的な問題ではなく、社会全体の価値観が揺れていた時代の空気を象徴しているように思える。現代のようにSNSでつながれる時代であっても、人との距離感に悩む人は多い。だからこそ、この作品は今読んでも心に響くのだろう。
私はこの作品を通して、「社会の変化に流されず、自分の生き方を見つける大切さ」を考えさせられた。苦しくても、言葉で気持ちを伝える努力をしていきたいと思う。
高校生の感想文では、「自分の意見+時代との関係」を書くことで説得力が増します。知識ではなく、自分なりに考えた結果を書くのがポイントです。
大学生向け:哲学的な視点を取り入れた例
大学生や大人が書く場合、作品のテーマや哲学的な問いを掘り下げて書くと非常に読み応えのある感想文になります。『人間失格』は、「自己とは何か」「人間とは何か」といった深いテーマを含んでいるため、それについて自分の言葉で考察するのが効果的です。
以下は一例です:
『人間失格』を読み進めるうちに、私は葉蔵という存在が「自我の不在」に苦しむ一種の哲学的モデルだと感じるようになった。彼は常に他人の目を気にし、自分の感情を表現することができず、「他者に映る自分」が本当の自分だと錯覚してしまう。
これは現代においても共通する問題である。SNSでは他者からの評価が重要視され、自己表現が「演出」になってしまうこともある。葉蔵のように「他人からの評価に依存する生き方」は、現代社会においても無縁ではない。
太宰が伝えたかったのは、「人間の弱さを否定せず受け入れることの大切さ」ではないか。誰もが不完全であり、時に他人とズレることもある。そんな自分を「失格」として切り捨てるのではなく、その弱さごと愛するべきだというメッセージが、この作品には込められていると私は考える。
このように、自分なりの「問い」と「答え」を探して書くことで、独自の視点が生まれます。難解な言葉より、自分の思考のプロセスを丁寧に表現することが大切です。
感情にフォーカスした感想文の書き方例
感情にフォーカスするスタイルは、読書中に自分が感じた気持ちを中心に書く方法です。物語の論理や構成よりも、「どう感じたか」「何が心に刺さったか」に注目します。これは感情が豊かな人や、物語に強く共感した人にとって自然な書き方です。
たとえば:
私は『人間失格』を読みながら、何度も胸が苦しくなった。葉蔵の「笑っていても心が泣いている」という表現に、自分の中の何かが震えた気がした。私も人の前では明るくふるまっているけれど、本当は不安でいっぱいなことがある。そんな自分を誰にも見せられなくて、ただ疲れてしまうときがある。
葉蔵の孤独は他人事ではなく、私の中にもある孤独と重なった。「人間失格」という言葉は、とても重くて怖い。でもその奥には、「それでも生きたかった」という気持ちがあるように思えた。
この本を読んで、誰かの弱さや寂しさにもっと優しくなりたいと思った。そして、自分の気持ちにもちゃんと目を向けてあげたい。そんなふうに感じた一冊だった。
感情を中心に書くスタイルでは、「感じたままを正直に書く」ことが最大の強みになります。心が動いた瞬間を丁寧に言葉にしましょう。
NG例とその改善ポイント
最後に、よくあるNG例とその改善方法を紹介します。ありがちなのは、以下のようなパターンです:
NG例:
「この本は面白かったです。主人公がかわいそうでした。人間関係は大切だと思いました。読んでよかったです。」
このような感想文は、内容が浅く、個人的な視点や具体性が欠けてしまいます。誰でも書けるような文章ではなく、「自分だから書けること」に焦点を当てましょう。
改善ポイント:
・なぜ面白いと思ったのか、どの場面が印象的だったかを書く
・「かわいそう」だけで終わらず、その気持ちがどこから来たか考える
・「人間関係が大切」→「葉蔵が人とうまく関われなかった理由」と関連付けて書く
改善例:
「葉蔵が自分を隠して人と関わろうとする姿に、見ていて苦しくなりました。彼は人と深くつながることを恐れていたのだと思います。私は、たとえ時間がかかっても、本音で話せる関係を築くことが大事だと感じました。」
このように書くと、一気に感想文の説得力が上がります。
スポンサーリンク
『人間失格』を読んだあとに考えてほしいこと
自分は「人間失格」なのか?と向き合う視点
『人間失格』を読み終わると、多くの人が「自分だったらどうだろう?」と考えるはずです。葉蔵は自分を「人間失格」だと考えましたが、実際に私たちは、どこからが“失格”で、どこまでが“普通”なのでしょうか。
葉蔵のように、失敗や人との距離感、孤独に悩んで「自分なんて価値がない」と感じたことがある人は少なくないと思います。しかし、もしそれだけで「人間失格」なら、世の中の多くの人が当てはまってしまいます。つまり、葉蔵の苦しみは「誰もが持ちうる感情」なのです。
ここで大切なのは、完璧じゃなくても、自分なりに生きていこうとする気持ちです。「人間失格」という言葉に怯えるのではなく、「人間らしさとは何か?」という問いに向き合うこと。感想文の中でも、「自分ならどう思うか」「葉蔵と同じような気持ちを持ったことがあるか」といった視点を書いてみると、とても深い内容になります。
葉蔵を否定するのではなく、彼を通して「自分の弱さ」と向き合う。それが、この作品を読む大きな意味ではないでしょうか。
生きづらさとどう向き合うか
現代社会でも「生きづらさ」を感じている人は少なくありません。人間関係、学校、家庭、SNS、将来への不安など、悩みの形は人それぞれです。『人間失格』の主人公・葉蔵も、まさにこの“生きづらさ”に悩み続けた人物でした。
葉蔵は、自分の本当の気持ちを誰にも話せず、無理をして笑って生きてきました。その結果、心が壊れてしまい、人間関係も社会からも距離を取るようになってしまいます。でも私たちは、葉蔵のようにすべてを抱え込まずに、「誰かに話す」「助けを求める」「自分を許す」といった選択肢を持つことができます。
感想文でこのテーマに触れるときは、「自分も同じように生きづらさを感じた経験があるか」「それをどう乗り越えようとしているか」といった、自分なりの体験や考えを盛り込むと、より深みのある内容になります。
この作品を読むことで、「生きづらさを感じてもいい」「それでも生きていくことには意味がある」と、そっと背中を押されるような感覚になるのです。
今の時代に読むからこそ気づけること
『人間失格』は戦後の混乱期に書かれた作品ですが、実は現代にこそ読んでほしい本でもあります。なぜなら、葉蔵が感じていた「孤独」や「不安」「人とつながれないもどかしさ」は、今の私たちにも当てはまるからです。
特にSNSやスマホの普及で、常に誰かとつながっているようで、実は「本当の自分」は隠している人が多いのではないでしょうか。葉蔵が「道化」としてふるまっていたように、現代でも「SNSでは明るくふるまっているけど、実際は違う」という人はたくさんいます。
この作品を読むことで、「本音でつながることの大切さ」「自分らしくあることの難しさ」を改めて考えさせられます。読書感想文では、「現代とこの物語の共通点」「今の時代に読むからこそ感じたこと」を書くと、作品との距離が一気に縮まります。
つまり、『人間失格』は昔の文学ではなく、今を生きる私たちに向けたメッセージでもあるのです。
太宰治が私たちに伝えたかったこと
太宰治という作家は、常に「弱さ」や「醜さ」と向き合ってきた人です。きらきらした希望ではなく、どちらかというと心の中にある「暗さ」や「痛み」を文章にして、読む人の心に寄り添ってきました。
『人間失格』は、その集大成とも言える作品であり、彼自身の告白のようにも感じられます。では、そんな太宰がこの作品を通して私たちに伝えたかったことは何なのでしょうか。
それは、「人間は完璧じゃなくていい」ということだと私は思います。笑っていても泣いていても、人間は人間。失敗しても、人と違っても、それでも生きていく価値があるんだと、太宰はこの作品で叫んでいるように感じます。
感想文の中で、「自分はこの小説から何を受け取ったのか」をまとめるとき、このようなメッセージを自分なりに言葉にすることで、感想文全体にしっかりとした芯が通ります。太宰が心から絞り出した言葉を、どう受け取ったか。そこにあなただけの答えがあります。
感想文を書いた後の「自分語り」のすすめ
感想文を書き終えた後、ぜひおすすめしたいのが「少しだけ自分語りをしてみる」ことです。これは、作品と自分の人生や考えを結びつけることで、より豊かな学びになる方法です。
たとえば、「この本を読んでから、人との関わり方を意識するようになった」とか、「誰かの弱さを受け入れたいと思えるようになった」といった、自分の変化や気づきを一言でもいいので加えてみてください。
また、「これからはもっと素直に気持ちを伝えられるようになりたい」「弱さも含めて自分らしく生きたい」といった前向きな一言を添えると、読書感想文が「自分の成長の記録」になります。
『人間失格』は読んで終わりではなく、「読んだあとに自分とどう向き合うか」が大切な作品です。感想文の最後に、少しだけ自分の言葉で未来を語ってみてください。それが、あなたにしか書けない最高の感想文になります。
よくある質問(FAQ)
『人間失格』は中学生でも読めますか?
はい。言葉や表現は少し難しいですが、内容は中学生でも理解できるように丁寧に描かれています。感情を中心に読み取ることがポイントです。
感想文の文字数はどれくらいが理想ですか?
学校によって異なりますが、原稿用紙2〜3枚(800〜1200字)が一般的です。記事内で紹介した構成を使えば自然に書けます。
読書感想文にあらすじは必要?
はい。ただし短く、自分の言葉でまとめるのがコツです。感想がメインになるようにバランスを取りましょう。
感想文でネガティブな意見を書いてもいい?
もちろんOKです。正直な感想は読む人の心を打ちます。ただし、理由や自分の考えも一緒に書くようにしましょう。
他の太宰治の作品と比べてどう?
『人間失格』は太宰治の作品の中でも特に暗く、深いテーマを持っています。『走れメロス』のような明るい話と読み比べるのもおすすめです。
まとめ
『人間失格』という作品は、時代や世代を超えて読み継がれている名作です。その理由は、主人公・葉蔵が抱える「人間関係の悩み」「自分をさらけ出せない苦しさ」「生きづらさ」といった問題が、現代を生きる私たちにも共通しているからです。
この記事では、感想文を書くうえで大切なポイントや構成のヒント、具体的な文例まで幅広く紹介しました。感想文を書く際に最も大切なのは、知識や語彙力よりも「自分が何を感じたか」を素直に表現することです。
葉蔵の苦しみに共感したなら、その気持ちを丁寧に言葉にしてください。言葉にすることで、自分の中にある感情や価値観も整理され、新しい気づきが得られます。
誰もが一度は「自分はこのままでいいのか?」と悩む時期があります。そんな時に、『人間失格』という作品が寄り添ってくれるかもしれません。そして、感想文というかたちで、自分の気持ちを見つめ直すことが、きっとあなたの力になります。
小説の『人間失格』についてはこちらから購入できます。