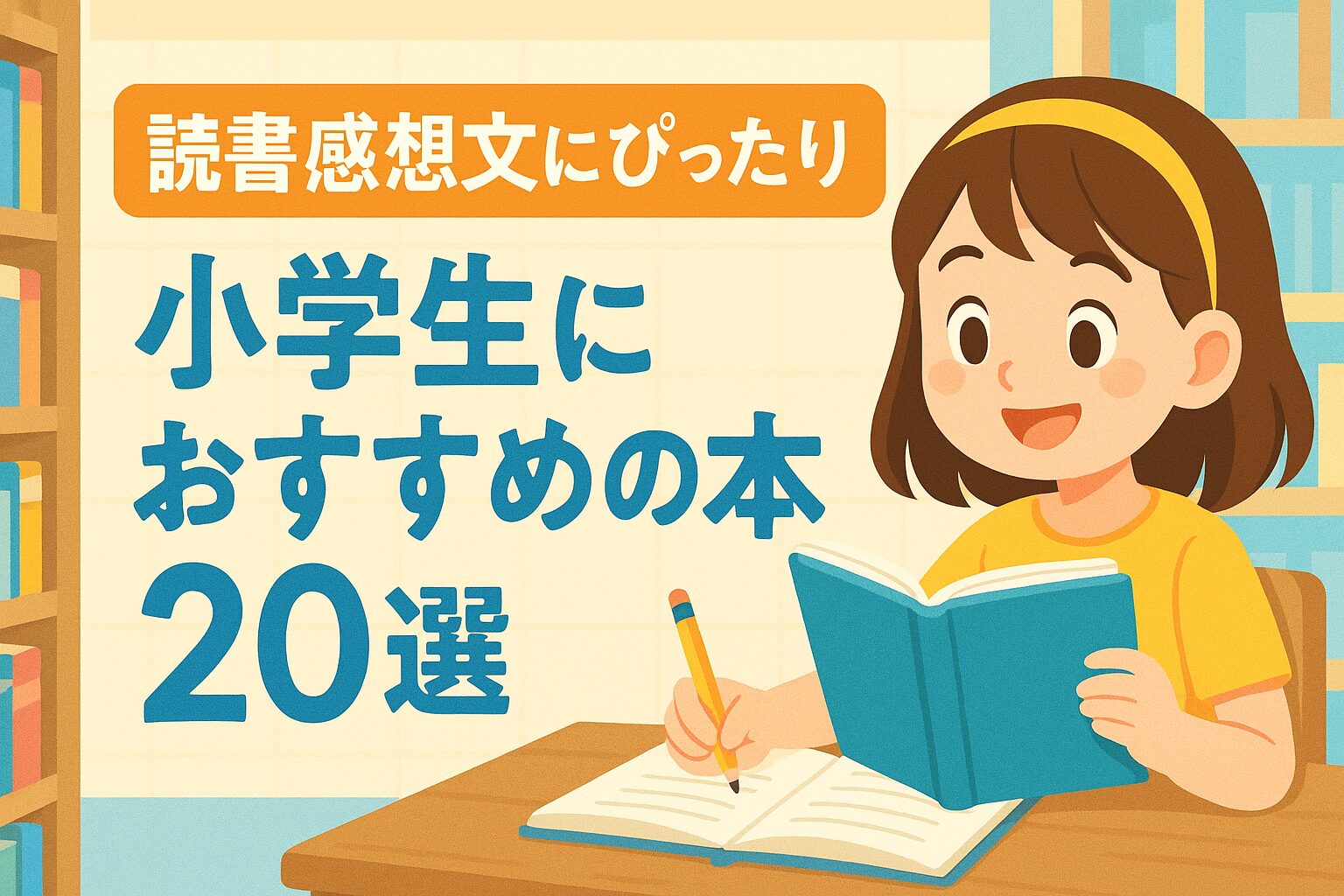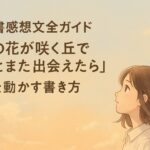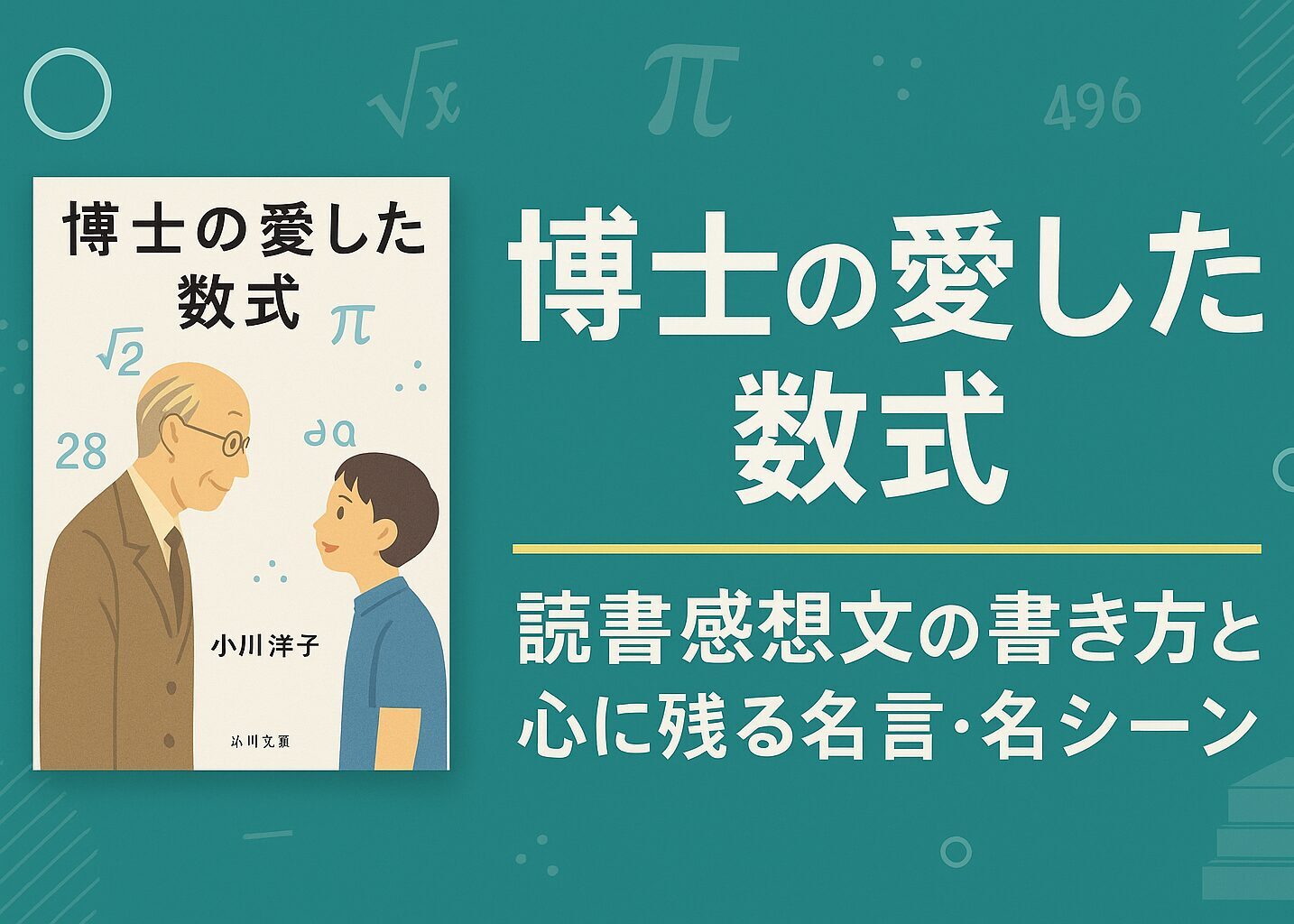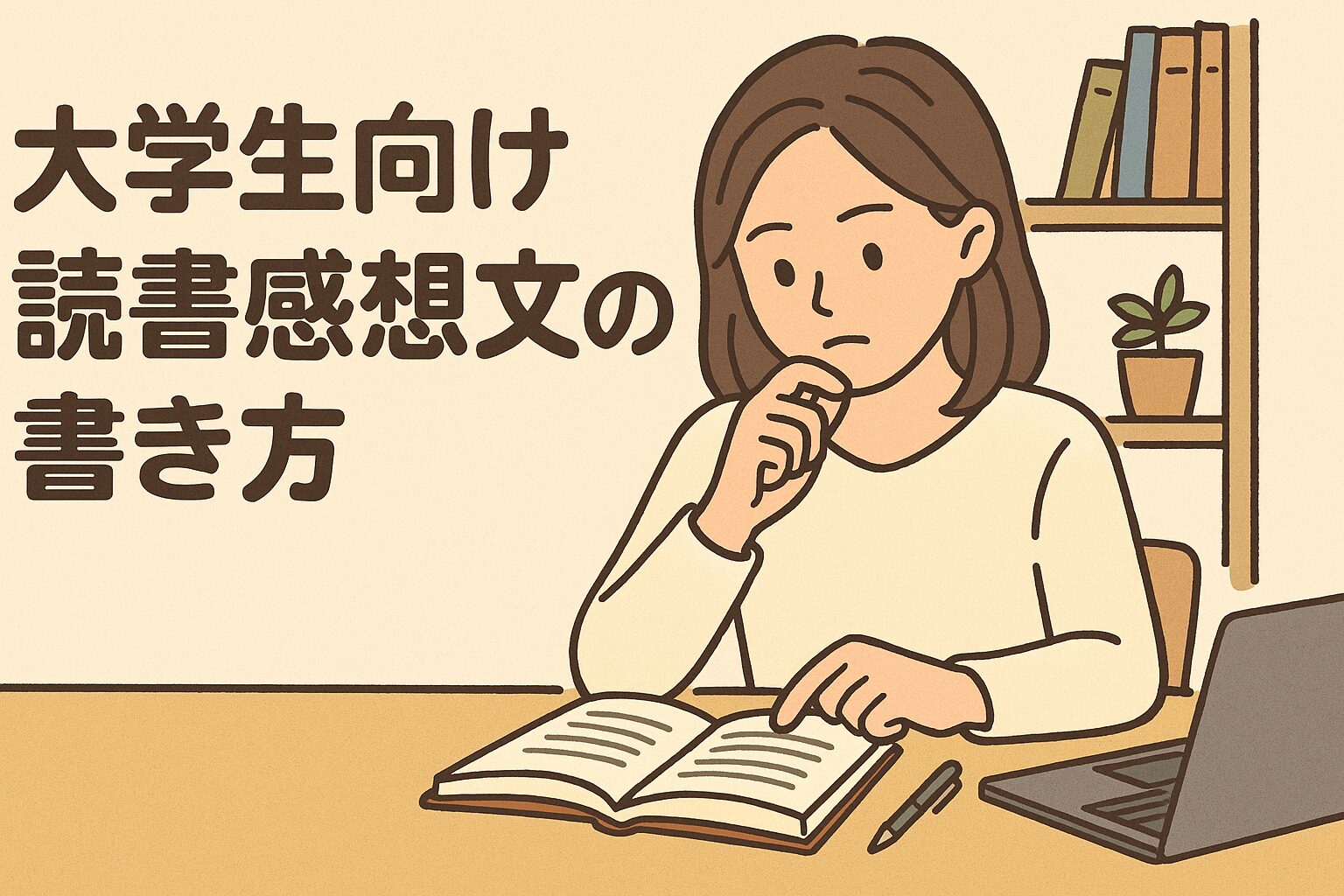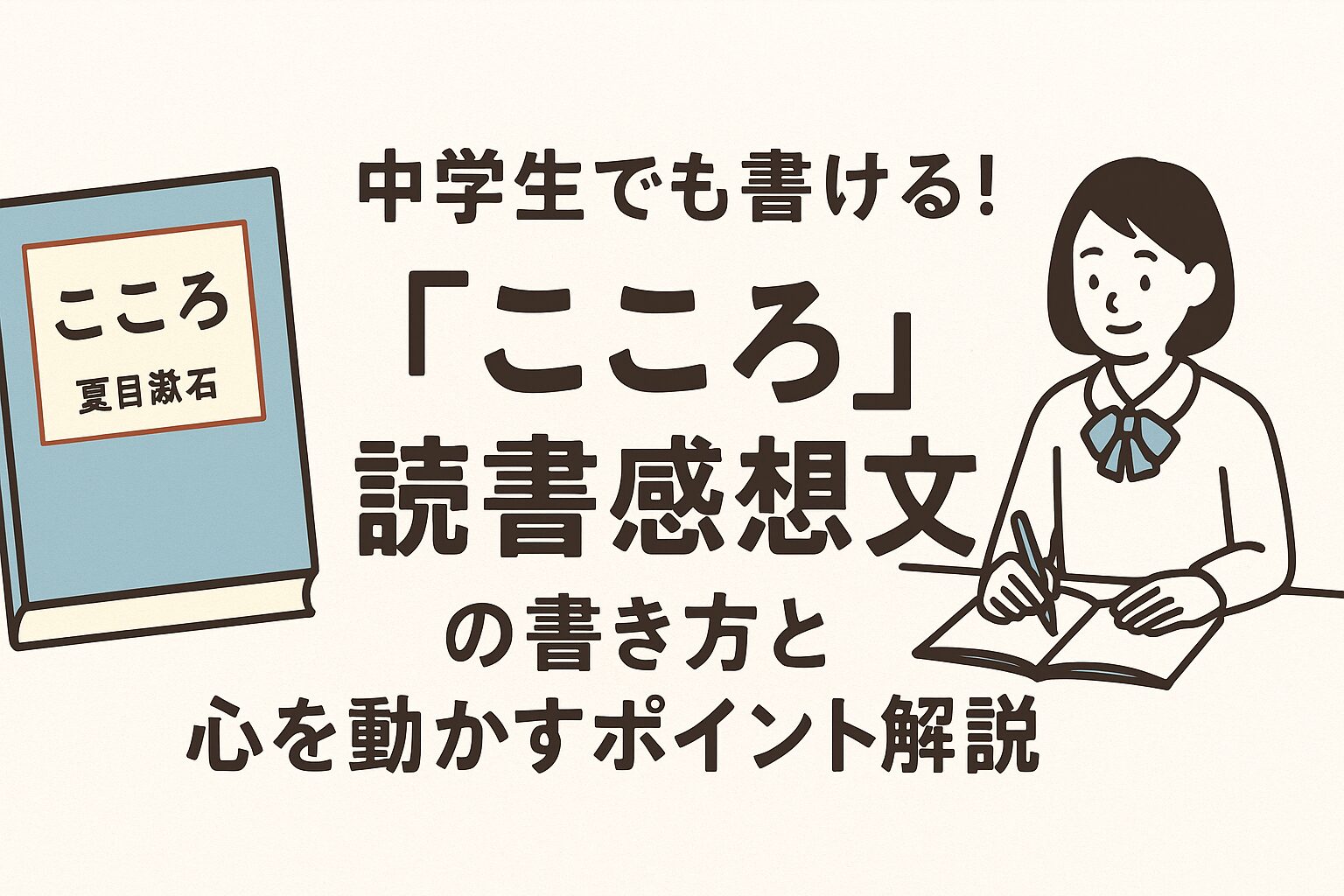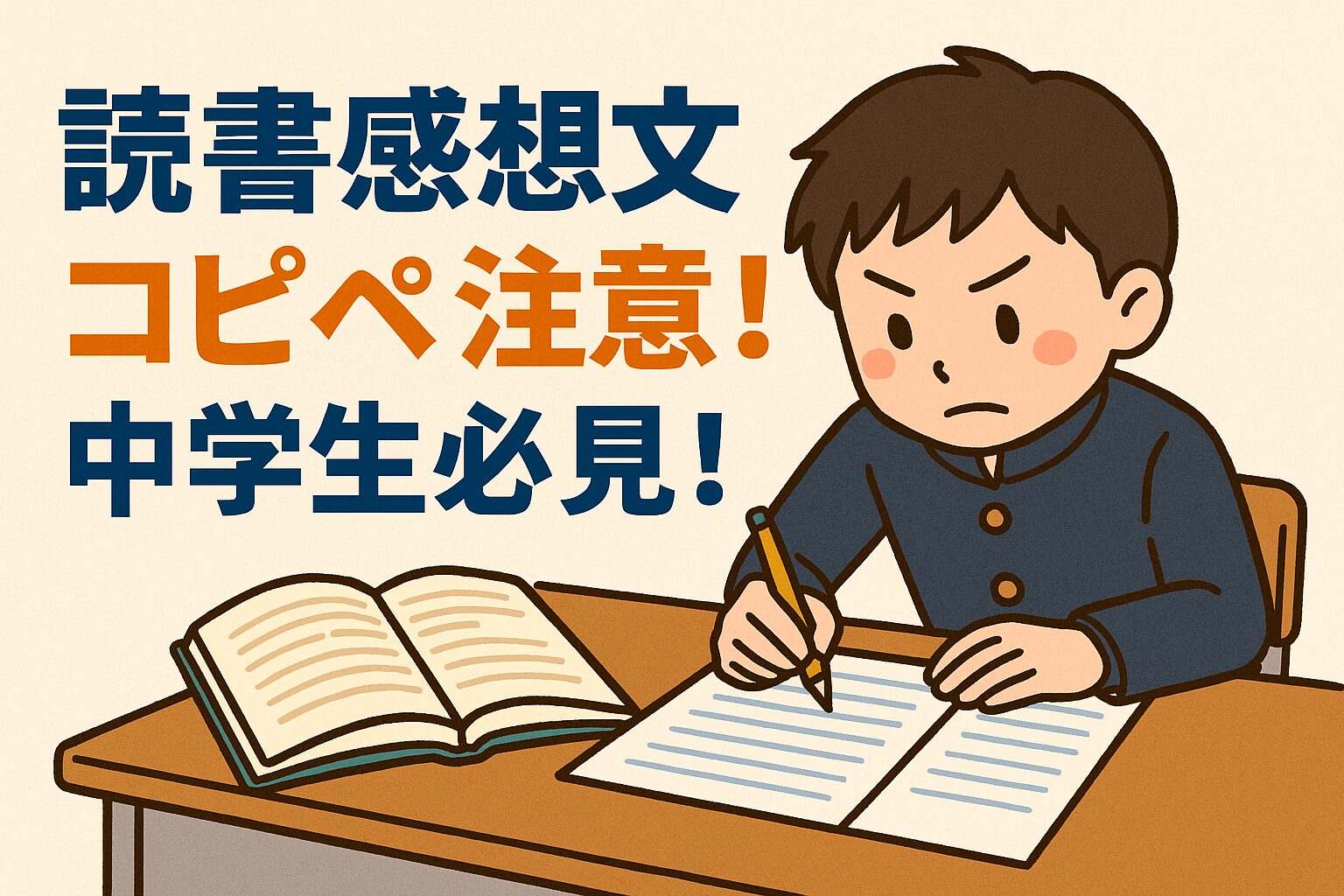読書感想文と聞くと、「何を書いたらいいの?」「どんな本を選べばいいの?」と悩む小学生や保護者の方は多いのではないでしょうか。特に夏休みの宿題として定番の読書感想文は、書き出しでつまずいてしまう子も少なくありません。
そこでこの記事では、小学生にぴったりの読書感想文向けおすすめ本を、学年別・ジャンル別にわかりやすくご紹介します。低学年から高学年まで、読書が苦手な子にもおすすめできる「感想が書きやすい本」や、「読みながら心が動く本」を厳選!
さらに、読書感想文の書き方や本の選び方のコツ、よくある質問(FAQ)にも詳しく答えています。「どうやって書けばいいのか分からない」「おすすめの本を知りたい!」という方は、ぜひこの記事を参考にしてください。読書感想文がもっと楽しく、もっと自由になりますように!
スポンサーリンク
小学生低学年(1〜2年生)におすすめの感想文向け本
絵本から読書感想文デビューにぴったりの本
小学校1〜2年生の子どもたちにとって、「読書感想文」というのは初めての体験かもしれません。本を読んで、それについて自分の思ったことを書く――それは簡単なようでいて、けっこう難しいこと。でも、絵本なら文章も少なく、絵もたくさんあるので、内容がわかりやすく、感想も書きやすくなります。
たとえば『おしいれのぼうけん』や『スイミー』といった絵本は、短いながらもストーリーに深みがあります。
読み終わったあとに、「どうしてこうなったんだろう?」とか「自分だったらどうしたかな?」といったことを考えやすいのが特徴です。感想文のポイントは、「思ったことを素直に書く」ことなので、絵本を読んで心が動いた場面を見つけてみましょう。
感想を書くときには、「このページの絵が好きだった」「○○がかわいそうだった」「ぼくも○○だったらこわいと思った」といった、気持ちを表す言葉を使うと、より自分らしい感想文になります。
読書が苦手なお子さんでも、絵本をきっかけに本に親しみ、少しずつ読む力と書く力を育てていけますよ。
短くて読みやすいけど深いテーマの本
低学年向けの本の中には、ページ数は少ないけれど、読んでいて考えさせられるような深いテーマを持った本がたくさんあります。たとえば『ともだちや』や『ごんぎつね』などは、友だちとの関係や思いやりの気持ちについて描かれています。
「なぜ○○はこんなことをしたのかな?」「○○の気持ちはどんなだったと思う?」など、物語の中でキャラクターの気持ちを考えることが、感想文を書くヒントになります。短いお話でも、「自分だったらどうするか」「同じことがあったらどう思うか」などを考えることで、オリジナルな感想が書けるようになります。
また、短い本は時間がかからず読めるので、何回も読み直して内容をしっかり理解できるのもポイントです。感想文を書く前にもう一度読んで、好きな場面や印象に残ったセリフを見つけておくと、書きやすくなります。
家族や友だちの大切さが伝わる物語
小学生の読書感想文では、「身近なテーマ」があると感想が書きやすいです。特に「家族」や「友だち」といった、子どもたちが日ごろから関わっている人たちとの絆が描かれた本は、共感しやすく、自然と感情も動きます。
たとえば『おじいちゃんがおばけになったわけ』では、大好きなおじいちゃんを亡くした子どもの気持ちが丁寧に描かれています。
この本を読んだあと、「自分のおじいちゃんを思い出した」「もし家族がいなくなったらどうしよう」など、心に浮かんだ気持ちを素直に書くことが感想文になります。
また、家族や友だちが出てくる話を読むことで、「ありがとう」や「ごめんね」といった気持ちの大切さに気づく子も多いです。自分の生活とつなげながら読める本を選ぶことで、より深い感想が書けますよ。
笑って泣ける感動ストーリー
「おもしろかった!」「笑っちゃった!」という気持ちも、読書感想文にはとても大事です。感動する話や笑える話は、子どもたちの心に強く残りやすいので、感想も書きやすくなります。
たとえば『バムとケロ』シリーズのようなユーモアたっぷりのお話や、『ちいちゃんのかげおくり』のようなちょっぴり切ないけれど心に残る話など、感情の動きが大きい本がおすすめです。
読書感想文では、「おもしろかった理由」や「どこで泣きそうになったか」「どんな気持ちになったか」を自分の言葉で書くことがポイントです。読んだときの気持ちを思い出しながら、「こういうところが好きだった」と伝えると、読む人にも気持ちが伝わります。
感想が書きやすい本の選び方とは?
本選びの段階で「感想文が書きやすいかどうか」はほとんど決まってしまうこともあります。特に小学校低学年では、「自分が興味のある内容」「読んで楽しいと感じる本」を選ぶことがとても大切です。
ポイントとしては、
- お話の長さがちょうどよい(30〜50ページくらい)
- 絵が多くてイメージしやすい
- 主人公が自分と同じくらいの年齢
- 何かを感じたり考えたりする場面がある
こうした本は、読んだあとに「何か言いたくなる」気持ちが生まれやすいです。反対に、内容がむずかしすぎる本や、登場人物が多すぎてわかりにくい本は、感想文が書きにくくなってしまいます。
図書館や学校の先生に「読書感想文におすすめの本」を聞いてみるのもよい方法です。身近な人と相談しながら、自分に合った1冊を見つけてみてくださいね。
スポンサーリンク
小学生中学年(3〜4年生)におすすめの本と感想のヒント
自分と重ねやすい主人公が登場する本
3〜4年生になると、読み物の内容も少し深くなり、登場人物の気持ちや行動を考える力が育ってきます。この時期には、「主人公の気持ちがよくわかる!」と感じられる本が特におすすめです。自分と似たような悩みや出来事を体験している主人公に出会うことで、感情移入がしやすく、感想文も自然と書けるようになります。
たとえば『かあさんのしっぽっぽ』では、親のことをもっと知りたいという主人公の気持ちに共感する子どもも多いです。また、『おれたち、ともだち!』のシリーズでは、友だち同士のやりとりやケンカ、仲直りの過程がリアルに描かれていて、自分の経験と重ねながら読めます。
感想文を書くときには、「自分もこんなことがあった」「○○の気持ちがわかると思った」というふうに、自分の体験と結びつけて書くと、とても読みごたえのある文章になります。
道徳的な学びがある名作
読書感想文の題材として、昔から多くの学校で勧められているのが、道徳的なテーマを持った名作です。「正しさ」「やさしさ」「勇気」「思いやり」など、人として大切なことをやさしく伝えてくれる本は、読むだけでも学びがあり、感想にも深みが出やすくなります。
たとえば『モチモチの木』は、こわがりな主人公が大切な人のために勇気を出す姿を描いています。
この本を読んで、「自分にもこんな勇気が出せるかな?」と考えることで、自分を見つめなおすきっかけになります。
こうした本を読むときには、「もし自分が主人公だったらどうする?」と考えながら読み進めるのがポイントです。感想文では、自分の考えと物語の出来事を比べながら書いていくと、読み応えのある文章になります。
自然や生き物をテーマにした作品
3〜4年生は、理科や生活科の授業でも生き物や自然に関心を持つ時期です。自然や生き物をテーマにした本は、学習とのつながりもあり、読書感想文としても書きやすくなります。
たとえば『ファーブル昆虫記』や『シートン動物記』などの動物が主人公の本は、命の重さや自然のすごさについて考えさせてくれます。
また、『泣いた赤おに』のように、人間のやさしさと自然の世界が交わるような作品も人気です。
こうした本では、「動物の気持ちになって考えてみた」「自然の中で生きるってすごいと思った」といった感想が生まれやすいです。授業で学んだこととも結びつけながら、自分が感じたことを自由に書いてみましょう。
人気シリーズ本の中から選ぶならコレ!
3〜4年生になると、シリーズ本にハマる子も増えてきます。読書感想文に使うなら、読みやすくて内容がしっかりしている人気シリーズがおすすめです。シリーズ本は登場人物や世界観が親しみやすく、1冊目を読んで気に入れば、他の巻もどんどん読みたくなります。
たとえば『かいけつゾロリ』や『黒魔女さんが通る!!』シリーズは、楽しくてユーモアもありながら、友情や成長のテーマも含まれているため、感想文の題材にもぴったりです。
また、『ズッコケ三人組』シリーズでは、子どもたちの日常の中で起こる出来事が、リアルに描かれています。
シリーズ本を感想文に使うときは、「シリーズの中でこの巻が特に好きな理由」や「この巻を読んで考えたこと」に焦点を当てて書くと、より個性が出ます。
読書感想文が苦手でも書けるコツつき本
「読書感想文って苦手……」という子どもたちも少なくありません。そんなときは、あらかじめ「感想文が書きやすい工夫」がされている本を選ぶとスムーズです。最近では、巻末に「読書感想文のヒント」や「質問に答えて書くワーク」がついている児童書もあります。
たとえば『10歳までに読みたい世界名作』シリーズには、あらすじや登場人物の紹介、感想を書くヒントなどが載っていて、初めての読書感想文にも安心です。
また、『読書感想文らくらくシート』付きの本もあり、質問に答えていくだけで感想文が自然に書けるようになっています。
苦手意識がある子には、「書きやすくて成功体験ができる」本を選ぶことが、なにより大切です。無理なく、楽しく感想文を書ける本で、まずは1冊、挑戦してみましょう!
スポンサーリンク
小学生高学年(5〜6年生)向け感動&考えさせられる本
命・いのちの大切さを感じる物語
高学年になると、命の重みや他人の立場に立って考える力が育ちます。そんな時期に読んでほしいのが「命の大切さ」をテーマにした物語です。読後に「生きること」「守ること」「別れ」を考えるきっかけになる本は、感想文の題材としても深みが出ます。
たとえば『ぼくがラーメンたべてるとき』は、自分の暮らしと世界の子どもたちの現実を対比して描かれた絵本で、短いながらも強いメッセージがあります。
また、『かあちゃん取扱説明書』では家族への感謝、『チョコレート戦争』では人の正義感や信念を描いており、それぞれ命や人の気持ちの大切さを感じられる本です。
感想文では、「なぜこの場面で胸が痛くなったのか」「どんな気づきがあったのか」を中心に書いていくと、気持ちが伝わる文章になります。重いテーマでも、自分の言葉で率直に感じたことを書けば、それが立派な読書感想文になります。
社会問題をやさしく伝える児童書
今の社会で起こっている問題――たとえば貧困や戦争、環境問題など――を、子ども向けにわかりやすく描いた児童書もたくさんあります。これらは「ニュースではよくわからなかったことが本を通してわかった」と思えるような、学びの多い読書体験を与えてくれます。
たとえば『おにたのぼうし』は、戦争中の優しさや思いやりを描いた作品で、命のやりとりを子どもの視点で感じることができます。
また、『カモメに飛ぶことを教えた猫』は、環境問題と動物の絆をテーマにしており、感動と同時に深いメッセージが込められています。
読書感想文では、「この本を通じて初めて知ったこと」「今の社会とどうつながっているのか」などを書いてみましょう。本を読んで世界が広がった経験は、読む人にも強く伝わります。
歴史を知れる読みやすい物語本
高学年になると、歴史にも興味が出てきます。ただ教科書だけでは難しく感じてしまうこともありますが、物語として描かれた歴史小説は、楽しみながら学べるうえ、感想文の題材としてもおすすめです。
たとえば『走れメロス』は、友情と信頼をテーマにした有名な話で、時代背景を感じながらも登場人物に感情移入しやすいです。
ほかにも『二十四の瞳』や『ひめゆりの塔』など、実際の戦争体験を描いた物語もあり、平和について考えるきっかけになります。
感想文では、「今と昔で何が違うのか」「なぜこの行動ができたのか」といった視点を持つと、単なるあらすじではなく、自分の考えをしっかり書けます。歴史を知ることは未来を考えることにもつながります。
実話ベースで心に残るおすすめ本
実際にあった出来事をもとにしたノンフィクション系の児童書も、高学年にぴったりです。フィクションにはない「現実の重み」があり、読むことで自分の生活や考え方を見直すきっかけになります。
たとえば『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、多文化社会の中で悩みながらも成長する子どもの視点が描かれています。
また、『ひとりで生きるには』などは、困難を乗り越えた人の実話から、自分自身の可能性や強さを感じ取ることができます。
読書感想文では、「こんなふうに生きたい」「この人の考えに共感した」など、自分の思いと結びつけて書くのがポイントです。実話だからこそ感じられる「本当のすごさ」や「重さ」を、素直に表現してみましょう。
高学年が書きやすい読書感想文の構成例
高学年になると、感想文も長くなり、「何から書いたらいいかわからない…」と悩むこともあるかもしれません。そんなときは、あらかじめ構成を考えておくことで、スムーズに文章を書くことができます。
感想文の基本的な構成は、以下のようになります。
| 段落 | 内容のポイント |
|---|---|
| ①導入 | 本を選んだ理由、読む前の気持ち |
| ②あらすじ | 簡単にお話の内容を紹介 |
| ③感想① | 印象に残った場面、感じたこと |
| ④感想② | 自分と比べて考えたこと、学んだこと |
| ⑤まとめ | 全体の感想とこの本から得たこと |
この構成にそって書けば、どこで何を書けばいいか迷わずに済みます。読みながらメモをとっておくと、あとで書くときにとても役立ちますよ。
スポンサーリンク
ジャンル別で選ぶ!読書感想文にぴったりの本
冒険ファンタジーで想像力を広げる
ファンタジーや冒険物語は、現実では味わえないワクワクする世界に飛び込めるのが魅力です。登場人物と一緒に冒険するような気持ちで読めるので、読書があまり得意でない子でも引き込まれやすく、感想も書きやすくなります。
たとえば『ハリー・ポッター』シリーズや『ライオンと魔女(ナルニア国ものがたり)』などは、壮大な世界観と成長する主人公の姿が人気です。
日本の作品では『クレヨン王国』シリーズや『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』もファンタジーの世界に親しみやすく、読書感想文の題材にもぴったりです。
感想文では、「この世界に行ってみたいと思った」「主人公の勇気に感動した」など、自分の想像と重ねながら感情を書いていくのがコツです。ファンタジーこそ、心が動いた場面を自由に表現してみましょう。
感動ノンフィクションで心を動かす
実際にあった話や、現実に起こった出来事をもとにしたノンフィクションは、「本当にあった話だからこそ」心に響きやすいジャンルです。中でも、感動や驚きのある内容の本は、読書感想文として強く印象に残る文章が書きやすいです。
たとえば『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』は、モノより心の豊かさを語る感動のスピーチ集。
また、『震災をわすれない ぼくたちの3.11』のような体験談は、命の尊さや助け合いの大切さをリアルに感じられます。
こうした本を読んだ後には、「この人の生き方に感動した」「自分もこんなふうに人を助けたい」など、自分の考えを重ねて感想を書いてみてください。事実の重みを感じながら書く文章は、読む人の心にも届きます。
日常系ストーリーで共感しやすい
身近な生活や学校、家族との関係を描いた日常系の物語は、小学生にとって「自分のことみたい」と感じやすく、共感をもとに感想文が書きやすいジャンルです。特に、ちょっとした出来事が大きな学びになるようなストーリーは、自分の体験とも重ねやすくなります。
たとえば『わかったさんシリーズ』や『おしりたんてい』は、日常の中に小さな冒険があり、親しみやすい登場人物が魅力です。
『こまったさんシリーズ』のように、ちょっとした事件やチャレンジが展開される物語も楽しく読めて、感想を書きやすいです。
感想文では、「主人公と同じようなことがあった」「このセリフにドキッとした」など、自分との共通点をもとに感想を広げるのがポイントです。等身大の気持ちを大切にしましょう。
お笑い・ユーモアで楽しく読める本
笑える本やユーモアたっぷりのストーリーも、立派な読書感想文の題材になります。「おもしろいだけじゃだめ?」と思うかもしれませんが、「なぜ笑えたのか」「どこが楽しかったのか」「笑いの中にどんな思いがあったのか」といった点に注目することで、しっかりした感想文に仕上がります。
たとえば『ズッコケ三人組』や『かいけつゾロリ』のようなシリーズものは、クスッと笑えて、友情や知恵、成長のエピソードがしっかりと描かれています。また、『こまったさん』や『マジック・ツリーハウス』も、おもしろさと学びがバランスよく含まれているのでおすすめです。
感想文を書くときは、「笑って終わり」ではなく、「なぜこの本が好きだったか」「主人公の行動から何を感じたか」など、自分の気持ちを言葉にすることが大切です。笑いを通して伝わるメッセージも、ちゃんとあるんですよ。
学校生活をテーマにした読みやすい物語
学校を舞台にした物語は、小学生にとってもっとも身近で、想像しやすいジャンルです。クラスのこと、友だち関係、先生とのやりとりなど、日々の出来事を題材にした話は、自分の経験と重ねながら読めるので、自然と「書きたいこと」が見つかりやすくなります。
たとえば『となりのせきのますだくん』や『あたし、ねむれないの』などは、学校でのドキドキや不安、友情などがリアルに描かれており、読みながら「自分も同じ!」と思える場面がたくさんあります。
『わたしのワンピース』のように、少しファンタジーの要素が入っていても、心の成長がテーマになっている本もおすすめです。
感想文では、「自分だったらどうするか」「こんなふうに友だちに言えたらいいな」など、具体的な気持ちを書くと、読む人の共感を呼ぶ文章になります。日常だからこそ、深く感じられる物語を選びましょう。
スポンサーリンク
読書感想文の書き方と本の選び方のポイント
本を読む前にしておくといい準備とは?
読書感想文をスムーズに書くためには、本を読み始める前にちょっとした準備をしておくことが大切です。まずは「どんな本か」をざっくり知っておきましょう。表紙やあらすじを見て、どんなお話か想像してみることで、読むときの集中力が変わってきます。
次に、「この本でどんなことを感じたいか」「なぜこの本を選んだのか」を考えてみてください。感想文の最初の部分(導入)にこの理由を書くことで、読者にも興味を持ってもらいやすくなります。
また、読みながら気になった言葉やシーンに線を引いたり、ふせんを貼っておくのもおすすめです。あとで感想文を書くときに、「ここが印象に残った」とすぐ思い出せるからです。
このように、読む前に少し意識をするだけで、読書の楽しさも深まり、感想文もずっと書きやすくなります。
感想がスラスラ書ける「心に残った場面」メモ法
感想文でいちばん大切なのは、「心が動いたことを書く」ことです。だからこそ、本を読みながら「心に残った場面」を見つけるのがカギになります。おすすめなのが「読書メモ」をつけながら読む方法です。
やり方はとても簡単。本を読んでいて「ドキッとした」「おもしろかった」「泣きそうになった」など感情が動いたときに、ページのすみに印をつけたり、ノートにメモを残しておくだけです。
たとえば、
- 25ページ:○○が怒られて悲しそうな顔をした → かわいそうだった
- 42ページ:○○が友だちを助けた → 自分もこんなふうに動けたらいいな
こんなふうに自分の気持ちを書き留めておくだけで、感想文のときに「何を書けばいいの?」と迷わなくなります。特に「なぜそう思ったのか」「自分だったらどうするか」も一緒に書いておくと、感想に深みが出ます。
感想とあらすじの違いってなに?
読書感想文を書くときに、よくある間違いが「あらすじだけで終わってしまう」ことです。もちろん、物語の内容を少し説明するのは大切ですが、それだけでは「感想」にはなりません。
あらすじとは、本の内容を短くまとめたものです。一方、感想とは「自分がどう感じたか、何を考えたか」という自分の心の動きを書くことです。
たとえば、
- あらすじ:「○○が迷子になって、○○と出会い、最後は家に帰った」
- 感想:「○○がひとりでがんばる姿に感動した。自分もピンチのときに助けを求める勇気を持ちたいと思った」
このように、感想は「自分の気持ち」が入っていることがポイントです。感想文を書くときには、あらすじはほんの少しにして、自分の考えや感じたことをメインに書きましょう。
読書感想文の基本構成を覚えよう
文章がうまく書けない理由の一つは、「何から書けばいいかわからない」ということ。そこで大事なのが「構成」をあらかじめ考えておくことです。読書感想文は、以下のような構成で書くとスムーズです。
| パート | 内容 | 書き出しの例 |
|---|---|---|
| はじめ | 本を選んだ理由や読む前の気持ち | 「この本を選んだのは、タイトルがおもしろそうだったからです。」 |
| なか | 本の簡単な紹介・印象に残った場面・感じたこと | 「○○が○○した場面にとても感動しました。なぜなら…」 |
| おわり | 学んだこと・本を読んで変わったこと・まとめ | 「この本を読んで、○○の大切さに気づきました。」 |
このようにパートごとに内容を分けて考えると、「何を書いたらいいか」がはっきりして、スラスラ書けるようになります。最初にメモを作ってから書き始めるのもおすすめです。
本の選び方で感想文の書きやすさが決まる!
読書感想文が書きやすいかどうかは、「どんな本を選ぶか」で決まるといっても過言ではありません。自分に合った本を選べば、読むのも楽しいし、書くのもスムーズになります。
選ぶときのポイントは次の通りです。
- 自分の年齢や読書力に合っているか(難しすぎない)
- 興味のあるテーマがあるか(動物、学校、冒険など)
- 読み終わったときに「何か言いたくなる」本か
また、過去に読んだことがあるお気に入りの本をもう一度読み直して、その感想を書くのもおすすめです。「前に読んだときと今では感じ方が違った」という書き方も、とても良い感想文になります。
図書館や本屋さんで、紹介コーナーを参考にするのもいい方法です。自分の「書いてみたい気持ち」が自然に湧いてくるような本を選んで、感想文にチャレンジしてみてください!
スポンサーリンク
よくある質問(FAQ)
どのくらいの本の長さが感想文にちょうどいいの?
読書感想文を書くための本の長さは、学年や読むスピードによって変わりますが、無理なく読みきれることが一番大切です。
低学年なら30〜50ページほどの絵本や短い物語がちょうどよく、中学年なら50〜100ページ、高学年になると100ページ以上の読みごたえのある本も選べるようになります。
あまり長すぎると途中で読むのが大変になり、感想文を書く前に挫折してしまうこともあるので、自分に合った長さの本を選びましょう。感想を書きやすくするためには、「話の内容をしっかり覚えておける長さかどうか」も大事なポイントです。
本を最後まで読めなかった場合はどうする?
読書感想文を書くつもりで本を選んだけれど、途中で読むのが難しくなってしまった……そんなときは、無理に最後まで読もうとしなくても大丈夫です。途中まで読んだ感想を書くのも一つの方法です。
たとえば、「途中まで読んでこんなことを考えた」「この場面が心に残った」という内容でも立派な感想文になります。読めなかった理由が「難しかった」「興味がわかなかった」などであれば、それを素直に書いてもよいでしょう。「なぜ読めなかったのか」も自分の大切な気づきです。
ただし、できれば「最後まで読んでみたい」と思える本を選ぶことが感想文をうまく書くコツでもあるので、選び直すことも検討してみてください。
読書感想文って何文字ぐらい書けばいいの?
読書感想文の文字数は、学校や学年によって指定されていることが多いです。一般的には以下のような目安になります。
| 学年 | 文字数の目安 |
|---|---|
| 1〜2年生 | 200〜400文字 |
| 3〜4年生 | 400〜800文字 |
| 5〜6年生 | 800〜1200文字 |
文字数が決まっている場合は、それに合わせて書くことが大切です。もし決まっていない場合でも、「心に残ったこと」を中心に書けば自然と必要な分量は書けるようになります。
文章を書くときには、最初に構成を考えておくとバランスよく書けます。「どこにどのくらい書くか」の計画を立てておくと、途中で長くなりすぎたり、短く終わったりすることを防げますよ。
家の人が手伝ってもいいの?
もちろん、おうちの人にアドバイスをもらったり、感想を話し合ったりするのはOKです。ただし、読書感想文は「自分の気持ちや考えを書くこと」が大事なので、文章を全部書いてもらうのはNGです。
書く前に「この本どうだった?」「どこが好きだった?」と聞いてもらったり、書いた感想文を読んで「ここはもっとくわしく書けるかもね」とアドバイスをもらうのは、文章をよくする助けになります。
感想文は「一人で書くこと」が目的ではなく、「自分の思いをことばにする練習」です。だからこそ、サポートをもらいながらでも、「自分の言葉」で仕上げることが一番大切です。
同じ本で兄弟・姉妹が感想文を書いても大丈夫?
はい、大丈夫です!兄弟・姉妹で同じ本を読んで感想文を書くことは、まったく問題ありません。むしろ、同じ本でも感じ方が違うところに気づける、よいチャンスにもなります。
ただし、それぞれの感想文が「自分の言葉」で書かれていることが大切です。「同じ場面が印象に残った」場合でも、「なぜそう思ったのか」や「自分の体験とのつながり」を書けば、全く違う感想文になります。
読書感想文は、「正解」があるものではありません。同じ本でも、それぞれが違う感じ方をするのが自然で、それこそが読書の面白さでもあります。自分だけの視点で自由に書いてみましょう!
まとめ
【学年や読む力に合わせた本選びが成功のカギ】
読書感想文で大切なのは、自分に合った本を選ぶことです。難しすぎる本や、内容が自分に合っていない本を選んでしまうと、読むのも感想を書くのも大変になります。逆に、自分の年齢や興味に合った本なら、楽しく読めて感想も自然と浮かんできます。
【感想が書きやすい本は「心が動く」体験ができる本】
どんなジャンルの本でも、「読んで心が動いた」と感じたなら、それは感想文にぴったりの本です。おもしろかった、泣きそうになった、びっくりした、感動した……その気持ちこそが、感想文の一番大切な材料になります。
【感想文は「正解」より「自分の気持ち」を大切に】
読書感想文に「正しい答え」はありません。他の人と同じ感想でなくていいし、書き方も決まっているわけではありません。自分がどう感じたか、自分の言葉でどう伝えるかを大切にしましょう。
【読書は自由で楽しい!感想文もその延長でOK】
「読書感想文=むずかしいもの」と思われがちですが、読書はもともと楽しいものです。だから感想文も、「楽しかった気持ちを誰かに伝える」くらいの気持ちで、自由に書いてみてください。
【一番大事なのは「自分なりの感じ方」を書くこと!】
うまく書こうとしなくてもかまいません。きれいな言葉じゃなくても、「こう思った」「これが印象に残った」と、自分の感じたことをそのまま書くのが一番大事です。その気持ちは、きっと読む人にも伝わります。