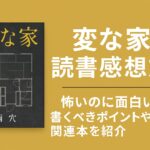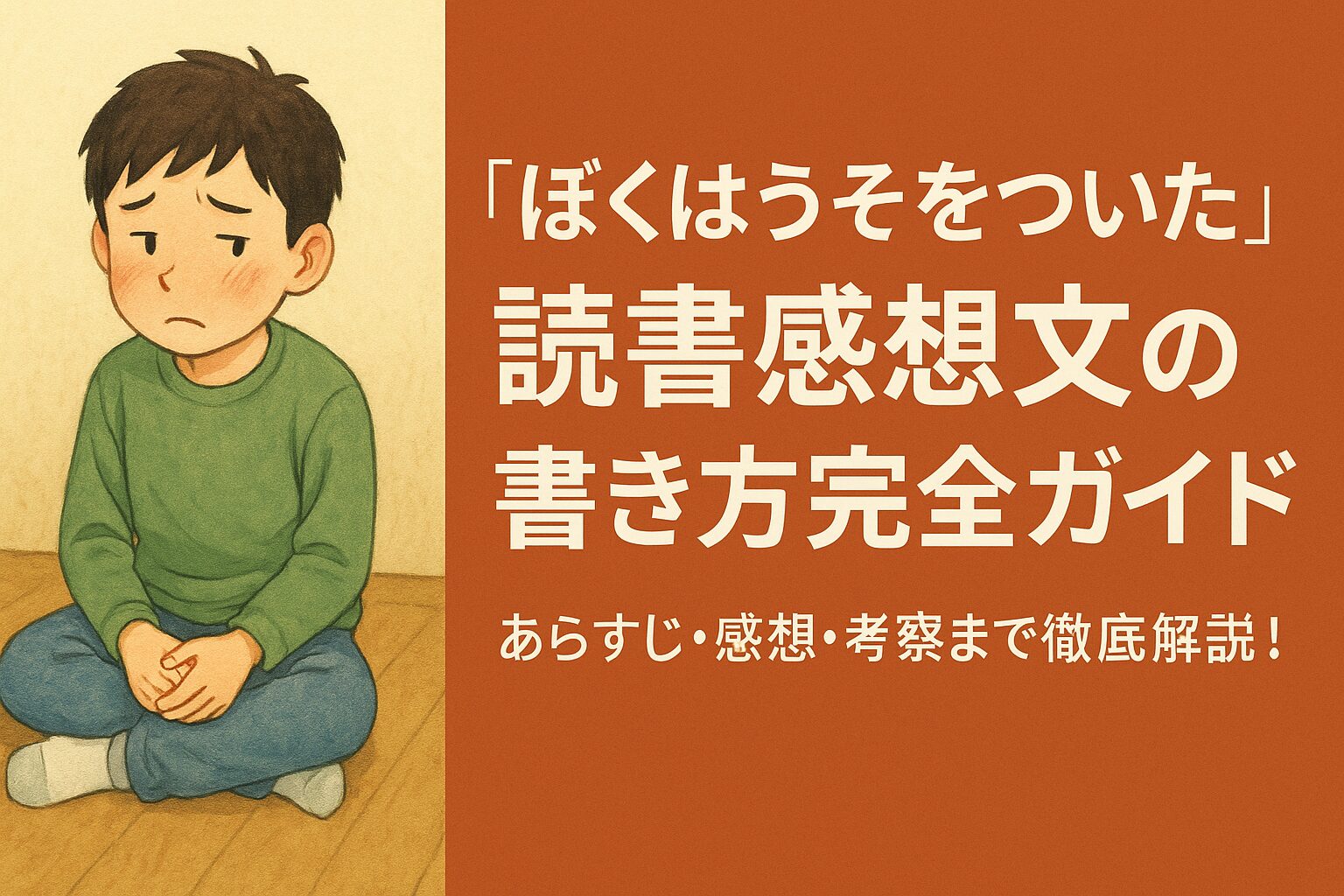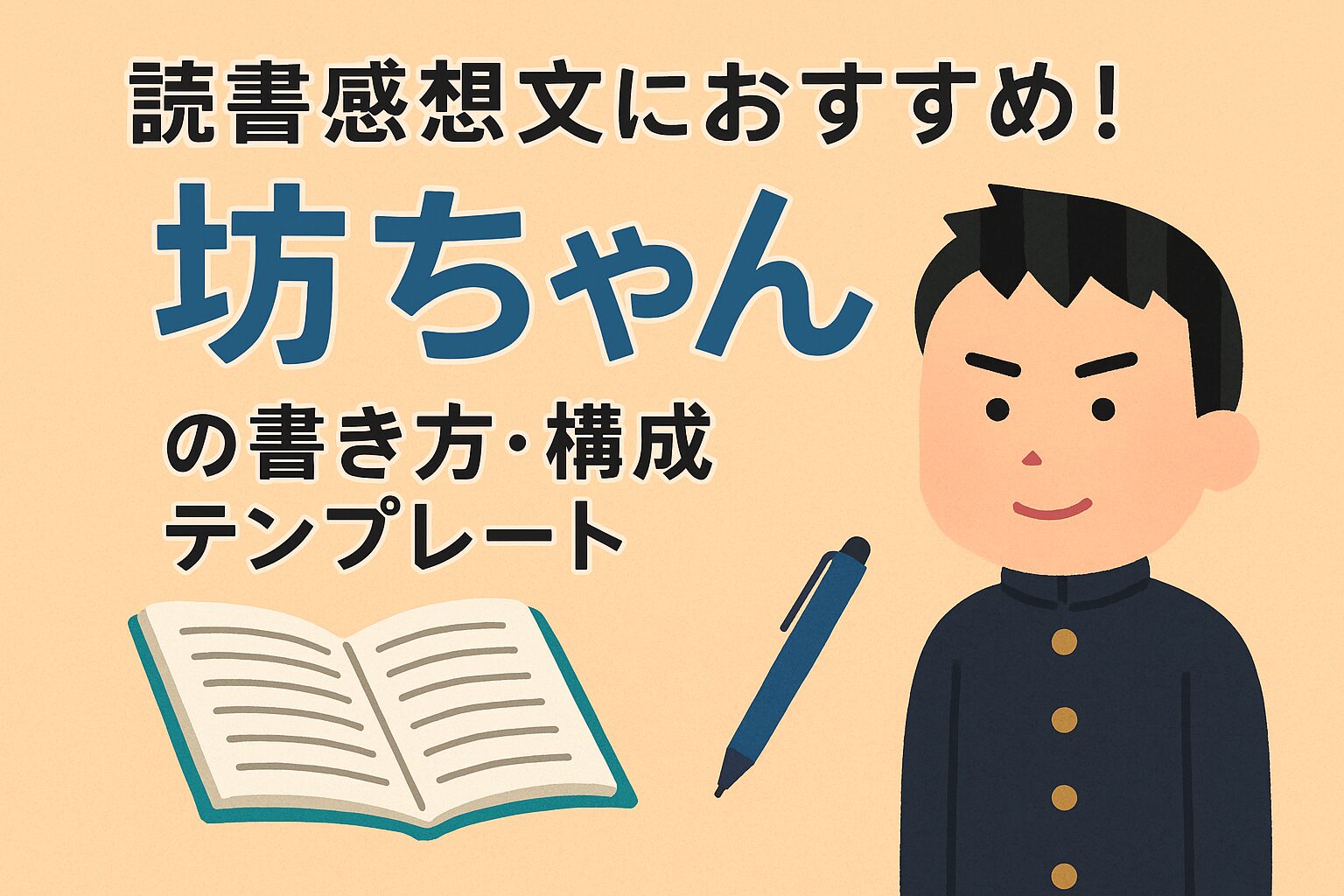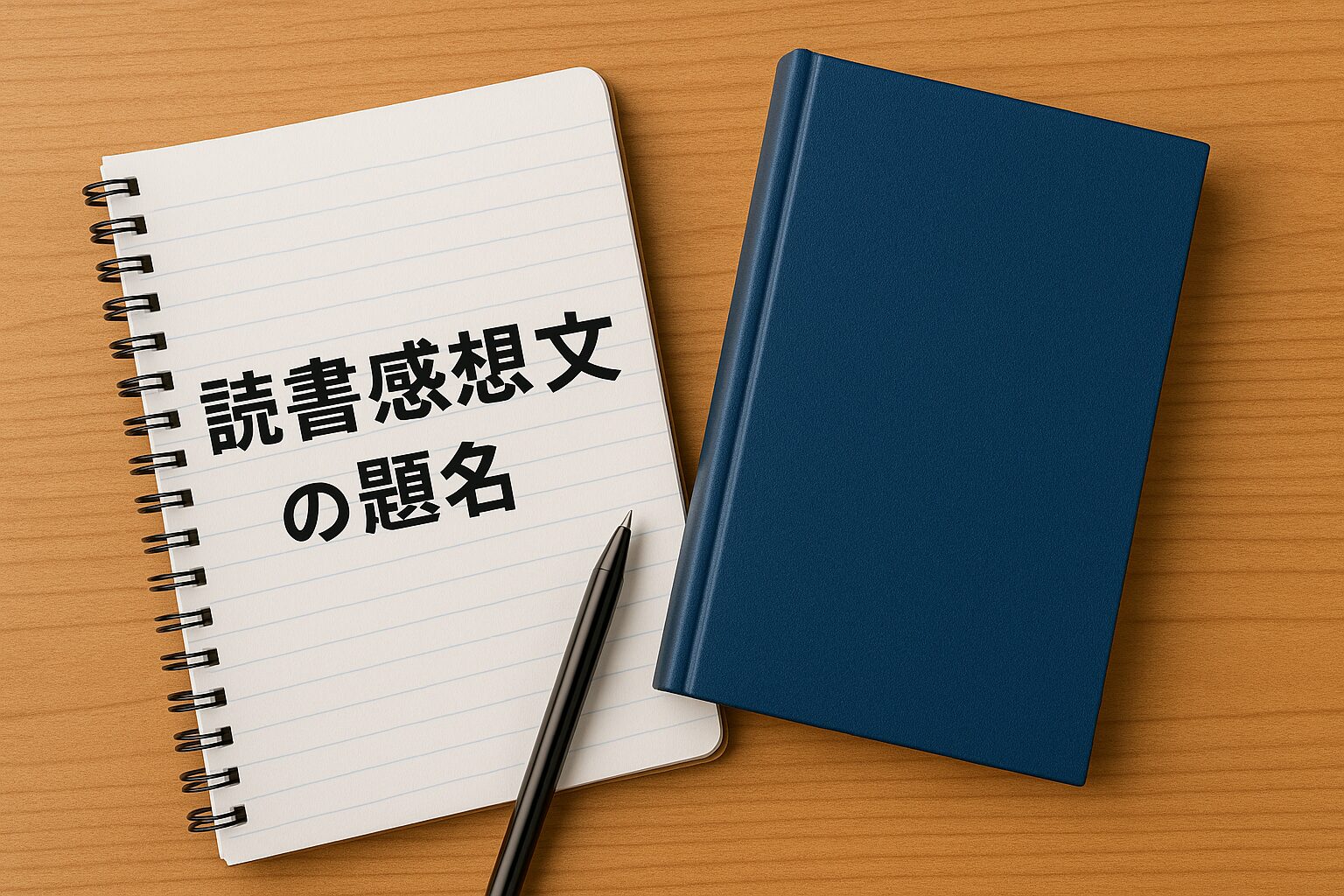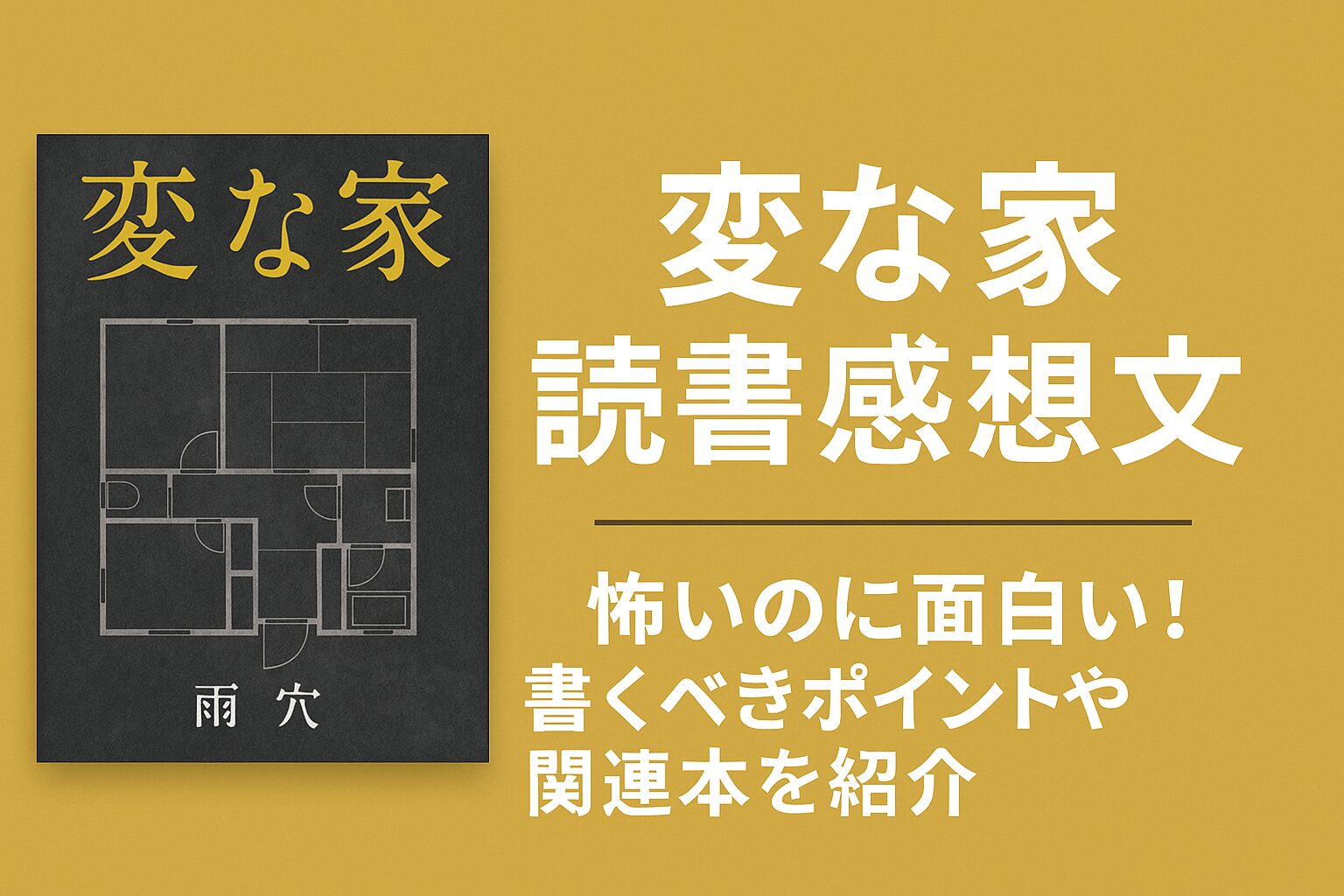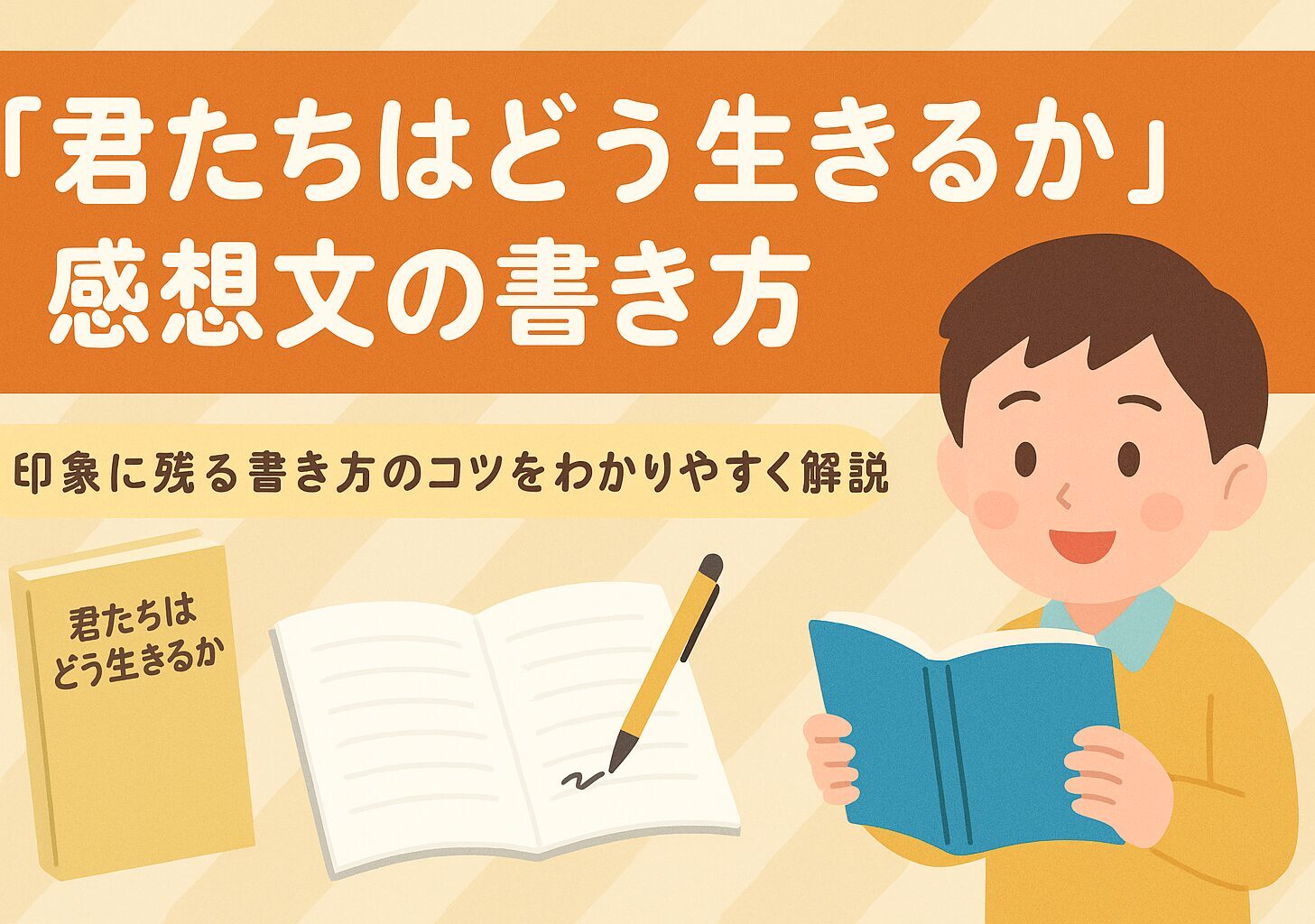読書感想文が苦手でも大丈夫!
本記事では、課題図書の選び方からスラスラ書けるテンプレート、学年別の書き方、感情の書き方のコツ、例文までを徹底解説しています。
読書がもっと楽しくなる感想文の書き方をやさしく紹介していますので、この記事を読み終わる頃には読書感想文に対しての苦手意識も薄れているのではないかと思われます。
初心者でも分かりやすく解説をしているので、是非とも参考にしてみてくださいね!
スポンサーリンク
課題図書選びと読書感想文の書きやすさの関係
初心者でも安心!課題図書を選ぶときのポイント
課題図書を選ぶときに大切なのは、「興味を持てるかどうか」です。たとえ学校から何冊かの候補が出ていたとしても、自分が「これ読んでみたい!」と思える本を選ぶことで、読書の時間が苦ではなくなります。
そして、読書感想文を書くときも内容が頭に入りやすく、スムーズに書けるようになります。選び方のコツとしては、まず「表紙」や「タイトル」で気になる本をチェックしてみましょう。次に、「あらすじ」や「帯コメント」を読んで、ワクワクするかどうかを感じ取ってください。
また、自分が好きなテーマ(冒険、動物、家族、友達、スポーツなど)がある場合は、そのジャンルに近い本を選ぶと良いでしょう。難しそうな本を無理に選ぶ必要はありません。
読書感想文で大事なのは「自分の気持ちを表すこと」ですから、無理して難しい内容に挑戦するより、等身大で読める本を選んだ方がいい結果につながります。
「読みやすさ」と「感想の書きやすさ」は違う?
「読みやすい本」=「感想が書きやすい本」と思いがちですが、実は必ずしもそうとは限りません。サラッと読めてしまう本ほど、感想が短くなってしまって何を書いたらいいかわからなくなるケースもあります。
一方で、少し難しい内容でも、自分にとって印象深い出来事や心が動いた場面があれば、その本について深く考えることができ、感想文は書きやすくなることがあります。
つまり、「読みやすさ」よりも「心が動かされたかどうか」が大事です。たとえば、登場人物の言葉にハッとした、似たような経験を思い出した、考えさせられたテーマがあった、などの体験があると、自然と「書きたいこと」が出てきます。
感想文を書くためには、「本との対話」が必要です。読み終わったあとに、「この本を読んでどう思った?」と自分自身に問いかけてみましょう。
物語・伝記・ノンフィクションの選び方
課題図書にはいくつかのジャンルがあります。たとえば「物語」「伝記」「ノンフィクション(事実に基づいた話)」などです。それぞれのジャンルには特徴があるので、自分に合ったものを選ぶことがポイントです。
物語はフィクション(架空のお話)で、登場人物の成長や冒険を通して、自分の感情と重ね合わせやすいというメリットがあります。特に小学生には人気です。
伝記は、歴史上の人物や実在の人の生涯を描いたもので、偉人の努力や考え方に感動したり、学んだりできる点が魅力ですので中学生にはおすすめです。
ノンフィクションは事実を元にした話で、環境問題、戦争、社会問題など、考えさせられるテーマが多く、より深い感想文が書ける素材となります。
ジャンルを選ぶときは、自分が興味を持てそうなテーマを意識してみてください。たとえば動物が好きなら動物に関するノンフィクションを、歴史が好きなら伝記を選ぶとよいでしょう。
自分の好きなジャンルを知っておこう
「どの本を選んだらいいかわからない」と思ったら、まずは自分が今まで読んできた本や好きな映画、アニメ、ドラマなどを思い出してみましょう。
冒険が好き?感動する話が好き?それともミステリーや謎解きが好き?
読書感想文を書くときは、特に感情移入できる作品ほど、書きやすくなります。
また、自分の好きなジャンルを知っておくことで、課題図書を選ぶときに迷いが減ります。
たとえば、「動物が主人公の話が好き」と気づけば、候補の中からそれに近い本を選べばよいのです。また、親や先生、図書館司書の人に「こういう話が好きなんだけど、似た本ある?」と相談するのもおすすめです。
ジャンルの好みは年齢とともに変わることもありますので、毎年あらためて「今の自分が読みたい本」を選ぶようにしましょう。
図書館・書店・ネットで課題図書を探す方法
課題図書は、学校で紹介されることもありますが、自分でも探す方法を知っておくと便利です。まずは図書館へ行って、子ども向けの本のコーナーや、課題図書コーナーをチェックしてみましょう。
多くの図書館では、夏休み前などに課題図書の特設棚が作られていて、一覧で見ることができます。貸出中の本があっても、予約することが可能です。
書店では、児童書コーナーに課題図書がそろっていることが多く、スタッフに聞けば年齢やテーマ別におすすめを教えてくれます。ネットの場合、「課題図書 小学生」や「読書感想文 おすすめ 本」などで検索すると、出版社や教育関連サイトがリストを公開していたり、レビューも見られたりします。
特にAmazonや楽天ブックスのレビュー欄は参考になります。どこで探すにしても、「選ぶ楽しさ」を忘れずに、本との出会いを大切にしてください。
スポンサーリンク
読書感想文の基本構成を理解しよう
はじめ・なか・おわりで書くってどういうこと?
読書感想文を書くとき、「はじめ・なか・おわりの構成で書きましょう」とよく言われます。これは作文の基本的な構成で、読み手にとってわかりやすい文章にするための大事なルールです。
「はじめ」では、どの本を読んだか、その本を選んだ理由、読んだ前の気持ちなどを簡単に紹介します。たとえば「タイトルにひかれて読んでみた」「友達にすすめられた」「学校で紹介された」など、どんなきっかけでも大丈夫です。
「なか」は感想文のメイン部分です。本を読んで感じたこと、心に残った場面、自分の考え、登場人物への共感などをしっかり書いていきます。ここで大事なのは、「あらすじ」ではなく「自分の気持ち」です。読んだ内容をただ説明するのではなく、「なぜその場面が心に残ったのか」「自分だったらどうするか」などを掘り下げて書くようにしましょう。
最後の「おわり」では、本を読んでどう思ったか、読んだあとの自分の変化や学び、これからの行動につなげるようなまとめを書きます。「今後も本をたくさん読みたい」「この登場人物のように優しくなりたい」など、自分なりの締めくくりができれば、読み手に印象を残すことができます。
この3つのパートを意識して書くことで、感想文の流れがスムーズになり、読みやすく伝わりやすい文章になります。
書きやすくするための「読書中メモ」のすすめ
読書感想文を書くときにおすすめなのが、「読書中にメモを取る」ことです。本を読んでいると、「このセリフ、すごく印象的!」「この場面、なんだか泣きそうになった」「あれ?ここってどういう意味だろう?」といった感情が自然に湧いてきます。それをその場でメモしておくと、あとから感想文を書くときにとても役立ちます。
方法はシンプルで、メモ帳やノートに書き残してもいいですし、付箋を本のページにはさんでおくだけでもOKです。気になるセリフや出来事、心が動いた場面などに印をつけておきましょう。
たとえば、以下のようなポイントを書き残しておくと便利です:
- 心が動いたセリフや文章
- 登場人物の行動で驚いたこと
- 自分だったらどうしたか
- 似たような体験をした思い出
- 読んで感じたこと(うれしい、悲しい、疑問など)
こうしたメモがあると、感想文を書くときに「何を書こうかな」と悩まずにすみますし、自分の考えを深めるヒントにもなります。読書感想文が苦手な人ほど、この読書メモを習慣にすると、大きな助けになりますよ。
「あらすじになってしまう」悩みの解決法
多くの人が読書感想文を書くときに陥るのが、「感想を書いているつもりが、ただのあらすじになってしまう」という問題です。これは読んだ内容を思い出して書いているうちに、物語を順番に説明するだけの文章になってしまうためです。読み手にとっても、「これは感想ではなくて内容の説明だな」と思われてしまい、評価が下がる原因になります。
この問題を解決するには、「自分の気持ち」を中心に書くことが大切です。つまり、「何が起こったか」よりも、「その時どう感じたか」「なぜそう思ったのか」を詳しく書くように意識するのです。
たとえば、ただ「○○は困っていたけど助けられてうれしそうだった」と書くのではなく、「○○が助けられた場面を読んで、ぼくも以前、友達に助けてもらったことを思い出して、心が温かくなった」といったように、自分の体験や感情を織り交ぜてみましょう。
コツは、「なぜ?」「どうして?」を自分に問いかけながら書くことです。「この場面で自分はどう感じた?」「なぜそう思った?」と掘り下げることで、感想らしい文章に変わっていきます。
感情や気づきを書くにはどうすればいい?
感情や気づきを上手に書くためには、自分の心の動きに注目することが大切です。読書中に「ドキドキした」「びっくりした」「うれしかった」「かなしかった」といった感情が出てきたとき、それを言葉で表す練習をしましょう。
ただ「うれしかった」「おもしろかった」だけでは、読み手にはあまり伝わりません。そこに「なぜそう思ったのか」「どの部分でそう感じたのか」を具体的に書くと、ぐっと伝わる文章になります。たとえば、「○○のセリフがやさしくて、登場人物の思いやりを感じて心が温かくなった」といったように、背景を説明しながら感情を伝えるとよいです。
また、気づきについても同様です。本を読んで「こんな考え方があるんだ」「自分の行動を見直そう」と思ったら、それを素直に書いてみましょう。無理に難しいことを書く必要はありません。大事なのは、「自分がどう変わったか」を伝えることです。
自分の感情や気づきを素直に書けるようになると、感想文の内容がぐっと深く、読みごたえのあるものになります。
書いたあとに読み返すべきチェックポイント
読書感想文を書き終えたら、必ず見直しをしましょう。見直しは、ミスを直すだけでなく、文章の流れや伝わり方を整えるためにも大切です。以下のポイントをチェックしてみてください。
- 「はじめ・なか・おわり」の流れになっているか?
- あらすじばかりになっていないか?
- 自分の感情や考えがきちんと書かれているか?
- 読み手に伝わりやすい表現になっているか?
- 同じ言葉を何度も使っていないか?
また、声に出して読んでみると、読みづらい部分やおかしなところに気づきやすくなります。家族や友達に読んでもらって感想を聞くのもおすすめです。「この部分、もっと詳しく書いてみたら?」といったアドバイスがもらえるかもしれません。
読書感想文は、書き終わった後の仕上げがとても大事です。ほんのひと手間加えることで、文章が一段と伝わりやすく、印象的になります。
スポンサーリンク
学年に合った感想文の書き方をマスターする
小学校低学年:感じたことを素直に書こう
小学校低学年のうちは、読書感想文を「上手に書く」ことよりも、「感じたことを素直に表現する」ことが大切です。まだ長い文章を書くのは難しい時期なので、難しく考えすぎず、「おもしろかった」「かなしかった」「びっくりした」といった気持ちを中心に書くようにしましょう。
たとえば、「うさぎのキャラクターががんばっていてすごいと思った」「おかあさんがやさしくて、わたしもそんなふうになりたい」といった、自分の感じたことをそのまま言葉にすればOKです。文章の構成は、「読んだ本のタイトル」「その中で心にのこったところ」「そのときどう思ったか」をシンプルに書くだけでも、立派な感想文になります。
また、家の人といっしょに「どんなところがすきだった?」「どんな気もちになった?」と会話をしながら書くと、気持ちが整理しやすくなります。まだ言葉でうまく表現できないことも多いので、大人が「こんなふうに書けるよ」とアドバイスしながら、一緒に楽しく進めていくことが成功のコツです。
小学校高学年:テーマや作者の意図を考える
小学校高学年になると、ただ「おもしろかった」「かなしかった」だけではなく、「なぜそう思ったのか?」を説明できるようになると、ぐっと内容のレベルが上がります。さらに、物語のテーマや作者が伝えたかったメッセージを考える力も育ってきます。
たとえば、「友だちの大切さを伝えたかったのかな」「家族の支えが主人公の力になっていたと思う」など、自分なりに読み取ったことを言葉にしていくのがポイントです。また、自分の体験と重ね合わせて考えると、より深い感想が書けます。「わたしも友だちとけんかしたことがあったけど、仲直りしたときにうれしかった」など、自分自身の出来事と結びつけて書くと、読み手にも伝わりやすくなります。
また、この学年からは、感想文の構成を意識して書くことも重要です。「はじめ・なか・おわり」の流れに沿って、1つの出来事についてしっかり書くように心がけましょう。
中学生:自分の考えを深めて伝える力をつける
中学生になると、感想文の目的が「読んだ感情を伝える」から「読んで考えたことを論理的に表現する」へと変わってきます。ただの感想だけでなく、自分の考えや意見をしっかり述べることが求められるようになります。
たとえば、ある登場人物の行動に共感した場合でも、「なぜ共感したのか」「その行動は社会にどう影響するか」「現実でも同じようなことがあるか」など、より広い視点で考えることが大切です。また、読んだ本の内容が現代社会の問題とどう関係するかを考えてみると、深い内容になります。
このときに役立つのが「問いかけ」の技術です。「どうしてこの人はこうしたのか?」「自分だったらどうするか?」と、物語を掘り下げる質問を自分にしてみましょう。その答えを文章にしていくことで、独自の視点を持った感想文になります。
さらに、文章構成にも注意しましょう。導入でテーマを示し、中心部分で考えを述べ、最後にまとめと今後の自分の行動につなげる。このように構造的に書くことで、読んだ人に説得力のある感想文になります。
学年が上がると求められる内容はどう変わる?
学年が上がるにつれて、読書感想文に求められる内容も変わっていきます。低学年では「感じたことを素直に書けているか」が評価の中心ですが、高学年や中学生になると、「読み取ったことを自分なりに考え、まとめられているか」が重要になります。
つまり、ただ「たのしかった」「おもしろかった」では不十分になってくるのです。高学年では、「なぜそう思ったのか」「どんな教訓があったのか」を詳しく書けることが求められます。中学生では、感想に加えて「問題提起」や「意見の対比」「自分の意見の理由」など、より論理的な文章力が求められるのです。
たとえば、戦争に関する本を読んだ場合、低学年なら「せんそうはこわいと思った」で十分ですが、中学生なら「なぜ戦争が起きたのか」「今の社会にどんな教訓があるのか」まで考えて書く必要があります。
学年に合ったレベルの内容を意識しながら書くことで、自然と読書感想文の完成度も上がっていきます。
家庭でできるサポートや声かけのコツ
読書感想文は子どもにとってハードルが高い課題のひとつです。親や保護者がサポートすることで、子どもは安心して取り組むことができます。ただし、やってしまいがちなのが「答えを教えること」ですが、これでは子どもの考える力が育ちません。大切なのは、子どもの気づきを引き出す「問いかけ」と「共感」です。
たとえば、「どの場面がいちばん印象にのこった?」「主人公の気持ち、どう思った?」といったオープンな質問をすることで、子どもは自分の感情に気づき、言葉にすることができます。また、否定せずに「そう思ったんだね」と受け止めてあげることが、安心して書く力を伸ばすポイントです。
低学年なら、いっしょに声に出して読んだり、感想を口に出して話したものを大人がメモしてあげるのも有効です。高学年や中学生には、「ここをもう少し詳しく書くともっと伝わるよ」など、書いた文章を見ながら優しくアドバイスしましょう。
無理に「もっとちゃんと書きなさい」と叱るのではなく、「あなたの思ったことを聞かせてね」と寄り添う姿勢が、感想文を書くモチベーションになります。
スポンサーリンク
書きたくなる!読書感想文の工夫テクニック
感情が動いた場面をメインに書いてみよう
読書感想文を書くとき、「どこから書き始めたらいいか分からない…」と悩むことがあります。そんなときは、自分の心が動いた場面を思い出してみましょう。「感動した」「びっくりした」「泣きそうになった」「笑ってしまった」など、どんな感情でもOKです。感情が動いたということは、それだけ印象に残っている証拠なので、そこを中心に書くと自然と文章がまとまりやすくなります。
たとえば、「主人公が家族とけんかして家を飛び出した場面にドキドキした」など、どの部分が印象に残ったかをまずは書き出してみましょう。そして、「なぜドキドキしたのか?」「自分ならどうしたか?」というように考えを深めていくと、感情が文章になり、立派な感想文になります。
この方法の良いところは、「本全体の内容を説明しなくてもいい」という点です。感情を中心に書くので、自然とあらすじではなく、感想らしい文章になります。まずは「心が動いた瞬間」を探して、そこをスタートにすると、感想文がグッと書きやすくなりますよ。
登場人物になったつもりで考えてみる
感想文を書くときに、「登場人物の気持ちがよく分からない」と感じたことはありませんか? そんなときは、登場人物になったつもりで考えてみるのが効果的です。「もし自分がこの人の立場だったら、どうするだろう?」「同じようなことをされたら、どんな気持ちになるかな?」と想像をふくらませてみましょう。
たとえば、主人公が友だちに裏切られてしまったとき、自分が同じ経験をしたことがあれば、そこから感想をふくらませることができます。「私も昔、友だちとけんかしたときに悲しかった。でも後から仲直りできてよかった。だからこの主人公の気持ちがよくわかる」といったように、経験と重ねることで、気持ちに寄り添った文章になります。
このように登場人物の目線で考えることで、「なぜこの人はこうしたのか?」という視点が生まれ、物語の深い部分に気づくことができます。そして、自分の考えや感想も自然と広がっていきます。これは特に中学生におすすめのテクニックですが、小学生でも十分使えますよ。
心に残ったセリフから感想を広げる方法
本を読んでいると、「このセリフ、すごく心に残る!」という一言に出会うことがあります。そんなときは、そのセリフを出発点にして感想文を書くと、とても書きやすくなります。心に残ったセリフには、その本のテーマや登場人物の思いがぎゅっと詰まっていることが多く、自分の考えや感じたことをふくらませるのに最適です。
たとえば、「あきらめなければ、夢はきっとかなう」というセリフが印象に残ったとします。そこから、「この言葉を聞いて、私はピアノの練習をあきらめかけたときのことを思い出した。だけど頑張り続けて発表会に出られたから、このセリフにとても共感した」といったように、自分の体験や考えをつなげて書くことができます。
この方法のポイントは、セリフに共感した理由や、その言葉から自分がどんなことを考えたかを具体的に書くことです。ただ「いい言葉だと思った」だけではもったいないので、自分の心の中に起きた変化や発見をしっかりと書きましょう。
セリフに注目するだけで、感想文がぐっと深く、印象に残るものになります。
同じ本を読んだ友達と話してみよう
読書感想文を書く前に、同じ本を読んだ友達や家族と感想を話し合ってみるのも、とても良い方法です。人によって印象に残る場面が違ったり、考え方が違ったりするので、「そんな見方もあるんだ!」と新たな気づきが得られることがあります。
たとえば、「あの場面で○○が怒ったの、私はちょっとやりすぎだと思ったけど、友達は『それくらい怒って当然だよ』って言ってて、なるほどと思った」など、自分では気づけなかった視点に触れることで、感想がふくらみます。
こうした会話をヒントに、「最初はこう思っていたけど、友達の話を聞いて気持ちが変わった」といった展開も、読書感想文の中で使えます。これは「考えが深まった」ことを示す良い表現になるので、先生からの評価も高くなるポイントです。
感想文は一人で黙々と書くもの、と思いがちですが、人と話して感じたことや考えたことを取り入れることで、より豊かで多面的な文章になります。友達との会話を通して、書く楽しさもきっとアップしますよ。
書き出しやまとめ方に困ったときの対処法
感想文でよくつまずくのが、「書き出し」と「まとめ方」です。「どう始めたらいいかわからない…」「最後は何を書いたらいいの?」という悩みを持つ人はとても多いです。そんなときに役立つのが、テンプレートや定番の表現を知っておくことです。
書き出しでは、まず「どんなきっかけでその本を読んだのか」から始めるのが王道です。「先生にすすめられて読んでみました」「表紙がかわいくて手に取りました」など、自分の素直な気持ちを最初に書けばOKです。その後に「読んでみたら、思ったよりも〇〇だった」というふうに続けると、自然な流れになります。
まとめ方では、「この本を読んで気づいたこと」「今後の自分への影響」「これからどうしたいか」を書くのが基本です。「この本を読んで、思いやりの大切さを学びました。これからはまわりの人にももっとやさしくしたいと思います」といった形で、自分の変化や行動に結びつけると良い印象になります。
どうしても思いつかないときは、ほかの感想文を参考にしたり、例文を読んだりして、書き出しや締めくくりのパターンを学びましょう。慣れてくると、自分の言葉で自然に書けるようになります。
スポンサーリンク
テンプレート&例文で感想文を仕上げよう
感想文の基本テンプレート(コピペOK)
読書感想文を書くときに「構成がわからない」「何を書いたらいいかわからない」という人におすすめなのがテンプレートです。テンプレートに沿って文章を作っていけば、自然と感想文が完成します。以下は、学年を問わず使えるシンプルなテンプレートです。
【読書感想文テンプレート】
①本を選んだ理由
「わたしは○○という本を読みました。この本を選んだのは、□□だったからです。」
②読んでみた感想(印象に残った場面)
「この本を読んで、いちばん心に残ったのは、○○の場面です。そのとき△△という気持ちになりました。」
③理由や自分の体験とつなげる
「なぜなら、□□ということがあったからです。わたしも似たようなことを経験したことがあり、そのときも△△と思いました。」
④気づいたこと・学んだこと
「この本を読んで、○○の大切さに気づきました。また、□□のように行動できる人になりたいと思いました。」
⑤まとめ
「これからは、○○のように行動しようと思います。とても心にのこる1冊でした。」
このテンプレートに、自分の体験や感情を入れるだけで、感想文が形になります。作文が苦手な人は、まずこの流れを使って書いてみることをおすすめします。
小学生向けの例文:物語編・伝記編
小学生向けに、物語と伝記それぞれの例文を紹介します。実際にどんなふうに書いたらよいかイメージがわかるように、シンプルでわかりやすい文で構成しています。
【例文1:物語「つばさをください(仮)」】
わたしは「つばさをください」という本を読みました。この本は、鳥になりたい男の子の話です。わたしがこの本を選んだのは、表紙の絵がきれいで気になったからです。
この本でいちばん心にのこったのは、男の子が高い山にのぼって「つばさがほしい」とさけんだところです。なぜなら、自分の夢をあきらめずにがんばっていたからです。
わたしも前にピアノのれんしゅうがうまくいかなくて、なきたくなったことがあります。でもこの本を読んで、がんばればいつかかなうかもしれないと思いました。
この本を読んで、「あきらめないこと」が大切だとわかりました。これからも、何かをがんばりたいときは、男の子のことを思い出そうと思います。
【例文2:伝記「マザー・テレサ」】
ぼくは「マザー・テレサ」という本を読みました。この本は、世界中の人を助けた女の人の話です。ぼくは、先生にすすめられてこの本を読んでみようと思いました。
いちばん心にのこったのは、マザー・テレサが、びょうきの人やまずしい人のために、じぶんの時間をすべて使っていたところです。ぼくは、そんなふうに人を大切にできるのがすごいと思いました。
ぼくも学校で、友だちがわらわれていたときに、なにも言えなかったことがあります。マザー・テレサのように、ゆうきを出して行動できる人になりたいと思いました。
この本を読んで、やさしさや思いやりの心の大切さがよくわかりました。これからは、まわりの人のことも考えて行動できるようにしたいです。
こうした例文を参考にしながら、自分の言葉でアレンジしていきましょう。
中学生向けの例文:問題提起型・比較型
中学生になると、ただの感想ではなく、自分の意見や考えをしっかり書く力が求められます。ここでは「問題提起型」と「比較型」の2つのスタイルの例文を紹介します。
【例文1:問題提起型(ノンフィクション「未来のための選択(仮)」)】
私は「未来のための選択」という環境問題をテーマにした本を読みました。なぜこの本を選んだかというと、最近ニュースで気候変動の話を聞いて関心を持ったからです。
この本には、プラスチックごみが海の生き物に与える影響が書かれていて、特にカメがストローを飲みこんでしまう場面が印象に残りました。私はその話を読んで、ショックを受けると同時に、自分の生活を見直そうと思いました。
私たちの便利な暮らしが、動物や地球を苦しめているという事実に、もっと目を向けなければならないと思います。プラスチックを減らすために、自分ができることは何かを考えるきっかけになりました。
この本を読んで、環境問題は他人事ではないと強く感じました。日々の選択が未来を変える、という言葉を大切にしたいです。
【例文2:比較型(小説「ぼくときみの交差点(仮)」)】
私は「ぼくときみの交差点」という小説を読んで、前に読んだ「ひまわりの記憶」との共通点を感じました。どちらの物語も、家族を失った子どもの心の成長を描いています。
「ぼくときみの交差点」では、主人公の少年が事故で弟を失い、自分を責め続ける姿が描かれています。対して「ひまわりの記憶」では、祖母との別れから立ち直る少女が主人公です。
どちらの作品も「人は誰かとつながることで前に進める」というメッセージが共通していて、読後に温かい気持ちになりました。私は家族との時間を当たり前に思っていたけれど、もっと大切にしたいと気づかされました。
このように、複数の作品を通してテーマや作者の伝えたいことを比較すると、より深い感想文になります。
どちらのパターンも、自分の考えをしっかりと書き、読者に伝える構成を意識してみましょう。
よくあるNG感想文とその直し方
感想文を書いていると、ついありがちなミスに気づかず書いてしまうことがあります。ここでは、よくあるNGパターンと、それをどう直せばよいかを紹介します。
| NGパターン | 改善ポイント |
|---|---|
| あらすじだけになっている | 感じたこと・考えたことを追加する |
| 「おもしろかった」「かなしかった」だけ | なぜそう思ったかを詳しく書く |
| 書き出しがいきなり内容から始まる | 本を選んだ理由やきっかけを入れる |
| まとめがなく終わってしまう | 本を読んで学んだこと、気づきを入れる |
| 同じ言葉のくり返しが多い | 言い換え表現を使って語彙を広げる |
特に注意したいのが、「あらすじ感想文」になってしまうことです。あらすじは説明文であり、感想文ではありません。自分がどう思ったのか、どんなことを感じたのかを書くことで、読み手にも伝わる文章になります。
また、「いい話だった」「すごいと思った」などの抽象的な言葉だけで終わらせずに、具体的な理由や体験を交えて説明すると、ぐっと説得力が増します。
書いたあとに、自分の文章をチェックする時間をとることで、こうしたNGを防ぐことができます。
最後に読み返すときのチェックリスト
読書感想文が書き終わったら、提出する前に必ず見直しましょう。以下のチェックリストを使えば、どこを直したらよいかが分かりやすくなります。
読書感想文チェックリスト
- 本のタイトルや著者名は書いてあるか?
- 読んだきっかけや理由は明記されているか?
- 感情や考えが具体的に書かれているか?
- あらすじばかりになっていないか?
- 文章の流れ(はじめ・なか・おわり)がスムーズか?
- 同じ言葉を何度も使っていないか?
- 誤字・脱字はないか?
- 文字数・行数の条件を満たしているか?
このチェックリストをもとに読み直せば、先生に伝わりやすい感想文に仕上がります。読み返すことで、自分の成長にも気づけるので、ぜひ時間をとって確認してみましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 読書感想文は何文字くらい書けばいいの?
A. 学校や学年によって異なりますが、小学生は400~800文字程度、中学生は800~1,200文字程度が一般的です。課題として指定されている場合は、文字数の指示をよく確認しましょう。
Q2. あらすじを書いても大丈夫ですか?
A. あらすじは最小限にとどめ、自分の感想や考えを書くことが大切です。読み手にとっては「何を感じたのか」が一番知りたいポイントです。
Q3. 感想文がどうしても書けないときはどうすればいい?
A. まずは印象に残った場面やセリフを思い出してみましょう。そこから「なぜ心に残ったのか」「自分ならどうするか」など、問いかけながら書き進めるのがコツです。テンプレートを使うのもおすすめです。
Q4. 読んだ本が難しくて内容がよくわかりません…
A. それでも大丈夫です!「わからなかった」と感じた部分を書き、その理由や疑問点を考えてみることも立派な感想になります。無理に難しい言葉を使う必要はありません。
Q5. 保護者はどこまで手伝ってもいいの?
A. 答えを教えるのではなく、子どもの気持ちを引き出す「質問」や「対話」でサポートするのが理想的です。たとえば「どこが面白かった?」「そのとき、どう思ったの?」と優しく聞いてあげましょう。
まとめ
読書感想文は、ただ本を読んで内容をまとめるだけの作業ではありません。自分の心がどう動いたか、どんなことを考えたかを言葉にすることで、初めて「感想」としての意味が生まれます。本を選ぶところから始まり、読書の途中での気づき、書き方の工夫、文章の構成、そして仕上げまで、それぞれにちょっとしたコツがあります。
本記事では、小学生から中学生まで幅広い学年に対応した書き方のポイントを紹介し、「書けない…」という悩みを解消するためのアイデアも盛り込みました。テンプレートや例文、チェックリストも活用すれば、誰でも安心して読書感想文に取り組むことができます。
読書を通して得た気づきや成長は、文字にすることでさらに深まります。ぜひこの記事を参考に、あなただけの素敵な感想文を書いてみてください。