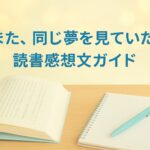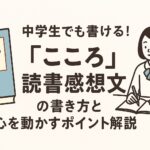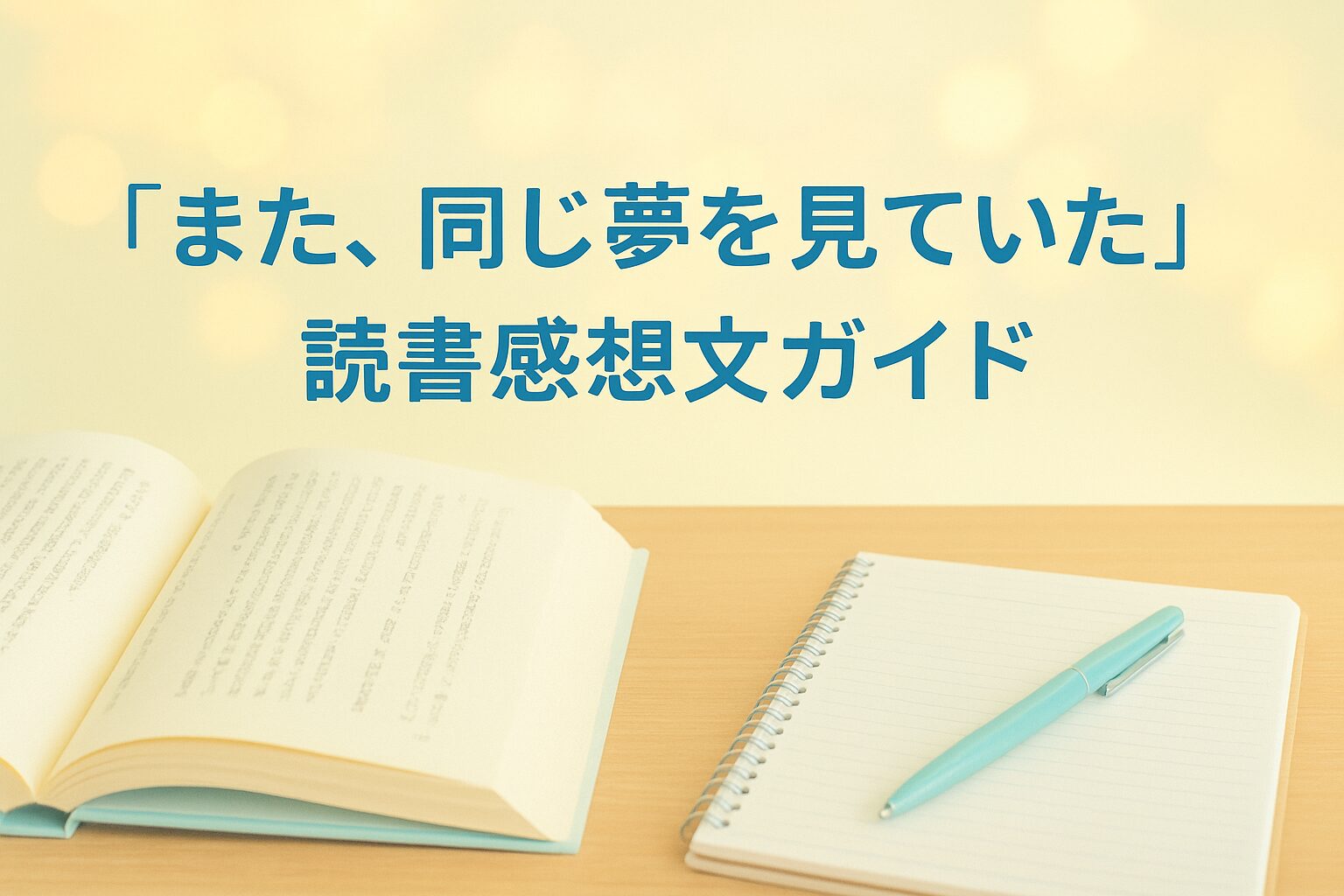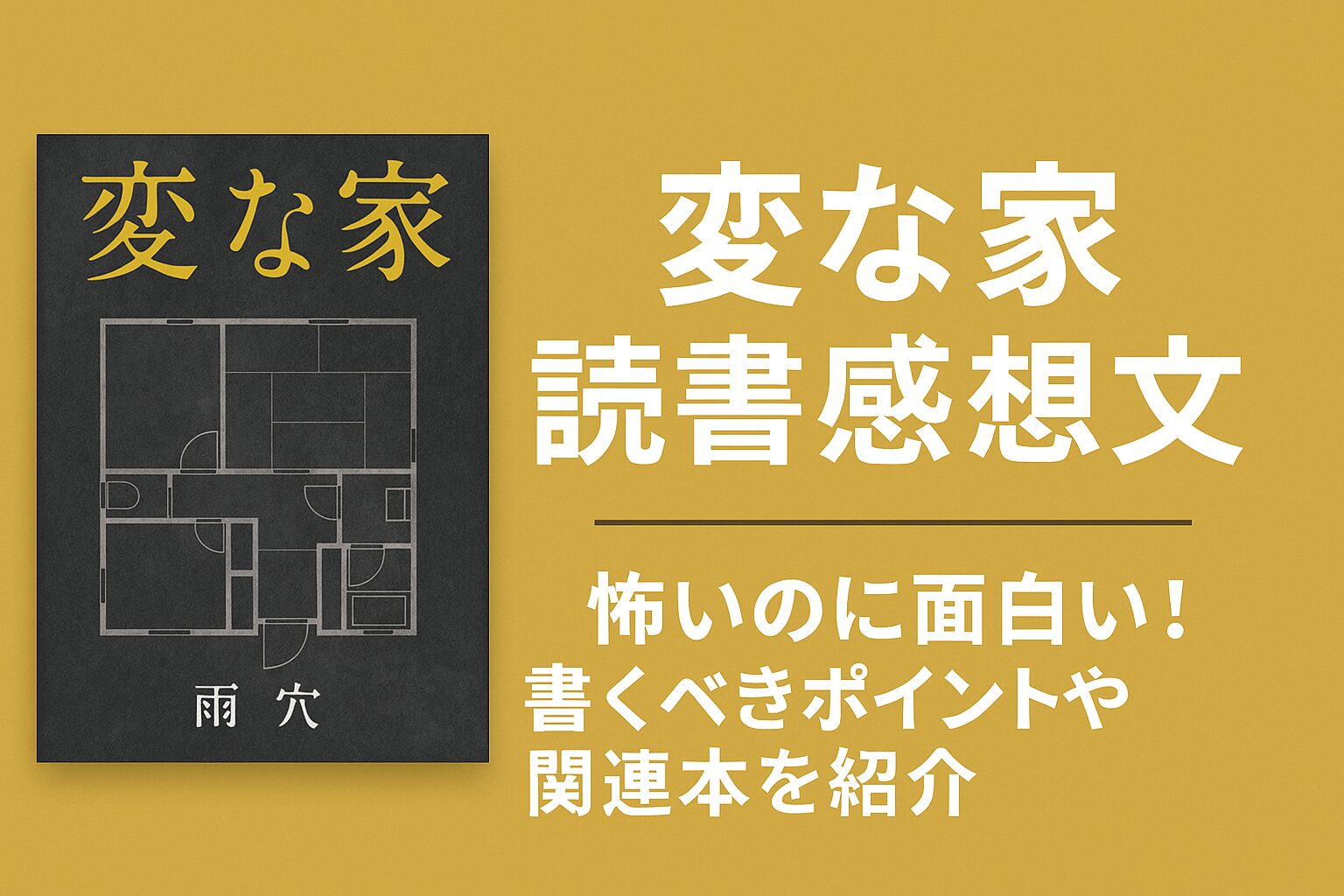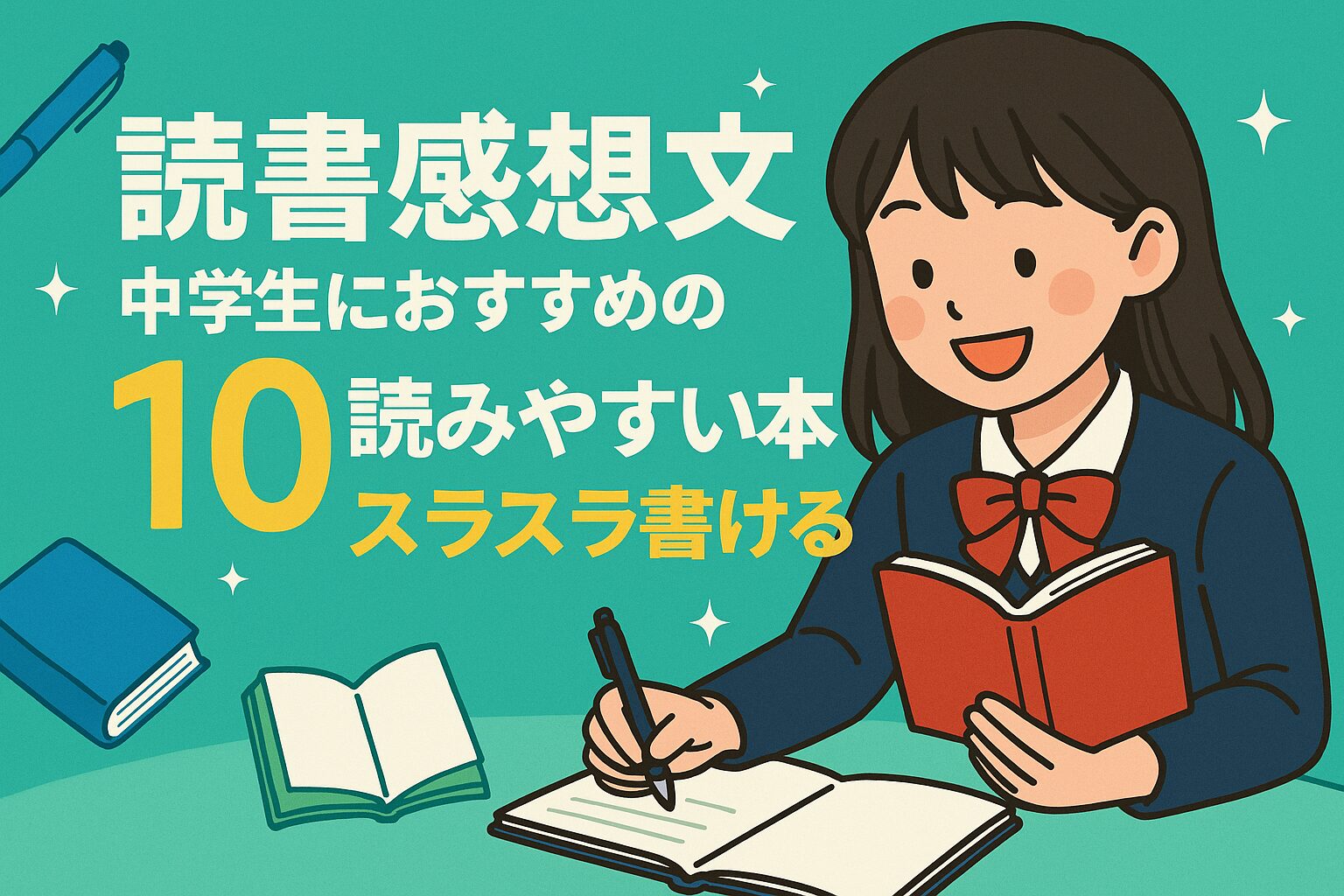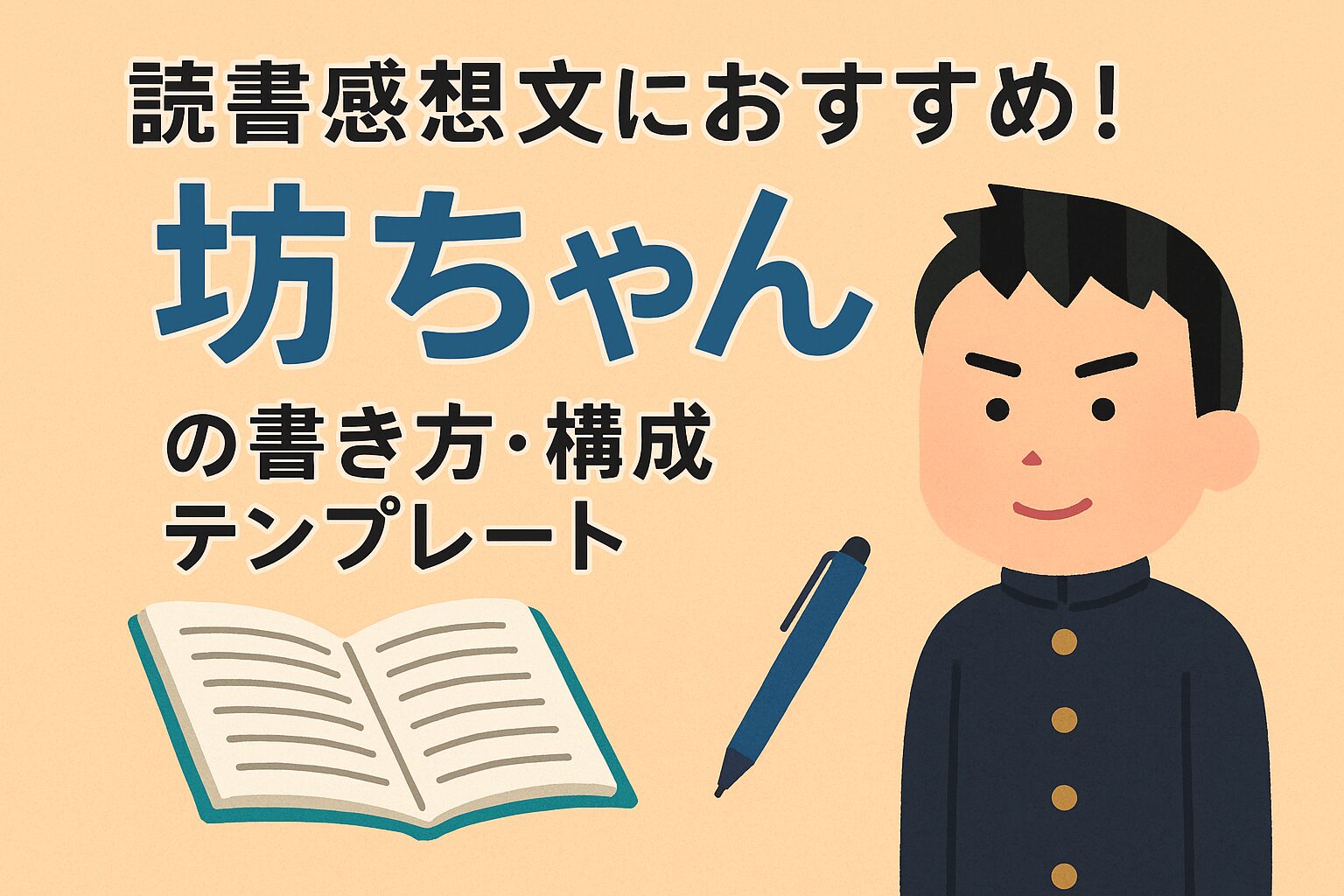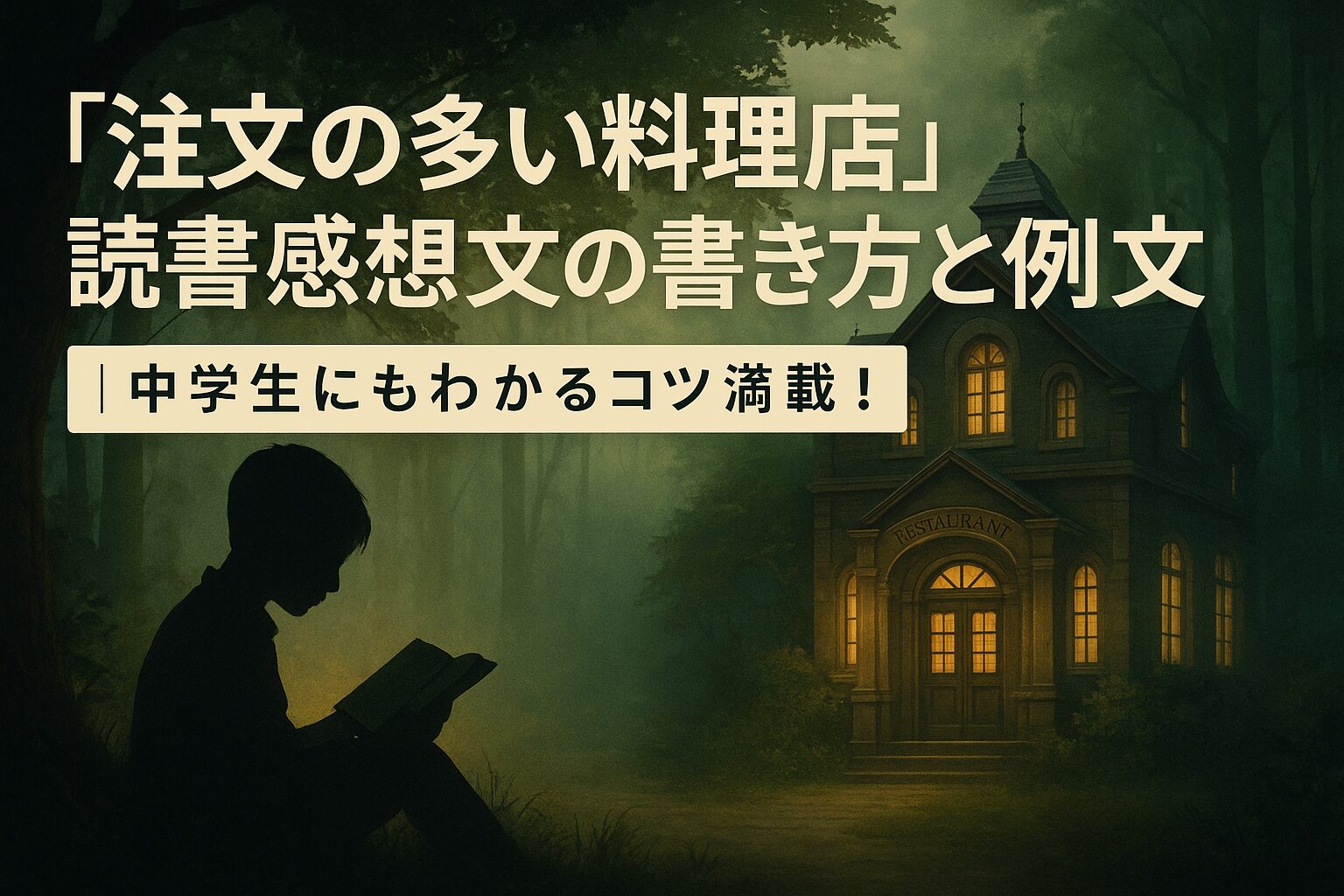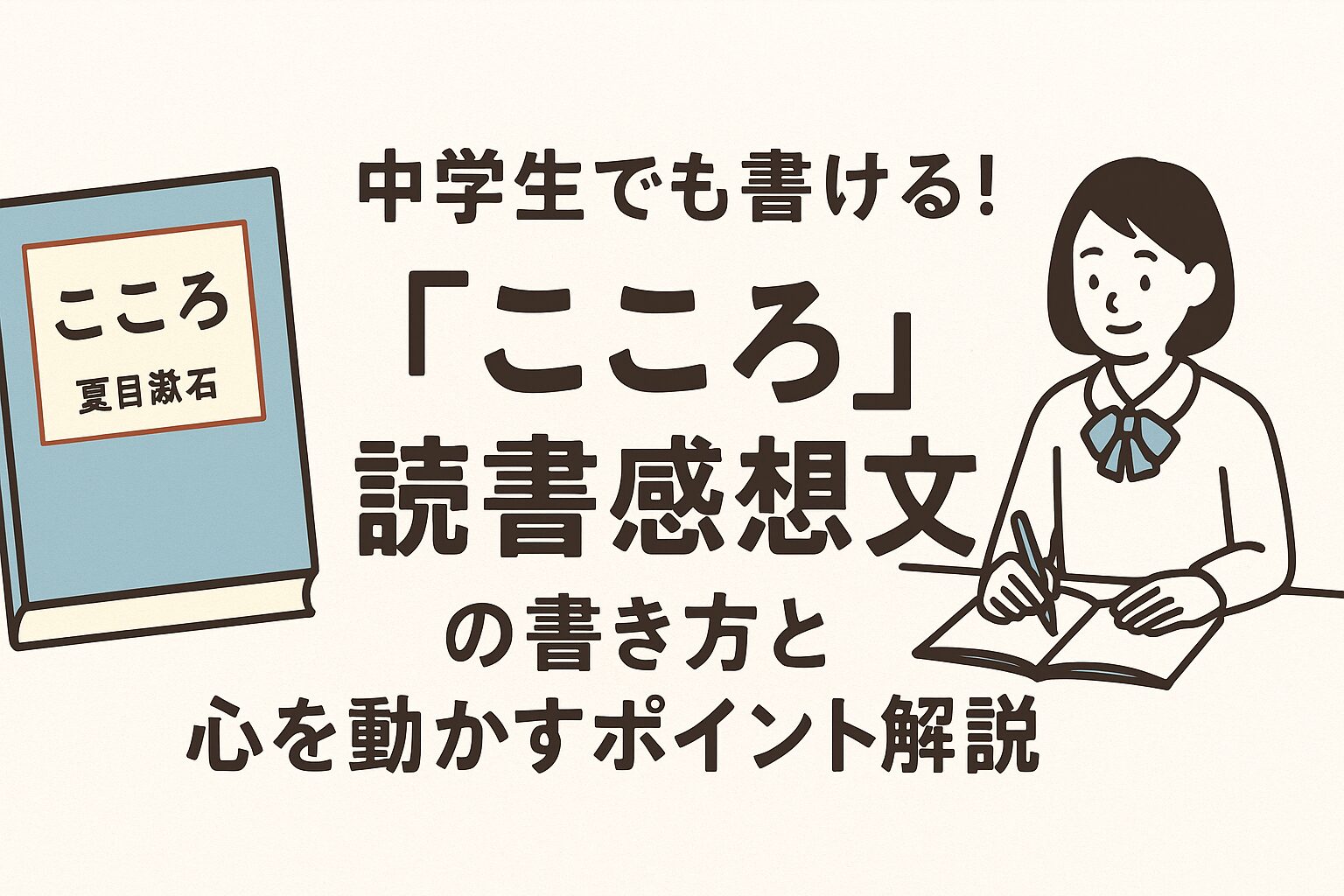「読書感想文、どう書けばいいのか分からない…」
そんなふうに悩んでいませんか?
この記事では、学校の課題やコンクールにも大人気の作品『かがみの孤城』をテーマに、感想文を書くコツと実例をたっぷり紹介します。感動した場面の伝え方や、自分らしい言葉での書き方まで、中学生にもわかりやすく解説しています。
「人と違っていい」「自分を否定しなくていい」という本のメッセージをどう感想文で表現するかが分かれば、きっとあなたの感想文も、読む人の心に届くはずです。
『かがみの孤城』はこちらから購入する事が出来ます。
スポンサーリンク
『かがみの孤城』ってどんな物語?心をつかむあらすじと世界観
舞台は“かがみ”の中!孤城に招かれた7人の子どもたち
『かがみの孤城』は、現代に生きる中学生・こころが主人公のファンタジー小説です。物語の始まりは、ある日突然、部屋の鏡が光り出し、その中に吸い込まれてしまうという不思議な展開。そこに現れたのはおとぎ話のような城と、オオカミのお面をかぶった少女「オオカミさま」。さらに、こころ以外にも6人の見知らぬ子どもたちが同じように鏡の中に呼び出されていました。
この“かがみの中の城”では、1年間だけ特別なルールのもとで過ごすことが許されています。子どもたちは毎日自由に登城できるけれど、17時までに帰らなければならない。そして、城のどこかには「願いが叶う鍵」が隠されていて、それを見つけた一人だけが願いを叶えることができるのです。
この舞台設定がすでにワクワクするポイントですが、実はこの不思議な孤城には、子どもたちそれぞれの“悩み”や“孤独”が深く関わっているのです。ファンタジーのようでありながら、現代の子どもたちが抱えるリアルな問題にしっかり向き合った世界観が、多くの読者を惹きつける大きな魅力になっています。
主人公こころの抱える“学校へ行けない”という悩み
物語の中心人物であるこころは、中学1年生。学校での人間関係に悩み、不登校になってしまった女の子です。親には心配をかけたくない、でも学校には行けない。そんな狭間で苦しみながら、自宅でひっそりと日々を過ごしています。彼女の姿は、今の時代を生きる多くの子どもたちにとって、決して他人事ではありません。
こころのように、表には出さないけれど、心の中に「行き場のない気持ち」を抱えている人は少なくありません。『かがみの孤城』は、そんな心の声を代弁してくれるような作品です。特にこころが感じる「誰にも理解されない」「自分なんていなくてもいいんじゃないか」という気持ちは、多くの読者の共感を呼びます。
こころが鏡の中の城で他の子どもたちと出会い、少しずつ心を開いていく姿は、読む人に勇気を与えてくれます。この「心の回復の物語」が、多くの読書感想文でも取り上げられる大きなポイントです。
一人じゃないと気づかせてくれる仲間たちとの出会い
鏡の城に招かれた子どもたちは、見た目も性格もバラバラです。でも、ひとつだけ共通しているのは「それぞれに学校に行けない理由がある」ということ。表面的には分かりませんが、少しずつ打ち解けていく中で、それぞれが抱えている苦しみや悩みが明らかになっていきます。
こころも最初は他人を信じられず、距離を置いていましたが、同じような立場の仲間たちと触れ合ううちに「自分だけがつらいんじゃない」と思えるようになります。特に印象的なのは、お互いに無理に励まし合うのではなく、ただそっと寄り添ってくれる関係性。これがとてもリアルで温かく、読む人の心を和らげてくれます。
この“一人じゃないと気づくプロセス”は、多くの子どもたちにとって大切なメッセージです。読書感想文を書く際にも、「仲間の存在の大切さ」「理解し合える関係」の部分を掘り下げると、ぐっと深みが出る内容になります。
孤城の秘密が明かされるラストに込められたメッセージ
物語の後半では、「孤城」の本当の目的や、招かれた子どもたちの関係性が明かされていきます。ネタバレになるため詳細は伏せますが、最後の展開は驚きと感動に満ちており、多くの読者が涙するポイントです。特に「なぜこの7人が選ばれたのか」「願いを叶える鍵の意味」などが明かされることで、これまでの出来事がすべてつながり、一気に物語の深みが増します。
ラストには、「人はつながっている」「誰もが誰かの助けになっている」という大きなテーマが込められています。単なるファンタジーではなく、人間の感情や希望、救いを丁寧に描いた結末は、感想文の中でも強い印象を与える部分となります。
読者自身の経験と重ね合わせることで、「自分にとっての大切な人」や「これからどう生きたいか」といった深い気づきにつながるでしょう。
なぜこの物語が幅広い年代に支持されているのか?
『かがみの孤城』は中高生だけでなく、大人にも多く読まれているベストセラーです。その理由は、物語が子どもたちの“現実”を真正面から描いているからです。いじめ、不登校、家庭の問題、将来への不安…。そういったテーマは決して子どもだけのものではなく、誰にでも通じる悩みです。
また、大人が読むことで「子どもの心に寄り添うとはどういうことか」を考えるきっかけにもなります。子どもの感想文としてだけでなく、親や先生にも読んでほしいという声が多いのも納得です。
年齢や立場を問わず共感できるテーマを持ち、読み終えたあとに「誰かにすすめたくなる本」として評価されているのがこの作品の強さです。だからこそ、読書感想文でも多く選ばれているのでしょう。
スポンサーリンク
読書感想文の書き方:『かがみの孤城』で心に響いたポイントとは?
自分と重なる登場人物を見つけよう
読書感想文を書くとき、まず大切なのは「自分の心に響いた登場人物を見つけること」です。『かがみの孤城』には個性の違う7人の子どもたちが登場しますが、その中の誰かに「自分に似てるかも」と感じることがあるはずです。たとえば、学校に行けずに悩むこころ、家族との関係に悩む子、将来のことが不安な子など、それぞれに抱える悩みが違います。
自分の経験と登場人物の気持ちを重ねることで、より深い感想が生まれます。「この子の気持ち、わかる」「私も同じようなことを感じたことがある」といった視点で書くと、読んだ人にも共感されやすい内容になります。
たとえば「私はこころのように、学校に行きたくなかった時期がありました」というように、自分のエピソードを取り入れることで、感想文に“あなたらしさ”が生まれます。感動した部分を書く前に、まずは「誰に共感したか」を明確にすると、書きやすくなります。
共感した場面を選び、具体的に書くコツ
登場人物を選んだら、次は「どの場面が心に残ったか」を思い出してみましょう。『かがみの孤城』は感動的なシーンがたくさんありますが、全部を書こうとせず、1つか2つに絞ることが大切です。たとえば、こころが仲間に本音を打ち明ける場面や、オオカミさまが語るラストの真実など、自分が特に心を動かされた場面を選びましょう。
そして、その場面で自分が「なぜ心を動かされたのか」をしっかり言葉にすることがポイントです。単に「感動しました」だけではなく、「そのセリフを聞いて、自分も涙が出ました。なぜなら…」と、自分の気持ちを深く掘り下げていくと、読み応えのある感想文になります。
また、場面を説明するときは、物語を知らない人にも伝わるように「誰が、いつ、どこで、何をしたか」を簡単に書いてから、自分の感想を加えると、流れがスムーズになります。
感動したセリフやシーンを引用してみよう
読書感想文をより印象的にするためにおすすめなのが、「心に残ったセリフや文章」を実際に本文から引用することです。たとえば、こころが「もう大丈夫。私は一人じゃない」と感じる場面のセリフや、仲間との約束の言葉など、自分が読んで「グッときた」フレーズを取り上げてみましょう。
引用するときは、ただ書くだけでなく、そのセリフがどんな意味を持っていたのか、自分にとってどう響いたのかをしっかり説明することが大切です。「この言葉を読んで、私は自分も誰かの力になりたいと思いました」というように、自分の気づきにつなげると、説得力のある感想になります。
引用のルールとしては、文章の前後に「 」や『 』をつけて、原文そのままを書くようにしましょう。多くても1〜2か所程度の引用にとどめるのが読みやすくするコツです。
読み終えて自分の考え方がどう変わったかを書く
感想文でいちばん大事なのは、「この本を読んで自分がどう変わったか、何を感じたか」を書く部分です。『かがみの孤城』を読むことで、「自分の悩みは一人だけのものじゃない」と気づいたり、「人を信じることの大切さ」に気づいたりした人も多いでしょう。
「読む前は、学校に行けない子は弱いと思っていたけれど、この本を読んで考え方が変わった」など、自分の中での“変化”を正直に伝えることが、感想文をぐっと深くしてくれます。
変化が小さなことでも大丈夫です。「仲間っていいなと思った」「人をもっと大切にしたいと思った」といった素直な気持ちが、読む人に届きます。本を通して“自分の気持ち”がどう動いたか、それをわかりやすく言葉にしましょう。
自分だけの視点で「この本から学んだこと」を伝える
最後に、自分なりに『かがみの孤城』から学んだことをまとめてみましょう。他の人と同じような感想でも、自分の言葉で書くことで、それが“自分だけの視点”になります。
たとえば「私はこの本を読んで、目に見えない苦しみを持っている人にやさしくしたいと思いました」というように、読んだあとに行動や考え方がどう変わるかを具体的に書くと、感想文の締めくくりにふさわしい内容になります。
自分にとって、この本の一番のメッセージは何だったのかを考えて、「だから私はこうしたい」という一言で終えると、読書感想文としてとても印象的です。
スポンサーリンク
実際に書いてみた!中学生向け読書感想文の例文公開
例文①:主人公こころに共感した読書感想文
『かがみの孤城』を読んで、私は主人公のこころに強く共感しました。こころは学校でつらい経験をし、不登校になります。私も中学に入ってから、友だちとうまくいかず、教室に行くのがこわくなったことがありました。だからこそ、こころが学校に行けずに悩んでいる気持ちがとてもよく分かりました。
特に印象に残ったのは、こころが「誰にも分かってもらえない」と思っていたとき、鏡の中の城で出会った仲間たちと少しずつ心を開いていくところです。自分だけが苦しんでいると思っていたけど、実は他の人も同じように悩んでいる。そんなふうに気づけるのは、とても大切なことだと思いました。
私も、勇気を出して友だちに自分の気持ちを話してみたことで、少しだけ楽になれたことがあります。こころのように、自分の殻を破るのは簡単ではないけれど、心を開くことで新しい世界が広がることをこの本から学びました。感想文としてだけでなく、自分の人生にとっても大事な気づきをくれた本です。
例文②:仲間との絆をテーマにした感想文
『かがみの孤城』を読んで、私は「仲間の大切さ」について深く考えました。物語の中で、7人の子どもたちは最初はお互いによそよそしい関係でしたが、少しずつ打ち解けていきます。学校に行けないという共通点を持つ彼らが、孤城という特別な場所で信頼関係を築いていく様子に心を打たれました。
私はこれまで、「一人でも平気」と思っていたけれど、この本を読んで「人とつながることの力強さ」を感じました。特に印象に残ったのは、リオンという少年が他の子どもたちをさりげなく気づかいながら接している場面です。彼のやさしさや、みんなを守ろうとする姿勢に胸が熱くなりました。
仲間って、ただ仲がいいだけではなく、お互いを理解し、支え合える存在なんだと思います。この物語を読んで、私も誰かの力になれるような人になりたいと思いました。つらいときに支えてくれる仲間がいること、それがどれほど心強いことかを、この本は教えてくれました。
例文③:いじめ・不登校を通して考えた自分の気持ち
この本の中で描かれるいじめや不登校の問題は、とてもリアルで、他人事とは思えませんでした。私は今まで、教室で何か困っている子がいても、どうしていいか分からず、声をかけることができませんでした。でも、『かがみの孤城』を読んで、「その子の心の中にはどんな気持ちがあるのか」と考えるようになりました。
特にこころが、母親に心配をかけたくないと思いながらも、本当の気持ちを言えない場面が心に残りました。私自身も、親に心配をかけたくなくて、つらいことがあっても「大丈夫」と言ってしまうことがあります。その気持ちにすごく共感しました。
この本を通して、私は「自分の気持ちを素直に話すことの大切さ」や、「見えないつらさがあることを知っておくことの大事さ」を学びました。これからは、まわりで困っている子がいたら、少しでも声をかけたり、そっと寄り添えたりできるようになりたいと思いました。
例文④:ファンタジーの中にある現実的な悩みへの気づき
『かがみの孤城』は一見ファンタジーのように見えますが、その中にはとても現実的な悩みが描かれています。学校に行けない、友だちと合わない、自分の居場所がない…。そんな悩みは、多くの人が経験することかもしれません。
私も、何となく学校に居場所がないと感じたことがあって、「このままでいいのかな」と思ったことがあります。だからこそ、鏡の中の世界でこころたちが安心して過ごせる時間をとても羨ましく思いました。同時に、「自分も誰かと心を通わせられる場所を作りたい」と思うようになりました。
ファンタジーの世界を通して、現実の自分の悩みと向き合うことができる。この本には、そんな不思議な力があります。物語の中の孤城は、まるで読者にとっての“心の避難所”のようにも感じられました。読むことで前向きな気持ちになれる、そんな一冊です。
例文⑤:最後の真実に涙した感想のまとめ方
物語の最後、鏡の城の本当の目的と、子どもたちがなぜ選ばれたのかが明かされる場面に、私は思わず涙してしまいました。これまでの出来事がすべてつながり、「ああ、そういうことだったのか」と驚くと同時に、深い感動がありました。
私は特に、「みんなが誰かの未来を救うためにそこにいた」という真実に胸を打たれました。普段の生活では、自分が誰かの力になっているなんて思わないことが多いけれど、この本は「人は誰かの希望になれる」ということを教えてくれました。
感想文のまとめとして、「読後に何を感じたか」を自分の言葉でしっかり書くことが大切だと感じました。私はこの本を読んで、自分自身ももっと人の気持ちに気づけるようになりたい、そしてつらい時でも前を向いて進んでいきたいと思いました。このように、最後の感想を未来への前向きな思いで締めくくると、読書感想文としての印象もとても良くなると思います。
スポンサーリンク
書きやすくするための準備とコツ:感想文をスムーズに仕上げる方法
読みながらメモを取っておくのが成功のカギ
読書感想文を書くうえで、読みながらの「メモ取り」はとても重要です。『かがみの孤城』のように登場人物が多く、ストーリーに深みのある作品では、あとから「あの場面、なんて言ってたっけ?」と思い出すのが大変になります。だからこそ、感動した場面や気になるセリフが出てきたときに、簡単にメモしておくことで、あとで感想文を書くときに役立ちます。
メモの仕方は、付箋を貼ってもいいですし、ノートやスマホに残してもOKです。例えば「こころがはじめて本音を言ったシーン、感動!」とか「オオカミさまの言葉にぐっときた」など、自分の感じたことを一言でもいいので残しておきましょう。
あとから振り返るとき、そのメモが感想文のネタになります。最初から完璧に書こうとするのではなく、思ったことを素直に書き留めることが大切です。
書く前に「何を伝えたいか」をはっきりさせよう
感想文を書く前に、「この感想文で一番伝えたいことは何か?」を決めておくと、文章がとても書きやすくなります。たとえば、「こころの成長に感動した」とか「仲間の存在の大切さを知った」といったテーマを1つに絞ると、全体の流れがブレにくくなります。
いろいろ書きたいことがあっても、無理に全部入れようとすると感想文がまとまらなくなってしまいます。だからこそ、「この本から一番学んだこと」を中心にして、そのテーマに合うエピソードや自分の気持ちを肉付けしていくイメージで書くとスムーズです。
テーマが決まると、読む人にも「この子はこう感じたんだな」という印象がしっかり残ります。作文でも感想文でも、中心となる“思い”があると、読みやすく伝わりやすい文章になります。
原稿用紙の構成を意識して段落を作る
読書感想文を提出するとき、多くの学校では原稿用紙に書くことが求められます。そこで大切になるのが「段落の構成」です。だいたい以下のような流れを意識すると、読みやすくバランスの取れた文章になります。
- 本を選んだ理由(導入)
- 心に残った登場人物や場面の紹介
- その場面で自分がどう感じたか、なぜそう感じたか
- 本を読んで自分の考えがどう変わったか、学んだこと
- 最後に、読後のまとめやこれからの自分について
このような流れで書くと、読み手にとっても分かりやすく、話の筋が通った印象になります。また、段落ごとに1つのテーマを意識して書くことで、自然と文章にメリハリがつきます。
文章の途中で一度止まって、「今、何を書いているんだっけ?」と振り返る習慣をつけると、段落構成もうまく整理できるようになります。
難しい言葉より“自分の言葉”で素直に書く
読書感想文でよくやってしまいがちなのが、「立派な言葉を使おうとすること」です。でも、それよりも大切なのは、「自分の言葉で、感じたことを素直に書くこと」です。たとえば、「感動しました」という言葉ひとつでも、「どこで」「どうして」「どんなふうに」と説明すれば、それだけで立派な文章になります。
難しい言い回しや漢字を使うよりも、自分が日常で使っている言葉で書いたほうが、読み手には気持ちがストレートに伝わります。「うまく書かなきゃ」と思うと筆が止まってしまうので、まずは「誰かに話すつもり」で書いてみるとよいでしょう。
『かがみの孤城』のように感情がゆさぶられる作品なら、自分の気持ちも自然と出てくるはずです。そうした“心の声”を言葉にすることが、読書感想文の魅力になります。
読んだ人が共感できるような言い回しを心がけよう
感想文は、「自分だけが分かる」文章ではなく、「読んだ人も共感できる」ことが大切です。そのためにおすすめなのが、「きっと〜だと思います」「私と同じように感じる人がいると思います」など、読者を意識した言い回しを取り入れることです。
また、感想を語るときも「私が思ったのは…」と自分視点で書くと、読み手にも納得感が生まれます。例えば、「この本は面白かった」だけではなく、「私はこの本を読んで、心の中に希望が灯ったように感じました」と書くと、より伝わりやすくなります。
さらに、例え話を使うのも効果的です。「こころの気持ちは、まるで冬の空のように重く感じた」というように、自分の感じたことをイメージで表現すると、読み手の心にも響きます。言い方ひとつで感想文の印象は大きく変わるので、できるだけ自分の気持ちを、相手に伝わる言葉で表現することを意識しましょう。
スポンサーリンク
読書感想文で伝えたいこと:『かがみの孤城』が教えてくれる大切なこと
「自分を否定しなくていい」と教えてくれる物語
『かがみの孤城』を読んで、一番心に残ったのは「どんな自分でも受け入れていい」というメッセージでした。主人公のこころをはじめ、鏡の城に集められた7人の子どもたちは、それぞれ何かしらの悩みやトラウマを抱えています。そんな中で彼らは、自分の過去や弱さを少しずつ受け入れていくのです。
学校に行けなかったり、人と関わるのが苦手だったり、自信が持てなかったり…そんな自分を責めてしまう気持ちは誰にでもあります。けれどこの物語は、そんな気持ちを「そのままでいいんだよ」と優しく包み込んでくれます。登場人物たちが変わっていく姿を見ることで、読んでいる私たちも「私も自分を許していいんだ」と思えるようになります。
感想文では、こうした「心が軽くなった体験」を正直に書くことが大切です。本から受け取ったメッセージが、あなた自身の言葉で語られることで、読み手にも深く伝わります。
他人と違っても大丈夫、というメッセージ
『かがみの孤城』では、「みんな違って当たり前」という価値観がしっかり描かれています。7人の子どもたちは性格も見た目もバラバラで、考え方も違います。でも、その違いを認め合い、理解し合おうとする姿がとても温かく、読んでいて励まされます。
現代の学校や社会では、「人と同じでなければならない」と感じる場面が多くあります。でも、この物語は、「違うからこそ面白い」「違いを大切にしていい」ということを、やさしく教えてくれます。
自分と誰かを比べて落ち込んだ経験がある人も多いはずです。だからこそ、感想文の中で「私はこの物語を読んで、他人と違ってもいいんだと思えた」と書くことは、多くの人の共感を呼びます。そして、それは自分自身にとっても、とても大切な気づきになるはずです。
親や先生にこそ読んでほしい理由
『かがみの孤城』は、子ども向けの物語に見えますが、実は大人にこそ読んでほしい作品です。なぜなら、この本には「子どもたちの心の叫び」がたくさん込められているからです。学校や家庭でのプレッシャー、人間関係のストレス、将来への不安…。大人には見えにくいけれど、子どもたちは日々さまざまな悩みを抱えています。
この物語を通して、大人が「子どもはこんなふうに感じているんだ」と気づくことで、もっとやさしい社会になるかもしれません。感想文の中で「私の親にも読んでほしい」「先生が読めば、もっと分かってもらえるかもしれない」と書けば、作品のメッセージの広がりを強く伝えることができます。
子どもの心に寄り添うことの大切さを、大人に伝える手段としても、この本はとても有効な一冊です。
子どもたちの心の叫びに気づくきっかけになる
『かがみの孤城』に登場する子どもたちは、誰もが「助けて」と大声で言えるわけではありません。むしろ、誰にも気づかれずに苦しんでいる姿が多く描かれています。その姿はまさに、現実の学校や社会にも当てはまるものです。
読書感想文を書くことは、こうした“声にならない声”に気づくためのきっかけになります。自分が今まで気づかなかった周りの人の悩み、見ようとしてこなかった他人の痛みに目を向けることができるようになります。
感想文の中で「私も、誰かが苦しんでいたら気づける人になりたい」と書くことで、読む人にも考えるきっかけを与えられます。本を読んで得た気づきが、自分自身の成長につながることは、感想文の大きなテーマの一つです。
読後に感じた“希望”をどう言葉にするか?
物語の終盤で明かされる真実や、登場人物たちが未来へ向かって歩き出す姿からは、大きな“希望”が伝わってきます。たとえ今がどんなに苦しくても、つながりを信じていれば、きっと前に進める――このメッセージは、多くの読者に勇気を与えてくれるはずです。
感想文では、この“希望”をどう感じたかを、自分の言葉で表現することが大切です。「読み終えたとき、心が明るくなった」「これから少しずつでも前を向こうと思った」といった具体的な感想を書くと、読書体験のすばらしさがより伝わります。
感動で終わるだけではなく、その感動が「自分を変える力」になったことを言葉にできれば、読書感想文としても高い評価が期待できるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 『かがみの孤城』の読書感想文は小学生・中学生・高校生どの年代向け?
A. どの年代でも書くことができますが、特に中学生におすすめです。作品の主人公が中学1年生であり、不登校やいじめといったリアルな悩みが描かれているため、同世代の生徒が共感しやすい内容になっています。ただし、感動の深さや読後の気づきは高校生や大人にも響くため、学年を問わず使えます。
Q2. 読書感想文で『かがみの孤城』を選ぶのはあり?評価されやすい?
A. とても評価されやすい作品です。テーマが現代的で深く、共感しやすい登場人物や感動的な結末もあり、感想を広げやすいからです。実際に全国の読書感想文コンクールでも多く取り上げられており、「心の変化」や「学び」を表現しやすい作品として人気です。
Q3. 『かがみの孤城』のどのシーンを書けば感想文が深くなる?
A. 自分の心が動いたシーンを選ぶのがベストですが、以下のような場面が感想文におすすめです:
- こころが初めて仲間に心を開くシーン
- 鏡の城のルールが明かされる場面
- ラストの“真実”が明らかになる感動の結末
これらの場面は物語のテーマが濃く表れており、感想や学びを深めやすいです。
Q4. 読書感想文にオススメの構成は?
A. 以下のような5段階構成がおすすめです:
- 本を選んだ理由
- 印象に残った場面や人物
- そのシーンで自分がどう感じたか
- 自分自身の経験とのつながりや気づき
- これからの自分にどう活かしたいか(まとめ)
この構成に沿って書けば、感情と論理がバランスよく伝わります。
Q5. 感想文に「ネタバレ」は書いても大丈夫?
A. 基本的には問題ありません。ただし、読んでいない人にも伝わるように「どういう場面か」を分かりやすく説明しながら、自分の感じたことをメインに書くことが大切です。ラストの大きなネタバレを書く場合は、「ここが一番心を動かされた」として、自分の言葉で感動を丁寧に表現するようにしましょう。
まとめ
『かがみの孤城』は、ただのファンタジー小説ではありません。そこには、現代を生きる子どもたちの悩み、苦しみ、そして希望がぎっしりと詰まっています。不登校、いじめ、居場所のなさといった重たいテーマを、やさしく、でも確かなメッセージとして届けてくれるこの作品は、読書感想文の題材としてもぴったりです。
感想文を書くときには、登場人物との共感ポイントや感動した場面、自分の気持ちの変化を中心に構成することで、読んだ人の心に届く文章になります。そして何より大切なのは、うまく書こうとすることではなく、自分の言葉で「感じたこと」を素直に伝えること。
このブログ記事が、あなたの感想文づくりのヒントや勇気になることを願っています。
『かがみの孤城』の感想文を書こうと思っている方はこちらから購入する事が出来ます。