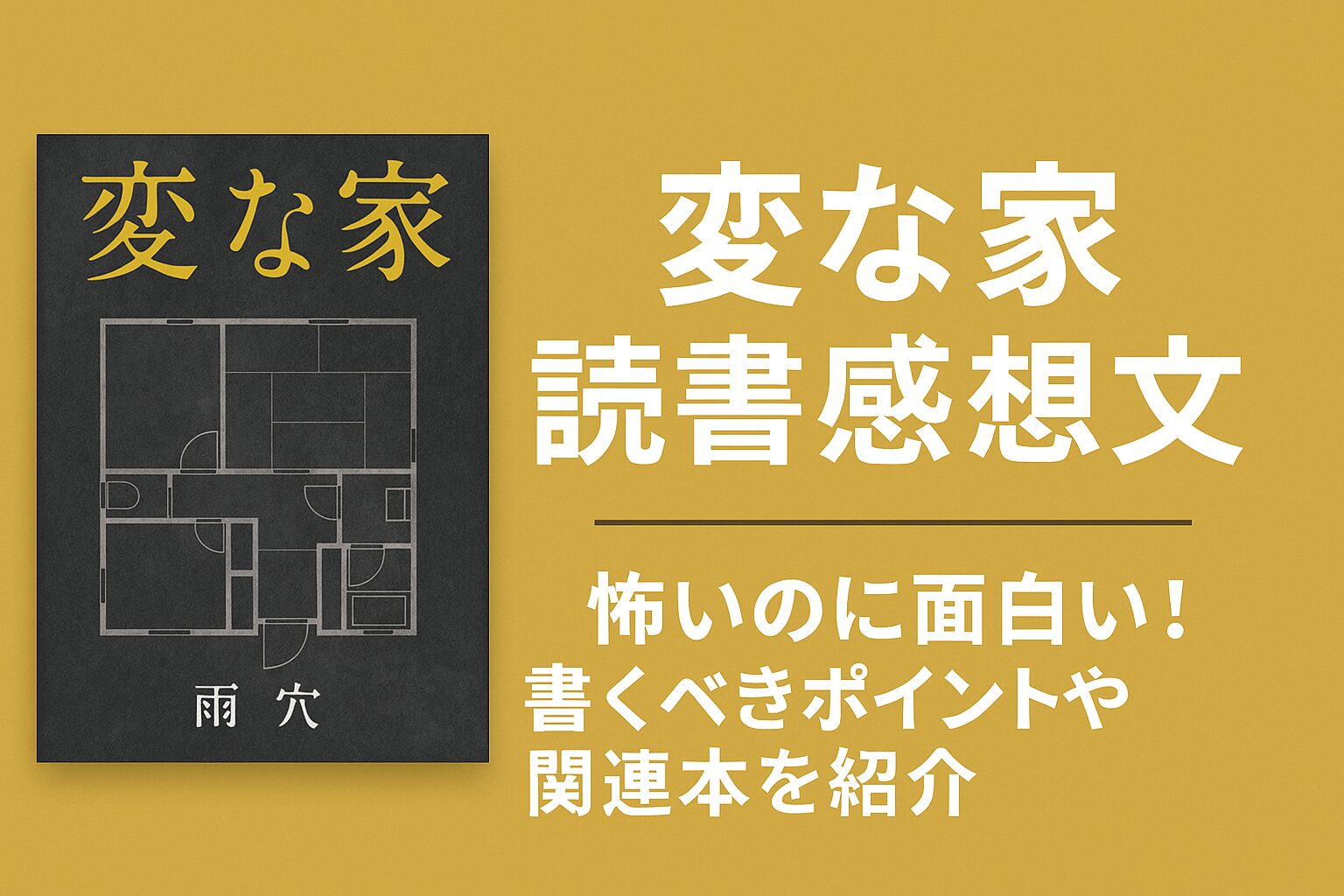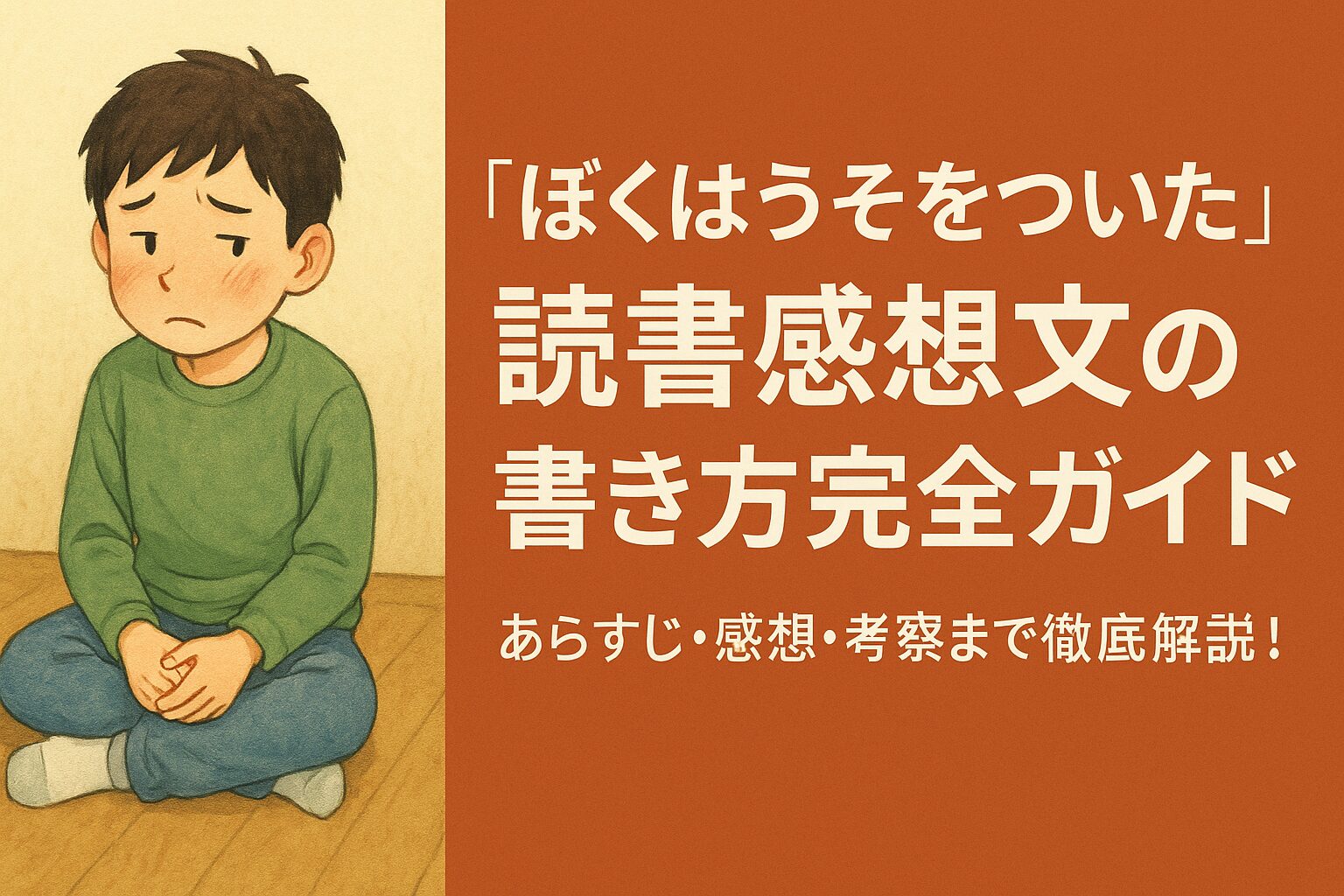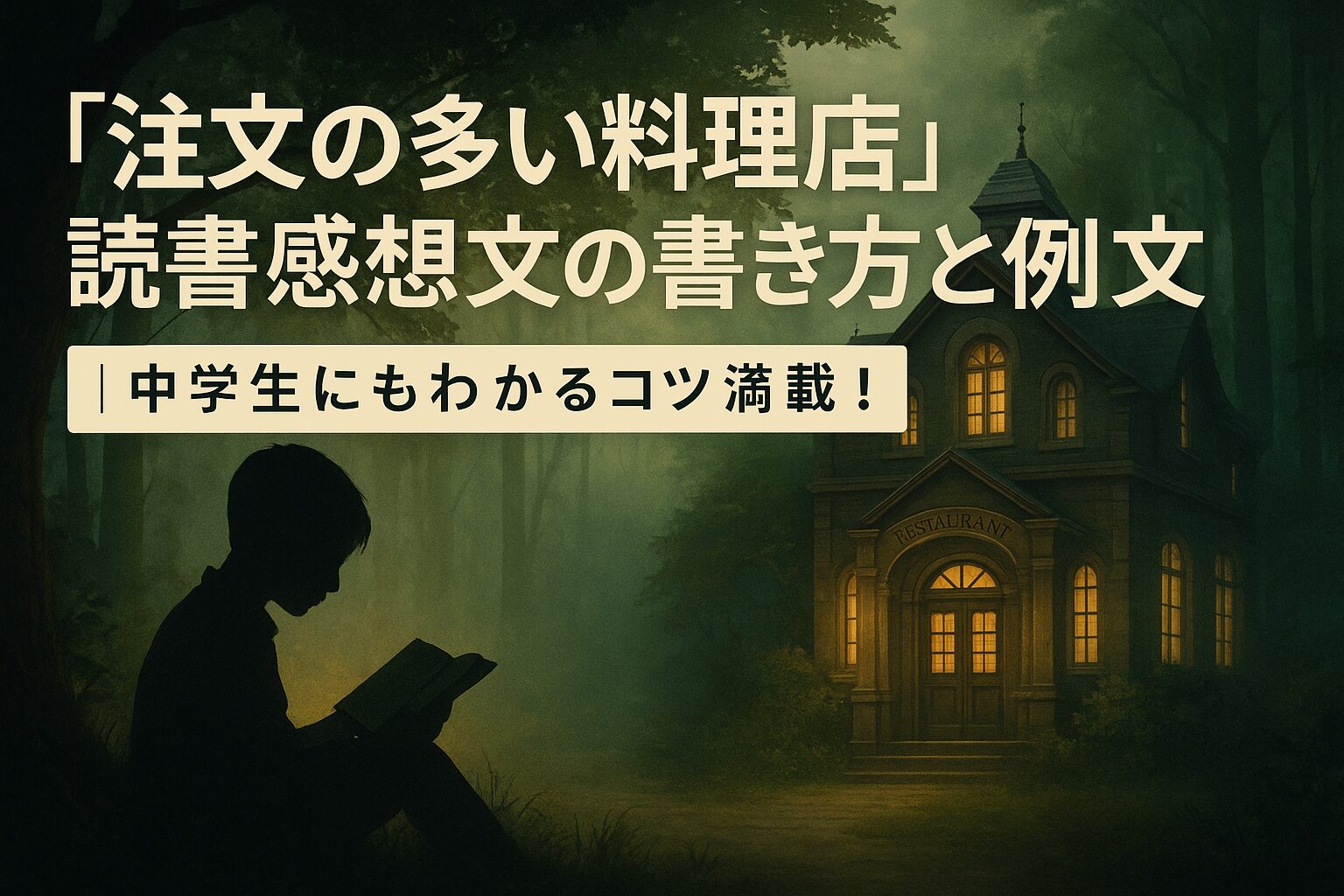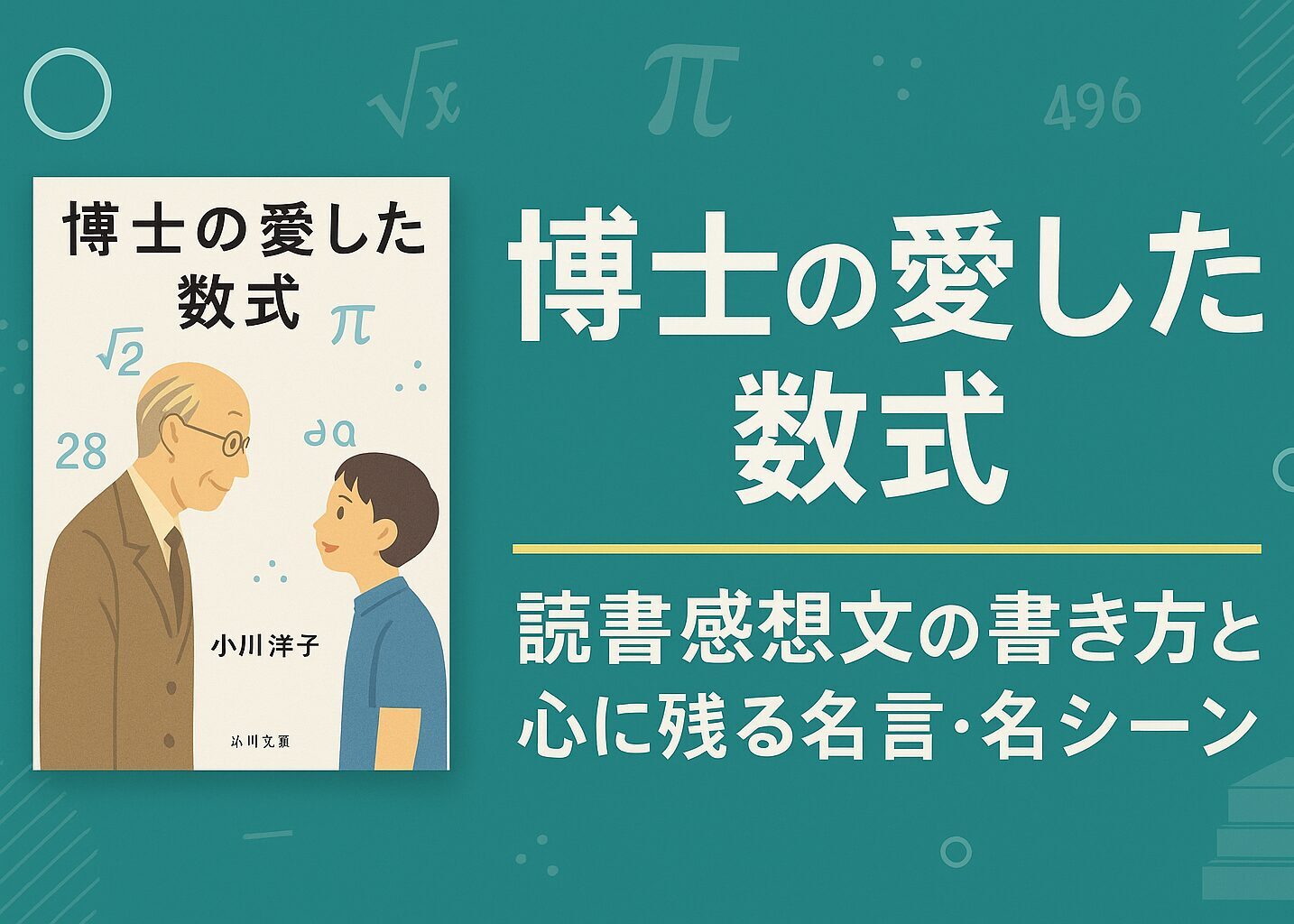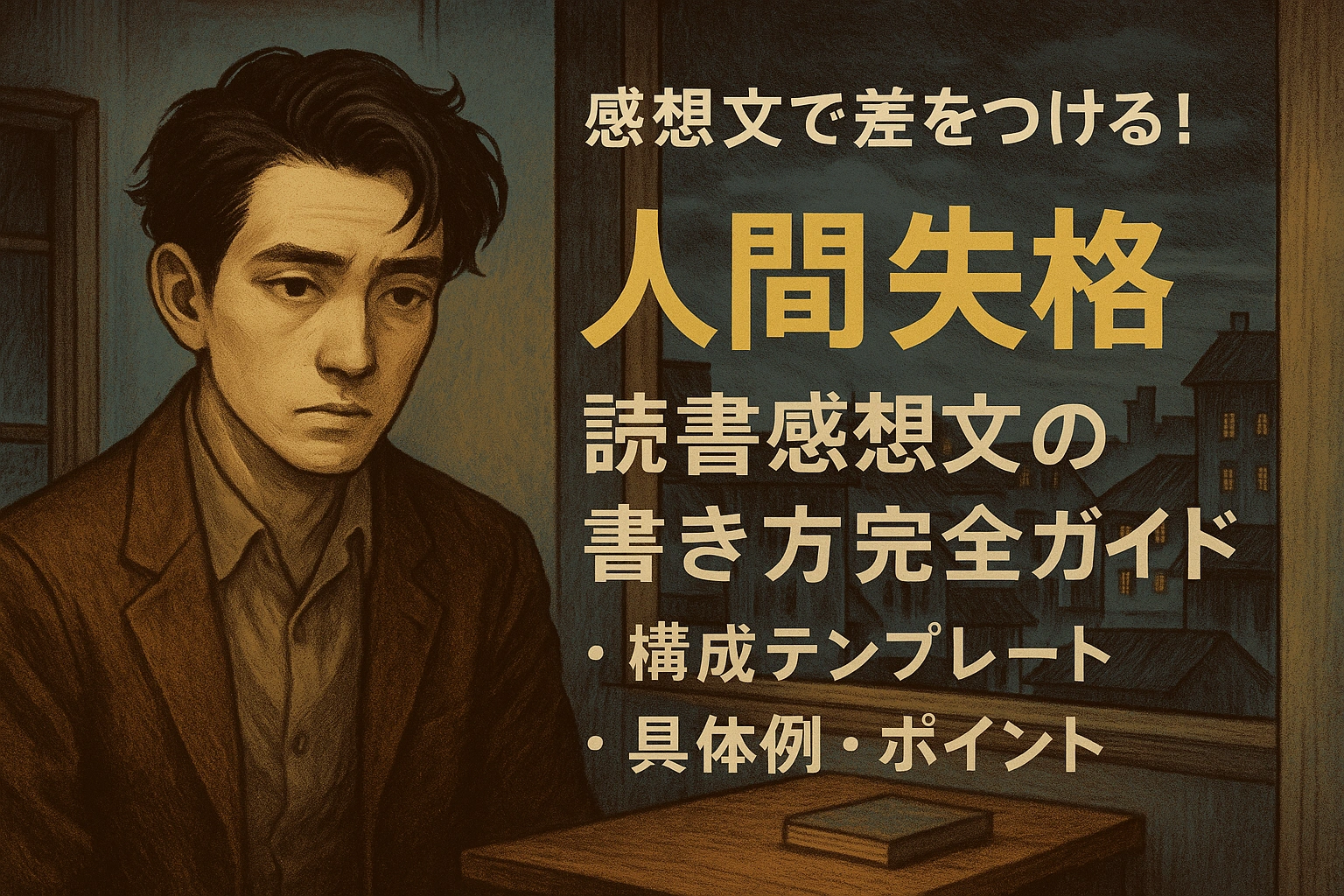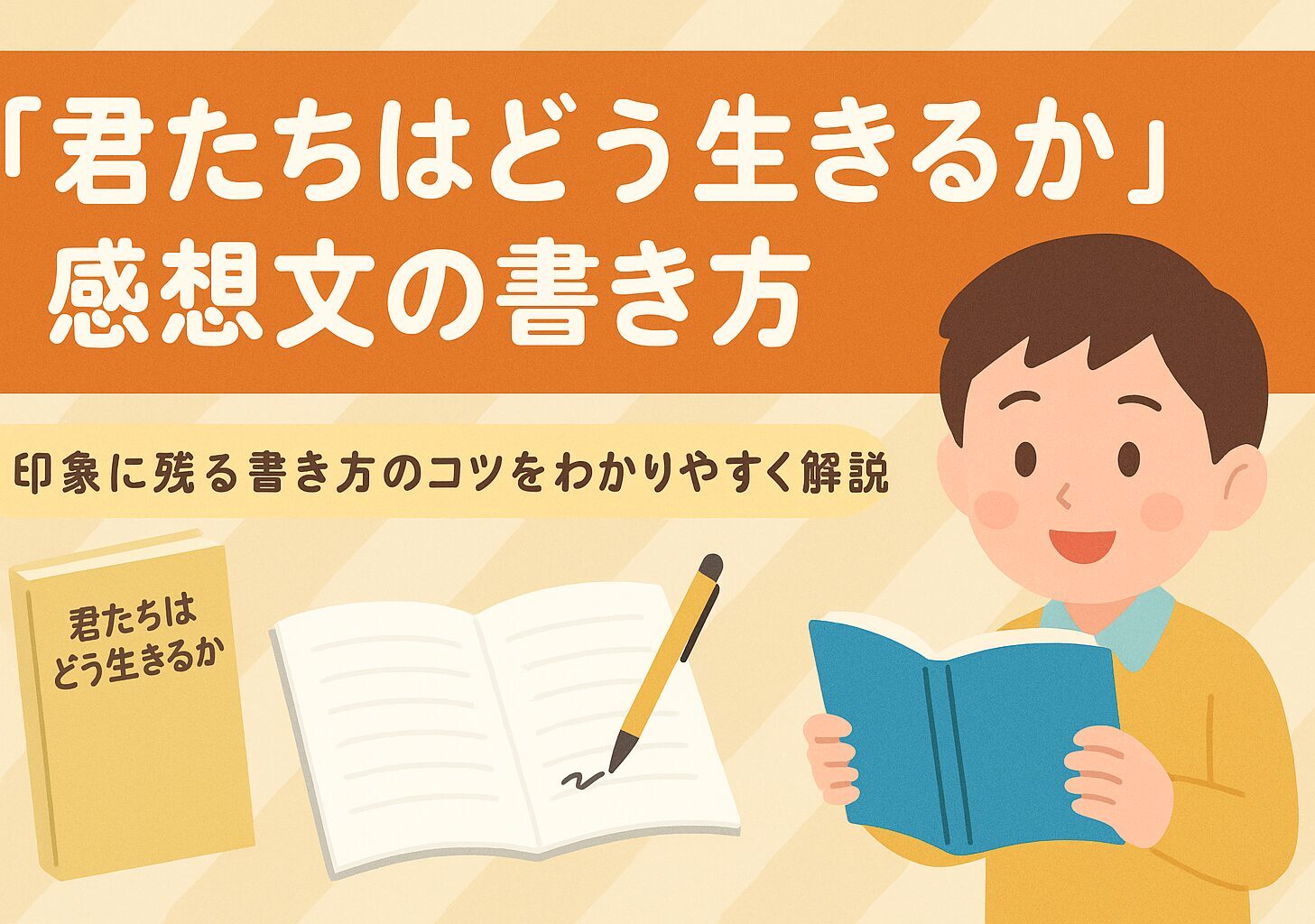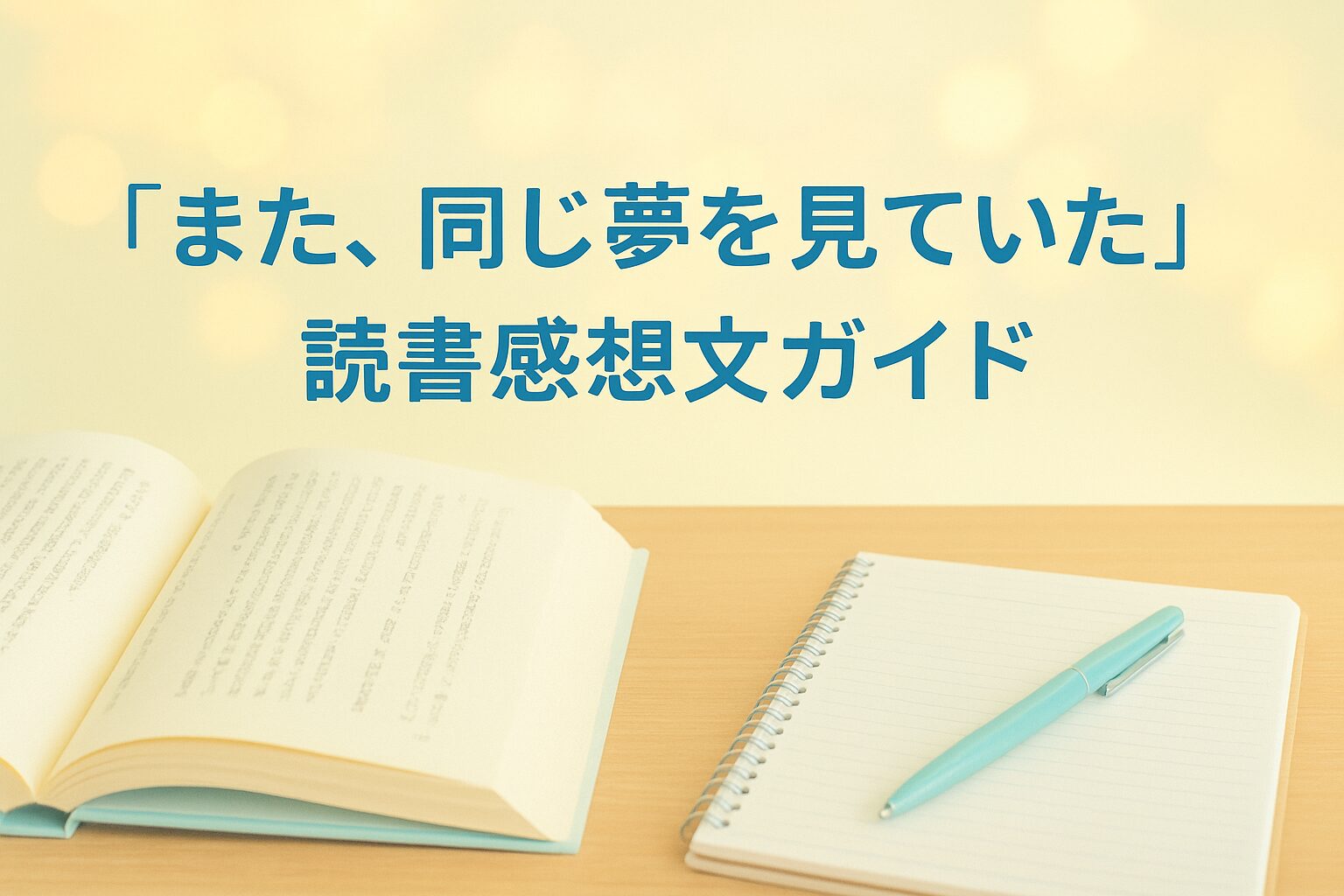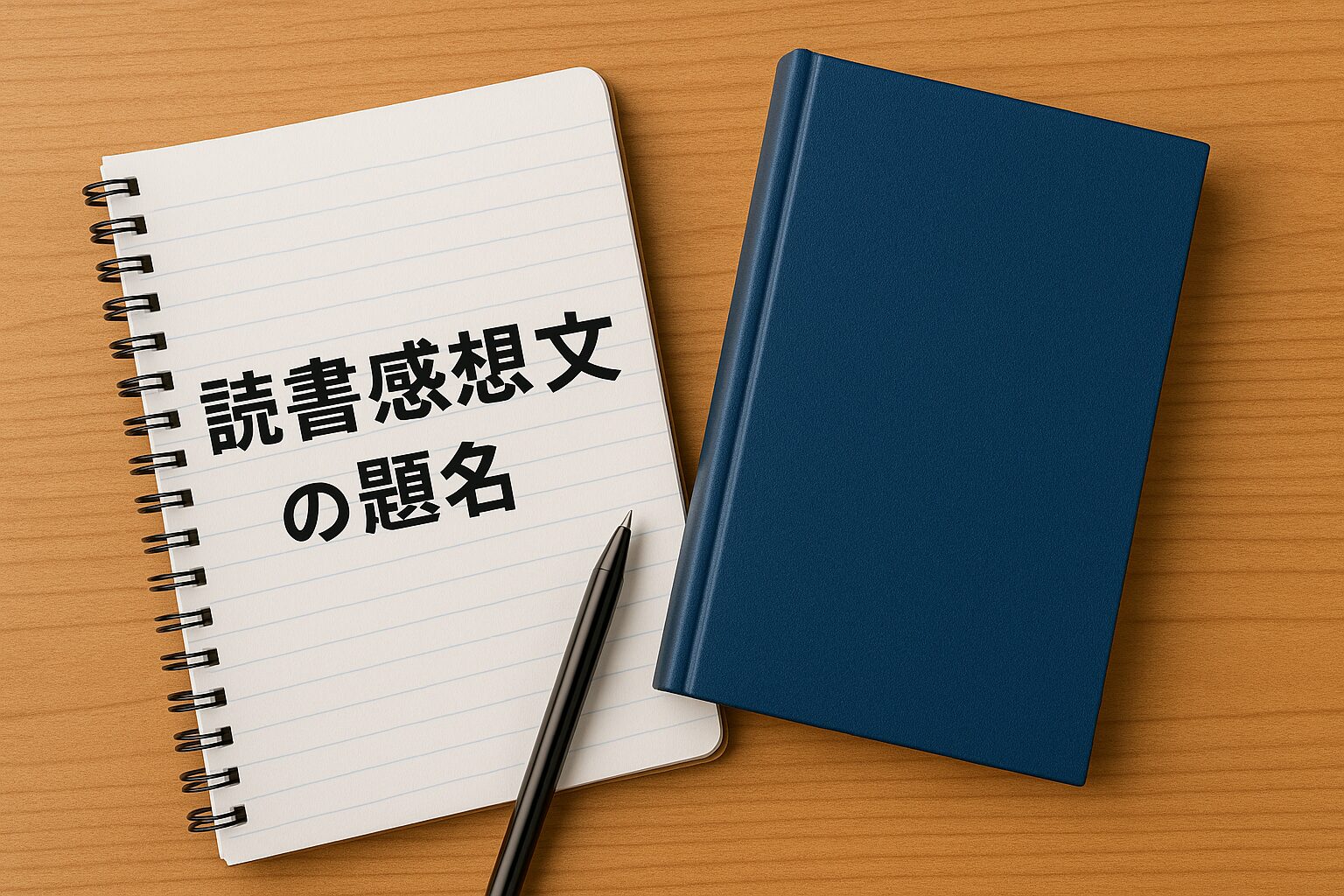「読書感想文にぴったりな本って、どれだろう?」
そう悩んでいるなら、『変な家』がおすすめです。
YouTubeで話題となり、書籍化されたこの作品は、ただのホラーやミステリーではありません。間取り図という誰もが見たことのある“家の設計”から、じわじわと広がる違和感と恐怖。読みやすい文章とテンポのいい展開で、中高生から大人までハマる人が続出中です。
この記事では、読後の感想、感想文に使えるポイント、書きやすい構成、さらにはおすすめ関連書籍まで、SEOを意識しながら徹底的に紹介します。感想文のネタ探しに悩んでいる方も、次に読む1冊を探している方も、ぜひ参考にしてみてください!
『変な家』はこちらから購入する事が出来ます👇
スポンサーリンク
変な家ってどんな話?読みたくなるあらすじ紹介
謎の間取りから始まるミステリー
『変な家』の物語は、一見何の変哲もない“間取り図”からスタートします。しかしその間取りには、どう考えてもおかしな点がいくつもあるのです。たとえば、玄関の真横に謎の空間があったり、トイレの位置が不自然だったり。普通の人なら「設計ミスかな?」と思うところですが、本書ではその違和感から“恐怖”が生まれていきます。
物語の語り手であるYouTuber「雨穴(うけつ)」は、この間取りに疑問を抱き、設計士・栗原とともにその謎を追い始めます。読者はこの調査の過程を一緒に体験していくような感覚になり、まるで自分が探偵になったような気分でページをめくってしまうのです。たった一枚の間取り図から、こんなにもスリリングで深い物語が展開するとは、読む前は想像もできないでしょう。
この設定だけで、すでに興味をそそられる人も多いはず。身近な「家」が舞台ということで、リアルさも抜群です。だからこそ、ちょっとした違和感が“怖さ”へと変わっていくんですね。
主人公「雨穴」と設計士「栗原」の奇妙な関係
『変な家』のストーリーでは、雨穴と設計士・栗原の関係がとても重要な鍵になります。雨穴はあくまでも「気になる間取りをネタにする」つもりで相談を持ちかけたのですが、栗原はその図面の異常さにすぐに気づき、徐々に“この家には何かある”と確信し始めます。
この2人のやりとりは非常に自然で、会話のテンポも良く、読んでいて引き込まれます。栗原はプロとしての視点から鋭い指摘を繰り出し、雨穴は読者目線に近い視点で「そんなことがあるの!?」とリアクションを取ります。まるで読者が2人の会話に加わっているかのような臨場感があるのです。
また、物語が進むにつれて2人の距離感にも微妙な変化が見えてきます。最初はただの調査協力者だったはずが、やがて一緒に恐怖と謎に向き合う“バディ”のような存在に変わっていくのです。このコンビの化学反応が、物語をより魅力的にしています。
一見普通な家に隠された恐怖
“普通の家”というのは、本来、安心できる場所です。しかしこの作品では、その「日常的な場所」こそが最大のホラー要素になっています。外見は全く普通、でも中身は何かがおかしい――。このギャップこそが、本作の恐怖の本質です。
家の中に「誰かを閉じ込めるための部屋」が存在する可能性や、間取りが意図的に改造されている事実など、読み進めるうちに恐ろしい可能性が次々と浮かび上がってきます。しかもそれが、実際に現実でもありそうな話なのが怖いところ。
読者は「この家の住人は一体どんな人だったのか?」「この部屋の使い道は何のため?」と、どんどん想像を掻き立てられます。そして想像すればするほど不気味で、怖い。文章だけなのに、まるでホラー映画を観ているような緊張感が味わえるのです。
物語を彩るリアルな描写と会話
『変な家』が読みやすく、そして面白い理由の一つに「リアルな描写と言葉」があります。登場人物たちの会話はとても自然で、わざとらしさがありません。また、「えっ、それ本当にあるの?」と思うような事例や資料が途中で紹介されることで、フィクションと現実の境界線が曖昧になる感覚も魅力です。
さらに、読者にとって親しみのある言葉遣いや、理解しやすい表現が多いため、中学生でも十分楽しめる内容になっています。「難しい言葉が多いと読むのがつらい」と感じる人でも、『変な家』ならスラスラと読み進められるでしょう。
この“読みやすさ”こそが、感想文を書くうえでも大きなポイントになります。読んで理解できるからこそ、自分の言葉で感じたことを書きやすいのです。
最後まで飽きさせない展開力
『変な家』は短めの章ごとに話が進んでいくため、テンポがとても良いです。どの章も「次が気になる!」という終わり方で構成されていて、ページをめくる手が止まりません。まるでミステリードラマの1話1話を観ているような感覚です。
また、伏線も見事に張り巡らされており、終盤には「なるほど!」と思わされる驚きの展開が待っています。最初に出てきた何気ない言葉や設定が、最後の真相につながっていく――そんな展開に読者は感心し、同時に戦慄することになります。
何度も読み返したくなる構成で、1回目は「怖い」、2回目は「なるほど」、3回目は「ここにもヒントがあったのか!」というように、読むたびに発見があります。それが『変な家』の中毒性とも言える魅力です。
スポンサーリンク
読後の感想:ゾッとするけど止まらない不思議な魅力
「変な家」はホラー?ミステリー?その境界線
『変な家』を読み終えると、多くの人が「これはホラーなのか?ミステリーなのか?」と迷うかもしれません。それだけジャンルにとらわれない独自の魅力がある作品なのです。たしかに物語の中には「怖い」と感じるシーンがたくさんあります。しかし、幽霊や怪奇現象が出てくるわけではなく、怖さの根源は“人間”にあります。
それと同時に、間取りというヒントをもとに謎を解いていく構成は、まさにミステリーの醍醐味。読者自身も「もしかしてこういうことかも?」と推理を楽しむことができ、知的好奇心も満たされます。ホラーの緊張感と、ミステリーの知的快感の両方を味わえる珍しいタイプの作品です。
この「どっちとも言えないけど面白い」という感覚が、他の作品にはない独特の読後感を生み出しています。そのため、ジャンルで作品を選ぶ読者にとっても、新しい発見になる一冊です。
家という身近な存在が怖くなる不気味さ
誰もが毎日過ごしている「家」という空間が、本作では恐怖の舞台になります。それは、特別な場所でもなく、日常の一部である「家」だからこそ、読者に強い印象を与えるのです。もしこれが古びた洋館や山奥の別荘だったら、非日常として割り切れていたかもしれません。でも、ごく普通の住宅街にある“変な間取りの家”という設定が、本作の怖さを何倍にもしています。
読み進めるほどに、「自分の家にも何か隠されていたら…」といった想像が頭をよぎり、日常の安心感が少しずつ崩れていく感覚があります。特に、誰もが一度は間取り図を見たことがある経験を持っているため、「あれって本当に安全な設計なのか?」と不安になる読者もいるでしょう。
日常が一瞬で非日常に変わる。その恐怖が、じわじわと心に染み込んでくるのが『変な家』の魅力でもあり、怖さの理由でもあります。
読み終わったあとも考え続けてしまう仕掛け
『変な家』は、読み終わった瞬間で終わる本ではありません。むしろ、読了後に「あれはどういう意味だったのか?」「実際にあんな家があったらどうなるのか?」といった疑問や想像がどんどん湧いてくる仕掛けが散りばめられています。
間取りの構造、人物の行動、登場しないキャラクターの存在……細部にまで意図が感じられる構成に、何度も振り返りたくなるのです。そして気づくたびに新たな怖さや驚きが生まれます。これこそが、読後も頭から離れない理由でしょう。
また、現実にありそうな話だけに、自分の暮らしとリンクしてしまう人も多くいます。たとえば、「あの廊下の突き当たりの部屋って何か意味あるのかも…」など、普段気にしない部分に疑いの目を向けるようになるのです。
ネタバレなしでも伝わる読後の衝撃
『変な家』は、ネタバレをしなくてもその魅力が十分に伝わる作品です。むしろ、ネタバレを避けて読んだ方が、後半の衝撃を存分に楽しめるでしょう。だからこそ、友達に勧めるときや感想文を書くときも、「あえて詳しく言わない」ほうが効果的だったりします。
たとえば、「読み始めはちょっとしたミステリーだと思ったのに、最後は本気で背筋が凍った」など、自分がどう感じたかを率直に書くことで、読者に興味を持たせられます。具体的な結末を明かさなくても、感情の動きや印象に残った点を伝えることで、十分に魅力が伝わるのです。
そしてこの“ネタバレなしでも伝えられる”という特徴は、感想文としても書きやすいポイントになります。読んだ人だけが共有できる驚きがあるからこそ、読者同士の共感も生まれやすくなるのです。
大人も中高生も楽しめる読みやすさ
『変な家』は文章の難易度が高くなく、語り口もカジュアルなので、大人はもちろん中高生にも読みやすい内容になっています。会話形式が多く、テンポが良いため、本を読むのが苦手な人でも「読みやすい」「一気に読めた」と感じる人が多いです。
特に読書感想文の題材としてはぴったりで、感想を書きやすいポイントがたくさんあります。怖いだけではなく「なぜ怖いのか?」「何が不思議なのか?」を考えながら読むことで、自然と考察する力も身につきます。
また、主人公が読者と同じような視点で話を進めてくれるため、物語に共感しやすく、自分の言葉で感想を書きやすいのも大きな魅力です。「読書感想文って難しそう…」と感じている中高生にも、自信を持っておすすめできる一冊です。
スポンサーリンク
読書感想文に使えるポイントと表現例
感情の動きと印象に残ったシーンの描写
読書感想文を書くときに一番大切なのは、「自分の感情がどう動いたか」をしっかり伝えることです。『変な家』には、驚き、怖さ、不思議さ、そして考えさせられるような場面がたくさんあります。読んでいて「ここが怖かった」「このセリフにドキッとした」と思った瞬間を、なるべく具体的に書くようにしましょう。
たとえば、「間取りに隠された意味を知ったとき、思わず鳥肌が立った」とか、「最初はただの間取りの話だと思っていたけれど、読み進めるうちに怖くなってきた」といった表現を使うと、感情の動きが伝わりやすくなります。
印象に残ったシーンを選ぶときは、必ず「なぜ印象に残ったのか」もセットで考えてみましょう。ただ「怖かった」ではなく、「家の中にこんな秘密が隠されているなんて、自分の家まで不安になった」といった、自分の感覚と結びつける表現が効果的です。
心に残ったセリフや場面の活用
感想文では、心に残ったセリフや場面を引用して、自分の考えを述べるのもとても有効です。『変な家』には、読者の想像力をかき立てるようなセリフや、思わずページを戻して読み直したくなるようなシーンがいくつもあります。
たとえば、「この家は、誰かを閉じ込めるために作られたんです」というようなセリフは、読者に強烈なインパクトを与えます。こうした言葉を引用しながら、「そのセリフを読んだとき、自分だったら絶対にこんな家には住めないと思った」などと、自分の気持ちを添えると、文章がより説得力を持ちます。
心に残るシーンとしては、雨穴と栗原が家の構造を分析する過程などが挙げられます。そのシーンを取り上げ、「まるで本当に探偵になった気分だった」といった表現を使うと、読者目線のリアルな感想として伝わりやすくなります。
作者の意図を自分なりに考えるコツ
感想文では、「この本で作者は何を伝えたかったのか?」を自分なりに考えてみることも大切です。ただストーリーを追うだけでなく、その背後にあるテーマやメッセージに目を向けると、より深い感想になります。
『変な家』では、「日常の中に潜む異常」「見えないものへの恐怖」「人間の闇」といったテーマが感じられます。読んでいて「安心できるはずの場所が一番怖い」と思ったなら、なぜ作者がそんな設定を選んだのか、自分なりに考えてみましょう。
考察のヒントとしては、「登場人物はなぜこの行動を取ったのか?」「この場面にどんな意味があるのか?」など、自問自答をすることです。たとえば、「家の間取りがおかしいのは、何か隠したいことがあるから。つまり、見えないものほど怖いという作者の意図があるのかもしれない」といった考察ができると、読み手としての深さが出ます。
感想文でのおすすめ構成パターン
感想文を書くとき、どう構成すればいいのかわからない…という人は多いです。そこで、おすすめの構成パターンを紹介します。
- 本を読んだきっかけや第一印象
「YouTubeで紹介されているのを見て興味を持った」「タイトルが気になった」など。 - あらすじを簡単に紹介(3~4行でOK)
ネタバレしすぎない程度に「変な間取りの謎を解く話」くらいでまとめましょう。 - 印象に残った場面やセリフと、その理由
自分の感情や考えをしっかり述べる部分。ここが一番のメインです。 - 作者の意図やテーマについての自分なりの解釈
自分なりの考察や「ここから何を学んだか」を入れると深みが出ます。 - まとめ・読んで良かった点や他の人にも勧めたい理由
感想文の締めくくりは、前向きな一言で終わると印象が良くなります。
この構成を使えば、自然な流れで800文字以上の感想文も無理なく書けるようになります。
書き出しや締めの例文紹介
書き出しや締めの文章で悩む人も多いと思いますので、例文をいくつか紹介します。
書き出しの例文:
- 「私は、あるYouTuberが紹介していたことで『変な家』という本を知りました。」
- 「“家”がテーマの物語は初めてで、どんな内容か気になって読み始めました。」
締めの例文:
- 「この本を読んで、当たり前の日常にも恐ろしいことが潜んでいるかもしれないと思いました。」
- 「『変な家』は怖いけれど面白く、たくさんの人に読んでほしい一冊です。」
こうした定型フレーズを自分の感想と組み合わせれば、自然で読みやすい文章が完成します。
スポンサーリンク
読書感想文を書くときの注意点とコツ
あらすじだけにならない工夫
読書感想文でよくある失敗の一つが「あらすじだけで終わってしまう」というパターンです。『変な家』のように展開が面白い作品は、つい「どんな話だったか」を説明したくなりますが、感想文は“自分がどう感じたか”を書くことが大切です。
あらすじは全体の1~2割程度にとどめ、あとは「印象に残ったシーン」「読んで驚いたこと」「考えさせられたこと」に重点を置きましょう。たとえば、「間取り図の中に“閉じ込められた人がいる可能性”があると知ったとき、恐ろしさで背筋がゾッとしました」というように、自分の感情を具体的に書くことがコツです。
「この本を読んでどんな気持ちになったのか」を中心に構成することで、あらすじに頼らずにしっかりとした感想文になります。
自分の考えをどう入れるか
「本の感想って、自分の意見ってどこに入れればいいの?」と悩む人も多いと思います。でも、感想文はまさに“自分の考えを書くためのもの”です。『変な家』の中で心に残った場面を取り上げて、それに対する「自分の考え」「もし自分だったらどうするか」を書くと、読み応えのある内容になります。
たとえば、「間取りを変えることで人の行動を制限することができると知って、家の設計にはこんな深い意味があるのかと驚きました」といったように、自分の発見や気づきを書くことが大切です。
また、「自分の家の間取りを改めて見直したくなった」など、読後の変化や影響について書くのも良い方法です。それが“この本を読んだからこそ感じたこと”として、感想文にオリジナリティを加えてくれます。
文字数を自然に増やすテクニック
読書感想文の指定文字数が800字や1200字になると、「書くことが足りない!」と焦ってしまうことがあります。そんなときに役立つテクニックをいくつか紹介します。
- 比喩を使って気持ちを表現する
例:「心に氷が張ったような気持ちになりました」「まるでパズルを解いているようでした」 - 登場人物と自分を比べる
例:「もし自分が雨穴の立場だったら、怖くて家に近づけなかったと思います」 - 読んだ前と後で気持ちがどう変化したかを書く
例:「最初はただのミステリーだと思っていましたが、読後には人間の怖さを感じました」 - 本を読む前の予想と読んだ後のギャップを書く
例:「タイトルを見たときは、おもしろい話かな?と思いましたが、実際は予想以上に深かったです」
これらを組み合わせれば、無理なく自然な形で文章を広げることができます。
評価されやすい視点の持ち方
学校の読書感想文などでは、「ただの感想」よりも「そこから学んだこと」や「気づいたこと」が書かれていると評価が高くなります。『変な家』のようにエンタメ要素が強い本でも、「なぜこのような家が存在したのか」「誰がどうしてこういうことをしたのか」など、少し深く考える視点を持つことが大切です。
たとえば、「間取りを通じて人間の心理が表れることを知り、普段何気なく暮らしている空間についても考えるようになりました」といったように、作品を通して得た気づきを書いてみましょう。
また、「物事の表面だけを見ていては本当のことはわからない」というような、物語を通して得た人生の教訓のようなものを書ければ、説得力も増します。
感想と考察のバランスの取り方
感想文は、「感じたこと」だけでも「考えたこと」だけでも物足りなくなってしまいます。大切なのはこのバランスです。『変な家』では、ストーリーの面白さに引き込まれるだけでなく、「家とは何か?」「安心とは何か?」といったテーマにも触れることができます。
まず最初に「読んでどう感じたか」をしっかり書いて、そのあとで「なぜそう感じたのか?」を考察してみる。この順番を守ることで、自然でバランスの良い感想文になります。
たとえば、「この話が怖かったのは、ただのホラーだからではなく、現実にも起こりそうな設定だからだと思います」といったように、“感情”→“理由”という形にするとスムーズに読める文章になります。
読書感想文では、この「感情」と「理由」のセットをいくつか用意することが、しっかりとした構成につながるのです。
スポンサーリンク
「変な家」が気に入った人におすすめの本5選
雨穴の他作品『変な絵』も読んでみよう
『変な家』を面白いと感じた人に、まずおすすめしたいのが同じ著者・雨穴による『変な絵』です。こちらも「見た目は普通。でも、よく見ると何かがおかしい」という構成で進んでいきます。
『変な絵』では、ある1枚の絵をきっかけに、不可解な事件が明らかになっていきます。『変な家』と同じく、読者の想像力を刺激し、じわじわと怖さが迫ってくるような独特の雰囲気が魅力です。
また、構成も非常に読みやすく、短めの章立てやテンポの良い展開が特徴。『変な家』のように、「読み始めたら止まらない!」という体験をもう一度味わいたい人にはぴったりです。雨穴の世界観にさらにハマりたい人には、間違いなくおすすめの一冊です。
家や空間が舞台のゾクッとする小説
『変な家』が印象的なのは、“家”という日常空間に不気味な設定が仕掛けられている点です。同じように、空間や場所にまつわる怖さを感じたい人には、小野不由美の『残穢(ざんえ)』がおすすめです。
この作品は、ある部屋で起きた怪奇現象を調べるうちに、土地や建物に隠された歴史が明らかになっていくというストーリー。怪異の直接的な描写は少なく、静かにじわじわと恐怖が積み上がる“語り”の力が秀逸です。
『変な家』と同様に、「その場所にまつわる何か」にフォーカスしていて、物理的な怖さというより“心理的な重さ”が読後にのしかかるような作品です。ミステリーとホラーの中間を楽しみたい人にはぴったりです。
同じように伏線回収が気持ちいい作品
『変な家』のもう一つの魅力は、丁寧に張られた伏線が物語の終盤で回収される快感にあります。この“伏線回収の気持ちよさ”を味わいたい人におすすめなのが、米澤穂信の『氷菓』です。
『氷菓』は高校生たちが日常の中にある小さな謎を解いていく青春ミステリーですが、その中に隠された真相や動機が明かされるたび、「そうだったのか!」という感動があります。
派手な展開はないものの、読み終えたときに「なるほど」と納得できる緻密な構成は、『変な家』と通じる部分が多くあります。論理的な展開を楽しみたい読者には特におすすめの一冊です。
中高生向けでも読みやすいミステリー
中高生が読書感想文を書くなら、難解すぎず、それでいて考えさせられる作品が最適です。そんな時におすすめしたいのが、住野よるの『君の膵臓をたべたい』です。
タイトルだけを見るとホラーのようですが、実は心温まる感動作で、ストーリーの進行とともに主人公の心の成長が描かれていきます。物語の中には驚きの展開もあり、感想文にもしやすいポイントがたくさん詰まっています。
文章も読みやすく、登場人物の心の動きが丁寧に描かれているので、感情移入しやすいのが特徴です。『変な家』のように読者の想像力を刺激する作品とは少し違いますが、読後の余韻や心に残る言葉という点で共通点があります。
感想文にも向いている話題の人気作
最後に紹介するのは、東野圭吾の『ナミヤ雑貨店の奇蹟』です。この作品は、悩み相談の手紙が届く古びた雑貨店を舞台に、人々の人生が交差していく感動の物語。短編集のような構成で読みやすく、それぞれの物語が最後には1本の糸でつながる伏線の見事さも魅力です。
『変な家』が“怖さ”や“違和感”を味わう本だとすれば、『ナミヤ雑貨店の奇蹟』は“心の温かさ”や“気づき”を与えてくれる本。読書感想文のテーマとしては、「人を思いやることの大切さ」「過去と向き合う勇気」など、多くの視点から書くことができるのもポイントです。
実写映画化もされているため、話題性もあり、「読んだ本」としてのアピールにもなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 『変な家』って本当に怖い話なんですか?
A. はい、じわじわと恐怖が迫ってくるタイプの作品ですが、幽霊などのホラーではなく“人間の怖さ”や“日常に潜む違和感”を描いたミステリーテイストの内容です。怖さよりも「続きが気になる!」という面白さが勝るという声も多いです。
Q2. 読書感想文に向いている理由は何ですか?
A. 物語がシンプルで読みやすく、それでいて深く考察できる要素が多いためです。感情の動き、驚き、テーマ性、そして文章量のバランスがちょうど良く、書きやすい構成が自然と作れます。
Q3. 小学生や中学生でも読めますか?
A. 中学生には特におすすめです。文章が平易で会話形式も多く、読みやすい構成になっています。小学生には一部の内容が少し難しいかもしれませんが、保護者のサポートがあれば十分読めます。
Q4. 感想文にネタバレは書いてもいいんですか?
A. 基本的にはネタバレを避けた方がよいです。とくに読んでいない人が読む可能性のある感想文では、「読んでみたい」と思わせる書き方が好まれます。印象に残った感情や場面に焦点を当てるのがコツです。
Q5. 似たようなテーマの本は他にありますか?
A. 雨穴さんの『変な絵』や、小野不由美さんの『残穢』などが挙げられます。どちらも日常の中に潜む異常さを描いた作品で、『変な家』が好きな方には特におすすめです。
まとめ
『変な家』は、わずか一枚の間取り図から始まるミステリーでありながら、人間の本質や恐怖の根源にまで踏み込んでくる、まさに“読後に語りたくなる”一冊です。
感想文を書く上でも、物語の構成がわかりやすく、主人公の目線が読者に近いため、自分の考えや感情を乗せやすいという大きなメリットがあります。読書感想文に不慣れな中高生にとっても、入りやすく、深く掘り下げることも可能な良質な題材です。
また、雨穴氏の他作品や、空間に秘められた恐怖を描いた作品など、読書の興味をさらに広げてくれる関連本も多く、読書体験としての広がりが感じられる作品でもあります。
「家」という誰にとっても身近な存在を舞台にしたからこそ、自分自身に引き寄せて感想を書きやすく、それでいて、何度も読み返したくなる深さがある――
『変な家』は、読む楽しみと書く楽しみをどちらも味わえる、まさに“感想文向き”の傑作です。
『変な家』はこちらから購入する事が出来ます。読書感想文として書くのに興味がありましたら是非とも手に取ってみてください👇