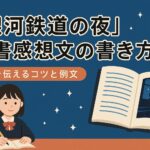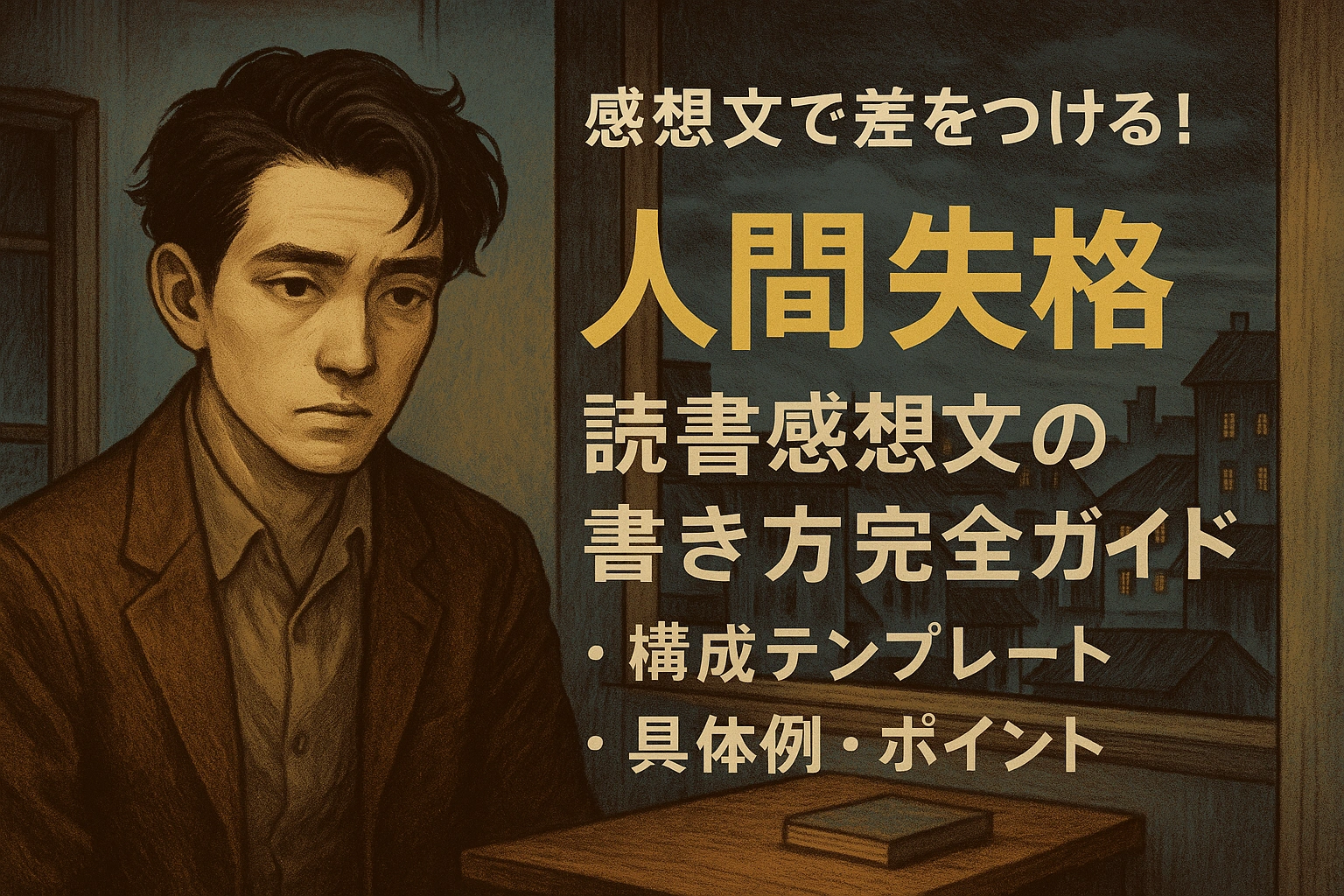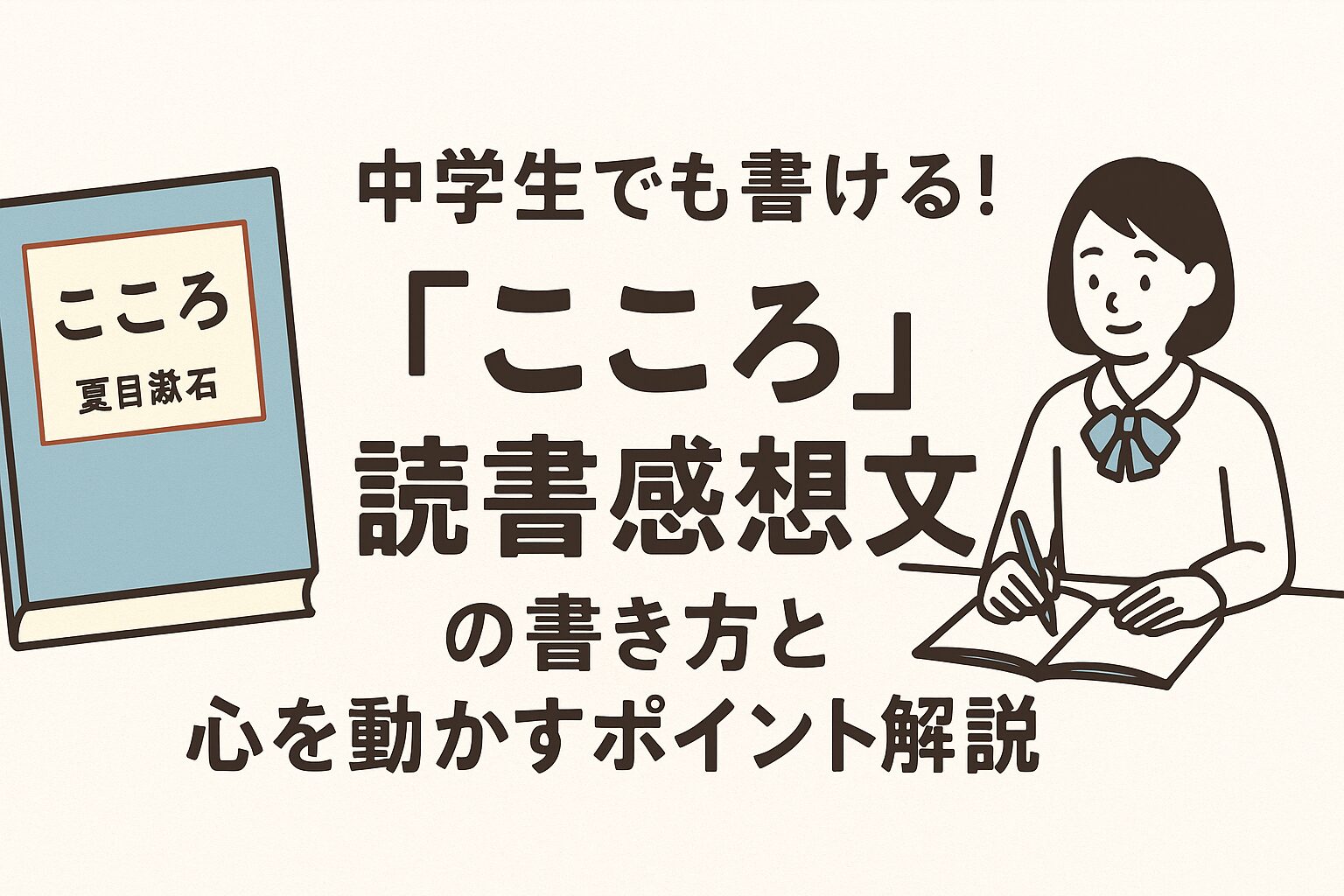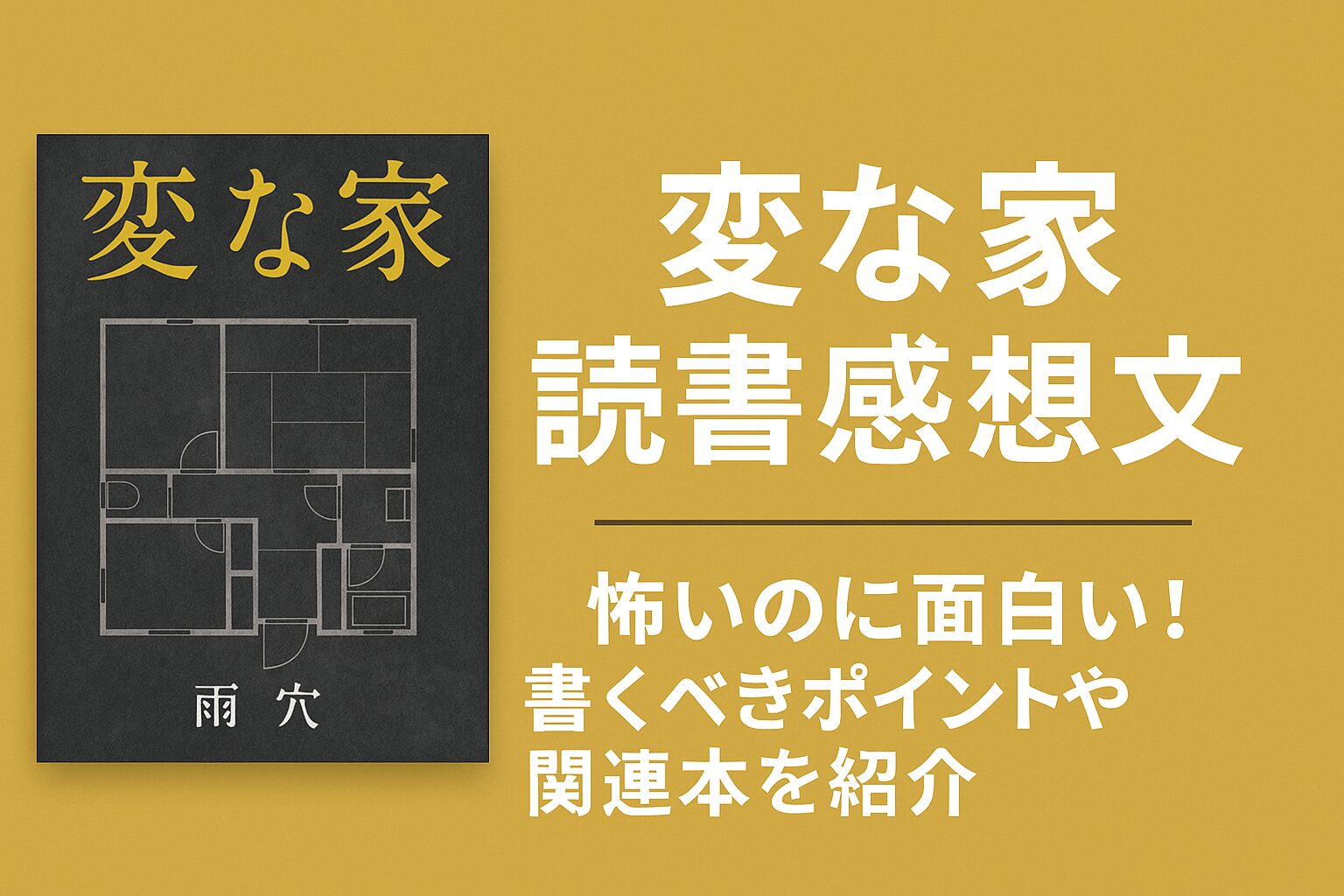「なんとなく読んだのに、気づいたら涙が出そうになった。」
そんな経験をさせてくれるのが、ブレイディみかこさんのベストセラー『僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー』です。日本人の母とイギリス人の父を持つ息子が、多様性あふれるイギリスの学校生活を通して見つめる「差別」や「自分らしさ」。中学生でも読みやすい語り口でありながら、深い学びと気づきが詰まったこの作品は、読書感想文にもぴったりの一冊です。
今回は、この本の魅力や感想文の書き方、使える名言などを、やさしく・わかりやすく解説します。これから感想文を書くあなたにも、読んだことがある人にも、きっと役立つ内容です。
『僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー』はこちらから購入する事が出来ます。
スポンサーリンク
「僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー」とは?心に残るノンフィクションエッセイ
作者ブレイディみかこの背景と執筆理由
ブレイディみかこさんは、イギリス在住の日本人ライターで、元々は保育士として働いていた経歴を持つ方です。彼女の視点はとてもユニークで、福祉や教育、移民といった社会の中でも見えにくい部分を、生活者としての立場から書いています。
この本を執筆したきっかけは、自分の息子が中学校に進学したことでした。その学校は、白人だけでなく、アジア系や黒人など、さまざまな国や文化を持った子どもたちが集まる多様な環境。そんな中で、子どもがどんなことを感じ、学び、ぶつかっているのかを、親としての目線で記録し、伝えたいという思いからこのエッセイは生まれました。
彼女の文章は難しい言葉を使わず、まるで親しい友達と話しているかのような感覚で読めます。だからこそ、多くの読者に「これは私たちの問題でもある」と気づかせてくれるのです。
舞台はどこ?イギリスのリアルな日常
物語の舞台は、イギリス南部の都市・ブライトン。海が近く、観光地としても知られていますが、決して裕福な人たちばかりが住んでいるわけではありません。むしろ、社会的に恵まれていない地域で、多くの家庭が経済的な問題を抱えています。
学校も例外ではなく、生徒の半分以上が給食費を支援されているような状況。そんな中、ブレイディさんの息子は、いろんな文化的背景を持つクラスメートと出会い、時には衝突し、時には笑い合いながら日々を過ごしていきます。
イギリスというと「進んだ国」「差別がない国」というイメージを持つ人も多いですが、この本を読むと、実はそんな単純な話ではないことがよくわかります。リアルなイギリスの姿が描かれているからこそ、日本の読者にも深く刺さるのです。
なぜ「イエローでホワイトでブルー」なのか?
タイトルにある「イエロー」は、日本人である著者や息子の肌の色。「ホワイト」はイギリス人の父親を指します。そして「ブルー」は、イギリスの学校で着る制服の色であり、また気持ちが落ち込んだり不安定な様子を表す英語表現でもあります。
つまりこのタイトルには、「私は日本人とイギリス人の間にいる存在で、時にはブルーな気持ちにもなる」という複雑なアイデンティティが込められているのです。たったひとつのタイトルの中に、国籍や文化、感情がぎゅっと詰め込まれていることに驚かされます。
このように、タイトルからして奥深く、それだけでも読者の心を引きつける力があります。
多様性の視点で描かれる親子の会話
この本の特徴のひとつが、親子の対話です。日々の学校生活で感じたことを息子が母親に話し、母がそれに対して考えを述べる——このシンプルなやり取りの中に、多様性への理解や疑問、そして成長が描かれています。
たとえば、ある日息子が「黒人の友達が差別されていた」と話します。母親はそれを「かわいそう」で終わらせるのではなく、どうしてそのようなことが起きるのかを一緒に考えるよう促します。この「一緒に考える」姿勢こそが、現代の教育に必要なものではないでしょうか。
家庭での日常的な会話から、社会全体の問題に目を向けることができる。そんなヒントがこの本にはちりばめられています。
作品が注目される理由とは?
この本は、刊行当時から大きな話題となり、数々の賞も受賞しています。その理由は、難しいテーマをわかりやすく、そして実感を持って語っているからです。
特に今の日本では、「多様性」や「人権」という言葉が飛び交う一方で、それを本当に理解する機会はまだまだ少ないのが現状です。この本は、そうしたテーマを学校でも家庭でも話し合えるきっかけにしてくれます。
また、ブレイディさんの息子がまだ中学生ということもあり、同年代の子どもたちが共感しやすい内容になっているのもポイントです。だからこそ、「読書感想文に最適な本」としても人気が高まっているのです。
スポンサーリンク
読んで感じたこと:人種差別と向き合う中学生の姿
子ども目線だからこそ伝わるリアルな経験
「僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー」が特別な本である理由の一つは、中学生の息子の視点から書かれていることです。大人が語る社会問題はどうしても理屈っぽくなりがちですが、子どもの言葉や行動には、直感的で正直な反応があります。たとえば、クラスで起きたちょっとした言い合いや、グループからはぶかれる場面。そんな日常のひとコマに、差別や偏見が見え隠れしているのです。
息子は、「なんでそんなこと言うの?」と素直に疑問を持ち、それを母親にぶつけます。大人なら見過ごしてしまいがちな小さな違和感を、しっかりと感じ取り、言葉にする力。その感受性が、読者にも「自分だったらどうするだろう?」という問いを投げかけてくれます。子ども目線だからこそ、余計なフィルターを通さずに本質が見える。そんな力が、この本にはあります。
先生や友達との関係で見える社会の縮図
この本を読んでいて驚かされるのは、学校という小さな世界が、実は社会そのものの縮図だということです。息子の学校では、先生やクラスメートとの関係を通じて、イギリス社会の中にある差別、偏見、階級意識がリアルに描かれています。
たとえば、教師が無意識のうちに特定の生徒に厳しく接する場面や、経済的に苦しい家庭の子がからかわれる場面。それらは、決して架空の話ではなく、現実の学校で起きていることです。そして、それは日本の学校でも似たようなことが起こっている可能性が高いと感じさせてくれます。
人間関係の中で起こる「小さな不平等」。それに気づくか気づかないかで、世界の見え方は大きく変わります。この本は、子どもと大人が一緒に「見えない偏見」について考えるための、貴重なヒントをくれるのです。
日本とイギリスの差別の違いに驚き
「イギリスは多文化の国だから、差別なんて少ないだろう」と思っている人も多いかもしれません。ですが、実際にこの本を読むと、そうした思い込みがくつがえされます。たとえば、アジア系の生徒が「チャイニーズ」とまとめて呼ばれる場面が出てきます。実際には中国人だけでなく、日本人や韓国人もいますが、外見が似ているからという理由で一括りにされてしまうのです。
一方、日本では「外国人だから」という理由で差別が起こることがあります。違いはあるものの、どちらの国にも「見た目や出身による差別」は存在しているという共通点に気づかされます。
大事なのは、「自分たちの国ではどうなんだろう?」と問い直すことです。読者にとっては、イギリスの話を通して、日本社会の中にある問題にも目を向けるきっかけになるはずです。異なる文化の比較は、自分たちの在り方を見つめ直す大切な材料となります。
差別に対する行動力の大切さ
読んでいて特に感動するのが、息子の「差別を見逃さない姿勢」です。まだ中学生という年齢でありながら、彼はクラスで差別的な言動を見聞きすると、自分の言葉でそれに反対します。ときには、友達を失うかもしれないリスクを抱えながらも、自分の信念を貫こうとします。
これはとても勇気のいることです。多くの人は、場の空気を乱さないように見て見ぬふりをしてしまいがち。でもこの本では、「間違っていることは間違っていると言う」という、シンプルだけど難しい行動を、息子が実践している姿が描かれています。
その姿に、読者は「自分もこうありたい」と感じるでしょう。小さな行動が社会を変える一歩になる。そう信じさせてくれるエピソードが、この本にはたくさん詰まっています。
共感と違和感を感じた場面まとめ
この本を読んでいて感じたのは、「共感できる部分」と「違和感を持つ部分」が、うまく共存しているということです。たとえば、息子が友達に対して抱く優しさや思いやりには強く共感できます。一方で、イギリス社会の中にある複雑な階級制度や、移民に対する冷たい目線には、驚きや違和感を覚えることもありました。
でもそれこそが、この本の魅力です。読者自身の考えや経験と重ね合わせながら、「これはおかしい」「これは自分も経験した」と感じることができる。それが本当の意味で「読む」という行為なのだと教えてくれます。
感想文を書くときにも、このように「どの場面で自分は何を感じたか」を整理してみると、オリジナルで深い内容になるでしょう。
スポンサーリンク
中学生にもわかる!「多様性」とは何かを学べる本
多様性とはどういう意味?
「多様性(たようせい)」という言葉は、最近テレビや学校でもよく聞くようになりました。でも、実際に「多様性って何?」と聞かれると、うまく説明できない人も多いのではないでしょうか。簡単に言うと、多様性とは「いろんな考え方や違いがあっていい」ということです。
人は見た目や話す言葉、文化、考え方など、たくさんの面で違っています。けれど、それぞれが「間違っている」とか「劣っている」ということではありません。むしろ、違うからこそ学び合い、助け合うことができる。それが多様性の考え方です。
この本では、息子がいろんな国の友達と接する中で、多様性を自然と学んでいく様子が描かれています。はじめは戸惑ったり、ケンカをしたりしますが、少しずつ「違いは悪いことじゃない」と気づいていく過程がとてもリアルで、読んでいて心が温かくなります。多様性とは、特別なことではなく、毎日の生活の中にあるということをこの本は教えてくれます。
「違い」は悪いことじゃない
多くの人は、まわりと「違っていること」に不安や怖さを感じます。特に中学生のころは、「みんなと同じじゃないと浮くんじゃないか」「変って思われたらどうしよう」と考えてしまうことがよくあります。でも本当に大切なのは、違いを否定することではなく、認め合うことです。
この本には、肌の色、宗教、家庭環境など、さまざまな「違い」を持つ人たちが登場します。中には、誰にも理解されずに苦しんでいる子もいます。でも、その中で息子は「違いはその人の一部にすぎない」と気づき、相手と向き合おうとします。
これは、日本の学校でも大切な考え方です。例えば、発達障害や外国にルーツを持つ子、家の事情が違う子など、それぞれに「違い」があります。でも、それを理由に仲間外れにしたりするのは間違いです。この本を読むことで、「違いを受け入れる」ことの大切さに気づかされます。
学校でのいじめや偏見とどう向き合う?
「多様性を認める」と言葉で言うのは簡単ですが、実際にはいじめや偏見が起きてしまうことがあります。例えば、肌の色や服装、宗教の違いでからかわれたり、特定のグループに入れなかったりすることもあります。
本の中でも、息子のクラスにはそうした場面が登場します。ある生徒は、家庭の経済的な事情で他の子から笑われたり、宗教的な理由で食べ物を選んでいることをバカにされたりします。でも息子は、そのたびに「それっておかしいよね?」と立ち上がるのです。
大切なのは、「誰かがからかわれているときに見て見ぬふりをしないこと」です。勇気を出して「それは違う」と言うのは難しいかもしれません。でも、この本の中で息子が示すように、その一言が誰かを救うこともあります。いじめを止める一歩は、ひとり一人の意識から始まるということを、この本はやさしく教えてくれます。
家庭でできる多様性の教え方
多様性について考えるきっかけは、学校だけでなく家庭にもあります。この本では、母親であるブレイディさんと息子の会話がとても印象的です。学校で起きた出来事について息子が話し、母親が一緒に考えたり、自分の考えを伝えたりする姿勢が、とても自然で参考になります。
たとえば、ある日息子が「友達が変な名前で呼ばれてた」と言ったとき、母親は「どうしてそんなことを言うんだろうね?」と問い返します。ただ怒るのではなく、一緒に「なぜ?」を考えることで、子どもは自分の頭で物事を考えるようになります。
家庭での会話は、子どもの考え方に大きな影響を与えます。「この子は変わってるから付き合わない」と言うのではなく、「どこが違うのかな?何が面白いのかな?」と話し合うことで、多様性への理解は深まります。この本は、そんな家庭での教育のヒントにもなる一冊です。
本を読んだ後に話し合いたい3つのテーマ
この本を読み終えたら、ぜひ家族や友達と話し合ってほしいテーマがあります。まず一つ目は「差別とは何か?」ということ。見た目や国籍、言葉が違うだけで差別されるのはなぜなのか、自分はどう感じたかを共有すると、自分の中の気づきが深まります。
二つ目は「自分の中にも偏見があるのか?」という問い。誰でも知らないうちに、他人を決めつけたり、先入観で判断していることがあります。この本をきっかけに、自分自身を見つめ直すことができます。
三つ目は「どんな世界が理想か?」です。みんなが違いを認め合える社会とは、どんなものなのか。どんな言葉を使い、どんな態度で接すればいいのかを考えることで、未来を変える一歩になります。
本は読むだけでなく、読んだあとにどう考えるかが大事。この本は、それを実践するためのヒントをたくさん与えてくれる作品です。
スポンサーリンク
読書感想文の書き方|この本を選んだ理由と伝えたいこと
読書感想文で伝えるべき3つの視点
読書感想文を書くときに大事なのは、「ただのあらすじ紹介」にならないようにすることです。特にこの本のように社会的なテーマを扱っている作品では、「読んでどう思ったか」「なぜそう思ったか」「その気持ちはどこから来たのか」という3つの視点を意識することが重要です。
まず、「どう思ったか」は正直な感情を書くことから始めましょう。「びっくりした」「腹が立った」「考えさせられた」など、心が動いた瞬間を見つけてください。
次に「なぜそう思ったか」は、自分の経験や知識とつなげると説得力が増します。例えば、「私も転校したときに似た経験をしたから共感した」など、自分だけの視点が光ります。
最後に「その気持ちはどこから来たのか」とは、自分の中の価値観や考え方と向き合うことです。「なぜ私はこの出来事を不公平だと感じたのか?」と自問することで、感想文に深みが生まれます。
この3つの視点を意識すれば、他の人とは違った、自分らしい感想文が書けるようになります。
自分と重ねた体験を書くコツ
感想文で読者の心を引きつけるには、「自分との共通点」や「似たような体験」をうまく盛り込むのが効果的です。この本を読んで、自分の学校や家庭での出来事と重ねて考えたことはありませんか?
たとえば、息子が友達を守ろうとして行動する場面。あなたが誰かに声をかけたこと、あるいは逆に何も言えなかったことなどと比べてみると、自然と気持ちが書けるようになります。
重ねる体験は小さなことでも構いません。「外国から来たクラスメートがいた」「みんなと違う意見を言ったら笑われた」など、身近な体験こそリアルな言葉になります。読書感想文に正解はありません。大事なのは、「自分の言葉で伝えること」です。
そのためには、「あのとき自分はどう感じた?」「何を考えた?」と一度自分に問いかけてみましょう。そうすれば、感想文の文章が自然に浮かんでくるはずです。
印象に残ったセリフを使うと効果的
読書感想文に深みを出すコツのひとつに、「印象に残ったセリフを引用する」という方法があります。文章の中で心に残ったセリフや言葉を取り上げて、それについて自分の考えを述べることで、感想に説得力が出てきます。
例えば、「人種差別は、大人だけの問題じゃないんだよ」という息子の言葉。これは、読者にも強いインパクトを与えます。ただ引用するだけでなく、「私はこの言葉を読んで、自分も学校で何気なく偏見を持っていたことに気づいた」といった感想を添えると、読み手にあなたの気持ちがしっかり伝わります。
印象に残るセリフを選ぶときは、「心が動いた瞬間」に注目すると良いでしょう。読んでいて涙が出そうになったり、ドキッとした場面には、たいてい強いメッセージが込められています。
感想文は、自分の感じたことに正直になることが何より大切です。心に残る言葉をきっかけに、思いを広げていきましょう。
まとめ方で印象が変わる!
感想文の最後のまとめ方によって、読み手の印象が大きく変わります。読書感想文の締めくくりでは、「この本を読んで、自分がどう変わったか」「これから何をしていきたいか」をしっかり書くことが大切です。
たとえば、「この本を読んで、人を見た目で判断しないようにしようと思った」「違いを受け入れることの大切さに気づいた」など、自分の変化を伝えると感想文に深みが出ます。
また、「これからは、周りの人の気持ちをもっと想像してみたい」など、未来に向けた行動目標を書くと、読み手に前向きな印象を与えることができます。
よくある失敗として、「面白かったです。以上。」で終わってしまうケースがあります。これだと読み手に何も伝わらず、もったいないです。最後の一文こそ、自分の気持ちを最大限に表現するチャンスと考えましょう。
読後にどう感じ、どう生きていくか。そこまで書ければ、きっと心に残る感想文になるはずです。
実際に使える読書感想文テンプレート
ここでは、「僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー」を読んだ読書感想文の例として、使いやすいテンプレートをご紹介します。
【書き出し】
私は「僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー」という本を読んで、いろいろなことを考えました。この本は、日本人とイギリス人の間に生まれた男の子が、多様な友達とともに成長していく物語です。
【印象に残った場面】
私が特に印象に残ったのは、○○の場面です。そこで主人公が言った「○○○○」という言葉に、私はとても共感しました。
【自分の経験と重ねる】
なぜなら、私も以前○○という経験をしたことがあるからです。そのとき、私も主人公と同じように○○と感じました。
【気づきと変化】
この本を読んで、私は人との違いをもっと大切にしたいと思いました。これからは、まわりの人をもっとよく見て、相手の立場に立って考えてみたいです。
【まとめ】
この本は、自分の生き方について深く考えるきっかけをくれました。とても心に残る1冊になりました。
このテンプレートをもとに、自分の気持ちを素直に書いていけば、しっかりした読書感想文が完成します!
スポンサーリンク
感想文に使える名言・心に残るフレーズ集
差別と勇気に関する言葉
この本には、「差別とは何か?」「どう向き合うか?」というテーマに深く関わる言葉がたくさん出てきます。中でも印象的なのが、息子が語る「差別って、大人がすることじゃなくて、子どもだってするんだよ」という一言です。このセリフには、大人でもハッとさせられる重みがあります。
多くの人は「差別はよくない」と言いますが、実際には自分が偏見を持っていたり、誰かを無意識に傷つけていることに気づいていない場合もあります。この言葉は、そんな“見えない差別”に気づかせてくれる力を持っています。
また、息子はただ考えるだけでなく、行動にも移します。たとえば、友達が差別的なことを言われているのを見て、勇気を出して「それは違う」と言う場面があります。その行動に込められたメッセージは、「差別をなくすのは、正しいと思ったときに行動する勇気」だということです。
感想文にこのセリフを取り上げることで、自分なりの考えを伝える良い材料になります。そして、「自分だったらどうする?」という問いを、読んでいる人に自然と投げかけることができるでしょう。
お母さんの言葉に学ぶ愛と教育
本書の中で印象的なのは、息子と母親の会話のシーンがとても多いことです。特に、お母さんが「あなたは正しい。でも、正しさをふりかざすのは、時に人を傷つける」と言った場面は、心に深く残ります。
この言葉には、教育者としての目線と、親としてのやさしさが込められています。正しさだけでは、人を動かすことはできない。伝え方、接し方が大切だということを、この一言から学ぶことができます。
感想文では、ただ「正しいことをする」と書くだけでなく、「どう伝えるか」も考える視点を加えると、より成熟した意見として読み手に伝わります。このセリフを取り上げて、「正しさと優しさのバランスの大切さ」を書くのもおすすめです。
また、このような親子の対話がとても自然に描かれている点も、この本の魅力の一つです。感想文の中でも「家族のあり方」や「親からの学び」などについてふれると、オリジナリティのある内容になります。
子どもが成長する瞬間のひと言
子どもが大人に近づいていくとき、それは「ひと言」でわかることがあります。本書の中で、息子が言った「自分がイエローでも、ホワイトでも、ブルーでも、自分は自分なんだ」というセリフは、その代表的な一言です。
これは、単にアイデンティティの問題ではなく、自分の存在に自信を持ち始めた瞬間を表しています。たとえ他人に何か言われても、「自分の価値は自分で決める」という強い意思が感じられます。
感想文でこのセリフを使うことで、「自分とは何か?」「自分の色とは?」といった深いテーマにつなげることができます。また、自分も人に流されそうになった経験を思い出しながら、「そのとき自分はどう行動したか?」を振り返るきっかけにもなります。
この一言は、読者にとって「成長とは何か?」を考えさせる大切なメッセージになります。
自分の「色」に自信を持つメッセージ
タイトルにもある「イエローでホワイトで、ちょっとブルー」という言葉自体が、まさにこの本の中心にあるメッセージです。この言葉は、見た目やルーツ、気持ちの揺れなど、さまざまな「色」が混ざってできた「自分」を表しています。
社会ではときどき、「あなたは何人?」「どこに属してるの?」という問いを投げられがちです。でも、この言葉はそんな「くくり」から自由になっていいんだというメッセージでもあります。
感想文においては、「自分はどんな“色”を持っているか?」をテーマに書くのも面白いです。たとえば、「私は地方出身で、言葉の違いで悩んだことがある」「家庭がちょっと人と違うと感じたことがある」など、自分の経験とつなげることで、より深みのある感想になります。
「みんな違って、みんな素敵」という多様性の考え方を、自分の色への自信に変える。そんな前向きな気持ちを伝えられるのが、このタイトルの持つ力なのです。
読後に考えたい一言まとめ
この本を読み終えた後、多くの読者が「自分も何かできることがあるかもしれない」と感じるはずです。そんな思いを一言で表すなら、やはり「沈黙は同意だ」というメッセージでしょう。
本の中で、差別を目撃したときに黙っている人が多いことについて、息子が「黙っていると、それは賛成してるのと同じだ」と語ります。この言葉には、行動の大切さがつまっています。
感想文の最後にこの一言を使って、「私はこれから、見て見ぬふりをしない人になりたい」と書けば、とても力強い締めくくりになります。
自分の中に残った言葉を振り返ることは、読書の最後の大切なステップです。この本は、そんな「残る言葉」がたくさんあるからこそ、多くの人の心に届いているのだといえるでしょう。
スポンサーリンク
よくある質問(FAQ)
Q1. 『僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ってどんな本?
A. イギリス在住の日本人ライター・ブレイディみかこさんが、息子と過ごす日常を通して「差別」「多様性」「教育」「貧困」などの社会問題を描いたノンフィクション・エッセイです。
Q2. 読書感想文に向いている理由は?
A. 中学生の視点で語られており、難しいテーマもわかりやすく身近に感じられるため、感情や考えを深めやすく、オリジナリティある感想文が書きやすい本です。
Q3. 中学生でも読みやすいですか?
A. はい、文章は平易で、会話形式も多いため中学生にも読みやすく、学校生活と重ねて共感しやすい内容になっています。
Q4. 読書感想文を書くときのおすすめの構成は?
A. 「印象に残った場面 → 自分との共通点 → 感じたこと・学んだこと → まとめ」という流れで書くと、まとまりがあり読みやすい感想文になります。
Q5. 実際に使える名言やセリフはありますか?
A. 「差別って、大人だけがするんじゃないんだよ」や「自分の色に誇りを持てばいい」など、印象的で使いやすいセリフが多くあります。
Q6. 読書感想文の文字数はどれくらい必要?
A. 学年によって異なりますが、一般的には400~1200字が目安です。この本なら十分に内容が深く、必要な文字数を自然に書くことができます。
Q7. 感想文でありがちな失敗とは?
A. あらすじだけを書いてしまう、感情が入っていない、自分の意見が薄い…といった点がよくあるミスです。自分の体験や気づきを盛り込むとよくなります。
Q8. 多様性について書く時のポイントは?
A. 「違いを認める」「共感する力を育てる」「無意識の偏見に気づく」などをキーワードに、自分が実際に感じたことと結びつけて書くと効果的です。
Q9. 本を読んでから感想文まで、どのくらい時間が必要?
A. 読書には2〜3時間、感想文には構成や下書きも含めて2〜3時間ほど確保すると、丁寧に仕上げることができます。
Q10. 感想文コンクールでも使える本ですか?
A. はい、社会性があり、テーマが深く、文章も洗練されているため、多くの学校や感想文コンクールでも高評価を得やすい作品です。
まとめ
「僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー」は、単なるエッセイ本ではなく、今を生きる私たちにとって必要な“問い”を投げかけてくれる作品です。多様性とは何か、自分らしさとは何か、そして差別にどう向き合うか。この本を読んだ読者一人ひとりが、自分の中にある「当たり前」や「思い込み」に気づき、何かしらの行動を考えるようになります。
感想文の題材としても最適で、特に中学生・高校生には心に響く内容が詰まっています。親子の会話、学校での出来事、社会の矛盾など、身近なテーマを通して社会問題を自分事として考えられるようになるのが、この本の一番の魅力です。
この記事を読んで「読んでみたい」「感想文を書いてみたい」と思っていただけたなら、それが一番の喜びです。読書は、自分自身と対話する最高の時間。ぜひこの本で、自分の「色」を見つけてみてください。
読書感想文にも最適な『僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー』はこちらから購入する事が出来ます。