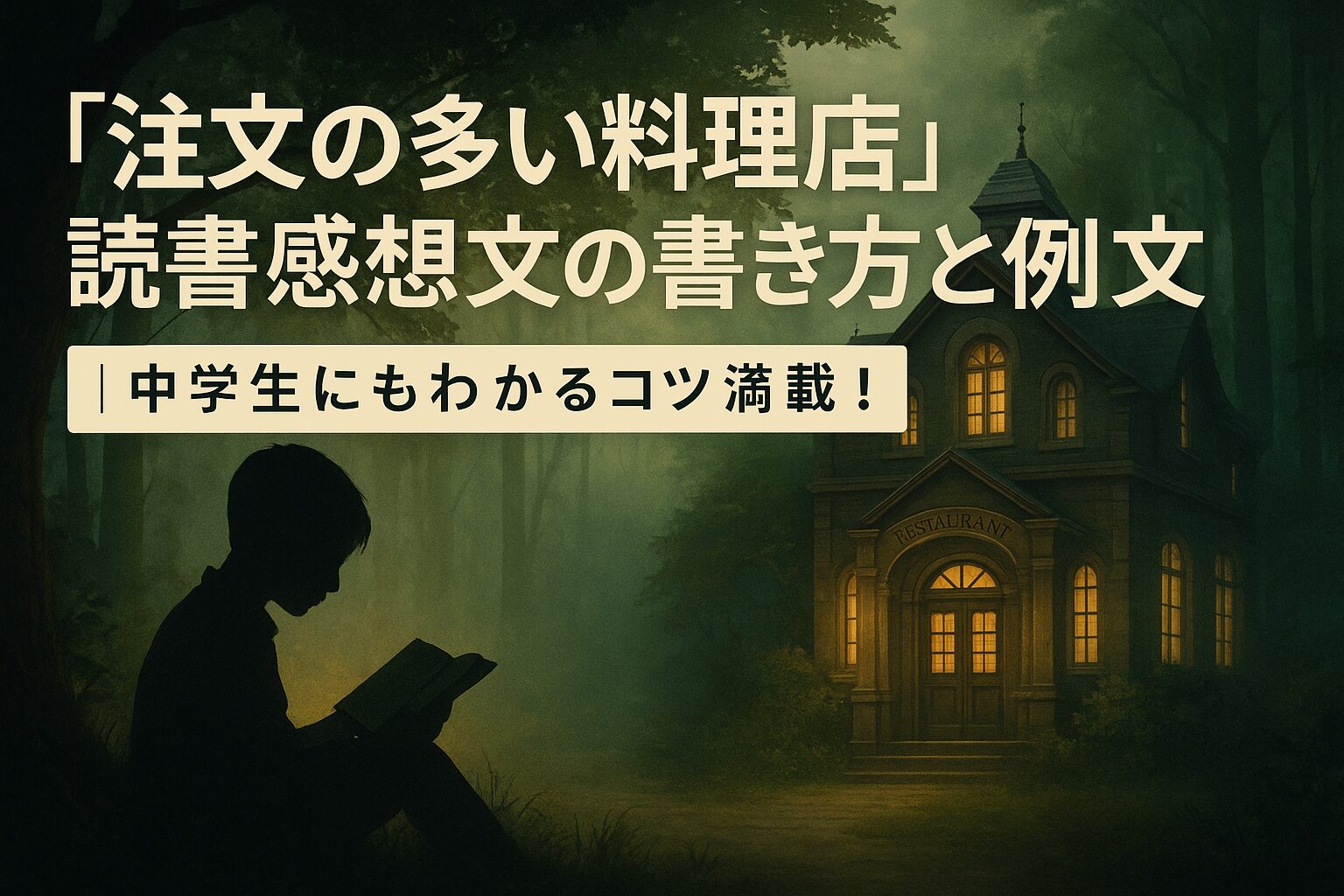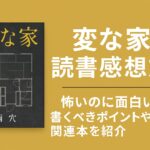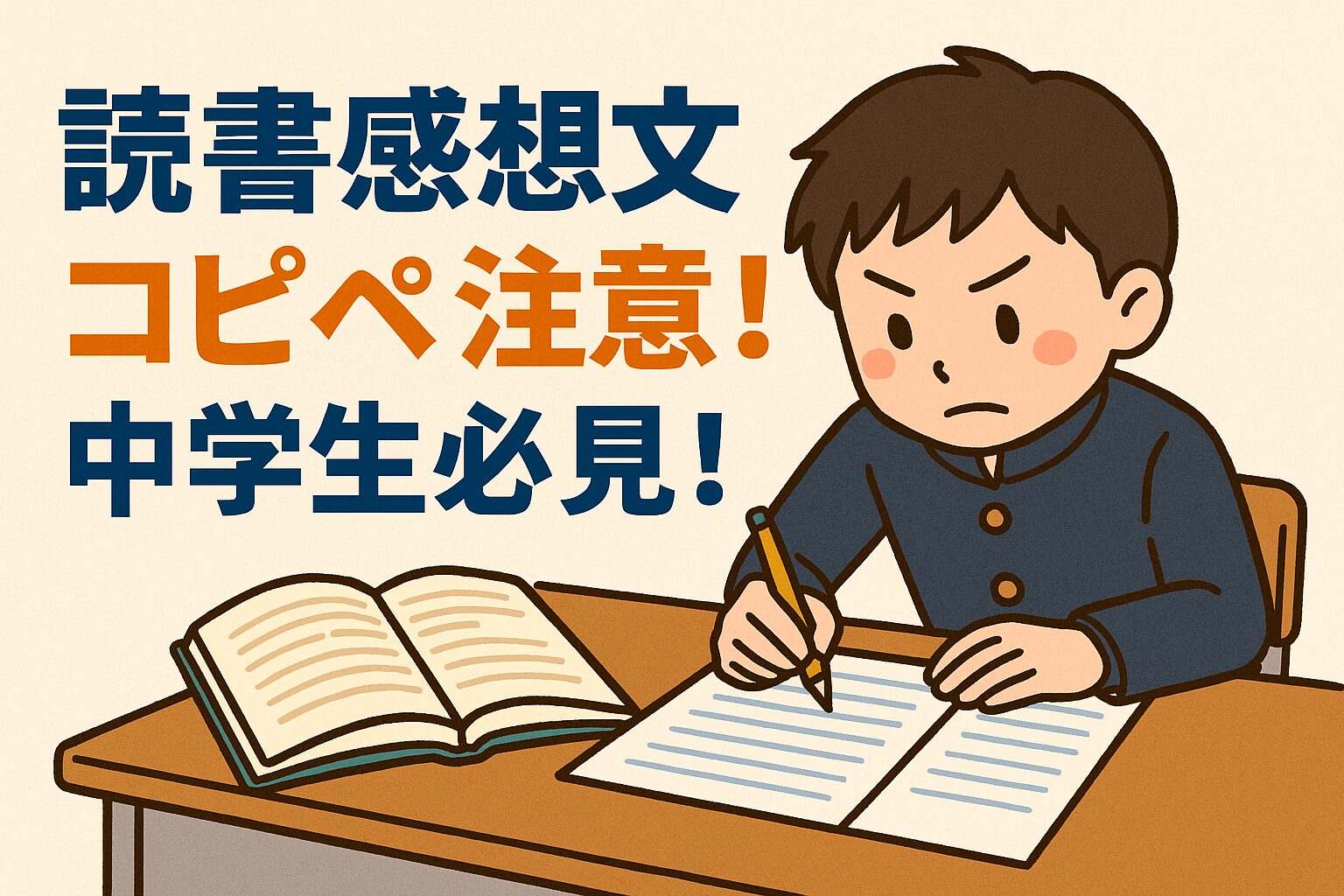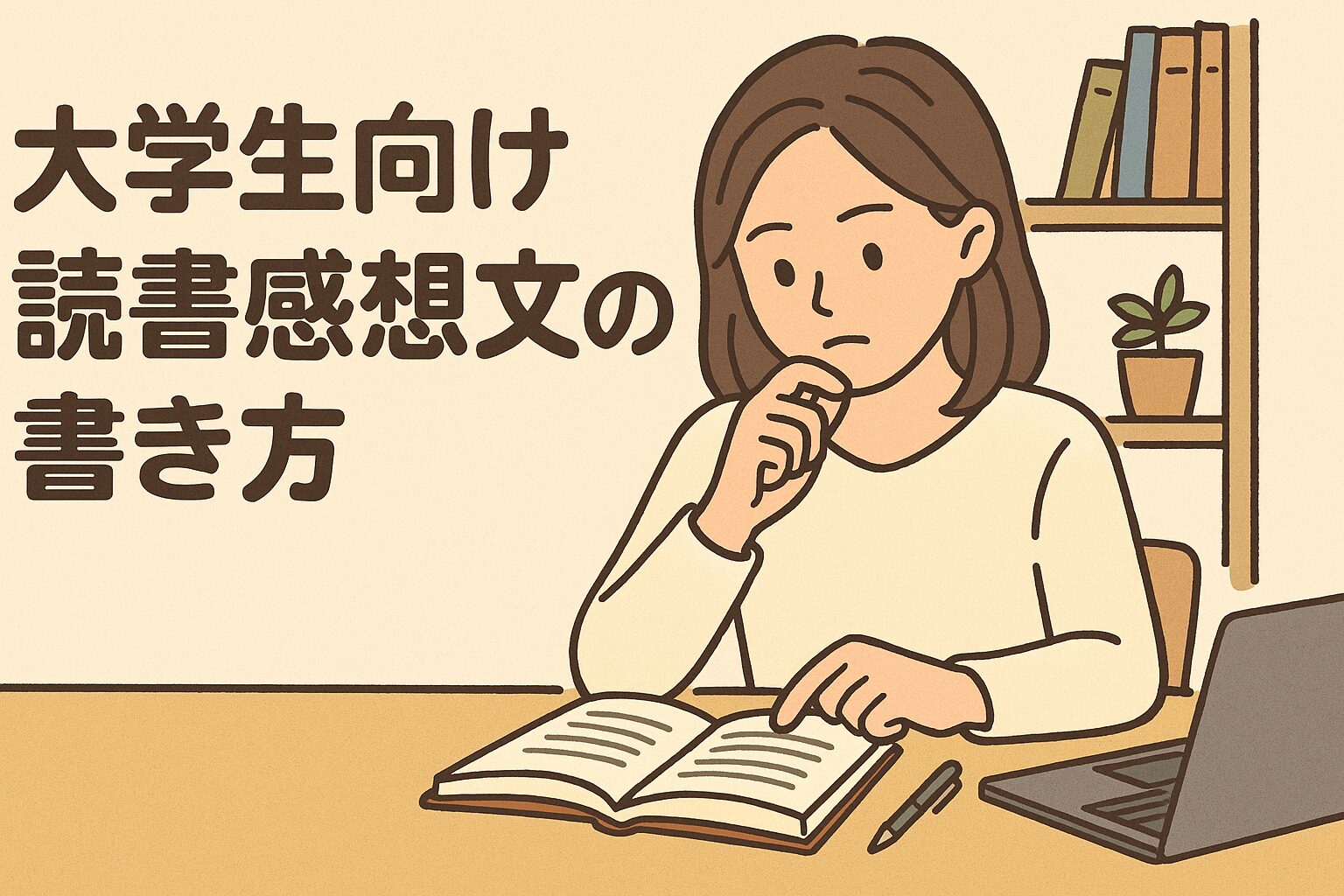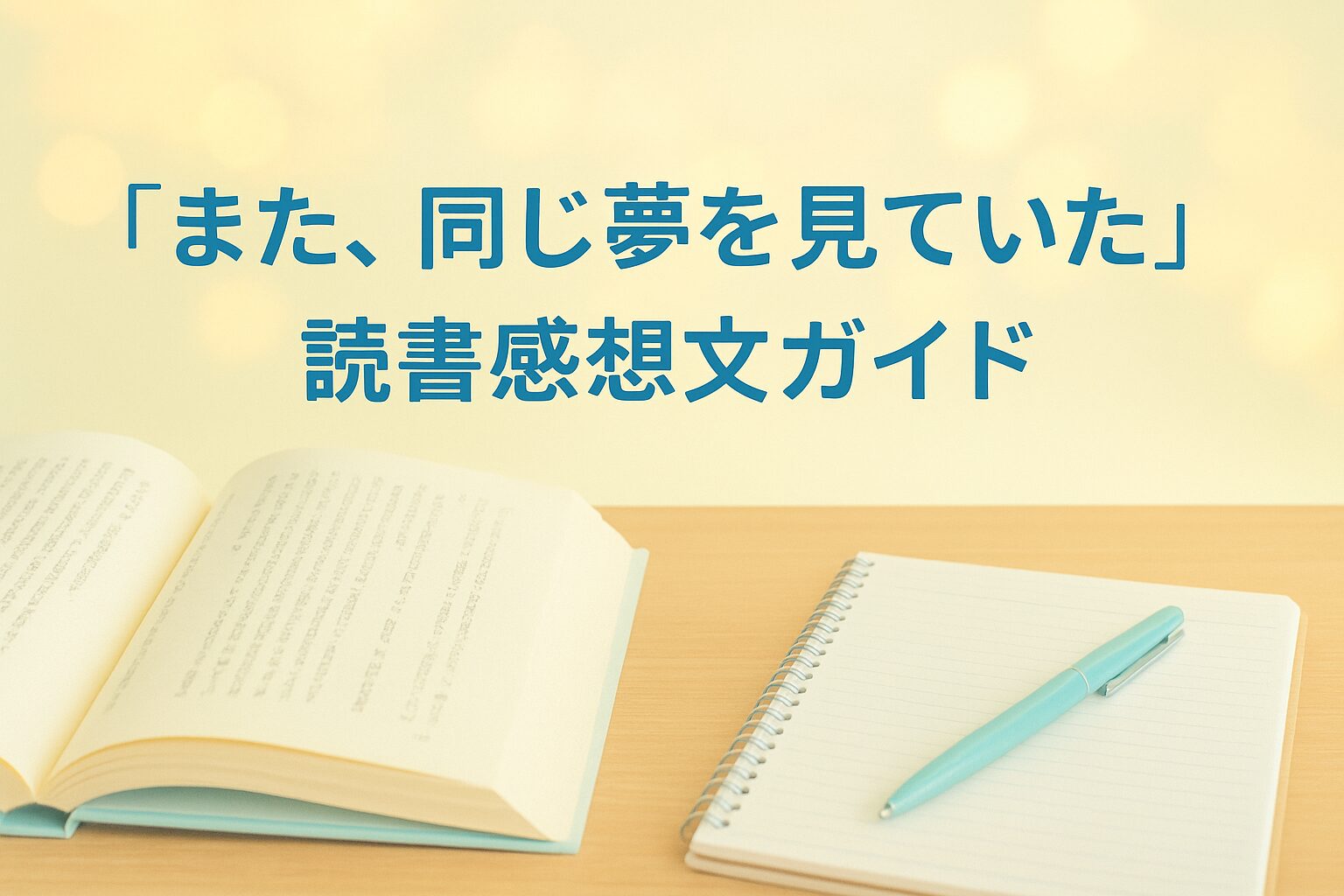「読書感想文って、なにを書けばいいの?」と悩んでいませんか?
特に『注文の多い料理店』のように不思議でちょっと怖い話だと、どう感想をまとめていいかわからなくなることもありますよね。
この記事では、『注文の多い料理店』を読んだあとの感想文の書き方を、具体的なステップや例文をまじえてわかりやすく紹介しています。小学生・中学生どちらにも役立つ内容なので、これから読書感想文を書く方はぜひ参考にしてください!
スポンサーリンク
『注文の多い料理店』ってどんな話?
作者・宮沢賢治の基本情報
宮沢賢治(みやざわけんじ)は、明治から昭和初期にかけて活躍した日本の詩人・童話作家です。彼は岩手県の自然や人々とのふれあいを大切にし、数多くの心あたたまる作品を残しました。代表作には『銀河鉄道の夜』『雨ニモマケズ』『風の又三郎』などがあり、どれも不思議で幻想的な世界観が特徴です。
『注文の多い料理店』はそんな宮沢賢治の童話の中でも特に人気が高い一作で、1924年に発表されました。この物語は、ただの子ども向け童話ではなく、大人が読んでも考えさせられる深いテーマが込められています。自然への畏敬や、人間の傲慢さへの警鐘、そしてユーモアと不気味さが絶妙に交じり合った世界が、読む人の心に残ります。
賢治の作品は、自分が生まれ育った土地への愛や、命の大切さ、そして「見えないものを感じる力」を育ててくれるものばかりです。『注文の多い料理店』もその1つとして、今もなお読み継がれています。
物語のあらすじを簡単に紹介
物語の主人公は、山に狩りに出かけた二人の紳士です。洋服をビシッと決めた二人は、山奥で迷ってしまい、疲れ果てた末に一軒の洋風の料理店「山猫軒」を見つけます。喜んで中へ入っていくと、次々と「お客さまへお願い」という形で奇妙な注文が出されていきます。帽子を脱ぐ、靴を脱ぐ、体を洗う……と進んでいくうちに、どんどんおかしなことに気づきます。
実はこの料理店、「人間を食べるための店」だったのです! 最後の最後に、何かに気づいた二人はどうなるのか? 読者はドキドキしながらページをめくることになります。
この話は短いながらも、ユーモアと怖さが入り混じっていて、読み終わったあとに「自分だったらどうするだろう」と考えてしまう不思議な魅力を持っています。
なぜ人気?今も読まれる理由
『注文の多い料理店』が長年にわたって読み継がれている理由は、その「メッセージの深さ」と「ストーリーの面白さ」にあります。まず、ただの童話ではなく、人間の傲慢さや自然に対する態度について考えさせられる内容になっています。山で道に迷い、自然の中で無力になる人間たちの姿は、現代にも通じる教訓です。
また、ストーリーのテンポが良く、途中の展開が予想外でワクワクさせられます。短いながらもドキドキ感があり、「えっ、どうなるの?」と一気に読めてしまいます。そして、ラストの意外な結末も、読者の心に強く残ります。
加えて、宮沢賢治の独特な言葉遣いや雰囲気が、子どもにも大人にも刺さる魅力を持っているのです。
他の作品との共通点
宮沢賢治の作品には、「自然」「命」「人間の心」といったテーマがよく登場します。たとえば『銀河鉄道の夜』では、死んだ友だちとの別れや、命の意味について描かれていますし、『風の又三郎』でも自然の不思議な力と人間の関係が大切にされています。
『注文の多い料理店』も同じように、自然と人間の関係をユーモラスに、でもちょっと怖く描いています。「自然はただ美しいだけでなく、時に人間にとっては手に負えないものになる」という視点は、他の作品とも通じる部分です。
こういった共通点を見つけながら読むと、賢治作品の世界観がより深く楽しめます。
小学生・中学生にも読みやすい理由
この作品が小中学生にも読みやすい理由は、まず文章がやさしく、リズムよく読めることです。難しい言葉は少なく、短い文でテンポよく物語が進みます。そのため読書があまり得意でない子でも、無理なく読み切ることができます。
さらに、お話が「ちょっと怖いけど面白い」ので、自然と引き込まれます。「次に何が起きるの?」「なんでこんなことが?」と、自分で考える力が自然と育ちます。
また、感想文に書きやすいような「印象的な場面」や「心が動くセリフ」が多いのも魅力です。読んで終わりではなく、感じたことを表現する練習にもぴったりな一冊です。
スポンサーリンク
読書感想文を書く前に考えるべきこと
自分が感じたことを大切にしよう
読書感想文で一番大切なのは、「自分が何を感じたか」を正直に書くことです。「この本はどういうメッセージを伝えているのかな?」と考えることも大切ですが、それ以上に大事なのは、「読んでいるときに自分の中でどんな気持ちがわいてきたか」に注目することです。
たとえば、『注文の多い料理店』を読んで、「ちょっと怖かった」「なんか変な感じがした」「最後にホッとした」と思ったら、それがあなたの感想の「タネ」になります。その気持ちに「どうしてそう思ったのか?」を自分なりに掘り下げていけば、それが立派な読書感想文になるのです。
人によって感じ方は違います。「友だちは笑ったところが、私は怖かった」なんてこともあります。それでも大丈夫。感想文に正解はないので、思ったことを素直に書くのが一番です。
不思議な話だからこそ「疑問」を持とう
『注文の多い料理店』は、不思議でちょっと怖いお話です。だからこそ、「なぜ?」「どうしてこうなったの?」という疑問がたくさんわいてくると思います。その疑問を大切にすることが、感想文を書くヒントになります。
たとえば、「なぜ料理店にはそんなにたくさん注文があったの?」「どうして二人の紳士は疑わなかったの?」「この話の本当の意味は何だろう?」といったことを自分なりに考えてみましょう。そして、その考えたことを感想文に書けば、「自分の考え」がしっかりと伝わる文章になります。
疑問をそのまま書くのもOKです。「ここがよくわからなかった」「これってどういう意味?」と素直に書くことで、読んでいる人も共感してくれます。
自分の体験と重ねてみよう
感想文にオリジナリティを出すコツの一つは、「自分の体験」と本の内容を重ねることです。『注文の多い料理店』で言えば、たとえば「山で道に迷ったことがある」「お店に入ってちょっと怖い思いをしたことがある」「ルールを守らないで困ったことがある」など、自分の過去の出来事とつなげてみましょう。
「本を読んで思い出したこと」や「似たような経験をしたこと」を書くと、感想にリアリティが出ますし、自分にしか書けない内容になります。これはとても大切なポイントです。
また、「この登場人物の気持ちが自分に似ている」と感じたときも、そこを深掘りしてみましょう。「自分もこういう場面でドキドキした」「あのときの気持ちと似ている」といった具体的な話が入ると、読んでいる人の心にも残ります。
心に残った言葉をメモしよう
読書感想文を書くとき、印象に残った言葉や文章をメモしておくととても便利です。『注文の多い料理店』には、何度も登場する「お願い」や、変わった表現がたくさんあります。読んでいて「ん?」と思ったところを線を引いておいたり、ノートにメモしたりすると、あとで感想文を書くときに役立ちます。
たとえば、「だんだん服を脱がされていく場面が怖かった」「『注文が多い料理店』という言葉の意味が変わって感じられた」など、気になったセリフや描写を記録しておくと、その部分をきっかけに感想が深まります。
読んでいるときに、「これ、なんかすごい!」と思ったら、それをすぐに書き留めておきましょう。それが感想文の材料になります。
感情の動きに注目してみよう
読書感想文は、「事実」よりも「感情」が大切です。『注文の多い料理店』を読んで、最初は楽しそうだと思ったのに、途中からだんだん怖くなって、最後にはホッとした――そんな風に感情が変化したら、それを書きましょう。
読んでいる間にどう気持ちが変わったかを順番にたどることで、自然な文章が書けるようになります。「ここで驚いた」「ここで不安になった」「ここで安心した」といった感情の流れを、自分の言葉で書いてみてください。
また、「この気持ちは初めてだった」「他の本では感じたことのない感情だった」といった特別な気づきがあれば、それも大切にしましょう。それが感想文の一番の「味」になります。
スポンサーリンク
『注文の多い料理店』感想文の書き方ステップガイド
① はじめに:読んだきっかけや本の印象を書く
感想文は「最初のつかみ」が大事です。読んだきっかけや、読み終わった直後の気持ちを簡単に書くと、読み手にとってもわかりやすい文章になります。たとえば、「先生にすすめられて読んだ」「表紙が気になって読んでみた」など、自分らしい理由でOKです。
また、読んだあとに「おもしろかった」「ちょっと怖かった」「不思議な話だった」といった率直な感想を書くことで、これからどんな気持ちで文章が進んでいくのかが自然と伝わります。
例文:
「今回私は、宮沢賢治の『注文の多い料理店』を読みました。最初はおもしろそうなタイトルだなと思って読み始めましたが、読み進めるうちにどんどん怖くなり、最後にはホッとした気持ちになりました。」
このように「読んだ理由+第一印象」のセットで書くと、書き出しとしてはとてもスムーズです。
② 内容紹介は短く、自分の言葉でまとめる
読書感想文では、あらすじを長々と書くのはNGです。読む人がすでに物語を知っていることも多いので、必要な部分だけを自分の言葉で簡潔にまとめるようにしましょう。
ポイントは、「全体を簡単に伝えること」と「自分の言葉で言いかえること」です。原文のセリフや描写をそのまま書くのではなく、自分の目線で説明するのがコツです。
例文:
「この物語は、二人の紳士が山で道に迷い、たまたま見つけた『山猫軒』という料理店に入る話です。お店の中には『注文』という形で次々におかしなお願いが書かれていて、だんだんと二人はおかしなことに巻きこまれていきます。」
こうした簡単な説明で十分です。そのぶん、感想や考えに多くの文字数を使いましょう。
③ 心に残った場面を選ぶ
感想文を書くとき、すべての場面を説明する必要はありません。むしろ「一番心に残った場面」や「特に印象に残った出来事」を1つか2つ選んで、それについて自分の気持ちを深く書くと、読みごたえのある文章になります。
たとえば、「体を洗わせる注文の場面が怖かった」「最後に犬たちが現れて助けるところが印象的だった」など、自分の心が動いた部分を思い出してみてください。
例文:
「私が一番印象に残ったのは、体にクリームを塗るように言われた場面です。最初はただの注文だと思っていたのに、『食べられる準備』だと気づいたときは、ゾッとしました。」
このように、驚きや不安、安心など自分の気持ちを書き添えることで、感情のこもった感想になります。
④ どう思ったか、なぜそう感じたかを書く
感想文で最も大切なのが、この「自分はどう思ったか、なぜそう感じたのか」という部分です。単に「怖かった」「面白かった」で終わるのではなく、「なぜ怖いと思ったのか」「何と比べてそう感じたのか」を考えて書くことで、内容がぐっと深くなります。
感情には理由があります。「こう思ったのは、自分だったら同じように感じるから」「以前に似た体験をしたことがあるから」といった、自分なりの考えをつけ加えてみましょう。
例文:
「私はこの話を読んで、人間が自然をなめてかかると、ひどい目にあうんだと思いました。二人の紳士は、お金や身なりに自信があって、自然の中でも強いと思っていたけれど、実はとても無力でした。そんな姿が、自分にも思いあたるところがあって、少し反省しました。」
自分の中で「気づき」が生まれると、読み手にも伝わるいい文章になります。
⑤ おわりに:自分の考えをまとめる
感想文の最後は、「この本を読んでどうだったか」「これからどうしていきたいか」といった、自分の考えや成長をまとめて終わらせましょう。読書を通して学んだことや気づいたことを、自分の言葉で整理するのがポイントです。
例文:
「この話を読んで、私は自然の中では人間が思っているほど強くないことを知りました。これからは自然や動物をもっと大切にしようと思います。そして、何かを疑う力や、まわりをよく見る目を持っていたいと感じました。」
このように「読んだあと、自分の考えがどう変わったか」を書くことで、感想文がしっかりまとまります。
スポンサーリンク
感想文の例文とワンポイント解説
小学生向け感想文の例文
ここでは、小学生でも書けるようなやさしい言葉で書かれた例文をご紹介します。感想文を書くときの参考にしてください。
例文:
ぼくは、『注文の多い料理店』という本を読みました。タイトルを見たとき、「料理店なのに注文が多いってどういうことだろう?」と思って、おもしろそうだったので読んでみました。
話の中では、山にしゅうりょうに行った二人の男の人が、ふしぎなお店に入っていきます。そこでは、いろいろな「おねがい」が書いてあって、だんだんへんな気持ちになりました。さいしょはふつうの店だと思っていたのに、どんどんこわくなってきました。
ぼくがいちばんこわいと思ったのは、男の人たちが体にクリームをぬるところです。まるで料理のじゅんびみたいで、「人がたべられちゃうの!?」とびっくりしました。
この本を読んで、自然の中では人間が思っているほど強くないということがわかりました。これからは、もっと自然のことを大切にしたいと思います。
ワンポイント解説:
この例文では「自分の気持ち」「印象に残った場面」「学んだこと」がしっかりと書かれていて、バランスの良い感想文になっています。むずかしい言葉は使わず、自分の言葉でまとめている点がとても大切です。
中学生向け感想文の例文
中学生になると、感想文に「自分の考えの深さ」や「理由づけ」が求められます。以下の例文を参考に、自分の気持ちをより具体的に伝えてみましょう。
例文:
私は今回、『注文の多い料理店』という童話を読みました。最初はユーモアのある話だと思っていましたが、読み進めるうちに、その裏にある深い意味に気づきました。
物語では、都会からやってきた二人の紳士が、山奥で迷い込んだ洋風のレストランで、どんどん奇妙な注文をされていきます。最初は服を脱ぐだけだったのに、次第に「体を洗う」「クリームを塗る」など、明らかに普通ではない内容になっていきます。その場面では、読んでいる私まで不安な気持ちになりました。
私がこの話から感じたのは、「自然の中で人間が思っているほど強くはない」ということです。都会の暮らしでは、自分の身なりやお金で何でもできると感じるかもしれません。でも自然の中では、そんなものは何の役にも立たないことを、この話が教えてくれたように思います。
また、人間の「傲慢さ」が危険を呼ぶというメッセージもあると思いました。私はこの本を読んで、自分が自然や他の人に対してどんな態度をとっているかを見直すきっかけになりました。
ワンポイント解説:
この例文では、「登場人物の行動に対する考察」や「自分の生活とのつながり」がしっかり書かれています。読み取った内容に対して「なぜそう思ったか」という理由を添えることで、説得力のある感想文になっています。
感想文にありがちなミスとは?
感想文を書くとき、よくあるミスには以下のようなものがあります。
| ミスの内容 | 解説 |
|---|---|
| あらすじだけで終わっている | 感想がなく、ストーリーの説明だけになってしまう。 |
| 「面白かった」「怖かった」で終わっている | なぜそう感じたかの説明がないと、感情が伝わりにくい。 |
| 他人の意見ばかりまねしている | 自分の気持ちや考えが書かれていないため、個性が出ない。 |
| 難しい言葉を使いすぎている | 無理にかしこまった言葉を使うと、読みづらくなることがある。 |
これらを避けるためにも、「自分がどう感じたか」を中心に書くことを心がけましょう。
感想が思いつかないときの対処法
「何を書いていいかわからない…」というときは、次のような方法を試してみましょう。
- 一番印象に残った場面を選ぶ
- 「このとき自分ならどうするか?」を考える
- 登場人物の気持ちを想像してみる
- 同じような体験がないか思い出す
- 他の人と感想を話してみる
特に効果的なのが、「自分だったらどうするか?」という視点です。これによって登場人物への共感が生まれ、自分なりの感想が自然に出てきやすくなります。
オリジナリティを出すための工夫
感想文に個性を出すためには、「自分だけの体験」「自分の生活とつながる考え方」を取り入れるのが一番です。たとえば、
- 「山で迷った経験があるから共感した」
- 「友だちとケンカしたときのことを思い出した」
- 「ニュースで見た出来事と似ていると思った」
など、日常の出来事と本の内容をつなげて書くことで、自分にしか書けない感想文になります。
また、物語に出てくるキーワードを使って、自分なりのタイトルをつけたり、感想の最後に自分のまとめの一言をつけたりするのも良い工夫です。
スポンサーリンク
読書感想文を書くことで得られること
自分の考えを言葉にする力がつく
読書感想文は、「考えたことを文章にして表す」というとても大切な練習になります。本を読んで、「面白い」「こわい」と思っても、その気持ちを人に伝えるには、自分の言葉で説明する力が必要です。
感想文を書くことで、「なぜそう思ったのか?」を自然と考えるようになります。それを文章にすることで、自分の考えが整理され、はっきりとした言葉に変わっていきます。
この力は、将来の作文やレポート、さらには人との会話でも役に立ちます。自分の考えを上手に伝えることは、どんな場面でも大事なスキルです。読書感想文は、その第一歩としてとても有効なのです。
想像力が広がる
読書をすることで、物語の中の世界を頭の中で思い浮かべるようになります。『注文の多い料理店』では、山奥の静かな森や、不思議なレストランの中の様子を、読者自身が想像して楽しむことができます。
その想像した世界をもとに、「自分だったらどう感じるか」「もしこの話が現実にあったらどうなるか」と考えることは、想像力を大きく育てることにつながります。
また、登場人物の気持ちを考えたり、物語の続きや別の展開を考えたりすることで、より豊かな発想ができるようになります。これは、絵を描いたり、物語を作ったりすることにも役立ちます。
読解力がアップする
感想文を書くには、ただ本を読むだけではなく、「どんな内容だったか」「何が言いたいのか」をきちんと理解していなければなりません。だからこそ、読書感想文を書くことは、読解力を伸ばすのにぴったりの方法です。
たとえば『注文の多い料理店』では、文章に直接は書かれていない「本当の意味」や「裏にあるメッセージ」を読み取る力が求められます。「なぜこんな展開になったのか」「何を伝えたいのか」と考えることで、文章の意味を深く読み取る練習になります。
この力は、国語だけでなく、社会や理科の教科書を読むときにも役立ちます。情報を正しく読み取る力は、これからの時代にとても重要です。
自分を見つめ直すきっかけになる
本を読むと、登場人物の行動や気持ちを通して、自分自身の考えや行動について考えるようになります。「自分だったらどうするか?」「こんなとき、私はどう思うだろう?」といった問いかけが、自然と心の中に生まれます。
感想文にその気持ちを書くことで、自分の価値観や考え方が見えてきます。これは、ただ本を読むだけでは得られない大きな気づきです。
『注文の多い料理店』のように、ちょっと不思議で考えさせられる話は、特に自分を見つめ直す良いきっかけになります。怖かった理由、安心した理由を深掘りすることで、「自分ってこういうふうに感じるんだな」と気づくことができます。
伝える力を磨ける
感想文は、「読んだ人に気持ちが伝わるように書く」ことが大切です。自分だけがわかる文章ではなく、他の人が読んでもわかりやすく、共感できるように書くことで、相手に伝える力が自然と身につきます。
これは、将来のプレゼンテーションや発表、さらには仕事や人間関係にも役立つスキルです。「どう書いたらわかりやすいかな?」「この言い方で伝わるかな?」と考えることが、伝える力を育てます。
特に、自分の気持ちや考えを順番に整理して書く練習になるため、話すときにもスムーズに言葉が出やすくなります。読書感想文は、文章を書く以上の価値を持っているのです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 『注文の多い料理店』の読書感想文はどれくらいの長さが必要ですか?
A.
学校によって違いますが、小学生なら400〜800文字、中学生なら800〜1200文字くらいが目安です。まずは心に残った場面を1つ選び、自分の気持ちを深く掘り下げるように書くと、自然と適切な長さになります。
Q2. あらすじはどこまで書いたらいいですか?
A.
感想文では、あらすじは短く1〜2文でまとめましょう。内容を説明するのではなく、「どんな話だったのか」をざっくり伝えるだけでOKです。そのぶん、感想や自分の考えを多めに書くのがポイントです。
Q3. 感想が思いつかないときはどうすればいい?
A.
「自分がびっくりした場面」や「もし自分だったらどうするか」を考えてみましょう。友達や家族に話しながら思い出すと、自分でも気づかなかった気持ちが見つかることがあります。
Q4. 感想文に正解はありますか?
A.
正解はありません!大切なのは、自分がどう感じたかを素直に書くことです。他の人と違う考えでもまったく問題ありません。むしろ「自分らしい視点」があると、読み手の心に残る感想文になります。
Q5. 『注文の多い料理店』で感想文を書くときのおすすめポイントは?
A.
- 登場人物の気持ちに注目する
- 不思議な注文の意味を考える
- 自分の生活とつなげてみる
- 自然と人間の関係をテーマにする
- 最後の場面のメッセージを読み取る
このような視点を持つと、感想に深みが出てオリジナリティも生まれます。
まとめ
『注文の多い料理店』は、短いながらも奥深いメッセージが詰まった宮沢賢治の代表作です。この物語を読むことで、自然に対する姿勢や人間の傲慢さへの気づき、自分を見つめ直すきっかけなど、さまざまな学びがあります。
読書感想文は、ただ読んで終わるのではなく、「自分はどう感じたか」「なぜそう思ったか」を言葉にすることで、文章力や思考力、表現力を育てる素晴らしいチャンスです。
本記事でご紹介したステップや例文、ポイントを参考に、ぜひ自分だけの感想文を完成させてみてください。「正解」を求めるのではなく、「自分だけの気持ち」に向き合って書くことが、最も大切なことです。