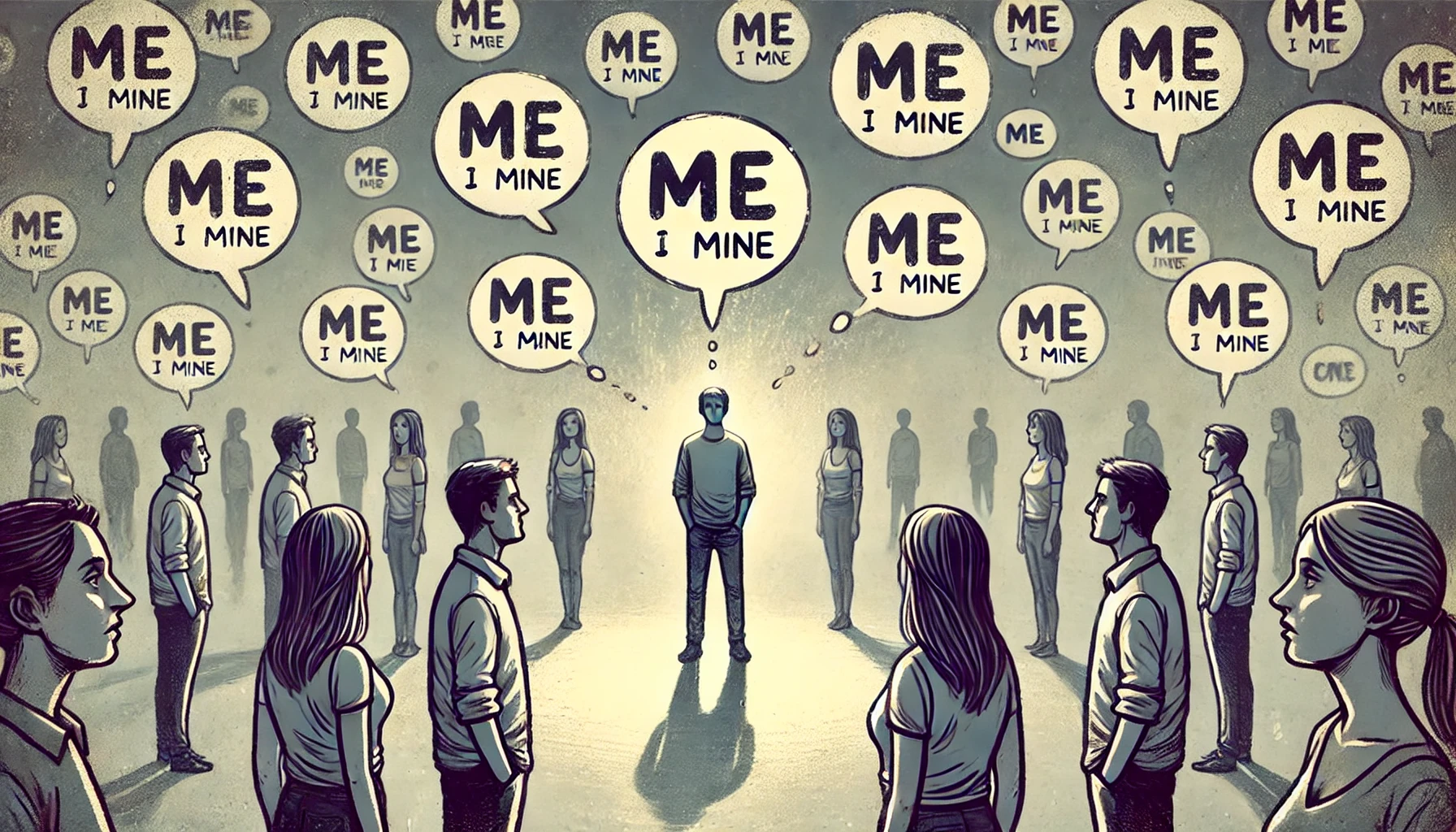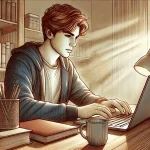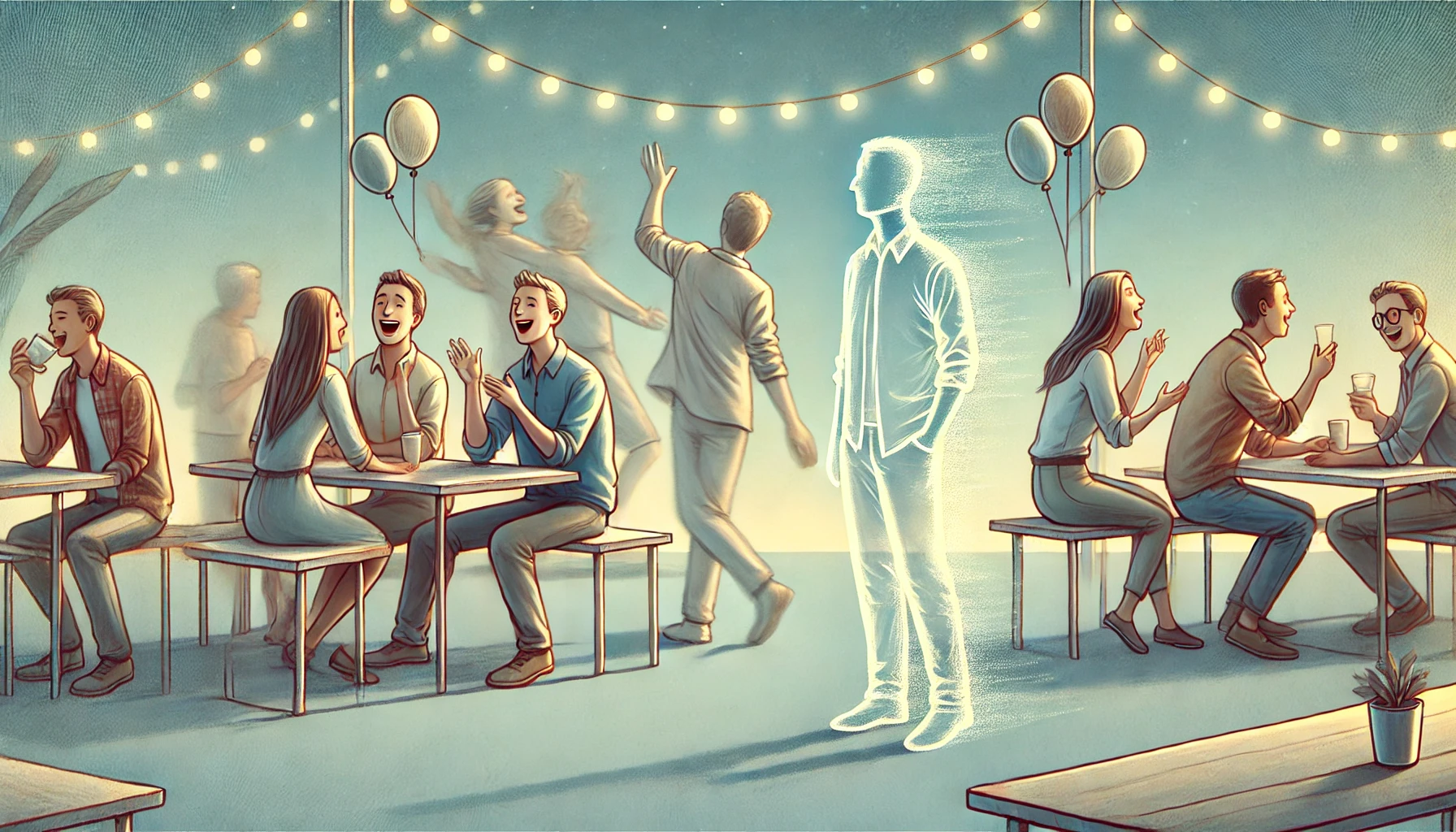あなたの周りに、 「自分のことしか考えない人」 はいませんか?
会話がいつも自分の話ばかりだったり、他人の気持ちを考えずに行動したりする人と付き合うのは、かなりのストレスになりますよね。
本記事では、 「自分のことしか考えない人」の特徴や心理、適切な付き合い方、そして変わる可能性 について詳しく解説します。人間関係のストレスを減らし、自分らしく過ごすためのヒントをお届けします!
スポンサーリンク
「自分のことしか考えない人」の特徴とは?
他人の気持ちを考えない発言が多い
「自分のことしか考えない人」は、無意識のうちに他人を傷つけるような発言をすることが多いです。たとえば、友人が仕事で失敗して落ち込んでいるときに、「それくらい大したことないよ」と軽く流したり、誰かが悩んで相談しているのに「そんなの気にしなければいいじゃん」と片付けてしまうことがあります。
このような発言の背景には、相手の気持ちを深く考える習慣がないことが影響しています。共感力が低いと、相手の気持ちを理解しようとする努力をせず、自分の感覚だけで物事を判断してしまうのです。
さらに、自分の考えを正しいと信じて疑わないため、相手が傷ついたとしても、「そんなつもりはなかった」と自己正当化しがちです。そのため、人間関係のトラブルを引き起こしやすく、周囲の人から距離を置かれることも少なくありません。
こうしたタイプの人と接する際には、あまり感情的にならず、「そういう言い方をされると私は悲しい」と自分の気持ちを伝えることが大切です。相手に悪気がない場合も多いため、指摘することで少しずつ改善されることもあります。
会話が常に自分中心になる
「自分のことしか考えない人」は、会話のほとんどが自分の話題ばかりになる傾向があります。たとえば、友人が旅行の話をしている最中に、「私もこの前旅行に行ってね」と話をすり替えたり、相手の話を途中で遮って自分の体験談を語り始めたりします。
こうした行動の背景には、承認欲求の強さがあります。自分の話を聞いてもらうことで「認められている」と感じ、満足感を得ているのです。しかし、相手の話に興味を持たず、自分の話ばかりする人とは長く付き合うのが難しくなります。
このタイプの人と付き合う際には、適度に相槌を打ちつつも、「それで○○さんはどう思ったの?」と相手の話を続けさせる工夫をすると、会話が一方通行になるのを防ぐことができます。
自分の利益を最優先する行動をとる
「自分のことしか考えない人」は、何かを決めるときに、自分にとっての利益を最優先する傾向があります。たとえば、友人同士で食事をするときに、自分の好きな店ばかり選んだり、職場でチーム作業をする際に、自分が楽できるように役割分担を調整したりすることがあります。
こうした行動は、本人にとっては自然な選択ですが、周囲の人から見ると「わがまま」「自己中心的」と感じられることが多いです。特に、他人の意見を尊重せず、自分の都合ばかりを押し通す場合、人間関係が悪化しやすくなります。
このような人との付き合い方としては、「私はこう思う」「私にとっても大切なことだから」と自分の意見をしっかり伝えることが重要です。遠慮して相手の意向にばかり合わせていると、どんどん自分の立場が弱くなってしまいます。
他人の成功を素直に喜べない
「自分のことしか考えない人」は、他人の成功に対して素直に喜べないことがあります。たとえば、友人が昇進した話を聞いても、「でも、忙しくなって大変じゃない?」とネガティブな面を指摘したり、「私だったらもっと上手くやれるのに」と心の中で比較してしまったりすることがあります。
この背景には、競争意識の強さや自己肯定感の低さが関係しています。自分と他人を比べてしまうことで、「自分が負けている」と感じ、相手を素直に祝福できなくなるのです。また、他人の成功を認めることで、自分の価値が下がると考えてしまう人もいます。
こうしたタイプの人と接する際には、あまり自慢話をしないように心がけたり、相手のプライドを傷つけない表現を選ぶと、関係がスムーズになります。
人間関係のトラブルが多い
「自分のことしか考えない人」は、気づかぬうちに人間関係でトラブルを引き起こしやすいです。たとえば、自己中心的な態度が原因で友人を失ったり、職場で孤立してしまったりすることがあります。
特に、相手の気持ちを無視して自分の意見ばかり押し通すと、人間関係のストレスが積み重なり、周囲の人から距離を置かれることになります。また、自分の非を認めず、トラブルの原因をすべて他人のせいにすることも、関係悪化の一因となります。
このような人と付き合う際には、必要以上に深入りせず、一定の距離を保つことが大切です。無理に関係を続けようとすると、こちらがストレスを抱えてしまうため、自分の心の健康を守るためにも「適度な距離感」を意識しましょう。
なぜ「自分のことしか考えない人」になってしまうのか?
幼少期の環境や育てられ方の影響
「自分のことしか考えない人」になる要因のひとつとして、幼少期の育てられ方が大きく関係しています。例えば、子どもの頃から両親が甘やかしすぎていたり、過度にわがままを許していた場合、他者を思いやる習慣が育ちにくくなります。
また、兄弟姉妹の中で常に優遇されていたり、親の関心を独占できる環境だった人も、「自分の意見が最優先されるのが当たり前」と感じるようになります。逆に、親が厳しすぎて他人に頼ることを許されなかった場合も、自己中心的な思考が育つことがあります。「自分のことは自分で何とかしなければならない」と思い込み、他人の気持ちを考える余裕がなくなってしまうのです。
さらに、家庭内で愛情が十分に注がれなかった場合も、他人に対して共感する力が育ちにくくなります。幼少期に無条件の愛情を受け取った経験が少ないと、他者との関係を「損得」で考える癖がつきやすくなり、「自分にとって得かどうか」で行動を決めるようになってしまうのです。
自己中心的な性格が形成される心理的要因
人間の性格は、環境だけでなく、もともとの気質や遺伝的な要因によっても形成されます。たとえば、もともと自分の考えを優先するタイプの人は、周囲に対して配慮することが苦手な傾向があります。
また、自己肯定感が極端に高い場合、「自分は正しい」と思い込んでしまい、他人の意見を受け入れにくくなります。逆に、自己肯定感が低い人の場合も、他人に認められたいがために自己主張が強くなり、結果的に自己中心的な行動をとってしまうことがあります。
特に、周囲から否定されることが少なかった人や、成功体験が多い人ほど、「自分の考えこそが正しい」と思いがちです。このため、他人の立場や意見を考慮することが難しくなり、知らず知らずのうちに自己中心的な行動をとるようになります。
承認欲求が極端に強い場合
「自分のことしか考えない人」の中には、承認欲求が非常に強いタイプの人もいます。このタイプの人は、自分が注目されたい、認められたいという気持ちが強すぎるため、他人の話を聞くよりも自分のことを話すことに夢中になります。
SNSなどで「いいね」やフォロワーの数を気にする人も、この傾向があることが多いです。他人に認められることで自己価値を確認しようとするため、自分のことをアピールすることにばかり意識が向いてしまいます。
こうした人は、「自分が認められている」と感じることで満足するため、他人の気持ちを軽視することが増えます。その結果、「相手がどのように感じるか」よりも、「自分がどう見られるか」に重点を置いてしまうのです。
競争社会による自己防衛本能
現代社会では、競争が激しく、自己アピールが求められる場面が増えています。特に、仕事や学業の場面では、「自分を主張しなければ生き残れない」というプレッシャーを感じることも多いでしょう。
そのため、「自分が成功するためには他人のことを考えている余裕はない」と考えるようになり、結果的に自己中心的な行動をとるようになります。特に、成果主義の職場や、厳しい受験競争を経験した人ほど、「自分を優先しなければ生き残れない」という思考が強くなりがちです。
また、ビジネスの場面では、リーダーシップや積極性が重視されるため、「周囲の意見を尊重するよりも、自分の考えを貫くことが成功につながる」と考えるようになる人もいます。その結果、私生活でも同じような態度をとってしまい、自己中心的な性格が強まるのです。
過去のトラウマや失敗体験の影響
「自分のことしか考えない人」には、過去に人間関係で深く傷ついた経験がある場合もあります。たとえば、信じていた友人に裏切られたり、過去に他人を優先して失敗した経験があると、「自分が傷つかないために、まずは自分を守らなければ」という防衛本能が働くことがあります。
こうした人は、「他人に尽くすと損をする」と感じているため、無意識のうちに自分中心の行動をとるようになります。また、人に対して壁を作ることで、自分を守ろうとする傾向もあります。
この場合、本人も自分が自己中心的だと気づいていないことが多いため、周囲の人が適切なフィードバックを与えることで、少しずつ改善されることがあります。
「自分のことしか考えない人」との付き合い方
期待しすぎず距離をとることが大切
「自分のことしか考えない人」と関わる際に、まず大切なのは 期待しすぎない ことです。「いつか分かってくれる」「話せば変わるかも」と思って接すると、こちらがストレスを感じるだけで終わることが多いです。
例えば、何度も「もう少し人の話を聞いてほしい」と伝えても改善されない場合、それは相手が変わる気がないか、そもそも他人の気持ちを考える習慣がないからかもしれません。そのような人に過度な期待を抱くと、こちらが疲弊してしまいます。
適切な距離を保つこと が、無駄なストレスを減らす最善の方法です。
例えば、以下のような対策を考えてみましょう。
- なるべく 一対一の深い関係にならない ようにする(適度な距離感を維持する)
- 相手に頼りすぎず、 自分の気持ちを大切にする
- 「こういう人なんだ」と割り切って接する
必要以上に関わらず、適切な距離感を意識するだけで、人間関係のストレスは大幅に減ります。
相手のペースに巻き込まれない工夫
自己中心的な人は、気づかないうちに 周囲の人を自分のペースに巻き込む ことが多いです。例えば、仕事の都合を考えずに突然予定を変更したり、自分の話だけを延々と続けたりすることがあります。
このような相手と付き合う場合、 「自分の意志」をはっきり持つことが大切 です。流されてしまうと、相手に振り回されてしまい、ストレスが溜まります。
具体的な対策として、以下のような方法があります。
- 「今は忙しいからまた今度ね」と、毅然と断る
- 「○○時までなら話せるよ」と時間を決めて対応する
- 「私はこうしたい」と自分の意見をはっきり伝える
また、会話の途中で相手のペースに乗せられそうになったら、一度 深呼吸をして冷静に判断する ことも有効です。相手に流されず、自分のペースを守ることが、健全な関係を築くポイントになります。
気持ちを正直に伝える方法
自己中心的な人と長く付き合うと、「この人には何を言っても無駄」と諦めてしまうことがあります。しかし、 伝え方を工夫すれば、相手が少しずつ変わる可能性もあります。
例えば、「あなたって本当に自分のことしか考えてないよね」と 直接的に責める言い方 をすると、相手は防衛的になり、逆効果になることが多いです。そのため、 「私はこう感じた」という伝え方 をすると、相手にも伝わりやすくなります。
✅ 悪い伝え方
「あなたって、いつも自分のことばかりで人の話を聞かないよね。」
✅ 良い伝え方
「私はもう少し、お互いに話せる会話ができるとうれしいな。」
また、相手の行動が問題になっている場合は、具体的な場面を挙げて伝える ことが効果的です。
✅ 具体的な伝え方
「この前、私が相談したときにすぐ自分の話になってしまって、ちょっと寂しかった。」
こうした方法を使うことで、相手が少しずつ自分の行動を振り返るきっかけになることもあります。
感情的にならず冷静に対応する
「自分のことしか考えない人」と話していると、イライラしたり、ストレスを感じることが多くなります。しかし、感情的になって怒ったり、文句を言ったりすると、相手は逆に反発してしまうことが多いです。
大切なのは 冷静な態度を保つこと です。
相手の発言にカチンときても、一度 深呼吸して「本当にこの言葉に反応する価値があるのか?」と考えてみましょう。
例えば、以下のようなシチュエーションを想定してみます。
✅ 悪い反応(感情的になる)
相手:「○○さんって、考えが浅いよね。」
あなた:「は?そんなこと言われる筋合いないんだけど!」
✅ 良い反応(冷静に対応する)
相手:「○○さんって、考えが浅いよね。」
あなた:「そう思うんだね。でも私はこう考えてるよ。」
感情的にならずに冷静に対応すると、相手も反論しにくくなります。さらに、「この人には適当に接しても通じないな」と思わせることができるため、少しずつ態度を変えさせることができるかもしれません。
必要なら関係を整理する選択肢も
「自分のことしか考えない人」との付き合いがあまりにもストレスになる場合、思い切って関係を整理することも検討しましょう。
もちろん、人間関係は大切ですが、 自分の心が疲れすぎてしまうなら、それは健全な関係とは言えません。
関係を整理する方法には、以下のようなものがあります。
- 徐々に距離を置く(連絡頻度を減らす)
- 会う回数を意図的に減らす
- 思い切って縁を切る(必要ならブロックも視野に)
相手が変わる見込みがなく、自分が一方的に我慢するだけの関係なら、 「離れる」ことも選択肢の一つ です。自分の人生を大切にするためにも、ストレスの原因となる人間関係を見直すことが重要です。
「自分のことしか考えない人」に影響を受けないための心構え
自分の価値観をしっかり持つ
「自分のことしか考えない人」と接していると、知らず知らずのうちに相手の考えに影響を受けてしまうことがあります。例えば、「自分の利益を最優先するのが当たり前」「他人の気持ちを考えるのは損」というような価値観を押し付けられることもあります。
そんなときに大切なのは、 自分の価値観をしっかり持つこと です。
✅ 自分の価値観を守るためのポイント
- 「自分はどうしたいのか?」を常に意識する
- 他人の考えを盲目的に受け入れない
- 自分の信念を持ち、相手の意見に流されない
たとえば、相手が「そんなの意味ないよ」「お前ももっと自己中心的になった方が得だよ」と言ってきても、 「私はそうは思わない」 とはっきりした態度をとることが大切です。
相手の影響を受けて自分まで利己的な考え方になってしまうと、大切な人間関係を失うリスクがあります。 自分はどんな人間でありたいのか? を常に意識し、価値観をしっかり持つことが大切です。
依存せず、対等な関係を築く意識
自己中心的な人と接していると、気づかぬうちに 「相手に合わせすぎる」 状況になりがちです。たとえば、「相手に嫌われたくないから我慢する」「どうせ話しても変わらないから従っておく」というように、自分を犠牲にしてしまうことがあります。
しかし、それでは 対等な関係 を築くことができません。
✅ 対等な関係を築くための意識
- 自分の意見をしっかり持つ
- 無理に相手のペースに合わせない
- 相手の都合ばかり優先しない
例えば、相手が急に予定を変更してきたとき、「まあ仕方ないか」とすべて受け入れてしまうのではなく、 「私はこの予定があるから無理だよ」 としっかり伝えることが重要です。
相手に依存せず、対等な関係を意識することで、ストレスを減らしつつ健全な関係を維持できます。
相手の行動に振り回されない工夫
「自分のことしか考えない人」と関わると、相手の言動に振り回されやすくなります。例えば、突然不機嫌になったり、こちらの気持ちを考えずに無理な要求をしてきたりすることがあります。
しかし、そんなときに 相手の態度に一喜一憂する必要はありません。
✅ 振り回されないための工夫
- 相手の気分に左右されないようにする
- 無理な要求には冷静に「できません」と断る
- 「これは相手の問題であって、自分の問題ではない」と割り切る
例えば、相手が突然怒り出したとしても、「私が悪いのかも」と悩みすぎず、 「この人はこういう性格なんだ」と割り切る ことで、精神的な負担を軽くできます。
自分の気持ちを守るためにも、相手の言動に過剰に反応しないことが大切です。
こちらの意思をハッキリ伝える重要性
「自分のことしか考えない人」は、相手の気持ちを察するのが苦手なことが多いです。そのため、こちらが遠回しな言い方をしても、 「気づいてくれるだろう」と期待するのは危険です。
相手に分かってもらうためには、 「私はこう思っている」とハッキリ伝えること が必要です。
✅ 効果的な伝え方の例
- 「私はこうしてほしい」
- 「この状況は私にとって不快だ」
- 「私はこの方法で進めたい」
例えば、自己中心的な友人が「今すぐ会おう!」と急に誘ってきた場合、嫌なら 「今日は無理だよ、また今度ね」 とはっきり伝えましょう。
言いづらいかもしれませんが、 相手に伝えなければ、ずっと相手のペースに巻き込まれることになります。
周囲のサポートを活用する
「自分のことしか考えない人」との関係に悩んだときは、一人で抱え込まず 周囲のサポートを活用する ことも大切です。
✅ 活用できるサポートの例
- 友人や家族に相談する
- 信頼できる同僚に話を聞いてもらう
- 必要ならカウンセラーに相談する
自己中心的な人と関わっていると、どうしてもストレスが溜まってしまいます。そんなときに、 誰かに話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなることがあります。
また、第三者の視点を取り入れることで 「この関係は続けるべきか?」 を冷静に判断することもできます。
一人で無理に解決しようとせず、周囲のサポートをうまく活用して、自分の心を守ることを忘れないようにしましょう。
「自分のことしか考えない人」は変われるのか?
自覚することで変わる可能性はある
「自分のことしか考えない人」が変わるためには、 まず自分の行動が周囲にどのような影響を与えているかを自覚すること が必要です。
しかし、自己中心的な人は 自分が自己中心的であることに気づいていない ことが多いです。そのため、周囲からの指摘やフィードバックが重要になります。
✅ 自覚を促す方法
- 具体的な事例を挙げてフィードバックする(例:「この前、○○のときに私の話を聞いてくれなかったよね」)
- 感情ではなく事実を伝える(「私の意見も尊重してほしいな」など)
- 周囲の反応を見せる(「最近、みんな○○さんに距離を置いてるよ」と伝える)
ただし、相手が強く反発する場合や、指摘しても改善が見られない場合は、無理に変えようとせず、距離を取ることも選択肢の一つです。
他者の気持ちを理解するトレーニング方法
自己中心的な人が変わるためには、 他者の気持ちを理解する練習 が必要です。共感力を鍛えることで、少しずつ他人の立場に立って考えられるようになります。
✅ 共感力を鍛えるトレーニング
- 「相手の立場だったらどう感じるか?」を考える習慣をつける
- 相手の話を最後まで聞くことを意識する
- フィードバックを受け入れる姿勢を持つ
例えば、会話の中で 「もし自分が相手の立場だったらどう思うか?」 を考えるだけでも、共感力は向上します。
また、日常的に他人の意見を聞く習慣をつけることで、 「自分の話だけをするのではなく、相手の話にも耳を傾ける」 ことができるようになります。
共感力を鍛える習慣を身につける
共感力が低い人は、 他人の感情に興味を持つことが苦手 なことが多いです。そのため、日常生活の中で 意識的に他人の気持ちを考える習慣 を身につけることが重要です。
✅ 共感力を鍛える習慣
- 映画や小説を読んで登場人物の気持ちを考える
- 「あなたはどう思う?」と相手に質問する癖をつける
- 「ありがとう」や「ごめんね」を意識的に伝える
たとえば、小説を読むときに 「この登場人物はなぜこう感じたのか?」 を考えるだけでも、共感力を鍛えることができます。
また、普段の会話の中で 「あなたはどう思う?」と質問する習慣をつける ことで、自然と相手の意見を尊重できるようになります。
他人と協力する経験を増やす工夫
自己中心的な人は、 他人と協力する経験が少ない ことが多いため、意識的に チームで活動する機会を増やすこと も有効です。
✅ 協力する経験を増やす工夫
- ボランティア活動に参加する
- グループワークやチームスポーツを経験する
- 相手の意見を尊重しながら何かを決める経験を増やす
例えば、ボランティア活動では 「誰かのために行動することの大切さ」 を学ぶことができます。
また、チームスポーツでは、 「自分勝手にプレーしても勝てない」 ことを体感することで、他人と協力する大切さを理解できるようになります。
成長する意欲があれば変わることが可能
最終的に、「自分のことしか考えない人」が変わるかどうかは、 本人の成長したいという意欲次第 です。
✅ 変わる可能性が高いケース
- 他人との関係を大切にしたいと思っている
- フィードバックを素直に受け止めることができる
- 自分の行動を振り返る習慣がある
✅ 変わる可能性が低いケース
- 他人の意見を全く受け入れない
- 自分が正しいと思い込んでいる
- 反省することが少ない
もし相手に 「もっと良い人間関係を築きたい」 という気持ちがあるなら、少しずつ変わる可能性があります。
しかし、 変わる気がない人を無理に変えようとするのは、時間の無駄になりやすい です。相手が成長しようとしていない場合は、無理に付き合おうとせず、自分の幸せを優先することも大切です。
まとめ
「自分のことしか考えない人」は、幼少期の環境や性格、社会の影響によって生まれることが多く、周囲の人との付き合い方に悩むことがよくあります。
対応策としては、以下のポイントが重要です。
- 期待しすぎず、適度な距離を保つ
- 相手のペースに巻き込まれない工夫をする
- 自分の意見をはっきり伝える
- 感情的にならず、冷静に対応する
- 必要なら関係を整理する
また、相手が変わる可能性があるかどうかは 本人の意識次第 ですが、共感力を鍛える習慣や協力する経験を増やすことで、改善できることもあります。
ただし、 変わる気がない人に無理に期待するのは逆効果 です。相手に合わせすぎず、自分の心を大切にしながら付き合うことが、ストレスを減らすポイントとなります。