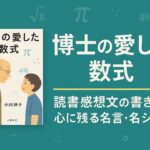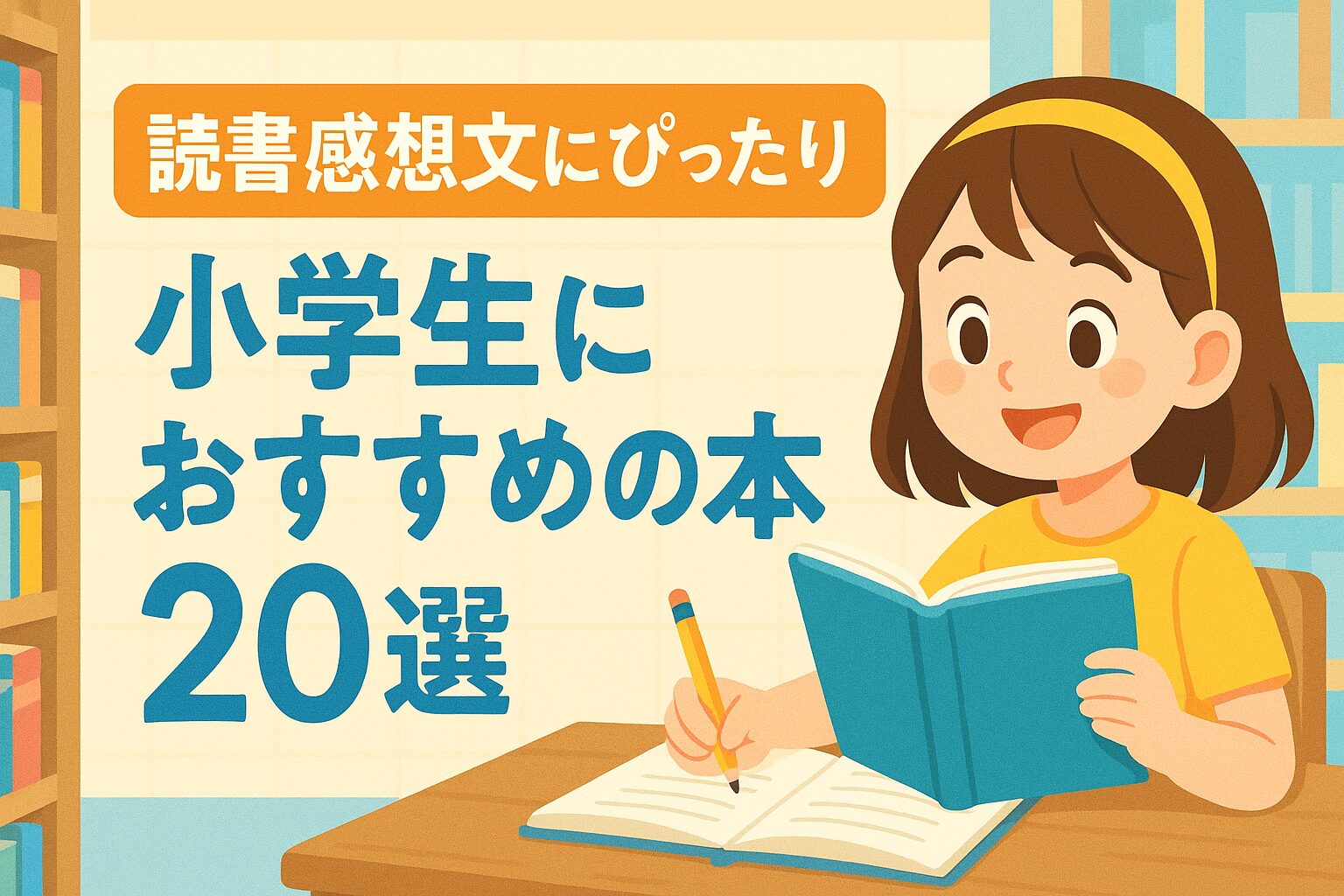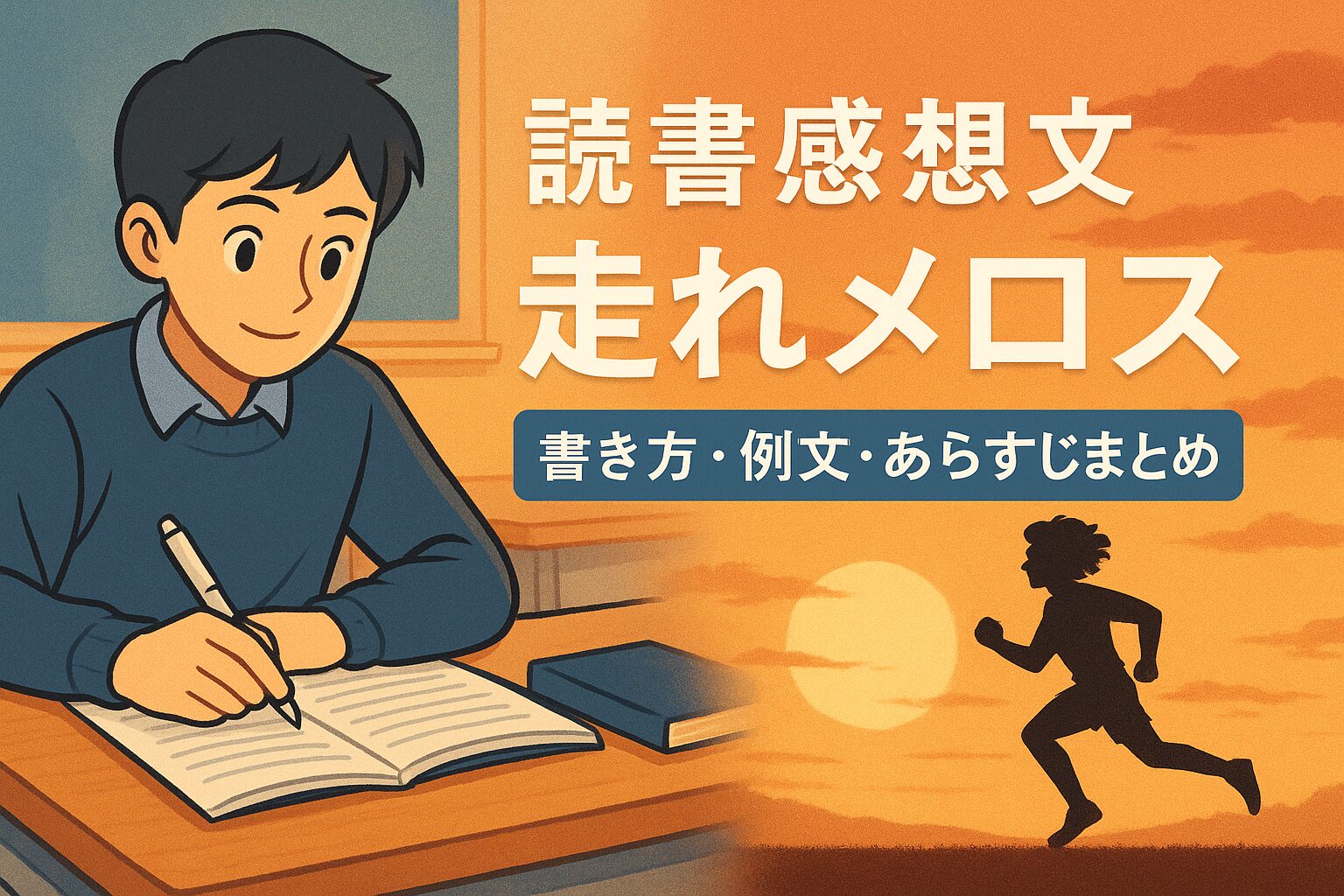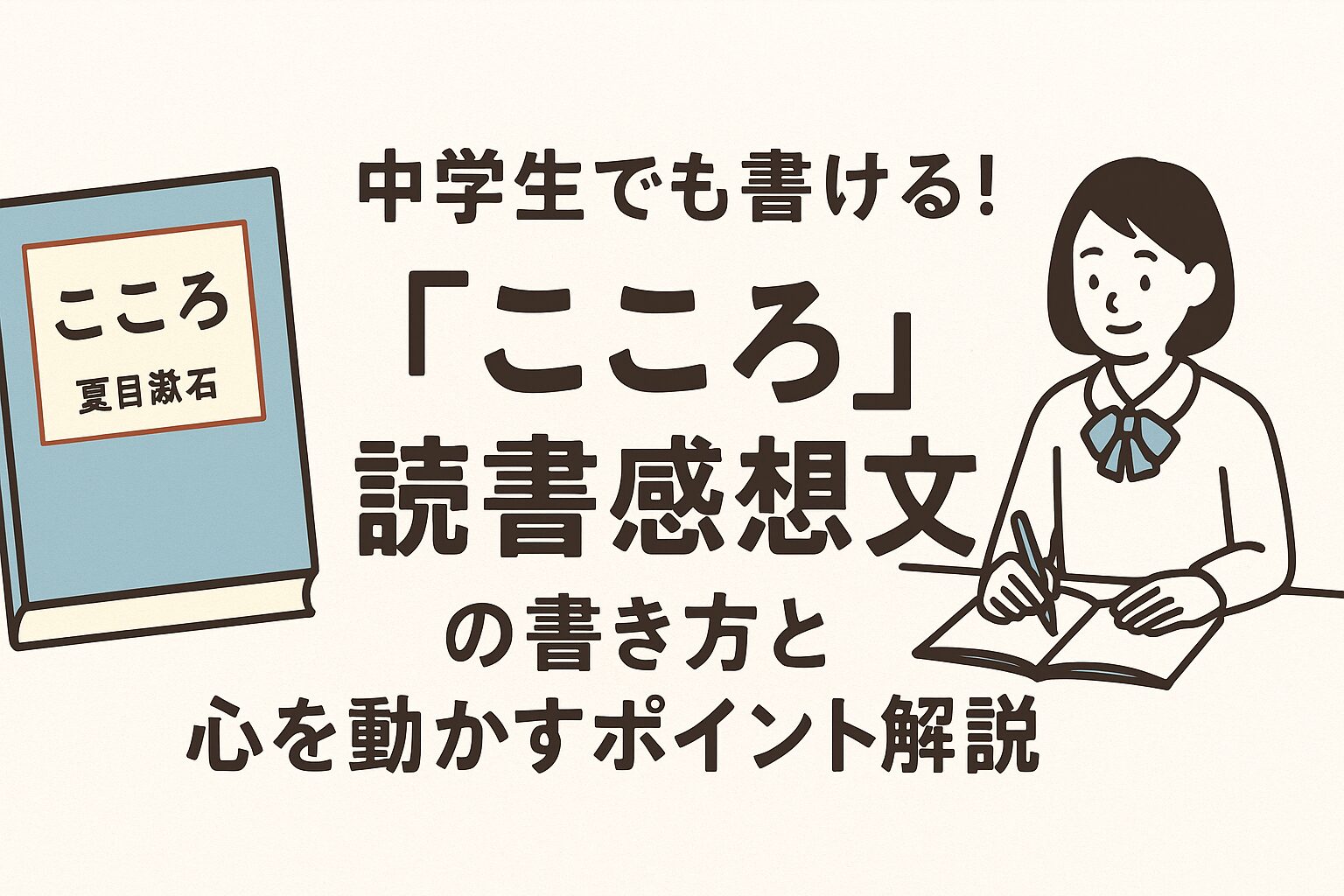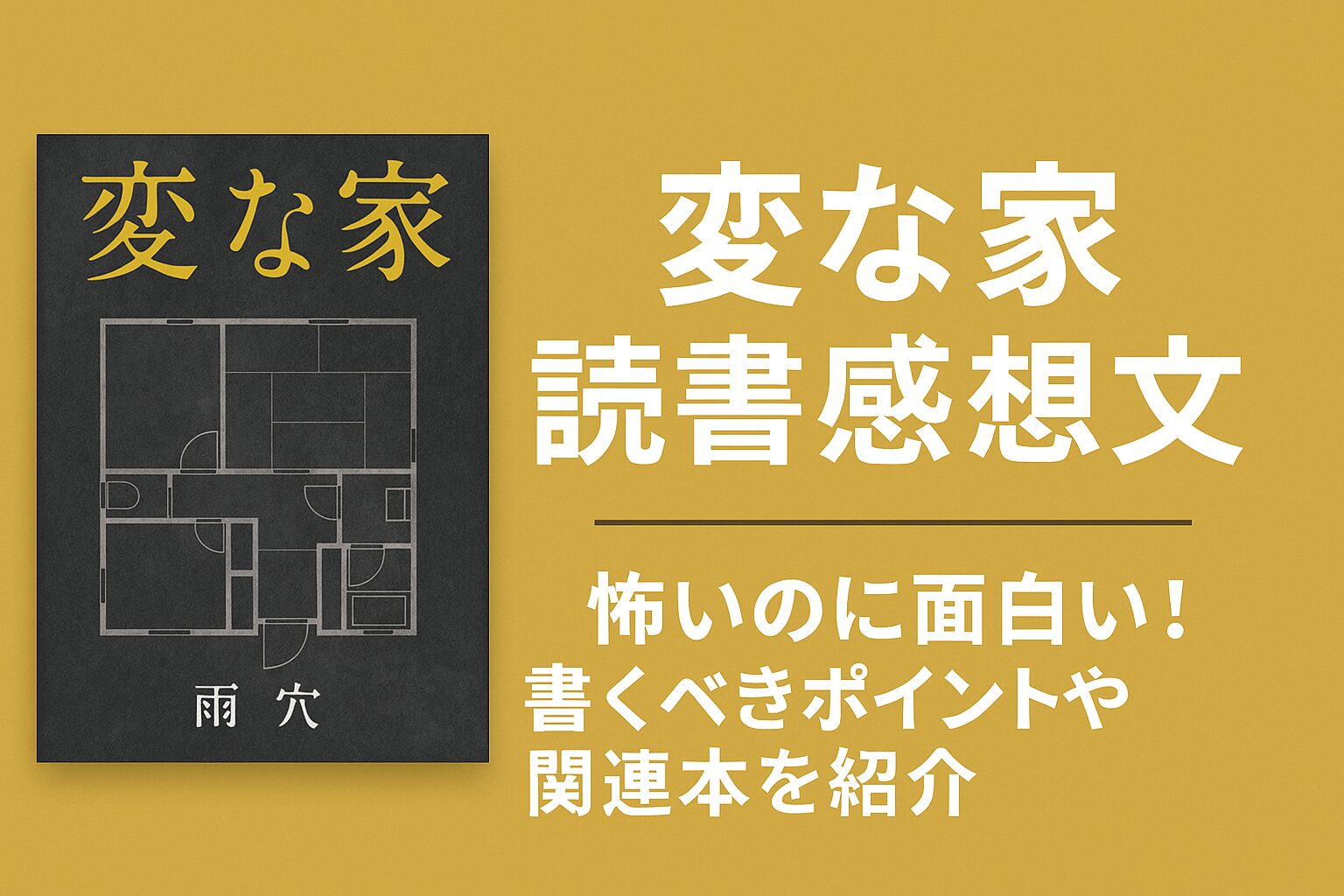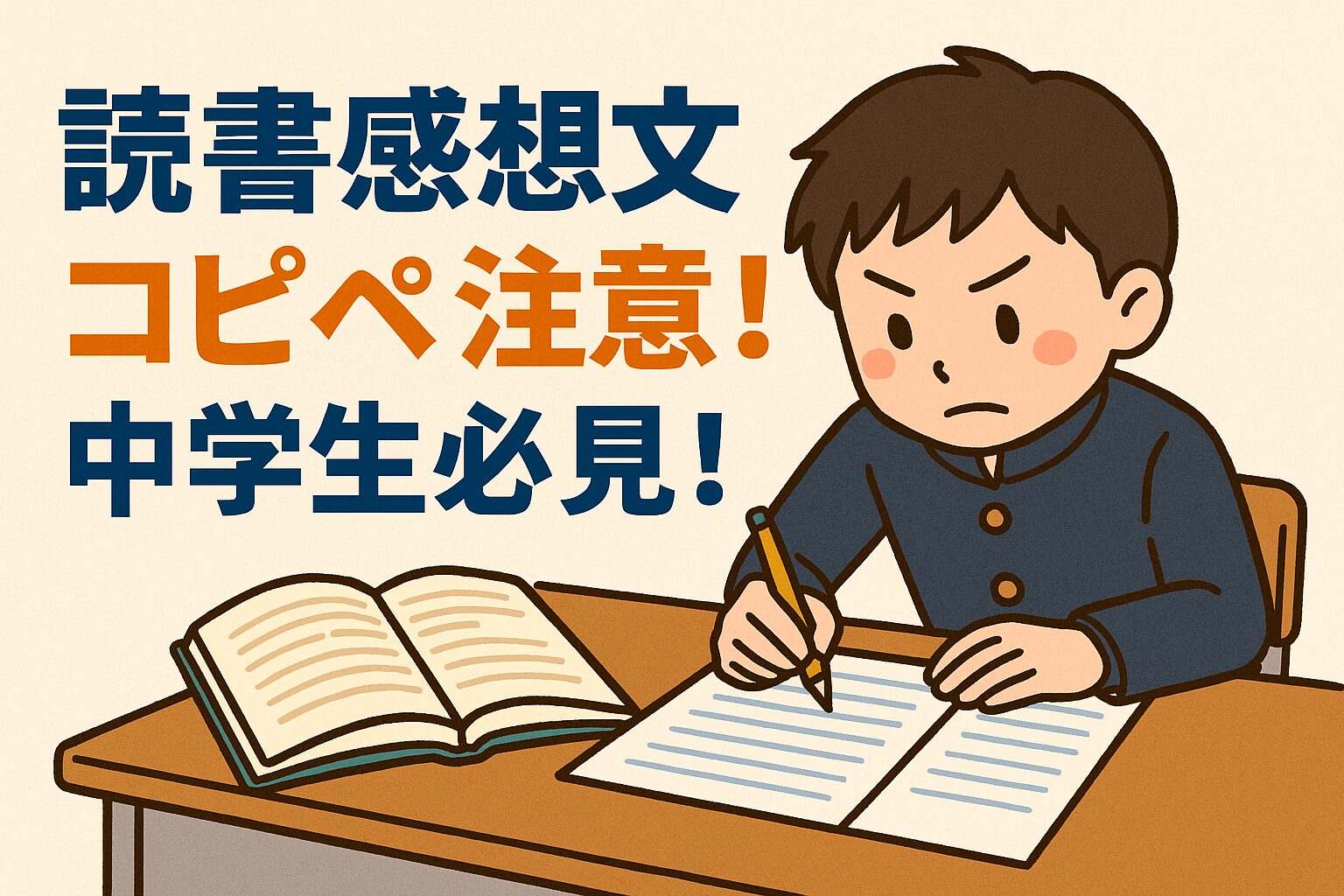「やりたいことって、なんだろう?」
日々の忙しさに流され、自分の本音を見失いそうな人へ。『アフリカでバッグの会社はじめました』は、そんなあなたの心に火を灯す1冊です。日本人女性がアフリカで起業?それってどういうこと?と気になった方は、ぜひこの読書感想文を読んでみてください。
夢、挑戦、失敗、そして再生…読後にきっと、あなたの世界が少しだけ広がります。
スポンサーリンク
アフリカで起業した日本人女性のリアルに学ぶ
ビジネスを始める動機とは?
本書『アフリカでバッグの会社はじめました』の主人公は、普通の日本人女性・萩原麻理さん。彼女がアフリカでバッグブランドを立ち上げたきっかけは、「自分の心が動くことを仕事にしたい」という純粋な思いでした。
日本での会社員生活にどこか違和感を覚えながら、旅行先で見たアフリカの手工芸品に魅了され、「この技術を世界に届けたい」と思うようになります。この動機は一見すると感情的ですが、実は深い洞察と覚悟に裏打ちされています。
現地の素材や技術を活かしながら、フェアな雇用を生むビジネスを作るという構想は、途上国支援のあり方そのものを問い直すものでした。やりたいことに正直に、でも社会に価値をもたらす形で実現しようとするその姿勢は、読み手に大きな気づきを与えてくれます。
文化の違いにどう対応したか
アフリカでビジネスをするには、当然ながら文化の壁が立ちはだかります。時間感覚の違い、言葉の壁、働くことへの価値観の違い…。
本書では、これらの違いに直面しながらも、萩原さんが「相手の文化を否定せずに理解しようとする姿勢」で乗り越えていった様子が丁寧に描かれています。特に印象的なのは「日本の常識は通じない」という割り切り方。
その上で、どうしたらお互いに気持ちよく働けるかを一緒に考え、ルールや価値観を現地の人たちと作り上げていく柔軟さが際立ちます。このプロセスから学べるのは、「違いを克服する」のではなく「違いを活かす」姿勢の大切さです。
グローバル化が進む今、どの職業にも通じるヒントが詰まっています。
現地スタッフとの関係づくり
現地で会社を立ち上げるとき、一番大事なのは「人との信頼関係」です。本書では、萩原さんが徹底して現地スタッフとフラットな関係を築こうと努力する姿が描かれています。
例えば、縫製を教えるときも「教える・教わる」の関係ではなく、「一緒に作り上げる」スタンスを貫きました。日本人だから偉いわけではないし、現地の人だから劣っているわけでもない。そのような先入観を持たず、ひとりひとりの強みを尊重していく姿勢が信頼を生み、やがてチームとして機能していきます。
この人間関係の構築は、単なる職場環境作りを超えて、「ともに未来を創る仲間」としてのつながりを深めていく様子がとても感動的です。
社会貢献とビジネスの両立
社会貢献とビジネスをどう両立するか?これは非常に難しいテーマです。しかし萩原さんは、「売れる商品を作る」ことと「人を支える」ことは矛盾しないと語ります。
バッグという商品自体のクオリティに妥協せず、むしろ現地の技術を活かして高付加価値な商品を作ることで、雇用が生まれ、収入が安定し、職人の誇りも育ちます。
このような「持続可能な仕組み」を作った点が、彼女のビジネスの最大の魅力です。一時的な寄付や支援ではなく、自立を促す形での関わり方は、今後の国際協力やSDGsの文脈でも非常に参考になります。
「利益を出すことが悪」ではなく、「正しい利益の出し方」が重要だと改めて気づかされる章です。
起業家精神とは何かを考える
この本を読み終えた後、「起業家とは特別な才能のある人ではない」と感じる人は多いと思います。萩原さんは決して天才的な経営者ではありません。しかし、共通しているのは「行動する勇気」と「継続する強さ」です。情報収集、計画、失敗、反省、再挑戦…。
その繰り返しの中で、自分の理想と現実のギャップを埋めていきます。特に印象的だったのは「失敗しても、自分が信じたことをやったという事実が残る」という言葉。
この言葉には、起業家としてだけでなく、人としての芯の強さがにじみ出ています。「起業」は一部の人のものではなく、自分らしく生きるための選択肢のひとつなのだと、この章から強く感じました。
スポンサーリンク
「やりたいこと」を見つけるヒントがここにある
自分の気持ちに正直になる大切さ
『アフリカでバッグの会社はじめました』を読んで最も心に残るのは、主人公が「やりたいこと」に対してまっすぐ向き合う姿です。現代の私たちは、社会の期待や周囲の目を気にして、「本当にやりたいこと」を無意識に押し殺してしまいがちです。
しかし萩原さんは、心の中で何度も浮かび上がる「アフリカ」「ものづくり」「人の役に立つこと」への想いを見過ごさず、それに真摯に向き合います。大きな夢でなくても、違和感やワクワクを見逃さずに掘り下げていくことが、自分のやりたいことを見つける第一歩なのだと実感します。
やりたいことが明確でなくても、自分の心が動いた瞬間を大切にすること。それが未来のヒントになると、この物語は静かに教えてくれます。
行動力が人生を動かす
萩原さんのすごさは、思い切って行動する力にあります。「アフリカでバッグのブランドを立ち上げたい」という想いを、実際に現地へ行き、工房を探し、仲間を集め、少しずつ形にしていくプロセスには驚かされます。
多くの人が「やりたいことはあるけど無理だ」と感じてしまうのは、最初の一歩が踏み出せないから。しかし、彼女のように完璧な準備をせずとも、とにかく「動いてみる」ことで道が開けるのです。
最初は小さな行動でも、それがつながり、チャンスを呼び寄せ、夢が現実になっていく過程は、まさに行動力が人生を変えるという事実を証明しています。
何かを始めたいと思っている人にとって、この行動力の大切さは強烈なメッセージとなるでしょう。
不安や迷いとの向き合い方
「やりたいこと」を見つけても、不安や迷いは必ずついてきます。本書では、萩原さんも何度も悩み、落ち込み、葛藤します。現地でのトラブル、日本にいる家族や友人の心配、資金面のプレッシャー…。
そうした困難の中で、彼女は「迷ってもいい、でも止まらない」と自分に言い聞かせながら前進します。この姿から学べるのは、不安をゼロにすることはできなくても、「それでもやる」という姿勢が大切だということです。
また、迷いがあるからこそ、人は立ち止まって考え、成長します。不安を抱えること自体が悪いのではなく、それをどう扱うかが重要なのです。
この考え方は、起業に限らず、進学・転職・人間関係など、人生のあらゆる場面で活きる視点です。
周囲の反対をどう乗り越えたか
新しいことを始めるとき、周囲の反対は避けられません。萩原さんも例外ではなく、「アフリカで起業なんて無謀」「もっと安定した仕事に就くべき」といった声を多く受け取ります。
それでも彼女は、相手を否定することなく、「自分の気持ちに嘘をつかない生き方をしたい」と丁寧に説明を重ね、時には距離を置きながらも理解を得ていきます。このエピソードから感じるのは、反対されることを恐れすぎない勇気と、対話を諦めない姿勢です。
また、全員に理解されることを目指すのではなく、「自分の人生を生きる覚悟」が大事だというメッセージも強く伝わってきます。誰もが人生で一度は「周囲とのズレ」に悩むもの。
そのときにどう振る舞うかが、その後の人生を大きく左右するのです。
「好き」を形にするということ
最後に注目したいのは、「好きなこと」をただの趣味で終わらせず、社会とつながる形に変えた点です。萩原さんはアフリカの工芸品やデザインが好きで、それをただ「見る」「買う」に留めず、「作って売る」というビジネスに昇華させました。
これは簡単なことではありません。好きなことを仕事にすると、時には嫌いになることもあるからです。しかし彼女は、ものづくりへの愛情を忘れずに、むしろビジネスの中で「好き」をどう活かすかを工夫していきます。このプロセスには、多くの学びがあります。
「好きなこと」を形にするには、覚悟と工夫が必要。でも、それが実現したときの喜びは、何ものにも代えがたいのだと感じさせてくれるストーリーです。
スポンサーリンク
アフリカの現実を知ることで世界が広がる
働く環境と生活事情
本書では、アフリカの働く環境や人々の生活事情がリアルに描かれています。日本では当たり前と思われている「定時に出社する」「納期を守る」「安定した電気や水道がある」といった環境が、現地では必ずしも整っていません。
例えば、電気が頻繁に止まるために作業が進まなかったり、スタッフが家族の用事を優先して急に欠勤したりと、日本人には驚くような出来事が日常的に起こります。しかし、これは単なる「ルーズ」さではなく、文化やインフラの違い、生活を支えるための優先順位の違いから来るものなのです。
萩原さんはそうした現実を理解しようと努力し、「日本と同じようにする」のではなく、「この地で最適なやり方」を模索します。これを読むことで、日本にいながらにして別の価値観や世界の現実に触れることができ、自分の常識がいかに限定されたものであるかを知るきっかけになります。
教育とジェンダーの問題
アフリカでは、まだまだ教育やジェンダーの問題が根強く残っています。特に女性や女の子の教育機会が限られている地域では、家庭の手伝いや結婚のために学校に通えないケースも多く見られます。
そうした中で、萩原さんが立ち上げたバッグブランドは、女性たちに職業訓練や就労の場を提供することで、大きな変化をもたらしています。仕事を通じて「自分でお金を稼げるようになる」ことで、女性たちは自信を持ち、家庭内での立場も変わっていくのです。
さらに、仕事をする母親の背中を見て、子どもたちが将来の夢を持つようになるという連鎖も生まれています。本書を通じて、教育とジェンダーの問題は単なる「女性の問題」ではなく、社会全体の発展に関わる大切な課題であることを学ぶことができます。
フェアトレードの意味とは?
「フェアトレード」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、その本質をきちんと理解している人は少ないかもしれません。本書では、萩原さんがフェアトレードの考え方をベースにビジネスを展開する様子が紹介されており、その具体的な意味がよくわかります。
単に「高く買ってあげる」ことではなく、「対等な立場で価値を認め合い、継続可能な取引を行う」ことがフェアトレードの本質です。現地の職人が自分たちの文化や技術を活かして製品を作り、それを正当な価格で買い取ってもらえるという関係性は、まさに尊厳ある仕事を生むのです。
また、消費者もその背景を知ることで、単なる「商品」以上の価値を感じることができます。フェアトレードは「やさしさ」だけでなく、「お互いをリスペクトする経済活動」なのだと気づかされます。
雇用が生む希望
仕事があるということは、単に収入があるという意味ではありません。それは「将来に希望を持てる」ということでもあります。本書に登場する現地スタッフの中には、以前は収入が不安定だった人や、学校を中退せざるを得なかった人もいました。
しかし、バッグの制作に関わることで、安定した収入を得られるようになり、自分に自信を持てるようになります。中には「今は娘を学校に通わせられるようになった」と語るスタッフもおり、その言葉に胸を打たれます。萩原さんは、「1人の雇用が家族全体を変える」と言います。
この言葉は決して大げさではなく、実際に現地で起きている変化です。経済的な自立がもたらすのは、生活の安定だけでなく、尊厳や未来への意欲。雇用は単なる手段ではなく、人を輝かせる力を持っているのです。
開発支援と自立支援の違い
本書を読んで印象的だったのは、「援助ではなく共に働く」という考え方です。多くの人が「アフリカ=支援が必要な場所」というイメージを持ちがちですが、萩原さんのアプローチはその真逆。困っている人に物資を与えるだけでは、その場しのぎにしかなりません。
しかし、「自分で稼ぐ力」を育てることで、人は本当の意味で自由になります。バッグの製作を通じてスキルを学び、品質管理や商品企画にも関わることで、スタッフたちは職人からプロフェッショナルへと成長していきます。
これは一方的な支援ではなく、「お互いに学び合い、成長し合う関係」で成り立っているのです。この違いを知ることで、私たちの中にある「助けてあげる」という上から目線の考え方が、静かに、でも確実に変わっていきます。
スポンサーリンク
女性起業家の生き方に学ぶ
「普通のOL」がなぜアフリカへ?
萩原麻理さんはもともと、ごく普通のOLとして日本で働いていた女性です。安定した企業に勤め、周囲から見れば何の不満もない生活。しかし、彼女の中には「本当にこのままでいいのか?」という小さな疑問が芽生え始めます。
そして旅先のアフリカで、鮮やかな布や手作りのバッグ、現地の人たちの明るさとたくましさに心を動かされ、「ここで何かを始めたい」という思いが強まっていきました。
このように、最初から特別な能力や夢があったわけではなく、小さな気づきや違和感に向き合い、自分の気持ちに素直になった結果として、アフリカへの道が開かれていきます。
このエピソードは、誰もが「特別な人」でなくても、新しい人生を切り拓けることを教えてくれます。
強さとやさしさを両立する姿
起業家というと、強くてたくましいイメージがありますが、萩原さんはその中に「やさしさ」もしっかり持ち合わせています。現地スタッフに対して厳しいことも言いますが、それは相手を信じているからこそ。
品質を守るためには妥協しない一方で、スタッフの体調や家庭の事情に配慮した柔軟な対応も忘れません。このように「強さとやさしさ」をバランスよく持ち合わせた姿勢が、多くの人の共感を集めています。
また、従業員にとっては「ただの社長」ではなく、「一緒に悩んでくれる仲間」として信頼を寄せられているのです。この両立は簡単なことではありませんが、人間としての魅力や信頼感は、こうした日々の積み重ねによって育まれるのだと感じます。
女ひとりで起業するという挑戦
女性一人でアフリカに渡り、現地で起業するというのは、想像以上にハードルが高い挑戦です。治安の問題、言語の壁、資金の不安、そして何より「女だからできないんじゃないか」という周囲の偏見もあります。
しかし萩原さんは、そうした困難にもめげず、一歩一歩着実に道を切り開いていきました。現地の人々との信頼関係を築き、ビジネスを形にし、スタッフに対しても「一人のプロフェッショナル」として対等に接するその姿勢は、多くの女性に勇気を与えます。
彼女は、「女だからできない」ではなく「女だからこそできることがある」と体現しています。日本でも、性別による固定観念はまだまだ残っていますが、この本を読むことで、性別の枠を超えて挑戦する意義を再確認することができます。
女性のロールモデルとしての価値
社会にはまだまだ女性のロールモデルが不足しています。特に「普通の人が何かを成し遂げた」という事例は少なく、成功者のストーリーは遠い世界のものに感じられることが多いです。
しかし、萩原さんの物語は違います。彼女の出発点は私たちと変わらない。だからこそ、その挑戦がリアルに響くのです。「やりたいことを見つけた」「失敗したけどまた挑戦した」「周囲に反対されたけど信じた道を貫いた」――そうしたエピソードのひとつひとつが、特別な才能ではなく、普通の努力や信念で成り立っているからこそ、多くの女性たちにとって「自分にもできるかも」と思わせてくれます。
この本は、現代を生きる女性たちの背中をそっと押してくれる、心強い存在です。
応援したくなるストーリー
萩原さんの物語は、とにかく「応援したくなる」力があります。その理由は、彼女自身が一貫して「人のために」「社会のために」何ができるかを考え、行動しているからです。単なるビジネスの成功話ではなく、その裏にある苦労や想い、人とのつながりが丁寧に描かれているからこそ、読み手の感情が動くのです。
また、失敗や迷いも包み隠さず描かれているため、読者は「自分と同じような悩みを持っていた人が、ここまで来たんだ」と勇気をもらえます。本を閉じたあと、「私も誰かの力になりたい」「何か始めてみたい」と自然に感じてしまう――そんな力のあるストーリーです。
この本を読めば、きっと誰もが「応援したい」と感じるはずです。
スポンサーリンク
読後に感じた5つの心の変化
自分も何か始めてみたくなる
『アフリカでバッグの会社はじめました』を読み終えたとき、多くの読者がまず感じるのは「自分も何か始めてみたい」という気持ちではないでしょうか。大きな夢でなくてもいい、小さな行動でもいい。
今の自分にできることを、まずはやってみよう――そんな前向きな気持ちが湧いてきます。萩原さんの行動力や勇気は、特別な才能から生まれたわけではありません。ごく普通の生活の中で、「心が動いたことに正直になる」ことから始まったのです。
その姿は、多くの人に「今のままでも、何かはできる」と教えてくれます。本書を通じて、自分の中にも小さな火種があることに気づかされ、その火を育ててみたいと思わせてくれる――そんな不思議な力があります。
失敗を恐れず挑戦したくなる
萩原さんの挑戦の中には、当然ながらたくさんの失敗もありました。商品が売れなかったこと、現地スタッフとのトラブル、資金繰りの苦しさ…。でも彼女は、それを恥ずかしいとは思わず、「挑戦には失敗がつきもの」と受け止めています。
この姿勢はとても勇気づけられます。日本の社会では失敗を避ける傾向が強く、「失敗=悪」という空気がありますが、本書を読むと、その価値観が大きく揺さぶられます。
失敗しても、そこから学べることがある。挑戦したこと自体に価値がある。そう考えられるようになると、人生の選択肢がぐっと広がります。
この本は、挑戦することの大切さと、その背後にある人間的な強さと柔らかさを、読者にそっと伝えてくれます。
世界とのつながりを意識する
私たちは日々、海外の商品を使ったり、外国のニュースを目にしたりしていますが、実際に「世界とつながっている」と感じることは意外と少ないものです。しかしこの本を読むと、アフリカで作られたバッグが日本で売られ、そのバッグが現地の家族の生活を支えていることに気づきます。
たった1つの買い物が、遠く離れた誰かの人生を変えているかもしれない。その事実は、とても感動的です。そして、自分の選択が社会をどう動かすのかを考えるようになります。
フェアトレードやエシカル消費といった言葉が、単なる流行語ではなく「自分ごと」になってくるのです。世界は広く、でも確実につながっている――そんなことを実感できる貴重な読書体験です。
日本での当たり前を見直す
アフリカの生活や文化に触れることで、私たちが「当たり前」と思っていることが、実はとても恵まれていると気づかされます。たとえば、清潔な水が出ること、毎日電気が使えること、時間通りにバスが来ること…。日本では当たり前でも、世界ではそうではない地域がたくさんあります。
本書では、そうした環境の中で懸命に生きる人々の姿がリアルに描かれ、読者に多くの気づきを与えてくれます。決して「かわいそう」という視点ではなく、「違いを理解する」というスタンスで描かれているため、読んでいて不快感はありません。
それどころか、私たちが普段気づかないことに感謝したくなるのです。
この本は、世界を見る目を変えるだけでなく、自分の生活を見直すきっかけにもなると言えるでしょう。
他人の夢も応援したくなる
読後に残るもう一つの温かな感情は、「誰かの夢を応援したい」という気持ちです。萩原さんが現地の人々と夢を共有しながらビジネスを作っていく姿は、まさに「夢の共有」の大切さを教えてくれます。
自分が挑戦することももちろん大切ですが、誰かが挑戦しているのを見て、応援することにも価値があります。この本を読むことで、「夢を応援する」という行為がどれほど力強く、素晴らしいことなのかを実感できます。
そして、身近な人が何かに挑戦しようとしていたら、自分も支えてあげたいと思えるようになるでしょう。人と人のつながりは、こうした応援の連鎖によって深まり、広がっていくのです。
本書は、そんなあたたかな連帯感を私たちに思い出させてくれます。
まとめ
『アフリカでバッグの会社はじめました』は、ただの起業ストーリーではありません。これは、ひとりの女性が自分の気持ちに正直に生き、行動し、そして他人の人生をも変えていく、壮大でリアルな物語です。読者はその中で、「自分らしく生きるとは?」「挑戦するとは?」「世界とどうつながるか?」という多くの問いを投げかけられます。
本書を通して見えてくるのは、アフリカの現実、文化の違い、女性としての葛藤、そして「ビジネスは誰かの幸せのためにある」という大切な価値観です。たった1冊の本が、ここまで心を動かすのかと驚くと同時に、自分自身の人生を見つめ直すきっかけにもなります。
読後には、やさしさと勇気が胸に残ります。そして何より、「何かを始めたくなる」。それがこの本の持つ一番の魅力かもしれません。日常に埋もれそうになっている「本当の自分の気持ち」を、そっとすくい上げてくれる一冊。あなたも、きっと誰かを応援したくなるはずです。