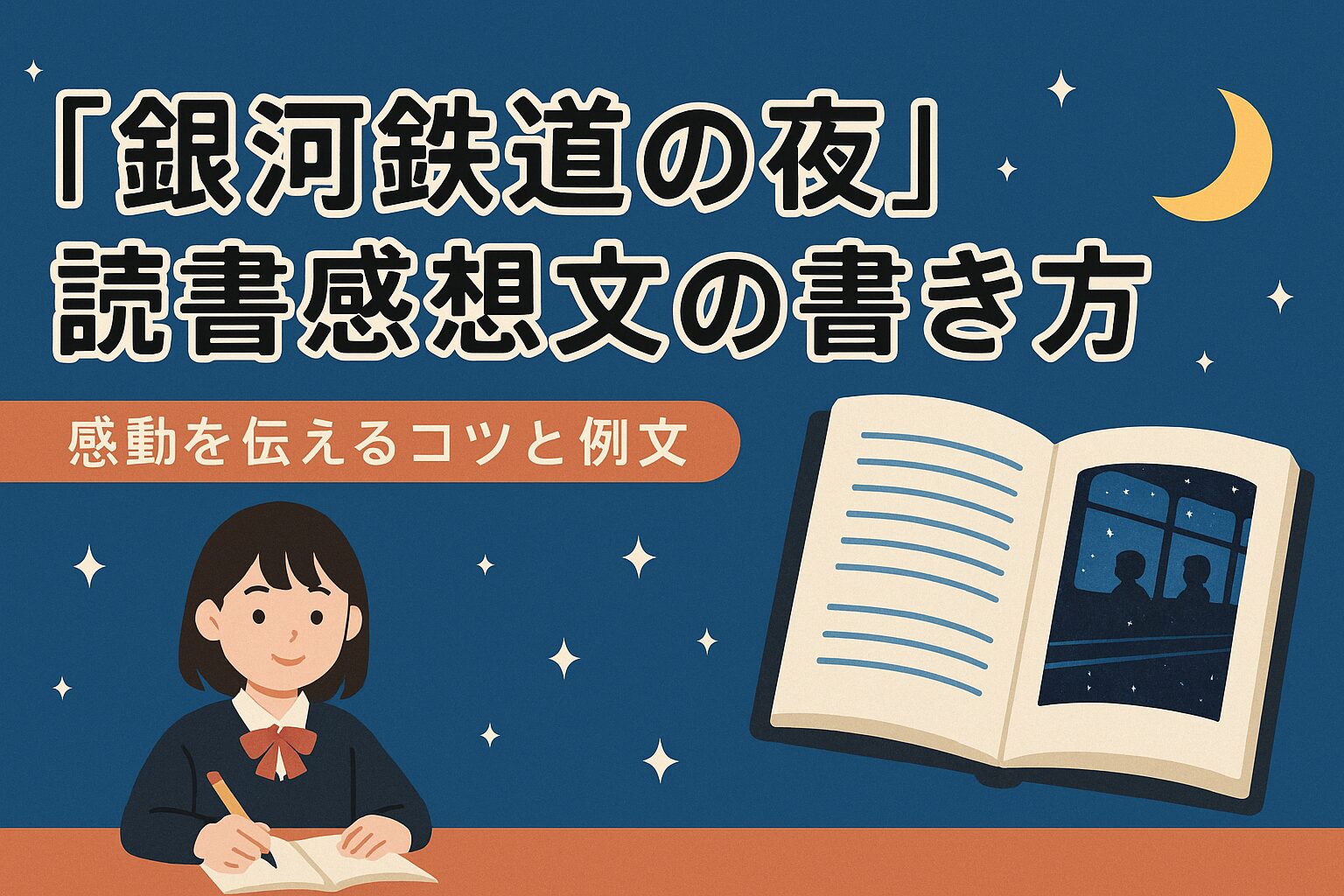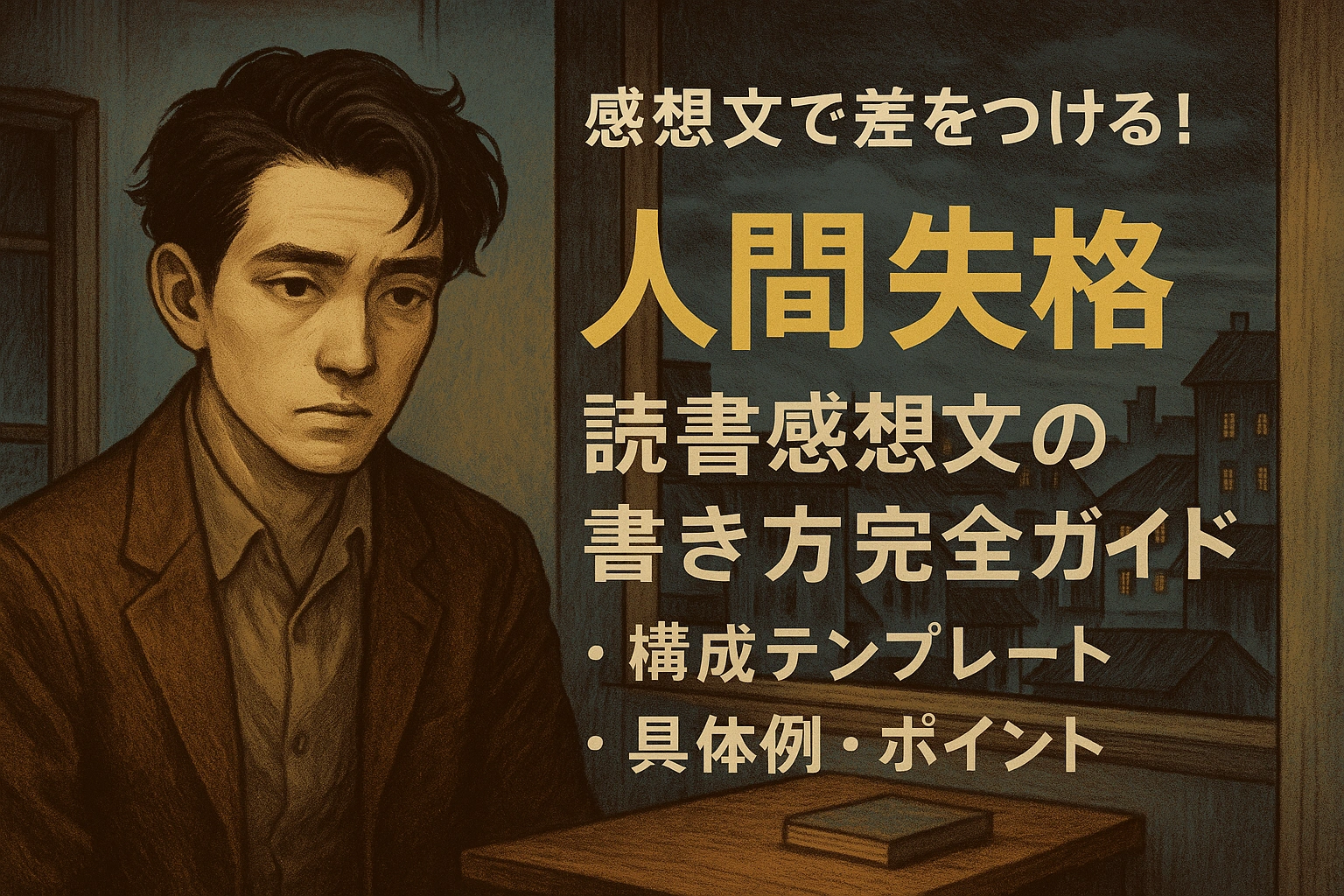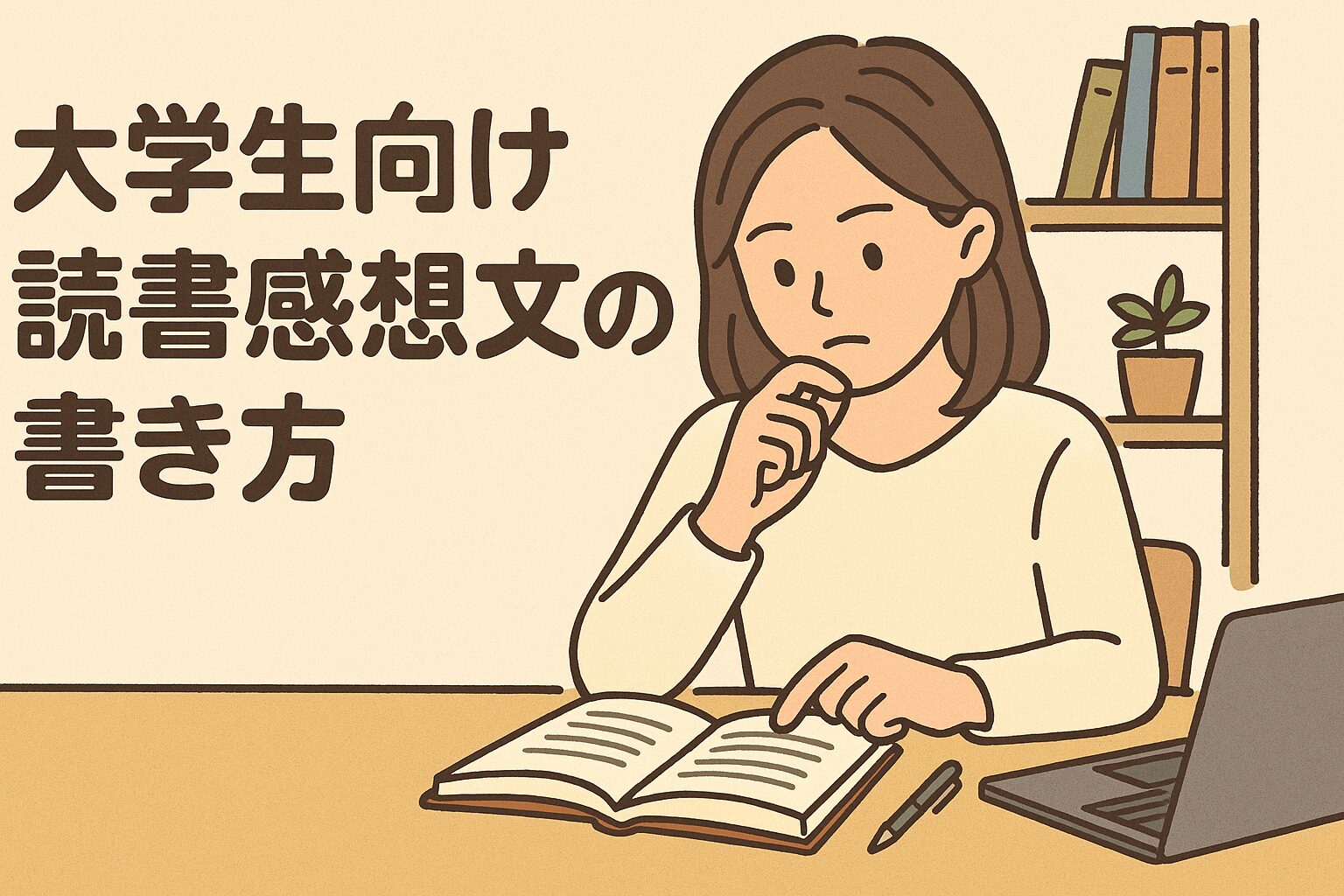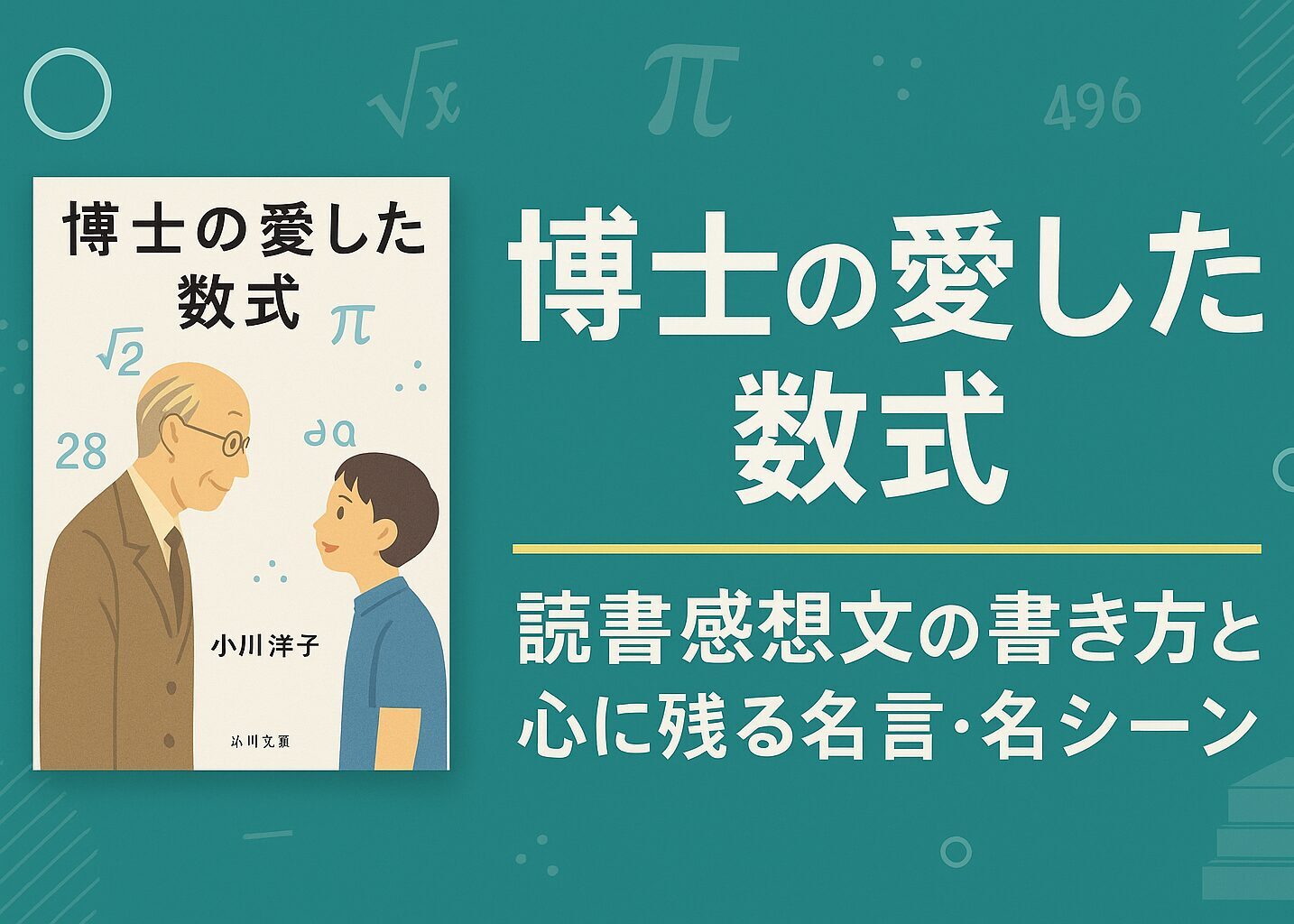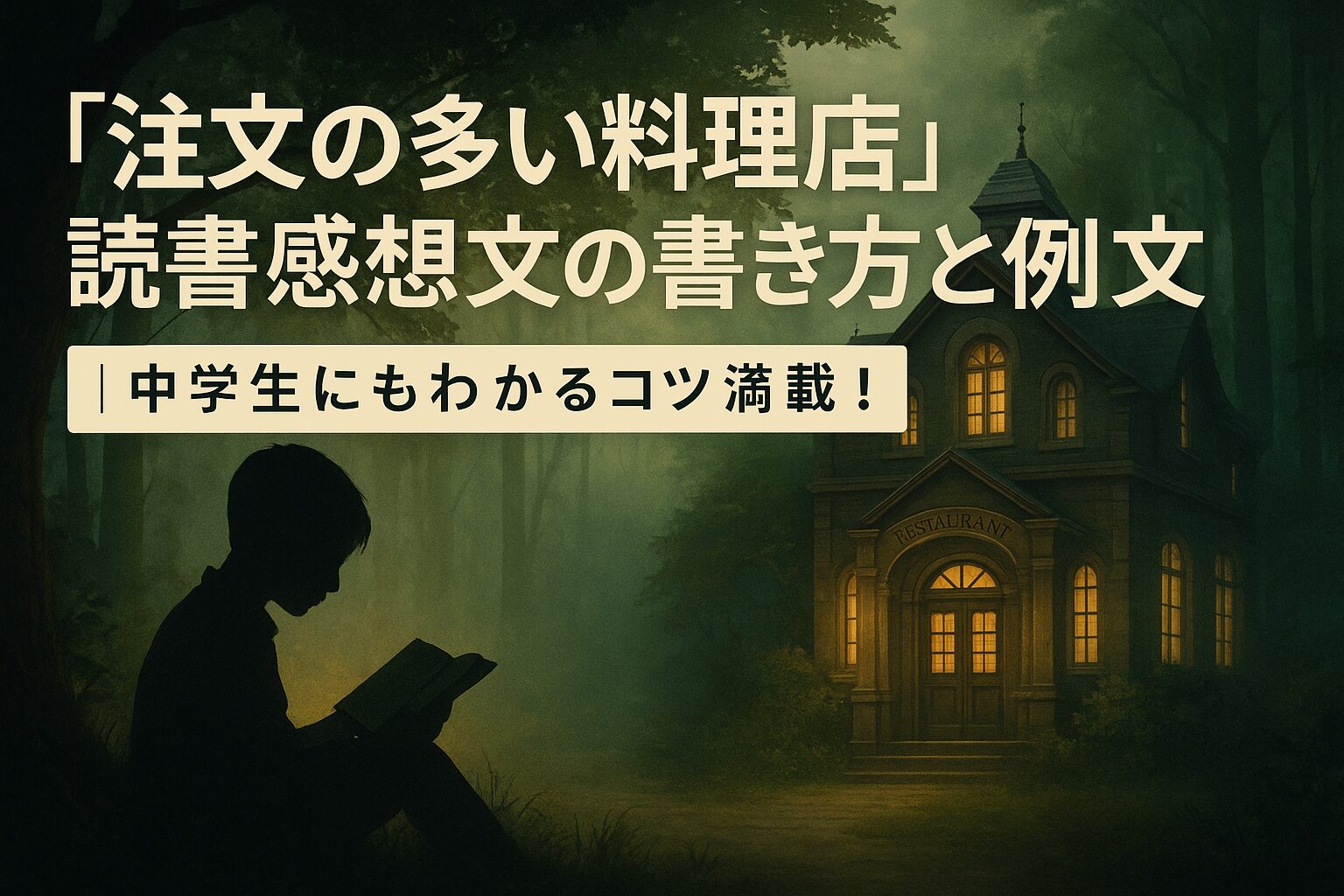「読書感想文、何を書けばいいかわからない!」
そんな悩みを抱えている中学生のみなさんへ。この記事では、読書感想文にぴったりな本の選び方から、忙しい人でもサクサク書ける裏ワザまで、わかりやすくご紹介します。
本選びに迷ったときに参考にできるおすすめリストも充実!さらに、感想文を書くための簡単な3ステップや、あらすじだけにならないコツもばっちり解説しています。
この記事を読めば、きっとあなたに合った一冊が見つかり、自信を持って読書感想文が書けるようになるはず。
さあ、いっしょに読書感想文マスターを目指しましょう!
スポンサーリンク
中学生に読んでほしい!読書感想文におすすめの本とは?
なぜ中学生の読書感想文には本選びが重要なのか?
読書感想文は、単に「読んだ本の内容をまとめる」ものではありません。本を読んだときに自分がどんなことを感じたか、どんなことを考えたかを、言葉にして表現する力が求められます。特に中学生は、論理的に物事を考えたり、自分の考えを他人に伝えたりする力を育てる大切な時期です。そのため、どんな本を選ぶかが、読書感想文の出来を大きく左右します。
たとえば、小学生向けの簡単な本を選んでしまうと、感想が「面白かったです」「楽しかったです」だけになりがちです。逆に、大人向けの難しい本に挑戦してしまうと、内容を理解するだけで精一杯になり、自分なりの考えを書く余裕がなくなってしまいます。
教育の専門家によると、中学生の読書感想文には「心が動く体験ができる本」や「新しい視点を得られる本」が特に向いているとされています。これは、自分自身の成長を感じたり、普段の生活では考えないようなテーマに触れることができるからです。
さらに、読書感想文は、先生やクラスメートに自分の考えを伝えるチャンスでもあります。自分らしい視点で感想を書くためには、興味を持てる本、自分にとって意味のある本を選ぶことが何よりも大切です。本選びからすでに感想文は始まっているのです。
感想文に向いている本の特徴とは?
読書感想文に向いている本には、いくつか共通する特徴があります。まず一つ目は、「登場人物が成長する物語」であること。中学生はちょうど心も体も大きく成長する時期なので、登場人物と自分を重ね合わせることで、自然と深い感想が生まれやすくなります。
二つ目は、「テーマがはっきりしていること」です。たとえば「友情」「家族愛」「冒険」「生きる意味」など、誰でも考えたことがあるテーマを持つ本は、自分の体験と結びつけやすく、感想文にオリジナリティが出やすくなります。
三つ目は、「物語に問いかけが含まれていること」。たとえば「正義とは何か」「本当の幸せとは」など、読者自身に考えさせるタイプの本です。このような本は、自分なりの答えを探す過程を感想文に書くことができ、非常に深みのある文章になります。
さらに、国語教育の専門家によると、読書感想文には「自分だけの視点」を持つことが大切だそうです。つまり、みんなが同じように感じるような本よりも、読み手によって受け取り方が変わる本の方が、オリジナリティのある感想文が書きやすいということです。
このような特徴を意識して本を選ぶと、読書感想文がぐっと書きやすくなります。
読みやすさ重視?深いテーマ重視?
本を選ぶときに悩むのが、「読みやすさを優先するか、テーマの深さを重視するか」という問題です。結論から言うと、最も大事なのは「自分が興味を持てるかどうか」です。
たとえば、ページ数が少なくても、テーマが重く、考えさせられる本もあります。逆に、分厚い本でも、ストーリーが面白くてどんどん読めるものもあります。読書感想文のために無理をして難しい本を選んでしまうと、途中で読むのが嫌になったり、内容が頭に入らなくなってしまうことも。
教育現場でも、「読み切れる本を選び、その中で深く考えることが大切」とよく言われています。読書感想文は、「どれだけ難しい本を選んだか」ではなく、「どれだけ深く自分なりに感じたか」が評価されるからです。
だからこそ、まずは興味を持てる本、自分が最後まで読めそうな本を選びましょう。そのうえで、できるだけテーマが深かったり、考えさせられる内容のものを選ぶと、感想文がより豊かになります。
成績アップを狙える本選びのコツ
読書感想文の成績を上げたいなら、「自分なりの考えを書きやすい本」を選ぶことがポイントです。特におすすめなのは、主人公が葛藤する場面がある本です。人間は葛藤する場面に感情移入しやすいため、自分の意見や感想を自然に引き出せます。
また、テーマに社会問題や倫理的な問いが含まれている本もおすすめです。たとえば、差別、戦争、環境問題などを扱った本は、自分の意見を持ちやすく、感想文に説得力が出ます。
さらに、国語科の先生たちは「自分の体験と本の内容をつなげて書く」ことを推奨しています。これは、単なるあらすじのまとめに終わらず、読んだ内容が自分の人生にどう影響したかを考えるためです。こうした本を選んで、体験や考えと結びつけて書けば、評価されやすい感想文になります。
本を選ぶ前に確認したい学校のルール
最後に、忘れてはいけないのが学校ごとのルールです。学校によっては「課題図書」が指定されていたり、「自由図書だけど、この出版社のものから選んでください」と決まっていることがあります。
特にコンクールに応募する場合、読める本の範囲が決まっていることがあるので、必ず事前に確認しましょう。もし課題図書の中から選ぶ場合でも、その中で自分に一番合った本を選ぶことが大切です。
先生や図書館司書の方に相談するのもおすすめです。彼らは生徒に合った本を紹介するプロフェッショナルなので、頼ることで失敗のない本選びができます。
本選びにしっかり時間をかけることが、感想文成功への第一歩です。
スポンサーリンク
ジャンル別おすすめ本【感動・冒険・歴史・ミステリー】
心を打つ感動系:涙なしでは読めない本
感動系の本は、読書感想文にぴったりのジャンルです。なぜなら、心を動かされる体験をしたとき、人は自然に言葉があふれてくるからです。「この本を読んでどう感じたか?」という感想を書きやすく、読み手にも伝わりやすくなります。
たとえば、吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』は、1937年に発表されたにもかかわらず、いまなお読み継がれている名作です。人間としてどう生きるべきかという普遍的なテーマが描かれていて、自分自身の行動や考え方を見直すきっかけになります。
また、ブレイディみかこの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、現代社会の中で生きる少年の視点から差別や貧困を描いており、中学生にもわかりやすく、なおかつ深い考察が可能です。
感動系の本は、登場人物に共感することで自然と心が動きます。読書感想文を書くときも、「自分だったらどうするか」「登場人物の選択に賛成か反対か」といった視点から考えると、オリジナルな文章が書きやすくなります。
ワクワクする冒険系:手に汗握るストーリー
冒険系の物語は、読んでいるだけでワクワクし、ページをめくる手が止まらなくなる魅力があります。中学生にとっては、想像力を広げる絶好のチャンスにもなります。
ジュール・ヴェルヌの『十五少年漂流記』は、無人島に漂着した少年たちが力を合わせて生き延びる物語です。友情、リーダーシップ、責任感といったテーマが散りばめられており、自分がもし同じ立場だったらどう行動するか、考えながら読むことができます。
また、C.S.ルイスの『ライオンと魔女』は、「ナルニア国物語」シリーズの第一作で、ファンタジーの世界を舞台に冒険と成長を描いています。想像力をふくらませることができるため、感想文では「この世界に自分が入ったらどうなるか」といった視点で書くのも面白いでしょう。
冒険系の本は、困難に立ち向かう勇気や仲間との絆など、大切なテーマが隠れています。それを自分なりに読み解くことで、深い感想文が仕上がります。
歴史好き必見!時代背景を学べる本
歴史に興味がある中学生には、歴史小説や戦争を題材にした作品がおすすめです。実際にあった出来事や過去の時代背景を知ることで、物語をより深く理解することができます。
太宰治の『走れメロス』は短編ながら、友情や信頼という普遍的なテーマを背景に、古代ギリシャを舞台としています。簡単なストーリーに見えて、実は人間の弱さや強さを描いており、深く掘り下げると感想文にも説得力が出ます。
妹尾河童の『少年H』は、戦争中の日本を生き抜いた少年の目線で描かれており、教科書だけでは学べないリアルな戦時中の生活を知ることができます。これを読めば、単なる知識だけではなく、戦争を生きるとはどういうことかを肌で感じることができるでしょう。
歴史系の本を選ぶときは、「この時代に自分がいたらどう感じたか」という視点を持つと、感想文がより豊かになります。
謎解き好き必見!ミステリー小説
謎解きが好きな中学生には、ミステリー小説がぴったりです。ミステリーはストーリーを追うだけでなく、伏線やトリックに気づく楽しみがあり、読書の面白さを存分に味わえます。
たとえば、青山剛昌の『名探偵コナン』の小説版は、マンガが好きな中学生にも親しみやすく、入り口としておすすめです。身近な謎解きから、友情や正義感について考えるきっかけになります。
湯本香樹実の『夏の庭―The Friends』は、少年たちがひとりの老人の死をめぐって成長していく物語。ミステリー的な要素を含みつつ、友情や命の大切さを静かに描いており、心に深く残る作品です。
ミステリーを読んだ感想文では、ただ「謎が解けた」というだけでなく、「自分だったらどう推理するか」「この結末に納得できたか」など、読者自身の考えをしっかり書くことが大切です。
短時間で読める短編集もおすすめ!
忙しい中学生には、短編集もおすすめです。短編集なら、1話ごとに完結しているため、短い時間で読めるだけでなく、感想文の対象としても扱いやすいメリットがあります。
中でも宮沢賢治は、日本を代表する童話作家ですが、ただ子ども向けというだけではありません。彼の作品は、自然、宇宙、人生について深く考えさせるテーマが多く、大人になっても新たな発見があります。
『銀河鉄道の夜』は、まさにその代表作です。友人との旅を通して生と死をテーマに描き出しており、中学生でも「生きる意味」や「大切なもの」について考えるきっかけになります。
宮沢賢治の作品の魅力は、言葉の美しさと、読者に深い問いを投げかける力です。たとえば、「幸せとは何か?」という大きなテーマについて、自分なりの答えを探して感想文を書くと、読み手にも強い印象を与えることができます。
また、宮沢賢治は自らも教師や農業指導者として生きた経験があり、作品にもその優しさと厳しさがにじみ出ています。その背景を少し調べてから読むと、さらに理解が深まりますよ。
同じく宮沢賢治の『注文の多い料理店』も、ユーモラスな中に深い意味が隠されており、読みやすさと考えさせられる要素のバランスが絶妙です。
短編作品は、短いながらもメッセージが凝縮されています。だからこそ、「この短い話から何を感じたか」をしっかり書くと、説得力のある感想文になります。
スポンサーリンク
読書感想文におすすめ!有名作家の名作まとめ
村上春樹の作品:中学生でも楽しめる?
村上春樹といえば世界的に有名な日本の作家ですが、「難しそう」と感じる中学生も多いかもしれません。実際、大人向けの作品が多いですが、村上作品の中には、中学生でも楽しめるものもあります。たとえば短編集『カンガルー日和』は、日常の不思議をやさしく描いた物語が多く、読みやすい内容になっています。
村上春樹の小説は、現実と夢の境目が曖昧で、物語の解釈がひとりひとり違うのが特徴です。そのため、「自分はこう感じた」「自分はこう読み取った」というオリジナルな感想を書きやすいのです。
また、作品を読むことで「人との距離感」「孤独感」「生きる意味」といったテーマに自然に向き合うことになり、感想文にも深みを出すことができます。
難しく感じる部分があったとしても、無理に完璧に理解しようとせず、「わからなかったこと」「不思議に思ったこと」も感想に書くと、リアルで素直な感想文になりますよ。
東野圭吾のミステリー入門
東野圭吾は、ミステリー小説界のトップランナー。難しすぎず、でも一筋縄ではいかないストーリー展開が魅力で、中学生にも読みやすい作家です。
なかでも『秘密』は、中学生にもおすすめの一冊です。事故で亡くなった母親の魂が娘の体に宿るという、不思議な設定からスタートします。親子の絆や、人生の選択について深く考えさせられる内容で、「家族とは何か」というテーマで感想文を書くことができます。
また、東野作品は伏線が巧妙に張られていて、読みながら「ここがこうつながるのか!」という驚きがあり、読む楽しさも抜群です。そのため、感想文でも「物語の仕掛けに気づいた時の驚き」や「結末に対する自分なりの解釈」を書くと、オリジナル性が高いものになります。
東野圭吾は、難しすぎず、それでいて感動や驚きがあるので、ミステリー初心者にもぴったりです。
梨木香歩の自然と生きる物語
梨木香歩の作品は、自然との共生や、人と人との心のつながりを優しく描いたものが多く、特に中学生におすすめです。
代表作『西の魔女が死んだ』は、主人公の少女と祖母との交流を通じて、成長と自立を描いています。自然豊かな環境での生活、祖母からの教え、心の葛藤など、どれも中学生にとって共感しやすいテーマばかりです。
読書感想文では、「自然に囲まれて生きることの意味」「家族との関係」「自立とは何か」などをテーマに、自分の考えを深めることができます。また、静かで丁寧な描写が多いため、文章から風景を想像しながら感想を書くのもポイントです。
梨木香歩の作品は、読むと心がじんわり温かくなるような力を持っています。無理に難しい言葉を使わず、感じたことを素直に書くと、自然な感想文に仕上がります。
森絵都のリアルな青春小説
森絵都は、リアルな感情描写と、思春期ならではの悩みや葛藤を見事に描く作家です。中学生にも親しみやすいストーリーが多く、読書感想文におすすめです。
『DIVE!!』は、飛び込み競技にすべてをかける中学生たちの物語です。夢に向かって努力する姿、仲間との関係、挫折と再起など、中学生なら誰もが共感できるテーマがぎっしり詰まっています。
森絵都の作品の特徴は、現実にありそうなリアルな感情と状況設定です。そのため、感想文では「自分だったらどう感じるか」「似たような体験があったか」を掘り下げて書くと、オリジナル性が高くなります。
青春小説は、読後に「もっと頑張ろう」と思わせてくれるパワーがあります。そのエネルギーを素直に感想文に込めれば、読み手にも熱意が伝わるはずです。
スポンサーリンク
読書感想文をラクに書くための3ステップ
まずは「印象に残ったシーン」をメモしよう
読書感想文を書くときにいきなり原稿用紙に向かうと、何を書いていいかわからなくなってしまいがちです。そこで最初におすすめしたいのが、「印象に残ったシーン」をメモすることです。
たとえば、「主人公が初めて友達とケンカする場面が心に残った」「自然災害のシーンに胸が痛んだ」など、どんな小さなことでも構いません。自分が強く心を動かされた場面をピックアップしておくと、あとで感想を書くときに非常に役立ちます。
この時、できれば「なぜ印象に残ったのか」も合わせてメモしておくとさらに良いです。たとえば、「自分も友達とけんかしたことがあり、共感できたから」「もし自分が同じ立場ならどうしただろうと考えたから」など、理由まで書いておくと感想文がぐっと書きやすくなります。
教育現場のプロによれば、「心が動いた瞬間を言葉にすること」が、オリジナルな読書感想文を書く一番の近道だそうです。まずは、読書中に小さな発見や感動をたくさんメモしていきましょう!
自分の経験と重ねて感じたことを書く
読書感想文が「ただのあらすじ紹介」になってしまう原因は、「自分の経験や気持ち」と本の内容をうまくつなげられていないからです。そこで意識したいのが、自分の体験と本の出来事を重ね合わせることです。
たとえば、主人公が夢に向かって努力するシーンを読んだら、「自分も部活で目標に向かってがんばったことがある」とか、「途中でくじけそうになったけれど、最後までやり遂げたことがある」といった体験を思い出してみましょう。
読書感想文では、自分の経験を交えることで、感情のこもったリアルな文章になります。これにより、読み手も「この子は本当にこの本から何かを感じ取ったんだな」と伝わり、感想文に説得力が生まれます。
国語教育の専門家も、「感想文は自分の体験との接点を見つけることで、ぐっと深みが増す」とアドバイスしています。少し恥ずかしくても、自分の本当の気持ちを書き出してみましょう。
最後に「この本をおすすめしたい人」を考える
感想文の締めくくりにおすすめしたいのが、「この本を誰にすすめたいか」を書くことです。これにより、読書感想文に自然な終わり方ができるうえに、読み手にも「なるほど」と思わせることができます。
たとえば、「友達とケンカをしてしまった人におすすめしたい」「将来について悩んでいる中学生に読んでほしい」など、具体的なターゲットを考えます。もちろん、自分と同じような気持ちを持っている人でもかまいません。
この「おすすめの相手」を設定することで、感想文のラストにメッセージ性が生まれ、読書体験がより意味のあるものになります。特にコンクール応募を目指す場合、この締め方は高評価を狙えるテクニックのひとつです。
「この本はこんな人にぴったりだと思った」という視点を持つだけで、感想文全体がぐっと引き締まりますよ。
「あらすじだけ」にならない書き方とは?
読書感想文でありがちな失敗が、「本のあらすじだけをずっと書いてしまう」パターンです。でも安心してください。ちょっとしたコツを意識するだけで、あらすじ感想文から脱出できます。
そのコツとは、「あらすじはできるだけ短くまとめる」ことです。最初に2〜3行でざっくりと「どんな話だったか」を紹介し、そのあとはすぐに「自分が心を動かされたポイント」に移りましょう。
たとえば、「〇〇という主人公が夢を追いかける物語です」と簡単に紹介したら、「特に印象に残ったのは〇〇の場面です」と、自分の感想や考えたことを中心に書いていきます。
学校の先生たちも、「あらすじはあくまで背景説明。感想文の主役は『あなたの感じたこと』」だとよく言っています。だから、物語の流れを説明しすぎず、自分の考えや感情をできるだけたくさん書くことを意識しましょう!
推敲のポイント:短く、わかりやすくまとめるコツ
読書感想文を書き終えたら、必ず推敲(すいこう)しましょう。
『推敲』とは、書いた文章を見直して、よりよい表現に整える作業のことです。
推敲のコツは、まず「読みにくいところ」「わかりにくいところ」がないかをチェックすること。たとえば、同じ言葉を何回も使っていないか、文章が長すぎてわかりづらくなっていないかを見直します。
また、できるだけ一文を短くして、ひとつの文にはひとつの内容だけを書くように意識しましょう。たとえば、「主人公が努力して夢をかなえたので、私も感動して、この本を読んでよかったと思いました」という長い文は、「主人公が夢をかなえる姿に感動しました。私もこの本を読んでよかったと思います。」のように、短く区切るだけで読みやすくなります。
プロの作家でも、何度も推敲を重ねて作品を仕上げています。だから、中学生の読書感想文でも、いきなり完璧を目指さず、まずは書いて、それからブラッシュアップする気持ちで進めましょう!
スポンサーリンク
忙しい中学生向け!読書感想文を書く裏ワザ
本を全部読めない時の対策
部活や習い事で忙しい中学生にとって、読書感想文のために一冊まるごと読むのは、なかなか大変なことですよね。でも、どうしても時間がないときのための裏ワザがあります。
まず、最初の数章とクライマックス部分、そして結末だけをしっかり読むという方法です。この3つのポイントを押さえるだけでも、ストーリーの大まかな流れと作者が伝えたいメッセージを理解することができます。
さらに、途中のエピソードは目次や章タイトルを参考にして、重要な場面だけを拾い読みすると効率的です。最近では、出版社公式サイトに「紹介文」や「立ち読み機能」がある場合もあるので、そちらも活用してあらすじをつかんでおくと安心です。
もちろん、全ページをしっかり読むのが理想ですが、忙しいときは「読み方の工夫」でカバーしましょう。大事なのは、自分が読んだ部分から感じたことを正直に書くことです。無理にすべてをカバーしようとしなくても大丈夫ですよ!
あらすじと感想を効率よくまとめる方法
感想文を書くときに時間を短縮するコツは、あらかじめメモを取っておくことです。読書中に印象に残ったシーン、心が動いたセリフ、自分が疑問に思ったことなどを箇条書きでメモしておきましょう。
読書が終わったら、そのメモをもとに、まず「簡単なあらすじ」を3〜5行くらいでまとめます。そして、感動した場面や心に残ったエピソードに絞って、そこに対する自分の気持ちや考えを書きます。
この流れを意識すると、無駄にダラダラとあらすじを書きすぎることが防げますし、感想文にしっかり「自分の視点」が入ります。
たとえば、感想文の骨組みをこのようにしておくとスムーズです。
- 本の紹介(簡単に)
- 印象に残った場面
- そこから自分が感じたこと、考えたこと
- この本を読んで自分が変わったこと
- 最後にまとめとおすすめの人
この型に当てはめて書くと、驚くほどスピーディーに感想文が完成します!
読書感想文テンプレートの活用法
どうしても何を書いていいか迷ったときは、読書感想文テンプレートを使うのがおすすめです。テンプレートとは、感想文を書くための「ひな型」です。
たとえば、こんなテンプレートがあります。
【テンプレート例】
- この本を選んだ理由
- 簡単なあらすじ
- 印象に残った場面
- その場面で自分が考えたこと・感じたこと
- この本から学んだこと
- まとめ・誰におすすめしたいか
この流れにそって書けば、何を書けばいいか迷う時間が減り、文章の流れも自然になります。
特に、読書感想文が初めての人や、苦手意識がある人にはテンプレートが心強い味方になります。もちろん、書きながら少しずつ自分なりにアレンジしてもOKです。テンプレートはあくまで「道しるべ」。自分らしさをプラスすることを忘れずに!
短い時間で感想を深める「3つの質問」
限られた時間で感想を深めたいときには、次の「3つの質問」を自分にしてみましょう。
- この本の中で、一番心に残った言葉やシーンは何か?
- その場面を読んだとき、自分はどんな気持ちになったか?
- この本を読む前と後で、自分の考え方や気持ちはどう変わったか?
この3つの質問に答えるだけでも、立派な感想文が書けます。特に、「考え方がどう変わったか」を意識すると、感想に深みが出て、「成長した自分」を伝えることができます。
忙しい中でも、たった3つの問いを深く考えるだけで、感想文にオリジナリティが生まれますよ!
最後の仕上げチェックリスト
感想文を書き終えたら、最後に次のポイントをチェックしましょう。
- あらすじだけで終わっていないか?
- 自分の感情や考えがしっかり書かれているか?
- 文章はわかりやすく、読みやすいか?
- 推敲してミスを直したか?
- まとめや「おすすめしたい人」が書かれているか?
このチェックリストに沿って見直せば、読書感想文の完成度がぐっと上がります。特に、自分の気持ちがちゃんと伝わっているかどうかは最重要ポイントです!
最後に一度声に出して読んでみると、リズムの悪いところやおかしな表現に気づきやすくなります。細かいところまで気を配ると、感想文のクオリティがグッと上がりますよ。
よくある質問(FAQ)
Q1. 読書感想文におすすめの本を読むとき、どこに注目すればいい?
本を読むときは「自分が心を動かされた場面」「登場人物の気持ちの変化」「自分と違う考え方」に注目すると、感想が書きやすくなります。
Q2. 短い本でも読書感想文を書いて大丈夫?
問題ありません!短い本でも、内容が深ければしっかりとした感想文を書けます。むしろ、限られたページ数だからこそ集中して読めるメリットもあります。
Q3. 読書感想文を書くとき、あらすじだけにならないコツは?
「あらすじ」はあくまで簡単にまとめるだけにして、自分の感想や考えたことを中心に書きましょう。「この本を読んで自分はどう思ったか?」を軸にすると、オリジナリティが出ます。
Q4. 本を全部読む時間がないときはどうすればいい?
本の冒頭とクライマックス、結末部分をしっかり読んで、その間の流れを簡単に把握すればOK。ただし、感想文には「自分が読んだ部分」で感じたことを正直に書くのが大切です。
Q5. どんなジャンルの本を選べばいい?
基本は「自分が興味を持てるジャンル」でOKですが、感想文に向いているのは「心が動く」ストーリーや「自分なりの考えが生まれる」テーマを扱った本です。
まとめ
最後に、今回紹介した中学生の読書感想文におすすめの本+ α についてのリストを以下にまとめました。
【中学生におすすめ!読書感想文向け本リスト】
| ジャンル | タイトル | 作者 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 感動系 | 『君たちはどう生きるか』 | 吉野源三郎 | 自分を見つめ直すテーマ。深い感想が書きやすい。 |
| 感動系 | 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』 | ブレイディみかこ | 差別や社会問題をやさしく学べる。 |
| 冒険系 | 『十五少年漂流記』 | ジュール・ヴェルヌ | サバイバルと成長の物語。冒険好きに。 |
| 冒険系 | 『ライオンと魔女』 | C.S.ルイス | ファンタジーながら人生の教訓も学べる。 |
| 歴史系 | 『走れメロス』 | 太宰治 | 友情と信頼をテーマに短く読みやすい。 |
| 歴史系 | 『少年H』 | 妹尾河童 | 戦時中を生きた少年のリアルな記録。 |
| ミステリー系 | 『名探偵コナン(小説版)』 | 青山剛昌・水稀しま | 謎解きしながら感想も書きやすい。 |
| ミステリー系 | 『夏の庭―The Friends』 | 湯本香樹実 | 死や友情を描く、深みのあるストーリー。 |
| 短編集 | 『銀河鉄道の夜』 | 宮沢賢治 | 哲学的なテーマにも挑戦できる。 |
| 短編集 | 『注文の多い料理店』 | 宮沢賢治 | 短くても深い感想が書ける作品。 |
| 有名作家 | 『ノルウェイの森』 | 村上春樹 | 青春の葛藤を描く(やや難しめ)。 |
| 有名作家 | 『秘密』 | 東野圭吾 | 不思議な設定と親子の絆を描く感動作。 |
| 自然系 | 『西の魔女が死んだ』 | 梨木香歩 | 自然と生きる知恵と成長の物語。 |
| 青春系 | 『DIVE!!』 | 森絵都 | 夢に向かって努力する青春ドラマ。 |
| 社会問題系 | 『わたしを離さないで』 |
読書感想文は、中学生にとって自分の感じたことを深く考え、言葉にする力を養う大切な機会です。大事なのは、難しい言葉を使うことでも、正解を探すことでもありません。自分が本を読んで何を感じ、何を考えたかを、素直に、自分らしい言葉で表現することです。
本を選ぶ段階から、すでに読書感想文は始まっています。興味が持てるテーマ、自分が共感できるストーリー、心を動かされるシーンを選び取ることが、感想文をスムーズに書くための第一歩です。
また、感想文を書くときは、あらすじを長々と書かず、自分の感想を中心にまとめること。印象に残った場面や、自分の経験と重ねた気持ちを大切にすることで、オリジナリティのある文章になります。
忙しい中でも、メモを取りながら効率よく読む工夫をしたり、テンプレートやチェックリストを使ってスムーズにまとめる方法も紹介しました。
今回紹介した本のリストやジャンル別の選び方を参考にして、ぜひ「これだ!」と思える一冊を見つけてください。そして、自分だけの読書体験を、あなただけの言葉で書き表してみましょう。
読書感想文は、書けば書くほど、きっとあなた自身の成長にもつながっていきます。
ぜひ楽しみながら挑戦してくださいね!