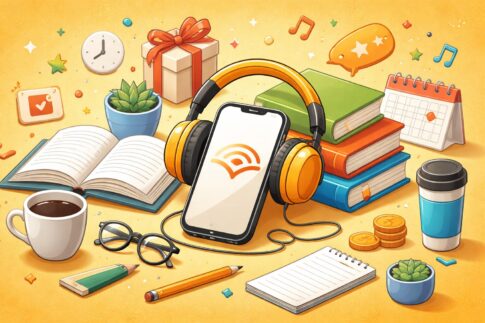「小学校の夏休みって、いつからいつまでなんだろう?」
お子さんの予定を立てるうえで、ふと気になる方も多いのではないでしょうか。実は、夏休みの期間は全国一律ではなく、地域や学校によって日数や開始日・終了日が異なることもあるんです。加えて、学年によって登校日の有無や、宿題の量などにも差が出ることもあり得ます。
そこで本記事では、2025年の小学校の夏休みがいつから始まり、いつまで続くのかを都道府県別にわかりやすくまとめました。また、夏休みに悩みがちな宿題や自由研究のアイデア、子どもと楽しく過ごすための工夫などもご紹介しています。
夏の計画を立てる前に、ぜひとも参考にしてみてくださいね!
スポンサーリンク
2025年の小学校の夏休みはいつからいつまで?

夏休み期間はどう決まるの?
小学校の夏休みは、国で一律に決められているわけではなく、各都道府県の教育委員会や学校ごとに日程が定められています。そのため、同じ学年の子どもでも、住んでいる地域や学校によって休みの開始日や終了日が異なることがあります。
学年や学校ごとの違いに注意
同じ地域でも、学校ごとや学年によって多少の違いがあることもあります。たとえば、1年生は夏休みの前後に「登校日」が設けられている場合があったり、クラブ活動や補習授業の有無によって登校日数が変わることも。
また、公立と私立では夏休みの設定に差が出ることもあるため、正確な日程は各学校から配布されるおたよりや、学校ホームページで確認しておくのが安心です。
一般的には、7月下旬から8月末ごろまでの約40日間が夏休み期間となるケースが多いですが、北海道や東北地方など一部の地域では、冬休みを長く設定している代わりに夏休みがやや短くなる傾向も見られます。
東京都内の具体的な日程
東京都の公立小学校の夏休みは、例年 7月20日頃から8月31日まで となっています。ただし、2025年は曜日の関係で微調整される可能性があります。東京都教育委員会の公式発表を確認するのが確実です。
また、私立小学校の場合は独自のカレンダーを持っているため、学校ごとの確認が必要です。
都道府県別|2025年の夏休み期間の目安
※下記は2024年の傾向をもとにした目安です。2025年の日程は各教育委員会の発表を参考にご確認ください。
| 地域 | 主な都道府県 | 夏休み期間(目安) |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道・青森・岩手・宮城など | 7月25日頃〜8月17日頃 |
| 関東 | 東京・神奈川・千葉・埼玉など | 7月20日頃〜8月31日頃 |
| 中部・北陸 | 新潟・静岡・愛知・石川など | 7月20日頃〜8月31日頃 |
| 近畿 | 大阪・京都・兵庫・奈良など | 7月20日頃〜8月31日頃 |
| 中国・四国 | 岡山・広島・香川・愛媛など | 7月20日頃〜8月31日頃 |
| 九州・沖縄 | 福岡・鹿児島・沖縄など | 7月20日頃〜8月25日〜31日頃 |
🌟 ポイント:夏休みの開始・終了日は、年度によって微妙に前後する場合があります。特に、登校日が設定されている地域や、台風・猛暑対策で変更がある場合もあるため、正式な日程は各学校・教育委員会の発表をご確認ください。
期間の決定要因
夏休みの期間は、以下の要因によって決まります。
- 都道府県ごとの教育方針(自治体の裁量で決定)
- 学校ごとのカリキュラム(公立と私立で違いあり)
- 祝日や授業日の調整(年間授業日数の確保)
- 地域の気候(暑さ対策や冬休みとのバランス)
休業期間の確認方法
お子さんの学校の具体的な夏休み期間は、以下の方法で確認できます。
- 学校の年間カレンダーをチェック(入学時や学期初めに配布)
- 学校の公式サイトを確認(お知らせや行事予定に掲載)
- 自治体の教育委員会の情報をチェック(公立小学校の休業日が掲載)
- 先生やPTAに問い合わせる(変更の可能性がある場合も考慮)
夏休みのスケジュールを早めに把握し、計画的に過ごせるよう準備を進めましょう。
スポンサーリンク
夏休みの宿題や自由研究はどう進める?
宿題が出るタイミングや内容は?
夏休みの宿題は、学期末の終業式やその前後に配布されることが多く、学校によって内容や量に差があります。主な宿題としては、ドリルや漢字練習、計算プリント、読書感想文、絵日記などが定番です。
また、学年が上がるにつれて課題の難易度や自由度が高くなる傾向があり、中学年〜高学年になると自主学習や発展的な内容が加わる場合もあります。保護者としては、子どもの得意・不得意を把握しながら、無理なく進められるようサポートしてあげたいですね。
学習計画の立て方
夏休みは長期休暇ですが、ダラダラ過ごしてしまうと新学期に学習習慣を取り戻すのが大変になります。そのため、 「毎日少しずつ取り組む学習計画」 を立てることが大切です。
計画のポイント
- 宿題の全体量を把握する(最初に全ページを確認)
- 1日あたりの目標を決める(1日1ページなど具体的に)
- 朝の時間を活用する(午前中に学習を終わらせる習慣)
- ごほうびを設定する(達成したら好きなことができる)
- 定期的に振り返る(進捗チェックを親子で行う)
自由研究のテーマ選びに困ったら
自由研究は、子どもの「なぜ?」を育む大切な学びの時間です。しかし、毎年テーマ選びに悩むご家庭も多いのではないでしょうか。身近な素材を使った実験や、季節にちなんだ観察記録、工作や調べ学習など、ジャンルはさまざま。
テーマに迷ったときは、子どもが興味を持っていることや、日常生活で「不思議だな」と感じたことをヒントにしてみるのがおすすめです。図書館やインターネット、学校配布の資料なども参考になりますよ。
生活リズムの重要性
夏休みに生活リズムが乱れると、学校が始まったときに 「朝起きるのがつらい」「授業に集中できない」 という問題が起こりやすくなります。
生活リズムを守るコツ
- 起床・就寝時間を固定する(夜更かしを避ける)
- 朝ごはんをしっかり食べる(1日のエネルギー補給)
- 適度な運動を取り入れる(散歩やラジオ体操)
- ゲームやスマホの時間を制限(ルールを決めて使う)
- 夜はリラックスタイムを作る(入浴・読書で自然な眠気)
おすすめの自主学習の進め方
宿題以外にも、自分で興味のあることを学ぶ「自主学習」も大切です。
おすすめの自主学習
- 読書感想文のための読書(好きな本を見つける)
- 自由研究のテーマ探し(実験・観察・工作など)
- 漢字や計算の復習(学年を超えた先取り学習もOK)
- 新聞を読む習慣(ニュースを親子で話し合う)
- 英語やプログラミングの体験(アプリやYouTubeを活用)
家庭でのサポート方法
子どもの学習や生活リズムを維持するには、 親のサポート も重要です。
親ができること
- 一緒に学習時間を作る(親も読書や勉強をする)
- 成果をほめる(できたことを具体的に伝える)
- 楽しい体験を提供する(学習と遊びのバランスをとる)
- 夏休みの計画を一緒に考える(目標を共有する)
学校や地域の学習支援
自治体や学校によっては、 夏休み期間中の学習支援 を行っていることもあります。
利用できる学習支援の例
- 図書館の読書イベント(読書感想文のサポート)
- 学校の補習授業(希望者向けの学習会)
- 地域の学習塾やオンライン講座(短期集中講座)
- 親子向けワークショップ(理科実験やプログラミング体験)
夏休みを有意義に過ごせるよう、 学習と生活リズムのバランスを意識しながら計画的に取り組みましょう!
スポンサーリンク
子どもと過ごす夏休みのアイデア
おうち時間を楽しく過ごすコツ
暑い日が続く夏休みは、無理に外出せず、おうちでゆったり過ごすのもおすすめです。読書やお絵かき、料理のお手伝い、手作り工作など、家庭内でできる遊びや学びの工夫はたくさんあります。
最近では、YouTubeや学習アプリを活用した「おうち学習」も人気。興味のあるテーマを一緒に調べてみるだけでも、知的好奇心が広がります。天候や気温に左右されず、安全に過ごせるのもおうち時間の魅力です。
日帰りレジャーや体験イベントの活用
夏休み期間中には、地域の施設や観光地でさまざまな子ども向けイベントが開催されることも多くあります。科学館や博物館、図書館のワークショップ、農業体験や自然観察など、日帰りで参加できるプログラムを活用すると、楽しい思い出づくりにもつながります。
公共施設の多くは低予算で楽しめるうえに、学び要素も豊富。感染症対策や暑さ対策を意識しながら、無理のない範囲で外に出かけてみるのも良いですね。
夏休みならではの思い出づくり
長いお休みの間には、普段なかなかできない体験を取り入れてみるのもおすすめです。たとえば、家族で花火を楽しんだり、夜に星空を眺めてみたりといった季節感のある体験は、子どもにとって特別な思い出になります。
また、家族で「夏休みの目標」を一緒に決めて、それを達成するためのチャレンジに取り組むのも素敵なアイデアです。楽しい体験の積み重ねは、子どもの心の成長にもつながっていきます。
夏休みのおすすめイベントと体験活動
地域の夏祭りやイベント情報
夏休みといえば、地域の夏祭りやイベントが楽しみのひとつです。全国各地で開催されるお祭りでは、 屋台グルメや伝統行事を楽しめる ほか、 花火大会や盆踊りなど も見どころです。
全国の代表的な夏祭り
- 青森ねぶた祭(青森県):大迫力のねぶたが街を練り歩く
- 祇園祭(京都府):豪華な山鉾巡行が見もの
- 仙台七夕まつり(宮城県):色とりどりの七夕飾りが美しい
- 阿波おどり(徳島県):踊り手と観客が一体になって楽しむ
- 隅田川花火大会(東京都):東京の夜空を彩る大規模花火
地域のイベントを探す方法
- 自治体の公式サイト(「○○市 夏祭り」などで検索)
- 商店街や地域の掲示板(ポスターやチラシを確認)
- SNSやイベントサイト(「夏祭り 2025」などのハッシュタグで検索)
地域の夏祭りは 地元の文化に触れるチャンス なので、家族で参加してみるのもおすすめです。
自然体験やキャンプのすすめ
自然の中で過ごす体験は、子どもにとって 貴重な思い出 になります。キャンプやアウトドア体験を通して、 自然の大切さや自分で工夫する力 を学ぶことができます。
おすすめの自然体験
- キャンプ(テント設営や焚き火体験)
- 川遊び・魚つかみ(安全に注意しながら楽しむ)
- 昆虫採集(カブトムシやクワガタを探す)
- 星空観察(天体望遠鏡を使って月や星を観察)
- 農業体験(野菜の収穫や田植え体験)
キャンプ初心者向けのポイント
- 初心者向けのキャンプ場を選ぶ(設備が整った場所がおすすめ)
- 持ち物リストを作る(テント・寝袋・ランタンなど必需品を準備)
- 事前に天気をチェック(雨の場合の対策も考える)
- ルールを守る(ゴミは持ち帰る・火の後始末を徹底する)
自然の中で過ごすことで、 子どもが自主的に考え行動する力 も育ちます。
博物館や美術館の特別展
夏休み期間中は、 全国の博物館や美術館で特別展 が開催されます。自由研究のテーマにもなるので、 遊びながら学べるスポット としておすすめです。
子ども向けの人気博物館・美術館
- 国立科学博物館(東京):恐竜の化石や宇宙の展示が人気
- 鉄道博物館(埼玉):実物の電車に乗れる体験ができる
- トヨタ博物館(愛知):歴史的な自動車の展示が豊富
- チームラボプラネッツ(東京):デジタルアートを体感できる美術館
- ジブリパーク(愛知):ジブリ映画の世界を体験できるテーマパーク
博物館・美術館を楽しむコツ
- 事前に公式サイトで展示内容を確認(特別展の開催日もチェック)
- 音声ガイドを活用(より深く学べる)
- 自由研究に活かせるメモをとる(写真OKなら撮影も活用)
- 混雑する時間帯を避ける(平日午前中が狙い目)
博物館や美術館は 学びながら楽しめるスポット なので、 暑い夏の日の室内レジャー としても最適です。
伝統文化の体験教室
夏休みは、日本の伝統文化に触れる良い機会です。 実際に体験することで、歴史や文化をより深く学ぶことができます。
子ども向けの伝統文化体験
- 茶道体験(お抹茶を点てる体験)
- 陶芸教室(自分だけの器を作る)
- 和菓子作り(お団子や練り切りを作る)
- 書道体験(筆で名前や好きな言葉を書く)
- 和太鼓・三味線体験(伝統楽器の演奏に挑戦)
体験教室の探し方
- 市町村の文化センターをチェック(「○○市 伝統文化 体験」などで検索)
- 旅行サイトやアクティビティ予約サイトを活用(アソビュー!やじゃらん遊び体験予約など)
- 地域のイベントカレンダーを確認(夏休み期間中の特別講座を探す)
伝統文化に触れることで、 子どもの感性や創造力が豊かになる ので、夏休みの貴重な経験としておすすめです。
親子で参加できるワークショップ
夏休みには 親子で楽しめるワークショップ も多く開催されます。
親子で楽しめるワークショップの例
- 工作体験(木工・レゴ・プラモデル)
- 料理教室(親子でピザ作りや和菓子作り)
- 科学実験(スライム作り・化学反応を学ぶ)
- プログラミング体験(ゲーム作り・ロボット操作)
- お菓子作り(チョコレートやクッキーをデコレーション)
ワークショップを探す方法
- 子ども向けイベントサイト(こどもちゃれんじ・アソビュー!)
- 地域の商業施設やデパートのイベント情報をチェック
- YouTubeやオンライン講座で自宅体験も可能
親子で一緒に体験することで、 子どもとのコミュニケーションが深まり、思い出に残る夏休み になります。
夏休みは普段できないことにチャレンジできる期間です。ぜひ 子どもと一緒に楽しい体験を計画してみましょう!
スポンサーリンク
夏休みの安全対策と健康管理
熱中症予防のポイント
夏休みの時期は気温が高く、熱中症のリスクが増します。特に 屋外での遊びやスポーツ、キャンプ などを楽しむ際には、しっかりと対策をすることが大切です。
熱中症を防ぐための基本対策
- こまめに水分を補給する(1日1.5L以上が目安)
- 塩分も適度に摂取する(スポーツドリンクや塩タブレット)
- 直射日光を避ける(帽子や日傘を活用)
- 涼しい服装を選ぶ(通気性の良い素材が◎)
- 室内でもエアコンを活用する(無理に節電せず快適な温度を保つ)
熱中症の初期症状チェック
- 頭がボーっとする
- めまいや立ちくらみ
- 異常な汗のかき方(大量の汗 or 汗が出ない)
- 吐き気や気持ち悪さ
もし熱中症になったら
- すぐに 日陰や涼しい場所 に移動する
- 水分を補給 する(できれば経口補水液)
- 体を冷やす(首・脇・足の付け根に冷却シート)
- 改善しない場合は すぐに病院へ
熱中症は 命に関わる危険な症状 です。夏休み中は 天気予報や気温を確認しながら行動する習慣をつけましょう。
水遊びやプールでの注意点
夏休みといえば プールや海、川遊び ですが、水辺での事故には十分注意が必要です。
安全に水遊びを楽しむポイント
- 子どもだけで水辺に行かせない(必ず保護者が付き添う)
- 遊泳禁止エリアでは遊ばない(流れが速い場所は特に危険)
- ライフジャケットを着用する(特に川や海では必須)
- 天候の変化に注意する(急な雷雨や強風の日は避ける)
- 水の事故が起きたときの対処法を学んでおく(心肺蘇生法など)
プール・海・川の安全ルール
| 場所 | 注意点 |
|---|---|
| プール | 飛び込み禁止・プールサイドを走らない |
| 海 | 離岸流(流される潮の流れ)に注意・クラゲに刺されないよう対策 |
| 川 | 浅瀬でも油断しない・流れが急な場所では遊ばない |
水の事故は 「大丈夫だろう」という油断が危険 です。楽しく安全に遊べるよう、 ルールを守って水辺での時間を楽しみましょう!
食中毒を防ぐ食事管理
夏は 食べ物が傷みやすい時期 なので、食中毒にも注意が必要です。特に お弁当やバーベキュー の際には、しっかりと管理しましょう。
食中毒を防ぐポイント
- お弁当には傷みにくい食材を選ぶ(梅干し・酢を活用)
- 調理後はすぐに冷やす(保冷剤やクーラーボックスを使用)
- 手をしっかり洗う(調理前・食事前に徹底)
- 肉や魚はしっかり加熱する(75℃以上で1分以上加熱)
- 作り置きは避ける(調理後は早めに食べる)
お弁当におすすめの食材
✅ 梅干し(抗菌作用あり)
✅ しっかり火を通した卵焼き
✅ 漬物(保存が効く)
❌ 生野菜(時間が経つと菌が増えやすい)
❌ 半熟の卵や肉(加熱不足のリスク)
食中毒になると 嘔吐や下痢、発熱 などの症状が出るため、 食品の扱いには十分注意しましょう。
外出時の防犯対策
夏休みは 子どもだけで外出する機会 も増えます。防犯対策をしっかりして、 安全に過ごせる環境を整えましょう。
子どもに教えておくべき防犯ルール
- 知らない人について行かない(「助けて」と言われても親に相談する)
- 遊ぶ場所を事前に伝える(外出前に行き先を共有)
- 暗くなる前に帰る(夜の外出は避ける)
- 防犯ブザーを持つ(すぐに使えるようにする)
- 困ったときは近くの大人に助けを求める(交番・お店の人など)
親ができる防犯対策
- スマホのGPS機能を活用(位置情報を把握)
- 見知らぬ番号の着信には応じないように伝える
- 帰宅時間を決める(遅くなるときは連絡を入れるルール)
最近は SNSを使ったトラブル も増えているため、 子どもがオンラインで知らない人とやりとりしていないかも注意が必要です。
心と体のリフレッシュ方法
夏休みは楽しいイベントが多いですが、遊びすぎて 疲れがたまる こともあります。体調管理のためにも、 心と体をリフレッシュする習慣を身につけることが大切です。
おすすめのリフレッシュ方法
- お昼寝を取り入れる(15〜30分の短時間でOK)
- ストレッチや軽い運動をする(肩回し・ヨガなど)
- スマホやゲームの時間を減らす(目の疲れを防ぐ)
- 自然の中でリラックス(公園での散歩や森林浴)
- 湯船につかる習慣をつける(シャワーだけで済ませない)
疲れを感じたら、 無理せず休むことが大切 です。特に 睡眠不足は夏バテや体調不良の原因 になるので、 しっかり寝て元気に夏を楽しみましょう!
スポンサーリンク
夏休み明けのスムーズな新学期準備
生活リズムの再調整
長い夏休みの間に 夜更かしや朝寝坊の習慣 がついてしまうと、新学期が始まってから 朝起きるのがつらい という状態になりがちです。そのため、 新学期の1週間前 から少しずつ生活リズムを戻していくことが大切です。
生活リズムを整えるポイント
- 就寝時間を30分ずつ早める(急に戻すとストレスになるため)
- 朝は決まった時間に起きる(休み中でも学校と同じ時間に起床)
- 朝ごはんをしっかり食べる(体内時計をリセットする効果あり)
- 日中に外で体を動かす(太陽の光を浴びると睡眠の質が向上)
- 夜はスマホやゲームの時間を減らす(ブルーライトは睡眠の妨げに)
目標:夏休みが終わる1週間前までに「学校モード」に戻す!
宿題や課題の最終確認
新学期直前に 宿題が終わっていないことに気づく…! というのは避けたいものです。計画的に進めるのが理想ですが、もし 宿題が残っている場合は効率的に進める工夫 をしましょう。
宿題チェックリスト
✅ ドリルやプリント類は終わっているか?
✅ 自由研究や作文は仕上がっているか?
✅ 読書感想文の本は読んだか?
✅ 工作や絵の課題は完成したか?
✅ 提出物に名前を書いたか?
宿題を効率よく終わらせるコツ
- 優先順位を決める(締切が近いものから取り組む)
- 短時間集中して取り組む(25分勉強+5分休憩の「ポモドーロ・テクニック」)
- 家族や友達と一緒にやる(わからないところを助け合える)
- 達成感を味わう(1つ終わるごとにカレンダーに✔をつける)
宿題は「早めに終わらせる」のが理想ですが、最後の追い込みも計画的に!
学用品や制服の準備
新学期を迎える前に、 学校で使う持ち物や服装の準備 も忘れずにチェックしましょう。
チェックリスト
✅ ランドセル・通学バッグ(中身を整理し、不要なものを取り除く)
✅ 筆箱・文房具(鉛筆が短くなっていないか、消しゴムは十分か)
✅ ノート・プリント(必要なノートは新しいものを用意)
✅ 給食セット(箸・ナフキン)(汚れや破損がないか確認)
✅ 制服・体操服(サイズが合っているか、ほつれや破れはないか)
✅ 上履き・靴(汚れがひどければ洗う or 買い替え)
直前に慌てないよう、前日までにしっかり準備を!
新学期に向けた目標設定
新学期を迎えるにあたり、 子ども自身が目標を持つこと も大切です。目標があると、学校生活が充実しやすくなります。
目標の立て方のコツ
- 具体的にする(「勉強をがんばる」→「毎日漢字を1ページ書く」)
- 達成しやすいものにする(無理なく続けられる目標を設定)
- 短期目標と長期目標を作る(「1週間ごとの小さな目標」+「学期全体の目標」)
- 親子で共有する(目標を書いて家族に伝えると意識が高まる)
目標設定の例
- 勉強の目標:「毎日30分宿題以外の勉強をする」
- 生活の目標:「夜9時には布団に入る」
- 友達関係の目標:「クラスの友達ともっと話すようにする」
- 習い事の目標:「サッカーの練習を週2回がんばる」
「できそうなこと」から始めるのが大切!
親子での振り返りと話し合い
夏休みが終わる前に、 親子で夏休みの振り返りをする時間 を作ると、新学期を前向きな気持ちで迎えられます。
振り返りのポイント
- 楽しかったことを話す(旅行・遊び・挑戦したことなど)
- がんばったことを振り返る(宿題・勉強・スポーツなど)
- できなかったことを次につなげる(来年の目標として考える)
- 新学期への期待や不安を共有する(楽しみなこと・心配なことを話す)
親子の会話例
👩「この夏休みで一番楽しかったことは何だった?」
👦「キャンプで星を見たこと!」
👩「素敵な思い出だね。学校が始まる前に準備したいことはある?」
👦「新しいノートを買いたい!」
👩「じゃあ、明日一緒に買いに行こうか!」
こうした会話を通じて、 子どもが新学期をポジティブな気持ちで迎えられるようサポート しましょう。
まとめ|2025年の夏休みを楽しく・有意義に過ごそう
小学校の夏休みは、地域や学校によって日程や過ごし方に違いがありますが、事前にスケジュールを把握しておくことで、余裕を持って計画が立てられます。
宿題や自由研究に取り組む時間、家族でのお出かけやリラックスできる時間など、バランスよく過ごすことが、夏休みをより充実させるポイントです。
今回ご紹介した内容を参考に、お子さんと一緒に「今年の夏休み、どう過ごす?」を話し合ってみるのも素敵ですね。
2025年の夏が、ご家族にとって楽しく実りある時間になりますように!