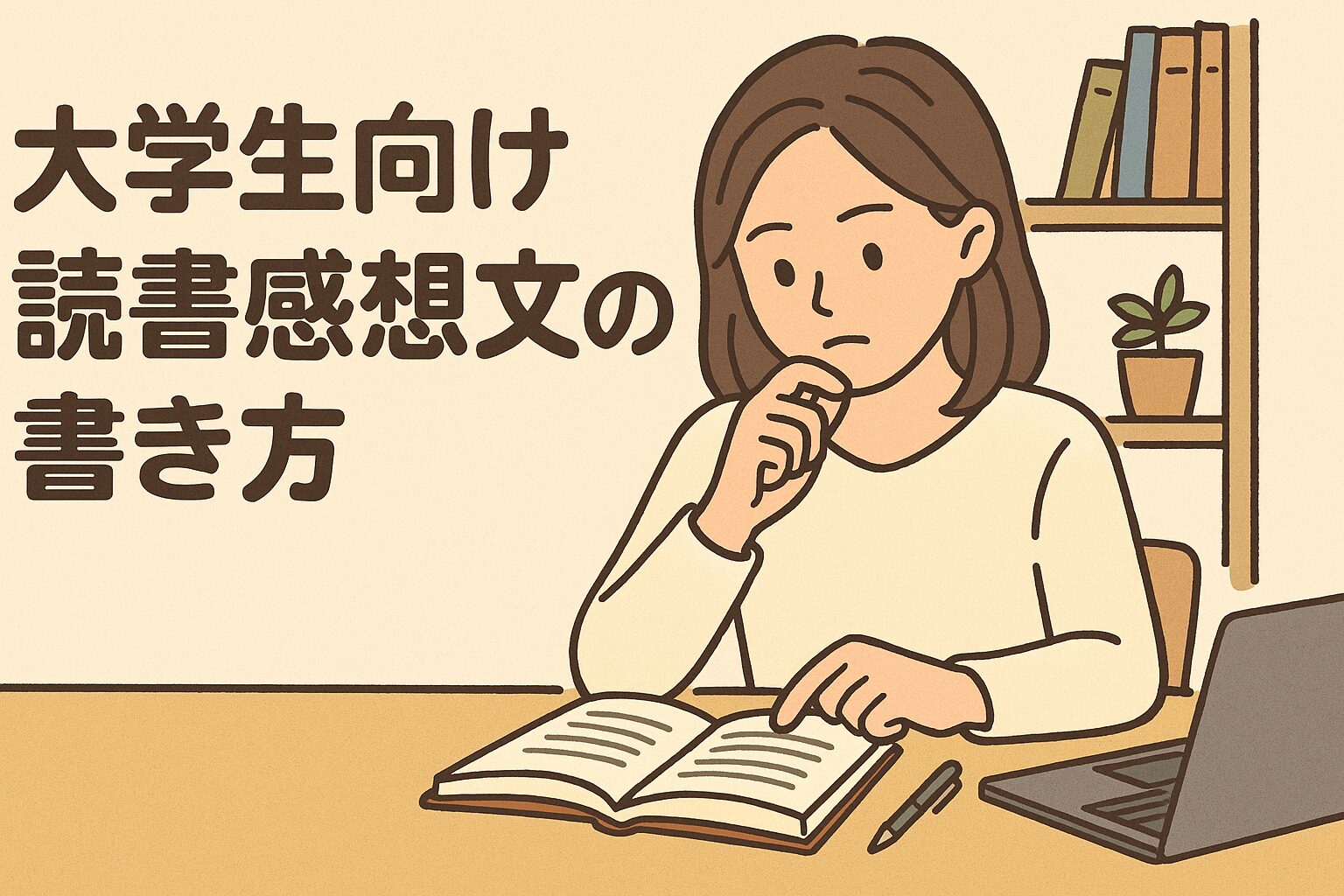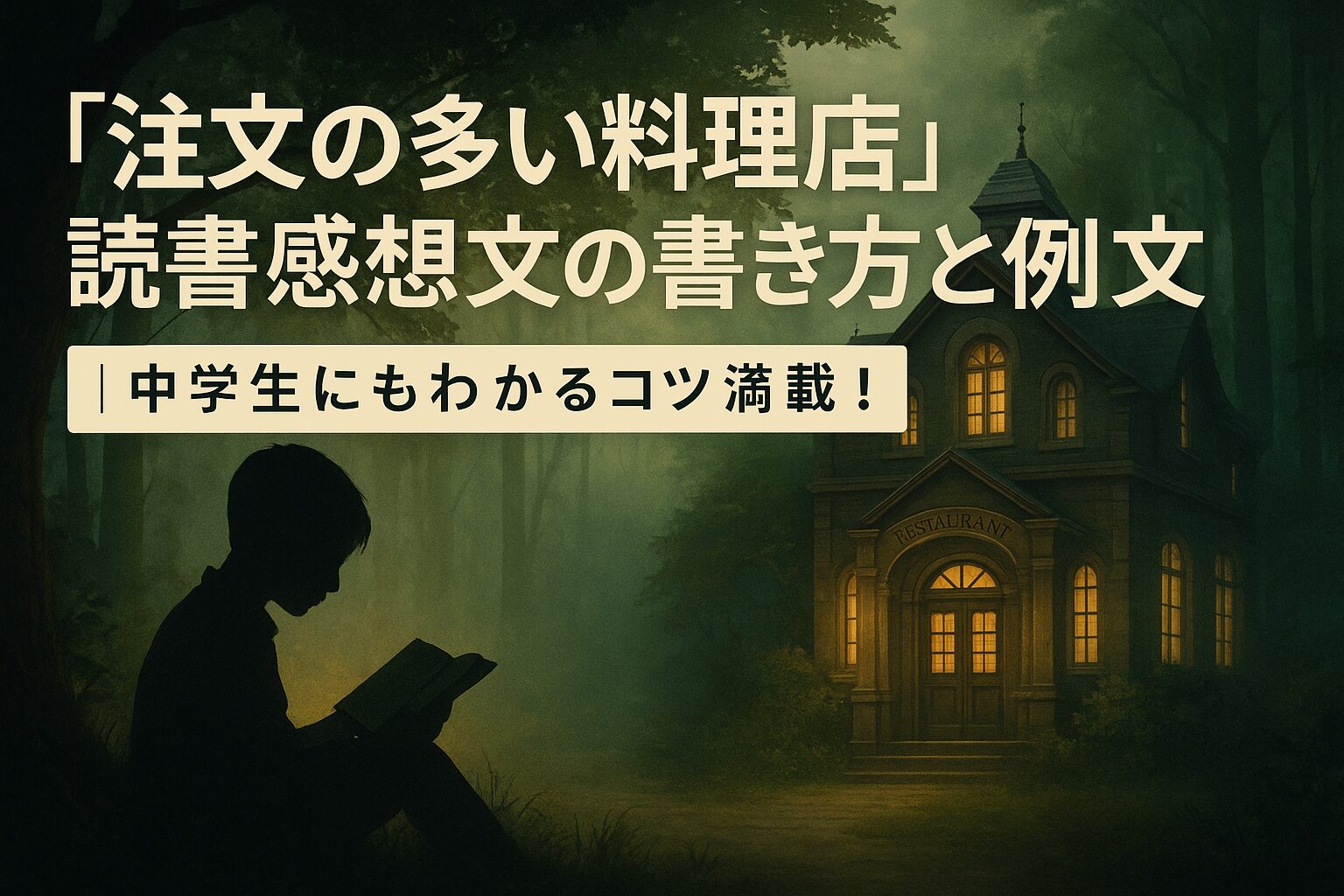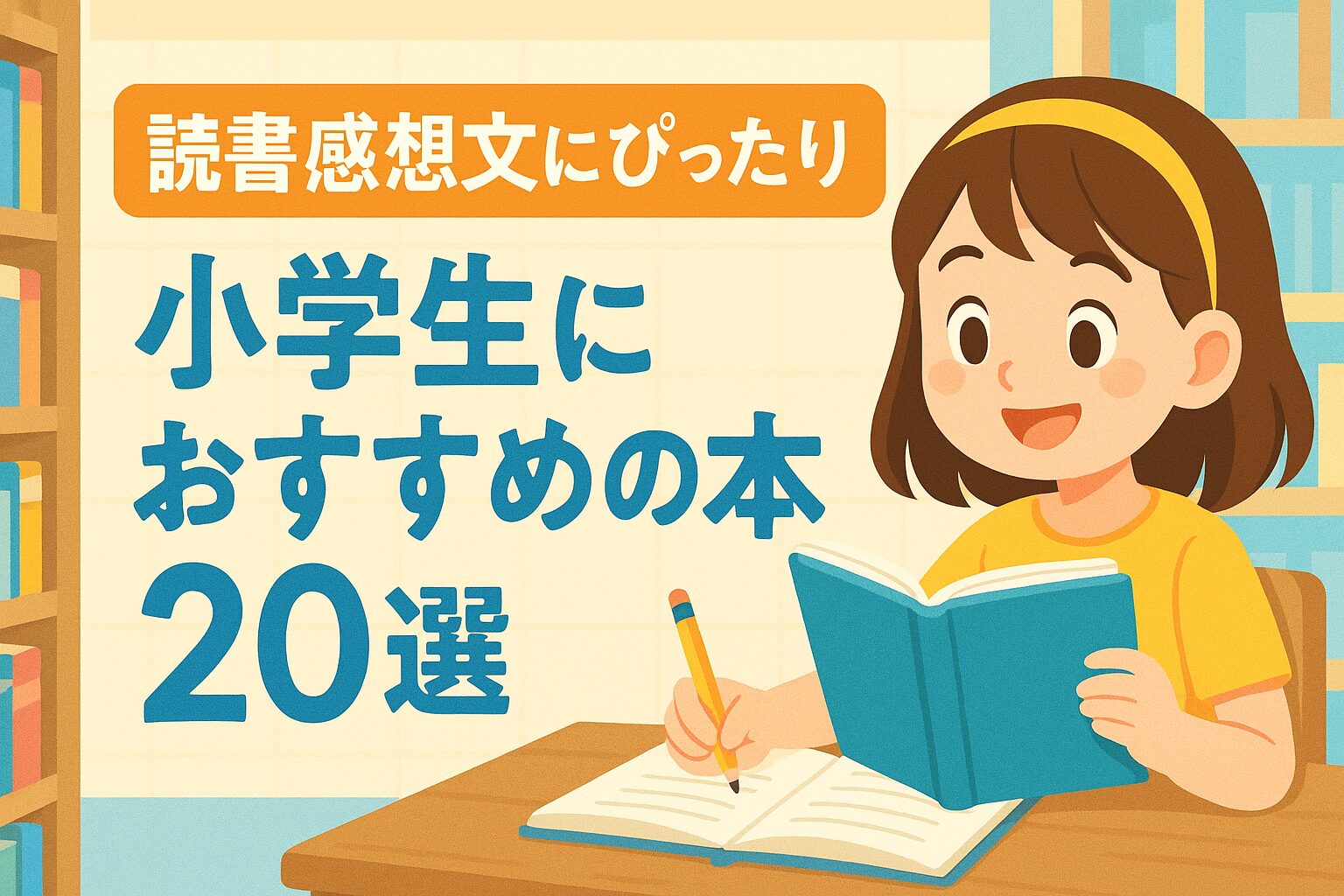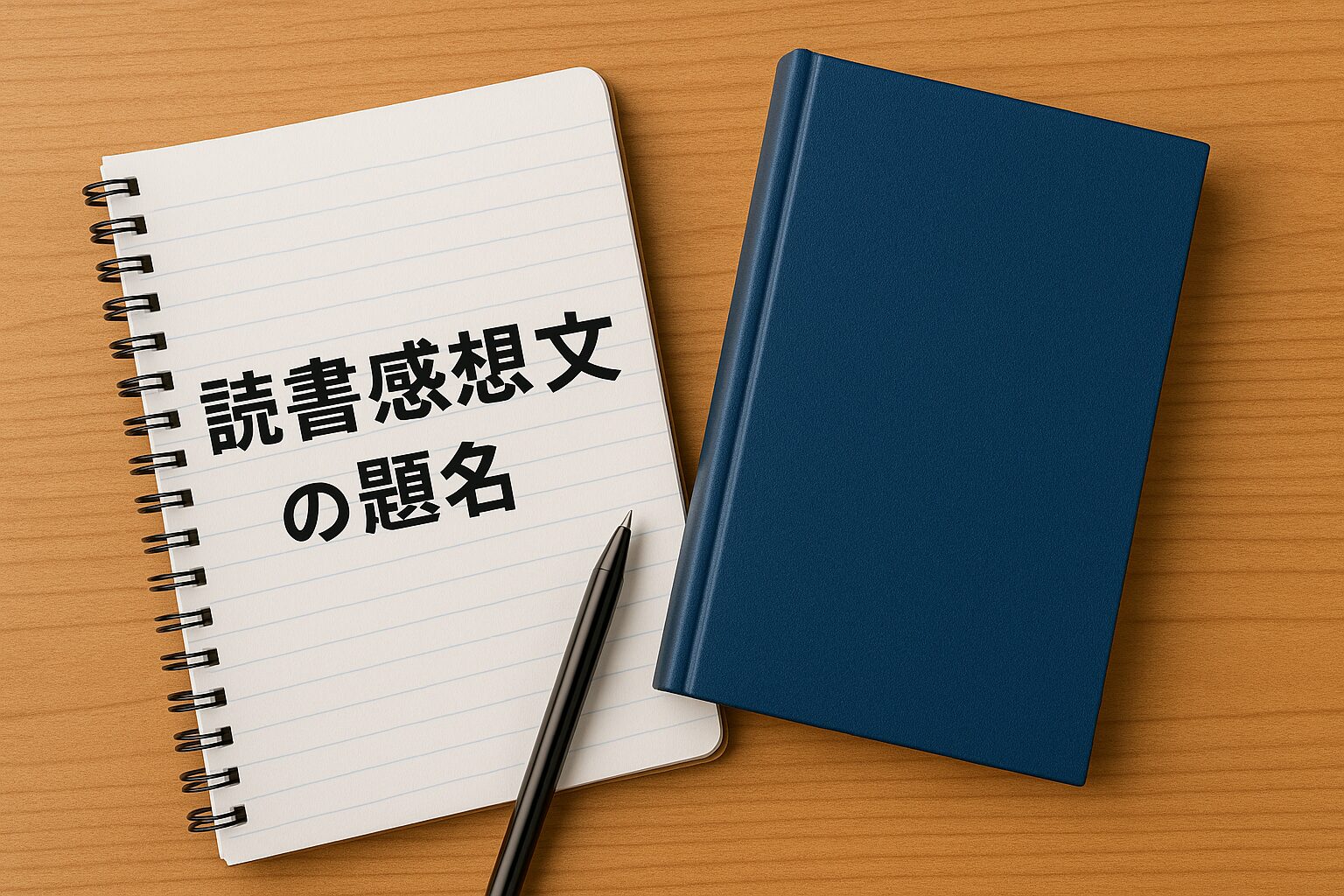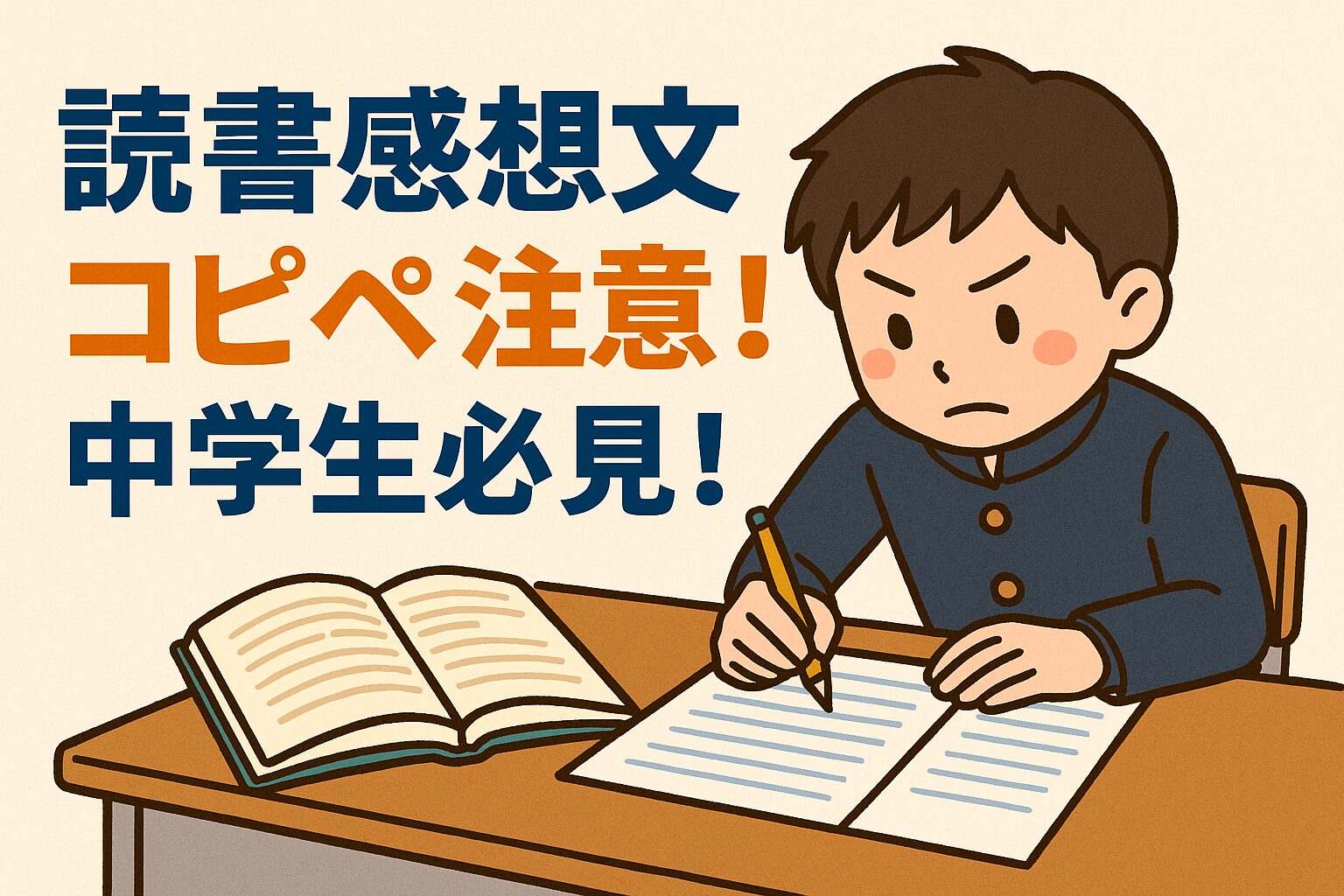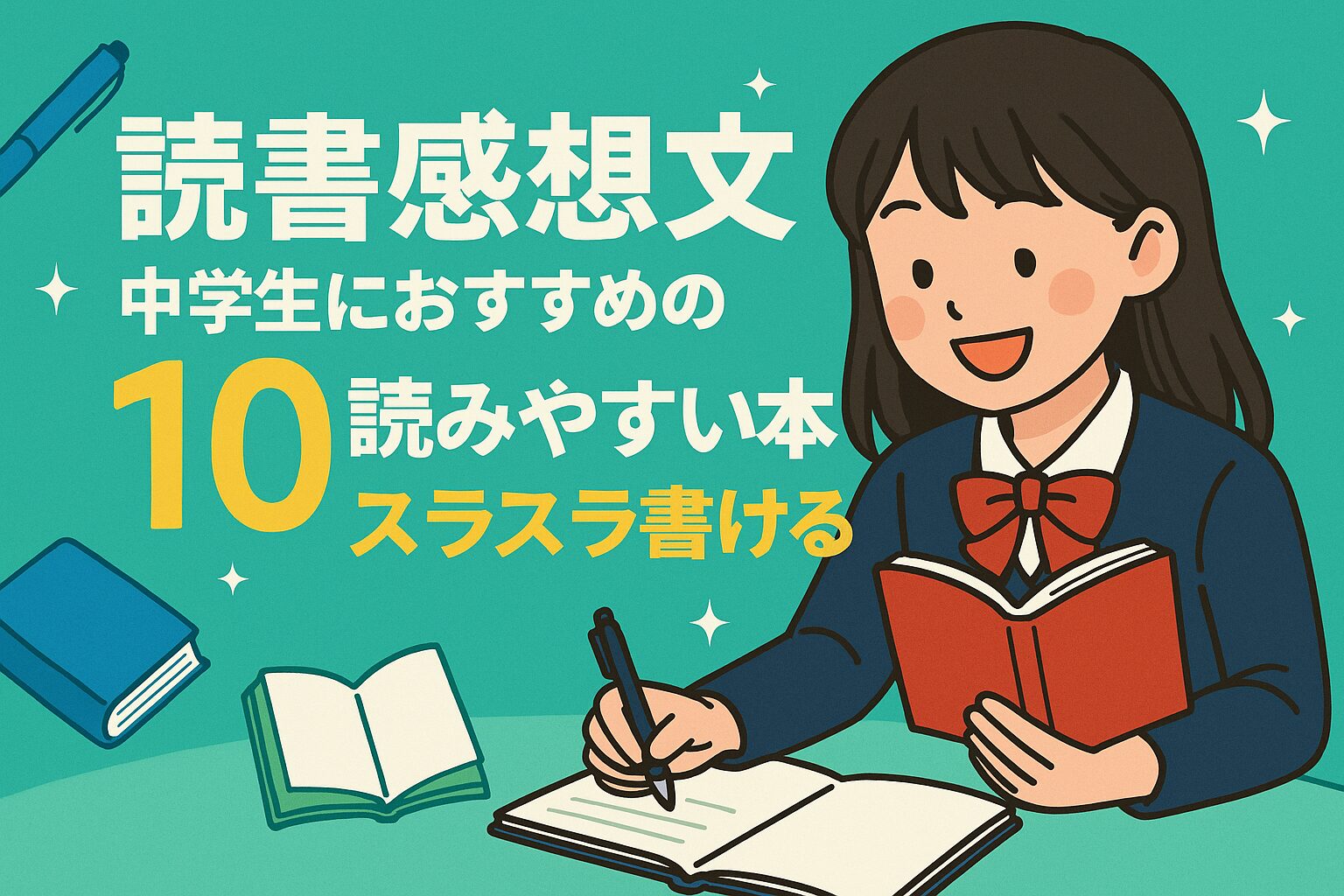「読書感想文って、何を書けばいいか全然わからない…」
大学生になると、高校までとは違う視点が求められる読書感想文に戸惑う人も多いのではないでしょうか?実は、評価される感想文には“ある書き方のコツ”があるんです。
そこで本記事では、大学生が読書感想文で高評価を得るための具体的な方法から、文章力を高めるテクニック、おすすめの書籍までを徹底解説。
誰でも読みやすく、印象に残る感想文が書けるようになります!
スポンサーリンク
大学生が読書感想文でつまずくポイントとは?
読書感想文と読書レポートの違い
大学生になると、「読書感想文」と「読書レポート」を混同してしまう人が多く見られます。しかし、この2つには明確な違いがあります。読書感想文は、文字通り「読んで感じたことや考えたこと」を中心に自由に書く文章です。
一方で読書レポートは、書籍の内容を要約し、著者の主張を正確に捉えたうえで、それに対する自分の意見や分析を論理的に述べるものです。つまり、感想文は「感情」に比重があり、レポートは「論理」と「根拠」に比重があります。
大学の授業で求められるものがどちらなのかを最初にしっかり確認することが重要です。感想文として提出する場合は、あらすじの羅列ではなく、自分の気づきや感じたことを中心に構成しましょう。
逆に、読書レポートとして求められている場合は、読書体験をもとに論点を深堀りして、他の文献や背景情報も交えて自分なりの解釈を書くことが求められます。
この違いを理解していないと、書き方自体を間違えて評価が下がる原因にもなりますので注意しましょう。
評価される感想文とされない感想文の差
評価される感想文と、そうでないものの違いはどこにあるのでしょうか。まず大きなポイントとして、「自分の視点があるかどうか」が挙げられます。
評価されない感想文は、多くが内容の要約に終始してしまい、著者が伝えたかったことをただ繰り返すだけになっています。逆に評価される感想文は、その本を読んだことで「自分がどう感じたか」「どう考えが変わったか」が明確に書かれているのです。
また、評価される感想文には「自分の経験」とのつながりがしっかりと描かれています。たとえば、登場人物の苦悩を自分の学生生活やバイトの経験に重ねることで、共感や疑問、気づきを深く掘り下げることができます。
単なる読後感ではなく、「自分の価値観と照らし合わせてどう変化したか」を表現することが、大学生の読書感想文では特に高く評価されるポイントとなります。
書き始められない原因トップ3
「何から書き始めればいいか分からない」という悩みは多くの大学生が持っています。書き始められない理由として代表的なものは次の3つです。
1つ目は「本の内容が難しすぎて理解が浅い」こと。難解な内容だと、印象に残るポイントが見つからず、書く材料が不足しがちです。
2つ目は「正解を書かなければ」というプレッシャーです。感想文に正解はありませんが、評価を意識しすぎると、自分の素直な感情や疑問を書けなくなってしまいます。
3つ目は「文章の構成が分からない」ことです。いきなり本文から書こうとせず、まずは印象に残った点を箇条書きにしてから組み立てるのがおすすめです。
これらの原因を理解し、書きやすい方法に切り替えることで、スムーズに書き始めることができるようになります。
「あらすじだけ」ではNGな理由
読書感想文でやってしまいがちなのが、「ほぼあらすじしか書かれていない」というパターンです。たしかにストーリーを紹介することは必要ですが、それが全体の大半を占めてしまうと、感想文としての評価は著しく下がってしまいます。
というのも、読む人はすでにその本の内容を知っていることが前提だからです。あらすじの羅列は、「読んでいない人向けの紹介文」に過ぎません。
大学生に求められるのは、「その本が自分にどんな影響を与えたのか」という視点です。ですので、あらすじを書く際はなるべく簡潔にまとめ、本文の大部分は自分の感じたこと、考えたこと、そこから得た学びに使いましょう。
また、登場人物の行動やセリフに対して自分がどう思ったのかを書くことで、あらすじを超えた深みのある内容になります。
自分の意見が薄くなる理由と対策
「なんとなく書けたけど、自分の意見が薄い気がする…」という悩みもよくあります。その理由の一つは、「何を言いたいのか」が明確になっていないことです。つまり、ただ思ったことをそのまま並べているだけでは、伝えたい主張がぼやけてしまうのです。
この対策としておすすめなのが、「問いを立てる」こと。たとえば「なぜ主人公はその選択をしたのか?」「自分ならどうするか?」という問いをもとに書くと、自然と自分の考えが浮かび上がってきます。また、文章を書き進める中で「この意見は本当に自分の言葉か?」と客観的に見直すことも大切です。
意見を明確にすることで、読書感想文は「読んで共感できる」「他人に読んでほしい」と思えるものに変わっていきます。
スポンサーリンク
読書感想文の基本構成と書き方
序論:本を選んだ理由を明確に書く
読書感想文を書く際、最初に大切なのが「なぜこの本を選んだのか」を読者に伝えることです。いわば導入部分であり、読み手に「この人はどんな視点でこの本を読んだのか」を示す役割を持っています。ここでしっかりと背景や動機を説明することで、文章全体の一貫性が生まれます。
たとえば、「講義の課題で指定されたから」ではなく、「タイトルにひかれて興味を持った」「自分の専攻と関連していそうだった」「友人にすすめられて読んでみた」など、少しでも自分の感情や選択の理由を込めると、読み手の共感を得やすくなります。さらに、「今の自分がこの本を読む意味」についても触れられると深みが増します。
この序論の部分で注意したいのは、長くなりすぎないこと。あくまで本題に入るための導線として、簡潔に自分の視点を示すことを意識しましょう。
本論①:印象に残った場面やセリフをピックアップ
本論のはじまりでは、自分が読んで一番心に残ったシーンやセリフを紹介するのが効果的です。なぜなら、そこを起点にして自分の感じたことや考えたことを掘り下げていけるからです。ただ「おもしろかった」「感動した」といった感想だけではなく、「なぜその場面が印象に残ったのか」「どんな感情がわいたのか」を詳しく書くようにしましょう。
たとえば、「主人公が親友に裏切られる場面に共感した」と書くのではなく、「自分も同じような経験をしたことがあり、胸が苦しくなった」など、具体的なエピソードを絡めると文章に説得力が出ます。また、セリフを引用する場合は、その前後の状況や登場人物の心情を簡単に説明し、そのセリフが自分にどんな影響を与えたかを述べると読みごたえのある内容になります。
本論②:自分の体験や価値観とリンクさせる
読書感想文で高評価を得るためには、本の内容と自分の体験や価値観を結びつけることが不可欠です。つまり、単なる感想ではなく、「自分ならどう考えるか」「似たようなことを経験したことがあるか」といった視点から深く掘り下げていくことが求められます。
たとえば、登場人物が困難を乗り越える話であれば、自分が過去に乗り越えた試練を思い出し、それとの共通点を見つけてみましょう。「自分も大学受験でくじけそうになったが、あきらめずに努力した」というように、自分の実体験とリンクさせることで、感情の深みが生まれます。
また、価値観の違いに着目するのも効果的です。「自分はこの登場人物とは全く違う考え方をする」「自分だったらこう行動する」など、異なる視点を持つことで、文章に厚みが出てきます。感想文を通して自分自身の内面も見つめ直せるような構成が理想的です。
本論③:他者の意見との違いも含めて考える
大学生に求められる感想文は、「自分の考え」に加えて「他者との比較」も含めると、より客観性が増して評価されやすくなります。たとえば、講義中のディスカッションで出た意見や、ネット上の書評、本の解説などを参考にしながら、「他の人はこう感じたが、自分はこう考えた」というように、視点の違いを意識して書くと、深い考察になります。
「この本は感動するという意見が多いが、自分はあまり感情移入できなかった。その理由は~」といった書き方をすることで、単なる共感だけではない、冷静な読書体験を伝えることができます。また、異なる意見を否定するのではなく、「なるほど、そういう見方もあるのか」と受け入れる姿勢を見せると、知的で柔軟な印象を与えることができます。
このように他者の視点を交えることで、読書感想文に「社会性」や「広がり」を加えることができるのです。
結論:読後の変化や学びをまとめる
感想文の締めくくりでは、その本を読み終えたことで自分にどんな変化が起きたのか、どんな学びを得たのかを明確にまとめましょう。「この本を読んだことで、考え方が変わった」「今後の生き方に影響を与えそうだ」といった形で、自分の中で起きた内面的な変化を言語化するのがポイントです。
また、「このテーマについてもっと調べてみたくなった」「似たジャンルの本を読んでみたい」といった未来に向けた行動のきっかけを示すことも有効です。読書によって自分がどう成長したか、あるいは成長する兆しが見えたかをまとめることで、読み手にも伝わる強いメッセージ性を持った文章になります。
結論部分は、全体の印象を決める大事なパートです。簡潔かつ感情をこめて、読後の余韻が残るように工夫しましょう。
スポンサーリンク
文章力をアップさせる5つのテクニック
主語と述語をしっかり合わせる
文章が読みにくい、伝わりにくいと感じる原因のひとつが、「主語と述語が一致していない」ことです。たとえば、「主人公の言動に感動した読者は、物語の深さを感じたと思います。」という文章では、誰が何をしたのかがぼやけてしまいます。「私は、主人公の言動に感動し、物語の深さを感じました。」と書くことで、誰がどう感じたのかが明確になります。
大学生になると、複雑な構文や難しい言い回しを使いたくなる気持ちも分かりますが、まずは基本に立ち返って、主語と述語がしっかり対応しているかを確認することが大切です。日本語は主語を省略しがちですが、特に感想文では「誰がどう思ったのか」を明確にするために、主語は積極的に入れた方が良いでしょう。
文章を書いた後には、主語と述語がきちんとつながっているか、自分の意図どおりに伝わるかを確認する習慣をつけると、読みやすく説得力のある文が書けるようになります。
接続詞を工夫して流れを良くする
文章の流れをスムーズにするために欠かせないのが、接続詞の使い方です。感想文では「そして」「しかし」「たとえば」などの接続詞を適切に使うことで、読み手が内容を理解しやすくなります。逆に、接続詞が多すぎたり、同じ言葉ばかり繰り返していたりすると、読みにくく単調な印象を与えてしまいます。
たとえば、「しかし」の代わりに「一方で」や「とはいえ」、「だから」の代わりに「そのために」や「ゆえに」など、言い換え表現を取り入れることで文章に変化をつけることができます。また、段落ごとに異なる接続詞を使うことで、話の展開が自然に感じられるようになります。
読書感想文は自分の考えを順序立てて説明する文章なので、接続詞は「論理の橋渡し役」として非常に重要です。使い慣れていない場合は、まず文章を書いたあとに接続詞の種類を見直し、バランスよく使われているかをチェックすると良いでしょう。
読点「、」の打ち方で読みやすさUP
文章が読みづらいと感じたとき、意外と見落としがちなのが読点(、)の打ち方です。読点には、意味の区切りを明確にしたり、読み手に呼吸のタイミングを与えたりする役割があります。特に長めの文章では、適切な場所に読点を入れることで、グッと読みやすさが向上します。
たとえば、「私はこの本を読んでとても感動しました。」という文章よりも、「私は、この本を読んで、とても感動しました。」と区切る方が、感情が伝わりやすくなります。逆に、必要のない箇所に読点があると、リズムが悪くなってしまうので注意が必要です。
読点を打つタイミングは、「意味が切れるところ」「強調したいところ」「主語と述語が長く離れている場合」などが基本です。ただし、入れすぎても逆効果なので、自分で音読してみて自然に聞こえるかを判断材料にすると良いでしょう。
難しい言葉を避けて簡潔に書く
大学生になると、つい難しい言葉や専門用語を使いたくなりますが、読書感想文では「分かりやすさ」が何より大切です。たとえば、「自己実現欲求が高まった」よりも「もっと自分らしく生きたいと思った」と言い換えた方が、読み手に感情が伝わりやすくなります。
また、難しい言葉を使うと、それだけで読み手にストレスを与えてしまうことがあります。特に感想文では、自分の素直な気持ちや思ったことを表現することが求められるので、複雑な表現よりも簡潔で自然な言葉を使う方が説得力があるのです。
文章を書いたあとには、「この言葉は中学生にも伝わるか?」という視点で見直してみましょう。もし難しい表現があれば、もっとシンプルな言い回しに言い換えてみることをおすすめします。読みやすい文章こそが、読者に伝わる良い文章なのです。
語尾をバリエーション豊かにする
読書感想文でよくある失敗のひとつが、「〜と思いました」「〜と感じました」の語尾ばかり使ってしまうことです。もちろん、感想文なのでこうした語尾は基本ですが、繰り返しすぎると文章が単調になり、読者が飽きてしまいます。
たとえば、「〜のように感じられた」「〜ではないかと考える」「〜と気づいた」「〜であると私は思う」など、語尾に少し工夫を加えるだけで文章にリズムが生まれ、知的で洗練された印象になります。文末を変えることで文全体の雰囲気も変わってきます。
また、感情を強調したいときは「〜と強く思った」「〜せずにはいられなかった」といった語尾を使うのも効果的です。文章の抑揚をつけることは、読書感想文に深みを与える大事なポイントです。
スポンサーリンク
高評価を狙う読書感想文のチェックポイント
書く前に「目的」を意識する
読書感想文を書くとき、多くの人が最初に手をつけるのが「あらすじを書くこと」ですが、これはあまりおすすめできません。なぜなら、何のために感想文を書くのかという「目的」が明確になっていないと、書いているうちに内容がブレたり、伝えたいことが分かりにくくなったりするからです。
大学の課題で求められる読書感想文は、ただの感想ではなく「自分の考えや成長」を言葉にして伝えることが目的です。そのため、「この本を読んで何を伝えたいのか」「自分の中にどんな変化があったのか」をあらかじめ考えておくことが大切です。書く前に、自分に次のような問いを立ててみましょう。「この本を読んで一番印象に残ったことは?」「何を学んだ?」「それをどう生かしたいか?」
こうした問いに答えることが、感想文の軸になります。目的をはっきりさせることで、文章がぶれずにまとまりやすくなり、読み手にも強く印象を残すことができるのです。
他の感想文を参考にしすぎない
読書感想文を書こうとすると、ついネットで「この本の感想文」と検索して、他の人が書いた例文を見たくなることがありますよね。参考程度に見るのは良いですが、そこに頼りすぎると、自分らしい言葉が書けなくなってしまいます。
他人の感想をそのままマネすると、文章に「自分の視点」がなくなってしまい、どこか他人事のような、深みのない文章になってしまいます。大学の課題では特に、オリジナリティや主体性が重視されるため、「自分がどう感じたか」「どのように解釈したか」がしっかり伝わる文章にすることが重要です。
どうしても書き始めに悩んだときは、「他人の感想を読む」のではなく、「自分が本を読んで印象に残った場面をメモする」ところから始めるのがおすすめです。他人の視点ではなく、自分の視点で文章を書くこと。それが、高評価につながる感想文を書く第一歩です。
誤字脱字チェックを怠らない
どんなに中身のある素晴らしい感想文でも、誤字や脱字が多いと評価は下がってしまいます。文章の正確さは、読みやすさにも直結しますし、「丁寧に書かれているかどうか」という印象にも影響を与えます。特に大学では、文章の完成度も成績に大きく関係してきますので、誤字脱字チェックは必須です。
チェックの方法としては、まず自分で声に出して読んでみること。黙読では見逃してしまうミスも、音読することで意外と気づけます。また、できれば1日時間を空けてから読み直すと、新たなミスにも気づきやすくなります。
さらに、WordやGoogleドキュメントの校正機能を活用するのも有効です。ただし、すべてを自動で任せるのではなく、自分の目でもしっかり確認することが大切です。「読み手への配慮」=「ミスを最小限にする意識」と考えて、丁寧に仕上げましょう。
時間を置いて読み返してみる
文章を書いた直後に読み返しても、なかなかミスや文章の不自然さには気づけません。それは、書いたばかりの時点では内容が頭に入っているため、「読んで理解する」より「覚えている」ことで読み進めてしまうからです。そんなときに効果的なのが、「時間を置いてから読み返す」ことです。
1〜2時間、可能であれば1日置いてから読み返すと、不思議なほど客観的に自分の文章を見られるようになります。「なんでこんな言い回しにしたんだろう?」「この文は少し回りくどいな」など、改善点が自然と見えてくるはずです。
また、読み返す際には「読者目線」を意識してみましょう。読み手が初めてこの文章を読んだとき、わかりにくく感じないか、論理が飛躍していないかを確認することが大切です。時間を置いて見直す癖をつけることで、文章の完成度は一気に高まります。
第三者に読んでもらってフィードバックをもらう
どんなにしっかりと読書感想文を書いたつもりでも、自分一人の視点だけでは気づけないことがたくさんあります。そんなときに有効なのが、「第三者に読んでもらう」ことです。友人や家族、同じ講義を受けているクラスメイトなどに読んでもらい、感想や意見をもらうことで、改善点が明確になります。
たとえば、「この部分、意味が少し分かりづらいかも」「ここはもっと詳しく書いた方が良さそう」など、自分では気づかなかったポイントを指摘してもらえると、文章がグッと洗練されていきます。また、褒められた部分も記録しておくと、自分の得意な書き方や表現方法が分かるようになり、今後の文章力アップにもつながります。
ただし、誰かに読んでもらう際は、「どこがわかりにくかった?」「どこが良かった?」など、具体的に質問をすることが大切です。そうすることで、より実りあるフィードバックを得ることができます。
スポンサーリンク
読書感想文を書くのにおすすめの本5選
短時間で読めて内容が濃い本
大学生は課題に追われがちで、じっくり読書する時間が取りづらいことも多いでしょう。そんなときにおすすめなのが「短時間で読めるけれど、内容に深みがある本」です。ページ数が少なくても、テーマが明確で考察の余地がある作品は、読書感想文の題材として非常に優れています。
おすすめの一冊は、村上春樹の『ノルウェイの森』のような長編ではなく、例えば中島敦の『山月記』や太宰治の『走れメロス』。いずれも短編ながら、文学的な奥行きと人間の葛藤が描かれており、自分の価値観や人生観と結びつけて感想を書くのに最適です。
短時間で読めるからといって内容が浅いわけではなく、むしろ短編の方が主題が絞られているため、感想文を書く際に焦点を当てやすく、まとめやすいという利点もあります。「あまり本を読まないから不安」「読み終える自信がない」と感じる人は、こうした短編から始めてみるとよいでしょう。
問題提起型で感想が書きやすい本
読書感想文を書く際に悩むのが「何を書けばいいかわからない」ということ。そんな時に助けになるのが、「問題提起型」の本です。つまり、社会的な問題や哲学的なテーマについて問いを投げかけるタイプの本で、読者に考えさせる要素が含まれているため、自分の意見を書きやすいという特徴があります。
例えば、小川洋子の『博士の愛した数式』は「記憶」と「人との関わり」という深いテーマを持っており、時間の流れや家族の形について自然に考えるきっかけになります。他にも、芥川龍之介の『羅生門』などは「人間の善悪」について鋭い問いを含んでおり、自分の倫理観と照らし合わせながら感想を書くことができます。
このタイプの本は、読んだあとにモヤモヤとした気持ちや疑問が残ることが多いですが、それこそが良質な感想文の材料になります。「読んで考えたこと」や「自分なりの答え」を書くだけで、自然と深みのある文章に仕上がるでしょう。
登場人物の心情が深く描かれている本
読書感想文で心を打つポイントのひとつに、登場人物への共感があります。特に感情移入しやすい本は、自分の経験と重ね合わせやすく、感想を書きやすくなります。登場人物の心理描写が丁寧に描かれている本を選ぶことで、その人物の葛藤や成長に焦点を当てて、自分の気持ちを言葉にしやすくなるのです。
例えば、重松清の『流星ワゴン』は、父と子、夫婦関係、人生のやり直しといったテーマが盛り込まれており、主人公の心の変化がとても繊細に描かれています。また、辻村深月の『かがみの孤城』も、登場人物たちの繊細な心の動きが丁寧に描かれていて、共感しやすく、若者の悩みを扱っているため大学生にもぴったりです。
このような本を選ぶと、「この場面でなぜ彼はそうしたのか」「私ならどうしたか」と考える視点が自然に生まれ、説得力のある感想文を書くことができるでしょう。
実話ベースで共感しやすい本
ノンフィクションや実話をもとにした作品は、現実感があり、読後に強く心に残ることが多いです。特に、実際に起きた出来事や人物の人生を描いた本は、事実の重みと人間のリアルな感情が混ざり合っており、大学生の視点で学べることが多くあります。
たとえば、柳田邦男の『犠牲(サクリファイス)―わが息子・脳死の11日』は、脳死と臓器提供という重いテーマを扱っており、「命の尊さ」や「自分だったらどうするか」といった深い思考を引き出してくれます。また、山田詠美の『ぼくは勉強ができない』なども、実在するような人物の成長と迷いが描かれており、現実味のある感想文を書く材料になります。
実話ベースの本は、感想文の中で「この話から私は○○を学んだ」「自分も似た経験がある」といった形で書きやすく、読む人にも誠実な印象を与えることができます。
社会課題に触れていて考察しやすい本
大学生として、社会に目を向けた読書感想文を書くと評価が高くなる傾向があります。そのため、環境問題、貧困、教育、ジェンダーなどの社会課題に触れている本を読むことで、より深く、自分の意見を表現できる文章が書けます。
おすすめは、三浦しをんの『風が強く吹いている』。これはスポーツを通じて仲間との絆や努力を描く物語ですが、同時に「貧困」「夢と現実のギャップ」といった現代的なテーマも含まれています。他にも、中村文則の『何もかも憂鬱な夜に』は、社会に馴染めない若者の内面を描いており、現代社会の構造に対する問題意識を深めるきっかけになります。
社会課題に触れることで、単なる「感動した」では終わらない、「考えさせられた」「もっと知りたくなった」といったレベルの高い感想文が書けるようになります。自分の専攻や将来の進路に絡めると、さらに評価されやすくなるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 大学生の読書感想文では何が評価されるのですか?
A.
大学生の読書感想文では、「読んだ本の内容を自分の視点でどう解釈し、どんな気づきや学びを得たか」が重視されます。あらすじの要約ではなく、自分の意見や感情、体験と絡めて考察できているかが評価ポイントになります。また、文章の論理性や構成、読みやすさも重要です。
Q2. 読書感想文と読書レポートの違いは何ですか?
A.
読書感想文は「感情」を中心に、自分の感じたことや気づきを自由に書くのが目的です。一方、読書レポートは「論理」が重視され、内容の要約・考察・批評などを客観的にまとめる必要があります。提出先(授業や課題)がどちらを求めているのかを事前に確認しましょう。
Q3. 感想文で「何を書けばいいか分からない」ときはどうすれば?
A.
まずは、読んで印象に残った場面やセリフをメモするところから始めましょう。そして「なぜそれが印象に残ったのか」「自分の経験とどうつながるのか」を考えてみると、自分の意見が見つかりやすくなります。問いを立てながら書くのも効果的です。
Q4. 感想文を書くのにおすすめの本はありますか?
A.
短編小説や実話ベースのノンフィクションがおすすめです。たとえば『山月記』(中島敦)や『博士の愛した数式』(小川洋子)、『かがみの孤城』(辻村深月)などは、テーマが明確で感想が書きやすいです。自分の関心と重なるテーマを選ぶと、より良い感想文になります。
Q5. 感想文の文字数が足りないとき、どう工夫すればよい?
A.
具体的な体験談や自分の価値観との比較を盛り込むと、自然と内容が膨らみます。また、登場人物の行動やテーマに対して「自分ならどうしたか?」という視点を入れるのも効果的です。問いかけ形式で展開すると文字数も増え、深みも出ます。
まとめ
大学生が書く読書感想文は、高校生までのものとは違い、より論理性や主体性が求められます。ただ本の内容をまとめるだけではなく、「その本を読んで自分は何を感じたのか」「どんな学びや変化があったのか」を言語化することが大切です。
本記事では、つまずきやすいポイントから始まり、構成の基本、文章力を高めるコツ、評価されるためのチェックポイント、そしておすすめの本まで幅広く解説しました。
読書感想文を書くことは、単なる課題ではなく、自分の考えや感情を整理し、他者に伝える力を育む絶好の機会です。最初は難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば誰でも質の高い文章が書けるようになります。ぜひ本記事を参考にして、心に残る感想文を書いてみてください。