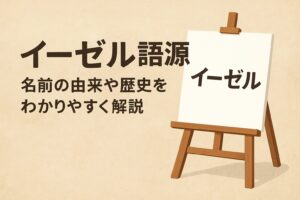5月は新緑の季節、そして日本の伝統的な行事が多く行われる月でもあります。端午の節句や八十八夜、母の日など、家族で楽しめるイベントが満載です。そんな5月の行事には、旬の食材を活かした「行事食」が欠かせません。
そこで本記事では、5月の行事食の意味や歴史、そして簡単に作れるレシピを紹介します。旬の味覚を取り入れながら、日本の食文化を楽しみましょう!
スポンサーリンク
5月の行事食について
5月に食べる行事食の意味と由来
5月の行事食には、古くからの伝統や季節の移り変わりを感じる意味が込められています。日本では、節句や農作業の節目に特別な食事を楽しむ文化があり、5月も例外ではありません。特に「端午の節句」にちなんだ食べ物は有名で、柏餅やちまきが食べられます。これらの食べ物には子どもの健やかな成長を願う意味があり、柏餅の柏の葉は「新芽が出るまで古い葉が落ちないこと」から、家系が絶えないという縁起の良い意味を持っています。
また、5月は農作業においても重要な時期で、八十八夜には新茶を楽しむ習慣があります。八十八夜とは立春から数えて88日目を指し、ちょうどこの時期に摘まれる新茶は「長生きの薬」とも言われるほど栄養価が高く、日本の食文化に深く根付いています。
さらに、5月の旬の食材を使った料理も行事食として楽しまれます。タケノコや新じゃがいも、そら豆などの野菜は春から初夏にかけて旬を迎え、料理に取り入れることで季節の恵みを感じることができます。
現代では、伝統的な行事食をアレンジして食卓に取り入れる家庭も増えており、和菓子だけでなく洋菓子で端午の節句を祝ったり、新茶をスイーツと一緒に楽しんだりと、形を変えながらも日本の食文化が受け継がれています。
日本の伝統行事と食文化の深い関わり
日本の行事と食文化は切っても切れない関係にあります。季節ごとに行われる行事には、それにふさわしい食べ物が用意され、人々が共に食事を楽しむことで絆を深めてきました。5月の代表的な行事である「端午の節句」や「八十八夜」も例外ではありません。
端午の節句では、男の子の成長を願う「柏餅」や「ちまき」が食べられます。柏餅は関東地方を中心に、ちまきは関西地方で広く親しまれており、それぞれの地域の風習に根ざした食文化を反映しています。一方、八十八夜には「新茶」が飲まれます。この時期に摘まれる茶葉は特に香りがよく、昔から縁起の良い飲み物とされてきました。
また、5月には「母の日」もあり、感謝の気持ちを伝えるための特別な食事を楽しむ家庭が多いです。カーネーションの花とともに、母親が好きな料理を振る舞うことが一般的ですが、最近ではスイーツ作りを一緒に楽しむ家庭も増えています。
このように、行事食は単なる食べ物ではなく、家族や地域の人々が共に過ごす時間を豊かにする役割を果たしています。
季節の食材を取り入れた行事食の魅力
5月の行事食の魅力は、旬の食材をふんだんに使うことにあります。たとえば、端午の節句の定番「ちまき」にも、よもぎを練り込んだものや、具材に季節の野菜を取り入れたものがあります。また、新茶を楽しむ際には、旬のそら豆やタケノコを使った料理を添えることで、季節感を味わうことができます。
旬の食材は、その時期に最も栄養価が高く、味も濃厚でおいしいのが特徴です。5月には、タケノコ、新じゃが、そら豆、カツオなどが旬を迎えます。これらを活かした料理は、行事食としてだけでなく、日常の食卓でも楽しむことができます。
また、旬の食材を使うことは、体にとっても良い影響をもたらします。例えば、新茶にはカテキンやビタミンCが豊富に含まれており、免疫力向上やリラックス効果が期待できます。タケノコは食物繊維が多く、腸内環境を整える効果があります。このように、5月の行事食は、単にお祝いのための料理ではなく、健康を支える役割も担っているのです。
現代の食卓に取り入れるポイント
伝統的な行事食を現代の食卓に取り入れるには、少し工夫が必要です。たとえば、忙しい家庭では手作りの柏餅やちまきを作るのが難しいこともありますが、市販のものを活用したり、和菓子店の柏餅を買ってくるだけでも、行事の雰囲気を楽しむことができます。
また、新茶を飲む習慣がない家庭でも、抹茶スイーツや緑茶を使った料理を取り入れることで、八十八夜を意識した食卓を作ることができます。さらに、母の日には特別な料理を作るだけでなく、外食やテイクアウトを利用して家族で楽しい時間を過ごすのも一つの方法です。
5月の行事食を取り入れることで、食卓に季節感をもたらし、家族の会話も弾みます。現代のライフスタイルに合わせたアレンジを加えることで、無理なく伝統の味を楽しむことができるでしょう。
海外の5月の行事食との比較
世界にも5月に特別な食事を楽しむ文化があります。例えば、アメリカでは5月の「メモリアルデー」にバーベキューをするのが定番です。また、メキシコの「シンコ・デ・マヨ(5月5日)」では、タコスやエンチラーダなどのメキシコ料理を楽しみます。
ヨーロッパでは、5月1日に「メーデー」を祝う国が多く、春の訪れを祝うために野外でピクニックを楽しむ習慣があります。イギリスでは「アスパラガス・フェスティバル」が開催され、新鮮なアスパラガスを使った料理が楽しまれます。
このように、世界各国にも5月に特別な食べ物を楽しむ文化があります。日本の行事食と比較すると、伝統や意味合いは異なりますが、季節の恵みを味わうという点では共通していることがわかります。
行事食は、その国や地域の文化を映し出すものです。日本の5月の行事食も、未来に受け継いでいきたい大切な食文化のひとつと言えるでしょう。
スポンサーリンク
端午の節句の行事食|男の子の成長を願う伝統料理
端午の節句とは?歴史と由来
端午の節句は5月5日に行われる日本の伝統行事で、男の子の健やかな成長を願う日とされています。この行事は奈良時代に中国から伝わり、もともとは厄除けのための行事でした。日本では武士の時代になると、男の子の成長を祝う風習へと変化し、現代に受け継がれています。
端午の節句には、家の外に鯉のぼりを飾り、室内には武者人形や兜を飾る風習があります。鯉のぼりは「鯉が滝を登ると龍になる」という中国の故事に由来し、男の子の立身出世を願う象徴とされています。兜や武者人形は、厄を払い、子どもを守る意味があります。
食文化としては、「ちまき」や「柏餅」を食べる習慣があります。これらの食べ物には厄除けや家の繁栄を願う意味が込められており、地域によって違いも見られます。現在では、家庭で伝統料理を楽しむだけでなく、レストランやスイーツ店でも端午の節句にちなんだメニューが登場するなど、時代に合わせて進化しています。
ちまきと柏餅の違いと意味
端午の節句に食べる代表的な食べ物が「ちまき」と「柏餅」です。どちらも縁起の良い食べ物ですが、地域によってどちらを食べるかが異なります。
- ちまき(主に関西地方)
ちまきは、もち米や団子を笹の葉や竹の皮で包み、蒸したものです。中国から伝わったとされ、邪気を払う食べ物とされています。特に関西地方では、端午の節句にはちまきを食べる習慣が根付いています。 - 柏餅(主に関東地方)
柏餅は、餅にあんこを包み、柏の葉で巻いた和菓子です。柏の木の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないため、「家系が途絶えない」という意味を持ち、縁起の良い食べ物とされています。関東地方では、端午の節句に柏餅を食べることが一般的です。
現代では、スーパーや和菓子店で手軽に購入できるため、どちらも楽しむ家庭も増えています。また、抹茶あんやみそあんなど、さまざまなバリエーションの柏餅も登場し、選ぶ楽しみも増えています。
端午の節句に食べる魚や野菜の意味
端午の節句には、柏餅やちまきのほかに、特定の魚や野菜を食べる習慣もあります。これらの食材には、それぞれ健康や成長を願う意味が込められています。
- カツオ(勝男)
「勝つ男」に通じることから、端午の節句の縁起物として食べられるようになりました。特に初ガツオは5月に旬を迎え、刺身やたたきにして食べるのが定番です。 - たけのこ
たけのこは成長が早く、「すくすく育つ」という意味を持つため、端午の節句の食材として好まれます。煮物や炊き込みご飯、味噌汁など、さまざまな料理で楽しめます。 - よもぎ
よもぎには強い香りがあり、邪気を払うとされています。ちまきや草餅によく使われ、端午の節句の行事食として親しまれています。 - 菖蒲酒
端午の節句には、菖蒲の葉をお酒に浮かべた「菖蒲酒」を飲む風習があります。菖蒲の強い香りが邪気を払うとされ、大人の間では健康を願う意味で飲まれています。
これらの食材を使った料理を食卓に並べることで、伝統を感じながら美味しく端午の節句を祝うことができます。
家庭で楽しむ端午の節句の献立アイデア
端午の節句を家庭で楽しむために、簡単に作れる献立を紹介します。
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| ちまき・柏餅 | 市販のものを用意するか、手作りで楽しむ |
| カツオのたたき | 初ガツオを使ったさっぱりとした一品 |
| たけのこご飯 | 旬のたけのこを活かした炊き込みご飯 |
| よもぎ団子 | よもぎを練り込んだお団子で邪気払い |
| 菖蒲湯 | お風呂に菖蒲を浮かべて、健康を願う |
これらの料理を組み合わせることで、手軽に伝統を感じられる食卓が作れます。特に子どもと一緒に柏餅やちまきを作るのも、思い出に残る楽しい時間になります。
端午の節句の行事食を手作りする方法
伝統的な行事食を手作りすることで、より深く端午の節句を楽しむことができます。
簡単柏餅の作り方
材料(5個分)
- 上新粉:100g
- ぬるま湯:80ml
- こしあん:100g
- 柏の葉(市販のもの):5枚
作り方
- 上新粉にぬるま湯を加え、耳たぶくらいの柔らかさになるまでこねる。
- 生地を5等分し、手のひらで平らに伸ばす。
- こしあんを包み、楕円形に整える。
- 蒸し器で10分ほど蒸す。
- 粗熱が取れたら柏の葉で包んで完成。
このレシピなら、子どもと一緒に作ることもでき、家族みんなで楽しめます。
まとめ
端午の節句は、男の子の成長を願う大切な行事です。柏餅やちまきだけでなく、旬の食材を取り入れた料理を楽しむことで、食卓がより華やかになります。現代のライフスタイルに合わせてアレンジしながら、伝統を大切にしていきたいですね。
スポンサーリンク
八十八夜と新茶|お茶と共に味わう5月の味覚
八十八夜とは?お茶と農業の関係
八十八夜(はちじゅうはちや)とは、立春(2月4日頃)から数えて88日目にあたる日で、毎年5月2日頃に迎えます。この時期は春から初夏へと季節が移り変わる大切な節目であり、農業にとっても重要な時期とされています。日本では古くから「八十八夜の別れ霜」と言われ、この日を過ぎると遅霜(晩霜)が少なくなり、農作業が本格的に始まる目安とされてきました。
特にお茶の産地では、八十八夜に摘まれた「新茶」が特別なものとされます。新茶は、その年の最初に収穫された若葉を使用したお茶で、香りがよく、渋みが少なく甘みのある味わいが特徴です。「八十八」という漢字には「米」という文字が含まれていることから、八十八夜は豊作を願う日ともされています。
また、新茶には生命力が宿ると考えられ、「八十八夜の新茶を飲むと長生きできる」という言い伝えがあります。これは、新茶に含まれるビタミンCやカテキン、アミノ酸が健康に良いとされていることにも関係しているのかもしれません。
現代では、八十八夜に合わせて各地の茶畑で新茶の収穫が行われ、茶道具店やスーパーでも「新茶」のシールが貼られた商品が並びます。この時期にしか味わえない特別なお茶を楽しみながら、季節の移り変わりを感じてみましょう。
新茶の特徴とおいしい飲み方
新茶は、その年の最初に収穫された茶葉を使ったフレッシュな味わいが特徴です。一般的な煎茶に比べて、香りが爽やかで渋みが少なく、まろやかな甘みが感じられます。特に、収穫されたばかりの新茶には、テアニンというアミノ酸が多く含まれており、これが新茶特有の旨味や甘みのもとになっています。
新茶のおいしさを最大限に引き出すためには、正しい淹れ方が重要です。
新茶の美味しい淹れ方
材料(1杯分)
- 新茶の茶葉:3g(小さじ1杯程度)
- お湯(70~80℃):150ml
手順
- お湯を沸かして70~80℃まで冷ます
- 高温のお湯を使うと、渋みが強くなりすぎるため、少し冷ましてから使用します。
- 急須に新茶の葉を入れる
- 茶葉は適量(約3g)を急須に入れます。
- お湯を注いで60秒ほど待つ
- 抽出時間は長すぎると渋みが出るため、1分ほどが適切です。
- 最後の一滴まで注ぐ
- お茶の成分は最後の一滴に凝縮されているため、しっかりと注ぎきります。
こうして丁寧に淹れた新茶は、爽やかな香りと甘みが際立ち、5月ならではの味わいを楽しめます。
八十八夜におすすめのお茶菓子
新茶と一緒に楽しみたいのが、和菓子や軽食です。特に、八十八夜の時期に旬を迎える食材を使ったお茶菓子は、新茶の風味を引き立ててくれます。
- 抹茶わらび餅:ひんやりとした口当たりが新茶と相性抜群。
- そら豆の甘納豆:5月が旬のそら豆を使った優しい甘みのお菓子。
- 柏餅:端午の節句と同じ時期なので、柏餅を新茶と一緒に味わうのもおすすめ。
- どら焼き:しっとりとした生地とあんこの甘みが、新茶の爽やかさとよく合う。
- 緑茶プリン:新茶の風味を活かしたスイーツとして人気。
これらのお茶菓子を用意し、家族や友人と一緒に新茶を楽しむことで、より豊かな時間を過ごせます。
お茶と相性の良い行事食レシピ
八十八夜の新茶と一緒に楽しめる料理として、和風の軽食や旬の食材を活かしたメニューがおすすめです。
新茶と一緒に楽しむ簡単おにぎり
材料(2人分)
- ご飯:2膳分
- 塩:少々
- たけのこ(細かく刻む):50g
- ちりめんじゃこ:大さじ1
- 白ごま:少々
作り方
- 炊きたてのご飯に塩を混ぜる。
- たけのこ、ちりめんじゃこ、白ごまを加え、よく混ぜる。
- おにぎりの形に握る。
- お皿に盛り、新茶と一緒に楽しむ。
新茶のさっぱりとした風味と、旬のたけのこやちりめんじゃこの旨味が絶妙にマッチします。
お茶文化を楽しむためのイベント紹介
新茶の季節に合わせて、全国各地で「新茶まつり」や「茶摘み体験イベント」が開催されます。代表的なイベントをいくつか紹介します。
| 地域 | イベント名 | 内容 |
|---|---|---|
| 静岡県 | 静岡新茶まつり | 新茶の試飲や茶摘み体験が楽しめる |
| 京都府 | 宇治新茶祭 | 宇治茶の新茶を味わうイベント |
| 鹿児島県 | 知覧新茶フェスティバル | 知覧茶の試飲・販売、茶摘み体験ができる |
これらのイベントでは、実際に茶葉を摘んだり、茶農家の話を聞いたりすることができ、日本のお茶文化を深く知ることができます。
まとめ
八十八夜は、日本の農業や食文化にとって重要な日であり、新茶を楽しむ絶好の機会です。新茶は香り高く、栄養価も豊富で、古くから「飲むと長生きできる」と言われています。
新茶と一緒に旬の和菓子や軽食を楽しむことで、5月の風物詩をより深く味わえます。また、新茶まつりや茶摘み体験などのイベントに参加することで、日本の伝統文化に触れることができるでしょう。
今年の八十八夜には、ぜひ新茶を淹れて、季節の味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか?
スポンサーリンク
母の日の特別な食事|感謝を伝える手作りメニュー
母の日に食べる定番料理とは?
母の日は毎年5月の第2日曜日に祝われる特別な日で、お母さんに感謝の気持ちを伝えるためのイベントです。日本ではカーネーションを贈る習慣がありますが、それと同時に「特別な食事」を用意する家庭も多くあります。
母の日に食べる定番料理には、以下のようなものがあります。
- オムライス:ケチャップで「ありがとう」と書くことで、気持ちを伝えやすい。
- ハンバーグ:家族みんなが大好きな料理で、お祝いの席にもぴったり。
- ちらし寿司:見た目が華やかで、お祝いにふさわしい。
- ローストビーフ:特別感があり、豪華な食卓を演出できる。
- フルーツタルトやケーキ:デザートとして、母の日を彩る定番スイーツ。
和食、洋食、スイーツまで幅広い選択肢があるため、お母さんの好みに合わせて選ぶのがポイントです。手作りすることで、より感謝の気持ちが伝わる特別な食卓になります。
母の日におすすめの和食・洋食メニュー
母の日にぴったりな和食・洋食のメニューを紹介します。
和食メニュー
- ちらし寿司:酢飯に色とりどりの具材を乗せて華やかに。
- 茶碗蒸し:優しい味わいで、食べやすい。
- 煮魚(鯛の煮付け):お祝いの席にぴったりな高級感のある一品。
- 味噌汁(赤だし):出汁のきいた味噌汁でホッとするひとときを。
- だし巻き卵:ふんわりとした卵焼きは、どんな食事にも合う。
洋食メニュー
- ローストチキン:オーブンで焼くだけで華やかなメイン料理に。
- エビグラタン:とろりとしたホワイトソースが人気。
- パスタ(トマト・クリーム・和風):簡単なのにおしゃれな一品。
- サラダプレート:カラフルな野菜を盛り合わせ、特別感を演出。
- バゲットとチーズの盛り合わせ:ワインに合うおつまみとしてもおすすめ。
お母さんの好みに合わせて、和食と洋食を組み合わせるのも素敵なアイデアです。
感謝を込めたスイーツ作りのポイント
母の日に手作りスイーツを用意するのも、特別感を演出する素敵な方法です。スイーツ作りのポイントは、「簡単に作れて見た目が華やかであること」。以下のスイーツは初心者でも簡単に作れるのでおすすめです。
おすすめスイーツ
- カーネーション風カップケーキ:ピンクのクリームを絞ってカーネーションの花を表現。
- いちごのショートケーキ:お祝いの定番スイーツで、見た目も華やか。
- ティラミス:材料を混ぜて冷やすだけで作れる簡単スイーツ。
- チーズケーキ:焼くタイプと冷やすタイプがあり、好みに合わせて選べる。
- 手作りクッキー:アイシングで「ありがとう」のメッセージを書いてプレゼントに。
特に、クッキーやカップケーキは子どもと一緒に作れるため、家族みんなで楽しむことができます。
母の日の食卓を華やかにする盛り付けアイデア
料理の味はもちろんですが、見た目も華やかにすると特別感が増します。母の日の食卓をより魅力的にするための盛り付けアイデアを紹介します。
- カラフルな食材を使う:トマトやパプリカ、いちごなど色鮮やかな食材を取り入れる。
- ハート型を活用する:オムライスやサラダをハート型に盛り付ける。
- お皿を白やピンクで統一:女性らしい色合いの食器を使うと、おしゃれな雰囲気に。
- カーネーションやリボンを添える:テーブルコーディネートのアクセントとして活用。
- プレートにメッセージを書く:ケチャップやチョコペンで「ありがとう」を描く。
こうした工夫をすることで、料理がより特別なものになり、お母さんにも喜んでもらえるでしょう。
家族みんなで楽しめる母の日の食事会プラン
母の日をより特別な時間にするために、家族で楽しめる食事会のプランを考えてみましょう。
1日のスケジュール例
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:00 | 買い物&料理の準備 |
| 12:00 | 母の日ランチ(和食or洋食メニュー) |
| 14:00 | みんなでスイーツ作り |
| 16:00 | お茶タイム&プレゼント贈呈 |
| 18:00 | 軽めのディナー(パスタやサラダなど) |
| 20:00 | 家族団らん&写真撮影 |
ポイントは、お母さんにできるだけ家事をさせず、家族が協力して料理や準備をすることです。食事を楽しんだ後は、お母さんにプレゼントを渡したり、思い出に残る写真を撮ったりするのも良いアイデアです。
まとめ
母の日は、感謝の気持ちを料理やスイーツに込めて伝える絶好の機会です。定番のオムライスやハンバーグ、ちらし寿司などを作ったり、手作りスイーツで特別感を演出したりすることで、お母さんに喜んでもらえるでしょう。
また、料理だけでなく、食卓の盛り付けや家族みんなでの食事会プランを工夫することで、より思い出に残る1日になります。今年の母の日は、手作りの料理と心のこもったひとときで、お母さんに「ありがとう」を伝えてみませんか?
スポンサーリンク
5月の旬の食材を使った行事食レシピ
5月に美味しい旬の食材一覧
5月は春から初夏へと移り変わる季節で、野菜や魚介類が豊富に旬を迎えます。旬の食材は栄養価が高く、味も格別なので、行事食に取り入れることで季節を感じることができます。
5月が旬の主な食材
| 食材カテゴリ | 旬の食材 | 特徴・おすすめの食べ方 |
|---|---|---|
| 野菜 | たけのこ | 柔らかく甘みがあり、煮物や炊き込みご飯に最適 |
| そら豆 | ほくほくとした食感が特徴で、塩茹でやかき揚げに | |
| 新じゃがいも | 皮が薄く甘みが強い。シンプルに蒸してバターと合わせるのがおすすめ | |
| アスパラガス | 歯ごたえがあり、グリルや炒め物、パスタにぴったり | |
| 新玉ねぎ | 水分が多く甘みが強いので、スライスしてサラダやスープに | |
| 魚介類 | 初ガツオ | さっぱりとした味わいで、たたきや刺身で楽しめる |
| 真鯛 | 旨味が豊富で、お祝い料理としてもよく使われる | |
| ホタルイカ | プリッとした食感が特徴で、酢味噌和えやパスタに | |
| 果物 | いちご | 甘酸っぱく、デザートやサラダに最適 |
| メロン | みずみずしい甘さが特徴で、そのまま食べるのがおすすめ | |
| 夏みかん | さっぱりとした酸味があり、ジュースやサラダにも使える |
これらの旬の食材を使うことで、5月ならではの味覚を存分に楽しむことができます。
季節の野菜を活かした伝統料理レシピ
たけのこご飯(4人分)
材料
- 米 … 2合
- たけのこ(茹でたもの) … 150g
- 油揚げ … 1枚
- だし汁 … 400ml
- 醤油 … 大さじ2
- みりん … 大さじ1
- 酒 … 大さじ1
作り方
- たけのこは薄切り、油揚げは細切りにする。
- 炊飯器に米を入れ、だし汁、醤油、みりん、酒を加えて軽く混ぜる。
- たけのこと油揚げをのせて炊飯する。
- 炊き上がったら10分ほど蒸らし、全体を混ぜて器に盛る。
たけのこの風味とだしの旨味が染み込んだ、春らしい炊き込みご飯です。
魚介類を使った5月のごちそうメニュー
初ガツオのたたき(2人分)
材料
- 初ガツオ(柵) … 200g
- にんにく … 1片
- しょうが … 1片
- 大葉 … 3枚
- 玉ねぎ(スライス) … 1/4個
- ポン酢 … 大さじ3
作り方
- フライパンを強火で熱し、ガツオの表面をさっと焼く(30秒程度)。
- 氷水にくぐらせて冷やし、水気を拭き取る。
- 厚めに切り、お皿に盛る。
- スライスした玉ねぎ、大葉、にんにく、しょうがをのせる。
- ポン酢をかけて完成。
香ばしく炙った初ガツオに薬味をたっぷりのせて、爽やかに楽しめる一品です。
5月の行事食にぴったりな汁物・副菜
そら豆と新玉ねぎの味噌汁(2人分)
材料
- そら豆(茹でて皮をむく) … 50g
- 新玉ねぎ(スライス) … 1/4個
- だし汁 … 400ml
- 味噌 … 大さじ2
作り方
- だし汁を火にかけ、新玉ねぎを入れて煮る。
- 柔らかくなったらそら豆を加え、味噌を溶き入れる。
- 器に盛り、お好みで七味唐辛子をふって完成。
新玉ねぎの甘みとそら豆のコクが感じられる、春らしい味噌汁です。
デザートで季節を感じる!5月の和菓子レシピ
いちご大福(4個分)
材料
- いちご … 4粒
- こしあん … 100g
- 白玉粉 … 100g
- 砂糖 … 30g
- 水 … 80ml
- 片栗粉(打ち粉用) … 適量
作り方
- いちごは洗ってヘタを取り、こしあんで包む。
- 白玉粉、砂糖、水を耐熱ボウルに入れて混ぜ、電子レンジ(600W)で1分加熱する。
- 取り出してよく混ぜ、さらに1分加熱。
- 片栗粉を敷いたバットに生地を移し、4等分する。
- 手に片栗粉をつけ、いちごを包むように丸めて完成。
手作りならではの柔らかい食感と甘酸っぱい苺の組み合わせが絶品です。
まとめ
5月は野菜や魚介類が豊富に旬を迎える時期です。行事食に取り入れることで、季節感を味わいながら栄養もしっかり摂ることができます。
特に、端午の節句や八十八夜、母の日などのイベントでは、伝統的な食材を使った料理を楽しむことで、家族の会話も弾みます。今回紹介したレシピを参考に、5月ならではの味覚を満喫してみてください。