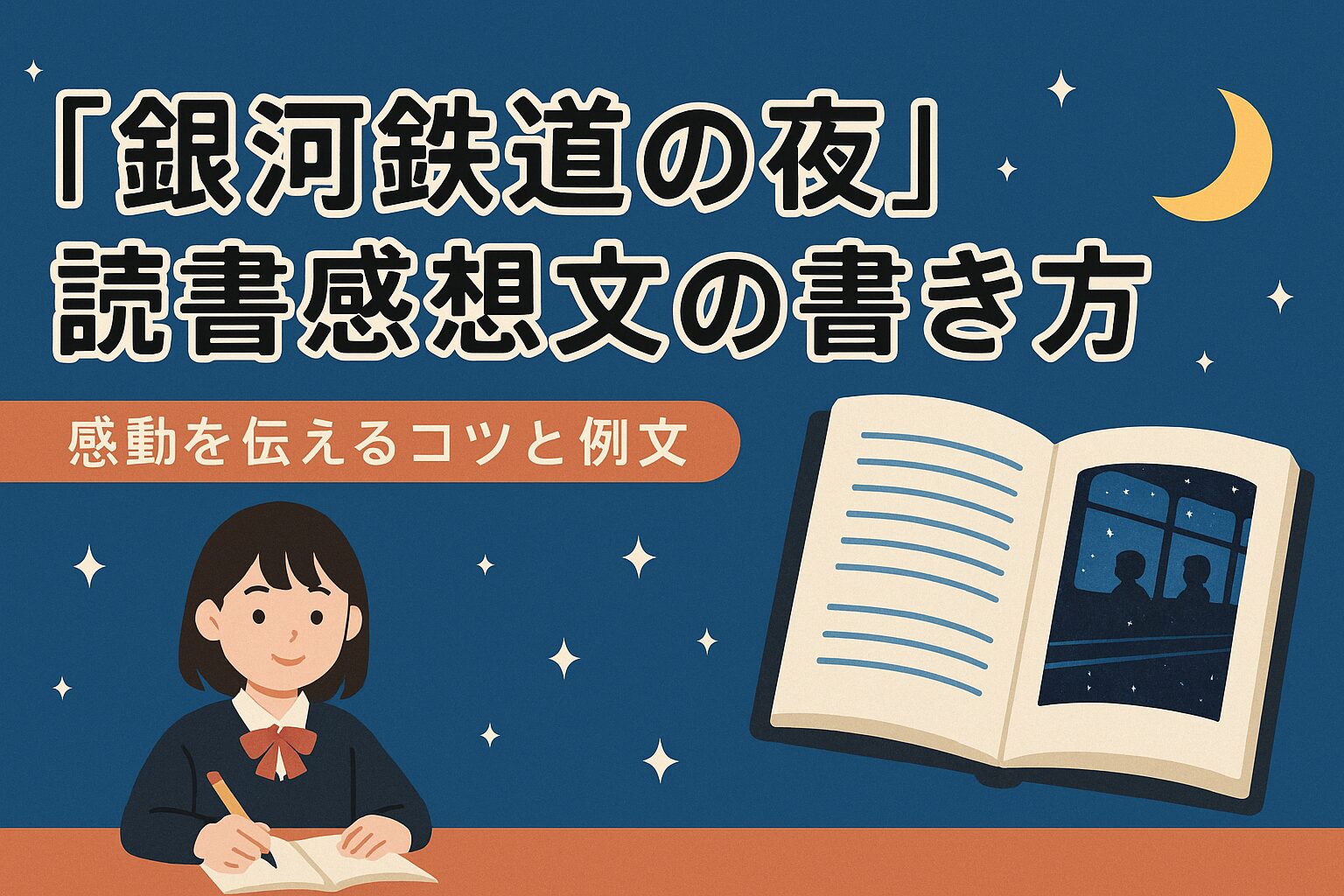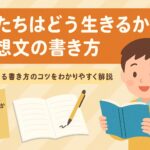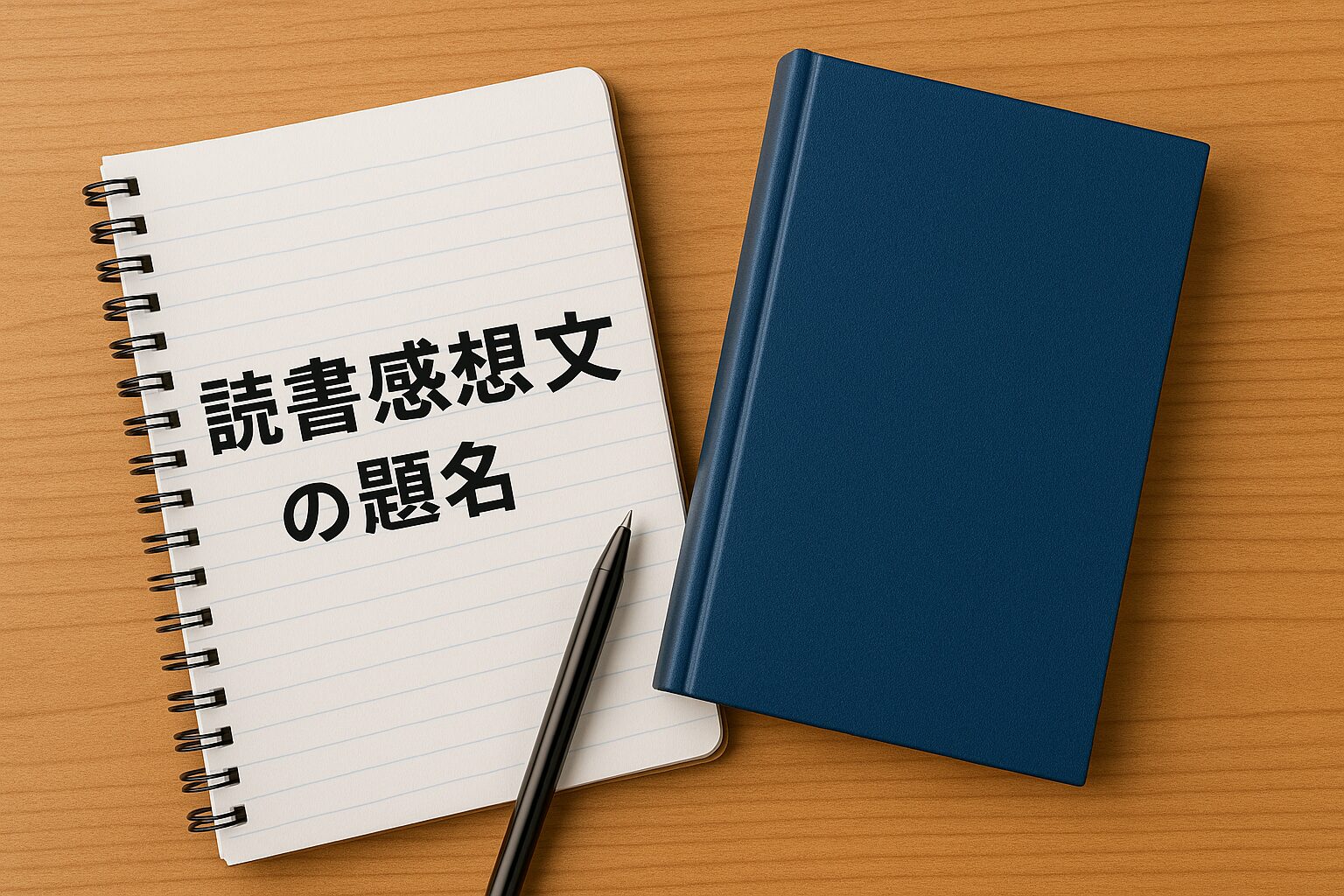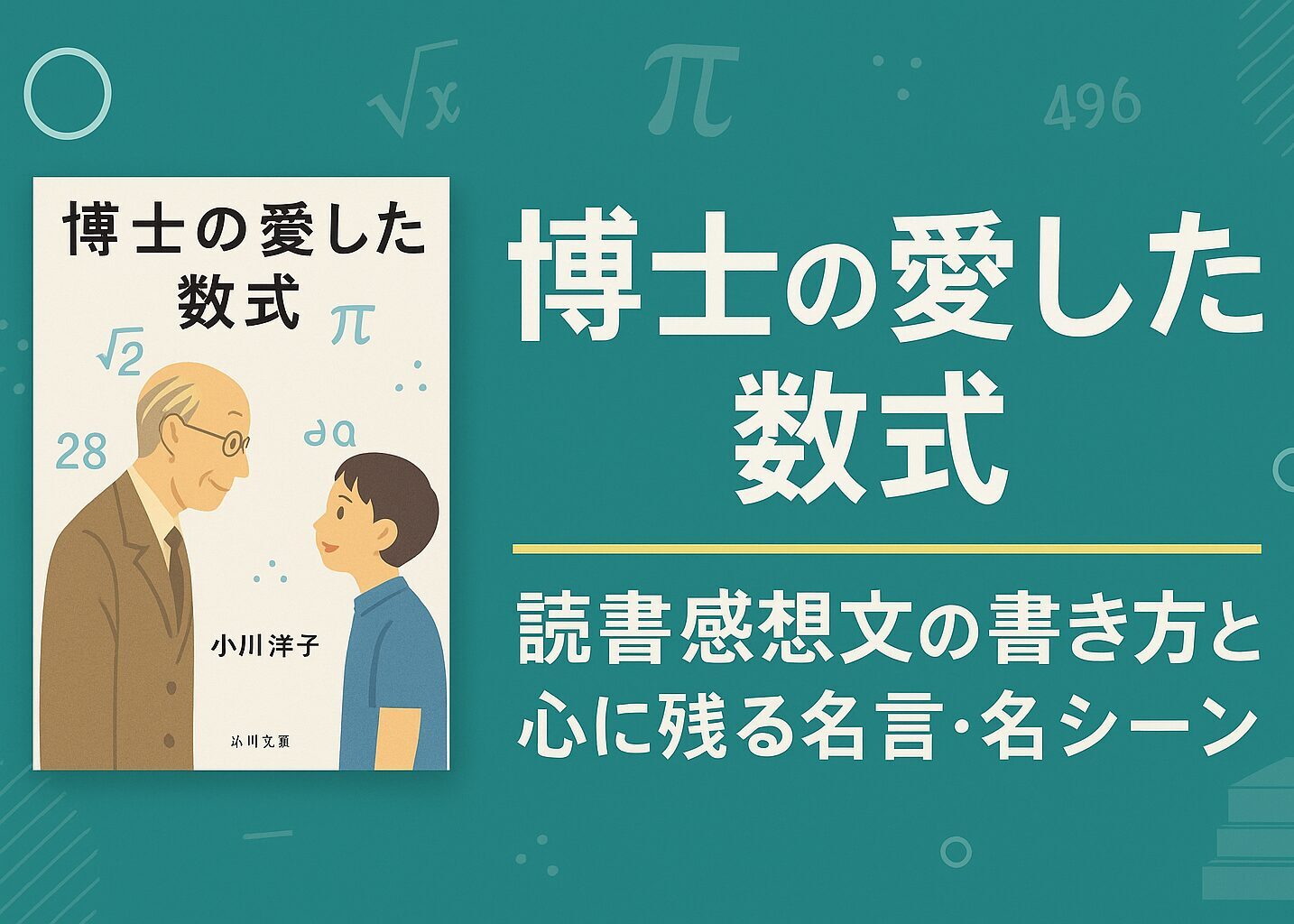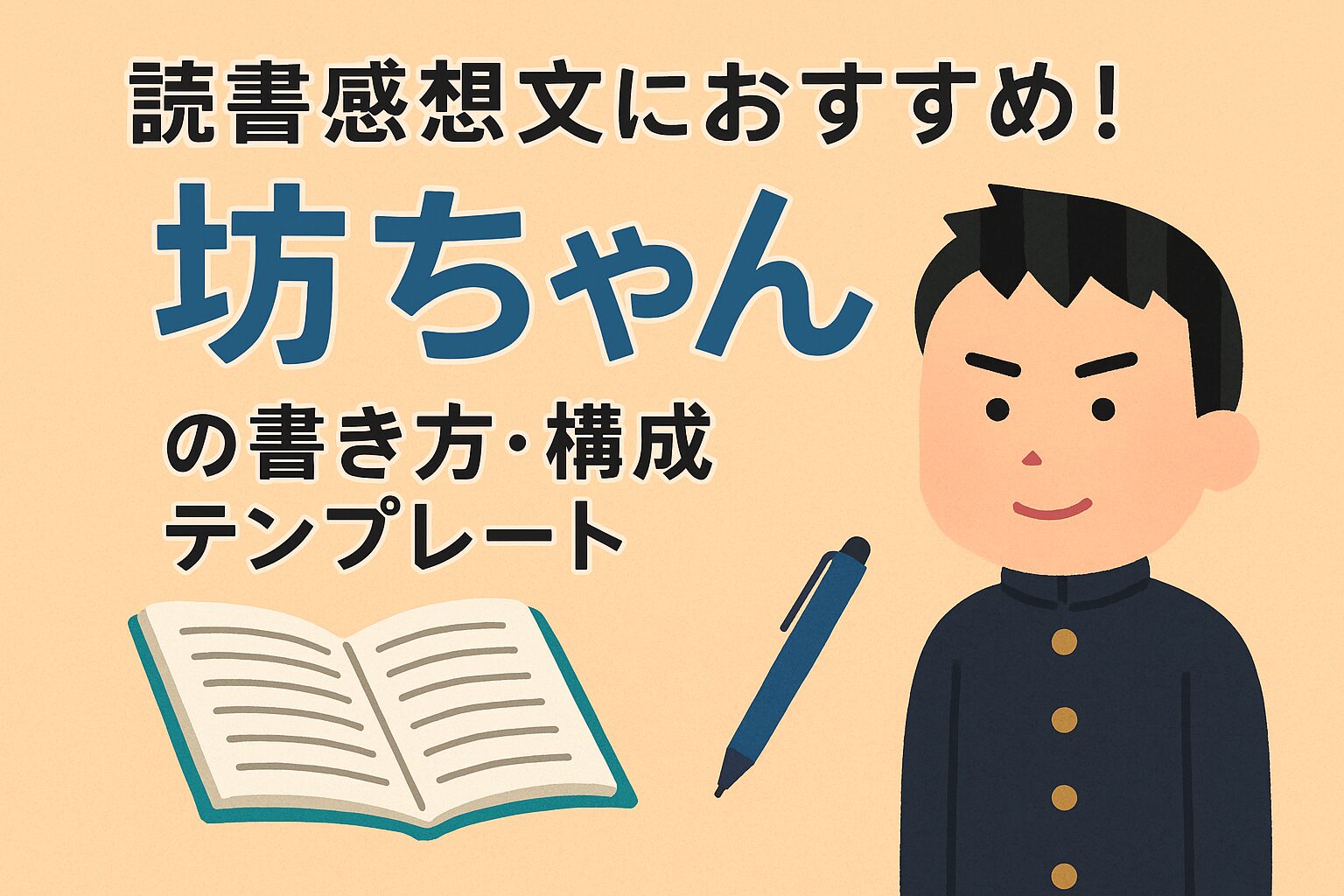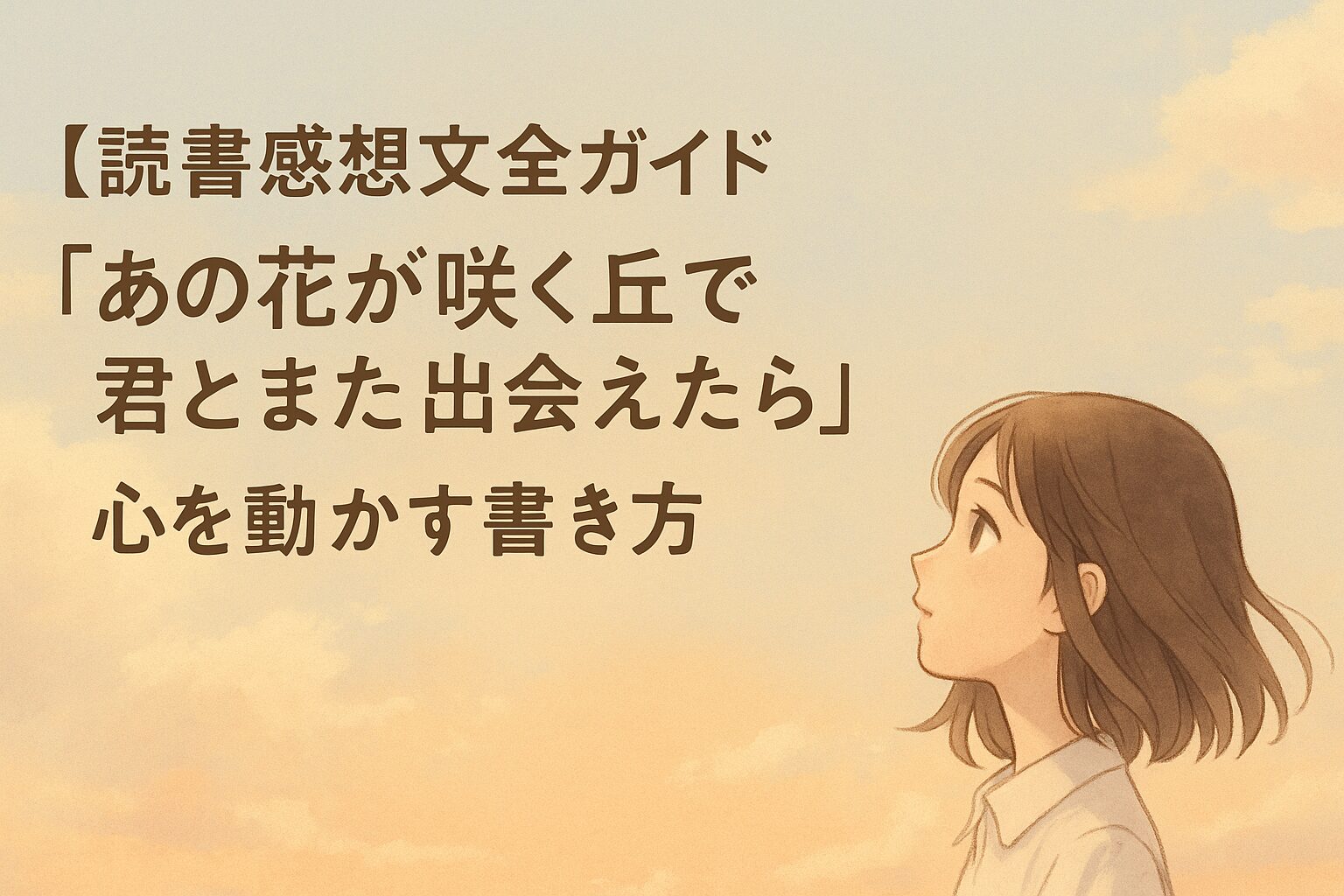「読書感想文、どう書けばいいの?」と悩んでいませんか?特に名作「銀河鉄道の夜」は、幻想的な世界観と深いテーマで、多くの読者の心をつかんで離しません。
そこで本記事では、この作品の感動ポイントをわかりやすく紹介しながら、中学生でも書ける読書感想文の書き方を丁寧に解説します。
実際の感想文例やNG例、表現力アップのコツも紹介しているので、これを読めば自信をもって感想文に取り組めるようになります!
『銀河鉄道の夜』はこちらから購入する事が出来ます。
スポンサーリンク
「銀河鉄道の夜」の魅力を知ろう
宮沢賢治ってどんな人?
宮沢賢治は、岩手県出身の詩人・童話作家で、自然と宇宙、宗教や科学をテーマにした作品を多く残しています。代表作には「風の又三郎」「よだかの星」などがありますが、その中でも特に有名なのが「銀河鉄道の夜」です。彼の作品には共通して、人間の内面の葛藤や、命の尊さといったテーマが込められていて、読む人の心を深く揺さぶります。
賢治は生前あまり評価されていませんでしたが、没後にその独自の世界観が高く評価され、多くの人々に愛されるようになりました。「銀河鉄道の夜」も、未完の形ながら人々の想像力をかき立て、長年にわたり読み継がれています。宮沢賢治という人物を知ることで、彼がこの作品に込めた思いや背景を、より深く理解することができるでしょう。
幻想的な世界観の背景
「銀河鉄道の夜」は、少年ジョバンニが親友カンパネルラとともに、星空の中を走る銀河鉄道に乗って旅をする物語です。実はこれは、現実の出来事ではなく、ジョバンニの夢とも魂の旅とも解釈できる不思議な体験です。物語の中では、天の川が鉄道になり、様々な乗客が登場します。その一人ひとりが人生や死に関わる何かを象徴していて、読む人にいろんなことを考えさせます。
特に印象的なのは、光り輝く星空や神秘的な風景の描写です。まるで宇宙の中を旅しているかのような気持ちにさせてくれます。宮沢賢治は理科が得意だったこともあり、天文学的な表現や用語も多く使われていますが、それが作品の幻想的な雰囲気をより引き立てています。
ジョバンニとカンパネルラの友情
物語の中心にあるのは、ジョバンニとカンパネルラという二人の少年の関係です。ジョバンニは貧しく、学校でも孤立しがちですが、カンパネルラはそんな彼を理解して寄り添ってくれる数少ない友達です。二人の間には深い信頼があり、互いに思いやる気持ちが強く感じられます。
銀河鉄道の旅の中で、二人はいくつもの出会いと別れを経験します。そして最後には、カンパネルラが列車を降りて、ジョバンニの前から姿を消します。ここで読者は、カンパネルラが現実世界で亡くなったことに気づき、ジョバンニが見た旅は、その死を受け入れるための心の旅だったのだとわかります。
この友情の描かれ方はとても感動的で、誰にでもある「大切な人を失うつらさ」と向き合うきっかけを与えてくれます。
「本当の幸せ」とは?作品のテーマ
「銀河鉄道の夜」には、はっきりとしたストーリーの結末がない代わりに、大きなテーマが描かれています。それが「本当の幸せとは何か?」という問いです。作中では、他人のために自分を犠牲にすることや、誰かを助けることが「ほんとうの幸福」だと語られています。
これは、自己中心的ではなく、他者のために生きることの大切さを教えてくれているのです。また、死をテーマにしながらも、悲しみだけでなくその先にある光や救いが感じられるように描かれていて、とても前向きな気持ちになれます。
この「幸せ」の意味を考えることで、自分の生き方や人との関わり方についても深く考えるきっかけになります。
読後に感じた心の余韻
「銀河鉄道の夜」を読み終わったあと、多くの人が感じるのは「静かな感動」です。派手な出来事が起こるわけではありませんが、心の奥にじんわりと染み込んでくるような印象を残します。特に、ジョバンニがひとりで夜の道を歩くラストシーンは、切なさと同時に希望も感じさせてくれる不思議な余韻があります。
読書感想文では、この「心の余韻」を自分の言葉で表現することがとても大切です。読んで感じたこと、思い出した出来事、自分の価値観の変化などを素直に書くことで、共感を呼ぶ感想文になります。
スポンサーリンク
読書感想文の書き方ポイント
まずは要約から始めよう
読書感想文を書くときは、いきなり感想を書くのではなく、まず物語のあらすじを簡単にまとめるところから始めましょう。読む人がその本を知らなくても内容がわかるように、話の流れを短く説明することが大事です。
ただし、長すぎる要約は避け、主人公がどんな人物で、どんな出来事があり、どんな結末を迎えるのかを、3〜5行程度にコンパクトに書くのがコツです。また、自分がどんな気持ちで読み始めたのか(例:課題だから読んだ、本のタイトルに興味があったなど)も一緒に書くと、文章に親しみが出ます。
感想文は「読む人に伝える文章」なので、まずは物語の土台をわかりやすく示して、感想につなげる流れを作ることが大切です。
心に残った場面を具体的に
読書感想文で一番大切なのは、「どこが心に残ったか」をはっきりさせることです。特に「銀河鉄道の夜」のような物語では、場面ごとの印象がとても大切になります。たとえば、ジョバンニとカンパネルラが車窓から美しい星空を眺める場面や、サソリの火の話が出てくる場面などは、読者の心に深く残ります。
自分が感動したシーンや、考えさせられたセリフがあれば、その場面を思い出して、できるだけ具体的に書いてみましょう。「夜の静けさが伝わってきた」「星が本当にきらめいているように感じた」「ジョバンニの孤独が胸に迫った」など、自分の五感で感じたように表現すると、文章にリアリティが生まれます。
また、その場面でなぜ心が動いたのか、自分の中のどんな思いや経験と重なったのかも一緒に書くことで、より深い感想文になります。感動した場面を「自分の心の中で再生するように」描いてみることが、読み手に響く文章のコツです。
自分の体験と重ねてみよう
感想文を読んだ人に「共感される」文章にするためには、自分の体験や日常の出来事と重ねることがとても効果的です。「銀河鉄道の夜」では、友情、孤独、家族、死といったテーマが出てくるため、誰にでもつながりを感じられる部分があるはずです。
たとえば、ジョバンニの孤独に共感したなら、自分が一人でいた時の気持ちや、友達に助けられた経験を書いてみましょう。また、誰かを思って涙を流したこと、言えなかった「ありがとう」や「ごめんね」があった時のことを思い出してみるのもよいです。
このように、「自分の物語」を少しだけ感想文に加えることで、その作品との距離がぐっと近づきます。単なる本の感想から、「自分の人生をふりかえる文章」になるのです。それこそが、感想文の本当の価値でもあります。
「問いかけ」で深い感想に
読書感想文で深みを出すためには、「問いかけ」をうまく使うのがおすすめです。たとえば、「カンパネルラはなぜジョバンニと一緒に旅をしたのか?」「本当の幸せとは何だろう?」といった、自分なりの疑問を文章に入れてみましょう。
問いかけることで、ただ「感動した」では終わらない、考えのある文章になります。また、読んでいる人にも「自分だったらどう感じるだろう?」と考えるきっかけを与えることができます。
もちろん、答えが出なくても大丈夫です。大切なのは「考えようとしたこと」そのものです。「自分はこう思うけれど、他の人はどうだろう?」といった視点を加えると、さらに文章が奥深くなります。読書は、ただ読むだけでなく、自分の価値観を広げてくれる行為でもあるので、問いかけはその大事なステップになります。
結論で伝えたい思いをまとめる
感想文の最後は、これまで書いてきたことをふり返って、自分の気持ちをまとめる部分です。ここでは、「この本を読んでどんなことを感じ、どんなことを学んだのか」を、自分の言葉でストレートに書きましょう。
たとえば、「本当の幸せとは、自分のためだけでなく誰かのために行動することだと思った」「悲しいけれど、命の重みについて考えるきっかけになった」など、読後の気づきや変化を素直に書くことが大切です。
また、「これからは、周りの人にもっと優しくしたいと思った」「友達を大切にしたいと改めて思った」といった、行動につながるような感想もよいでしょう。読み終えたあとにどんな行動や考えが芽生えたかを書くと、読書体験がより生きたものになります。
最後に、「この本に出会えてよかった」というような気持ちを添えると、読者にも気持ちが伝わりやすくなります。
スポンサーリンク
実際の感想文例(中学生向け)
導入文:なぜこの本を選んだか
私が「銀河鉄道の夜」を読もうと思ったきっかけは、国語の授業で先生がこの本を紹介してくれたからです。「星空を走る鉄道」という言葉にロマンを感じたのと、宮沢賢治という名前を何度も聞いたことがあったので、どんな話か気になって読み始めました。
正直に言うと、最初は難しそうなイメージがあって、自分に読めるか不安でした。でも、読み進めるうちに、不思議な世界にどんどん引き込まれていきました。言葉は少し古かったけれど、ジョバンニの心の動きや、空に広がる幻想的な風景が目に浮かんでくるようで、とても印象的でした。
この本を選んだのは偶然でしたが、読んでみて「これはただの物語じゃない」と感じました。自分の人生や、人との関わりについて深く考えさせられる内容で、読み終わったあともずっと心に残る作品でした。
展開:心に残った場面の紹介
「銀河鉄道の夜」の中で、特に心に残ったのは「サソリの火」の話です。サソリは、自分の命を守るために逃げたことで他の命を犠牲にしてしまい、「今度生まれたら、ほんとうに自分の体をみんなの幸せのために使おう」と願う場面があります。ジョバンニとカンパネルラがそれを聞く場面は、とても静かで、でも心に強く響く印象的なシーンでした。
この話を読んだとき、私は「自分の幸せだけを考えるのではなく、誰かのために何かできることが本当の幸せなのかもしれない」と思いました。サソリの思いは、カンパネルラの行動にもつながっているように感じました。
この場面を通して、自分の行動が人にどう影響するのか、そして「人のために生きる」ということの意味について深く考えました。美しいけれど切ないシーンで、読んでいて自然と胸が熱くなりました。
感想:感じたことと考えたこと
物語を読み終わったあと、私はしばらく言葉が出ませんでした。特にカンパネルラが列車を降りた場面では、胸がしめつけられるような気持ちになりました。ジョバンニは最後までカンパネルラを探し続けますが、その姿から強い友情と、別れの悲しさが伝わってきました。
この物語は、死という重いテーマを扱っているのに、読んだあとに不思議とあたたかい気持ちになります。悲しいのに、どこか希望があるような、そんな不思議な読後感です。ジョバンニが一人で歩いて帰る最後の場面も、まるで夜空の中を歩いているようで、「彼はきっと少しだけ大人になったのだろうな」と感じました。
この本は、読む人それぞれの人生のタイミングによって、感じ方が変わる作品だと思います。私はこのときこの本に出会えて本当に良かったと思いました。
自分と照らし合わせた考察
私は以前、大切な祖父を亡くしたことがあります。そのとき、なぜ人は死ぬのか、どこへ行くのかという疑問が心から消えませんでした。「銀河鉄道の夜」を読んで、カンパネルラが列車を降りる場面に祖父の姿を重ねてしまいました。
もしあの列車が天国に向かっているとしたら、祖父もあんなふうに静かに旅立っていったのかな、と想像しました。そして、ジョバンニのように、私は今も祖父のことを思いながら、少しずつ日常を歩いているのだと思います。
この本を読んで、死は終わりではなく、「旅立ち」なのかもしれないと感じました。悲しみはすぐには消えないけれど、そこに意味や希望を見いだすことはできる。そんな気づきが、この物語から得られました。
結び:この本を読んで学んだこと
「銀河鉄道の夜」は、単なるファンタジーの物語ではありませんでした。そこには、人の心、命の意味、そして本当の幸せとは何かという、大切なテーマが込められていました。ジョバンニの旅は、私たち一人ひとりが生きていく上で向き合わなければならないことと重なっています。
この本を読んで私は、もっと人に優しくなりたい、自分の行動が誰かの幸せにつながるようにありたいと思いました。そして、たとえ別れがあっても、大切な人との思い出はずっと心の中で生き続けるのだということも学びました。
中学生の私にとって、こんなに心に残る本に出会えたのは大きな経験です。これからも、たくさんの本を読んで、いろんなことを感じ、考えていきたいです。
スポンサーリンク
よくある読書感想文のNG例と改善法
あらすじばかり書いてしまう
読書感想文でやってしまいがちなのが、「あらすじばかりを書いてしまう」ことです。たとえば、「最初にジョバンニが学校から帰って…その後に銀河鉄道に乗って…」と、物語の流れを細かく説明して終わってしまうケースです。これでは、感想文というより「読書記録」になってしまいます。
感想文は「読んでどう感じたか」「何を考えたか」を伝える文章です。あらすじは最低限でOK。読者に物語の概要が伝わるように、短くまとめましょう。その代わり、感動した場面や考えさせられた出来事について、丁寧に自分の思いを語ることが大切です。
改善方法としては、最初にあらすじを3〜4行で簡潔にまとめ、その後に「私はこの場面でこう感じた」「この言葉が心に残った」といったふうに、感情や考えを中心に書くように意識しましょう。
感情が伝わらない文章
「感動した」「びっくりした」「考えさせられた」などの言葉は、感想文に登場しがちですが、それだけでは読み手には気持ちが伝わりません。「どうして感動したのか」「どんなふうにびっくりしたのか」まで、具体的に書くことがとても大切です。
感情を伝えるときには、できるだけ自分の言葉で説明しましょう。たとえば、「ジョバンニが一人で星空を歩く場面で、自分も夜空を見上げているような気持ちになり、胸がぎゅっとなった」といったように、自分の体験や感覚を交えて書くと臨場感が出ます。
改善のコツは、感情を「描写する」こと。気持ちを言葉だけでなく「映像」に変えて、読んでいる人にも伝わるようにするのがポイントです。
例え話がない単調な表現
単調な表現ばかりが続くと、読書感想文は読みにくく、印象にも残りません。「楽しかった」「よかった」「すごかった」だけでは、自分の感じたことを十分に表現できていないからです。
そんなときに効果的なのが、例え話や比喩を使うことです。たとえば、「この場面はまるで心の中に静かに雨が降っているようだった」や「カンパネルラの優しさは、あたたかい毛布のように感じた」など、五感や身近なものにたとえることで、読者にもイメージしやすくなります。
言葉に感情を込めるためには、少しの工夫が必要です。身近なものを使った例えは、文章に彩りを与え、読みやすくしてくれます。難しい言葉を使わなくても、自分なりのたとえで十分伝わるのです。
本の内容に触れていない
感想文で意外と見落としがちなのが、「本の内容にちゃんと触れていない」というパターンです。感想ばかりが並びすぎて、「この人、本当に読んだのかな?」と思われてしまう文章になることがあります。
感想を書くときには、必ず本の内容とつなげましょう。たとえば、「ジョバンニが牛乳を買いに行く場面で、貧しさや孤独を感じて胸が痛くなった」と、具体的な場面とセットにして書くのがコツです。そうすることで、感想にも説得力が生まれます。
改善のためには、印象に残ったセリフや出来事をピックアップし、その場面を自分の視点でふり返ることが大切です。「どこで、何が起こって、それをどう感じたか」という流れを意識すれば、内容と感想が自然につながります。
誤字脱字や語尾の乱れ
どんなに素晴らしい内容の感想文でも、誤字脱字や語尾がバラバラだと、読みにくくなってしまいます。「〜です」「〜ます」が途中で「〜だ」「〜である」になっていたり、「思いました」と「思う」の語尾が混ざっていると、読み手に違和感を与えてしまいます。
感想文を書いたあとには、必ず自分で読み返してみましょう。できれば声に出して読むと、言い回しや語尾のリズムがおかしいところに気づきやすくなります。もし時間があれば、家族や友達に読んでもらって意見を聞くのもおすすめです。
改善ポイントは「読みやすさを意識すること」。文章は読んでもらうものです。正しく、美しく、そして自分らしく伝えるためには、最後の見直しがとても重要です。
スポンサーリンク
書いた感想文をさらに良くするコツ
誰かに読んでもらってフィードバック
自分で書いた感想文をより良いものにするには、誰かに読んでもらうのがとても効果的です。親や友達、先生に見てもらうことで、「ここが分かりにくい」「この部分が良かった」といった客観的な意見をもらうことができます。
自分では「うまく書けた」と思っていても、読む人にとっては伝わりにくい表現になっていることもあります。逆に、「普通だな」と感じていた部分が、「感動した!」と言われることもあるかもしれません。
フィードバックをもらったら、素直に受け止めて改善してみましょう。感想文は「一発勝負」ではなく、何度も直しながら完成させるものです。他人の目を通すことで、新しい気づきが生まれ、文章がより読みやすく、伝わりやすくなります。
声に出して読んでみる
書き終わった感想文は、必ず声に出して読んでみましょう。目で読んでいると気づかない文章の違和感や、文の長さ、リズムの悪さに気づくことができます。たとえば、「この言い回しはくどいな」「語尾が続いていて読みにくいな」といったように、耳で聞くことで改善点が見えてきます。
声に出すことで、文の自然さもチェックできます。たとえば、「ジョバンニはすごくかわいそうで、すごく悲しかった」という文を声に出して読むと、「すごく」が重なっていて不自然だと気づけます。その場合は、「とてもかわいそうで、胸が締めつけられるようだった」など、違う表現にしてみましょう。
特に発表の場がある場合、読む練習にもなって一石二鳥です。感想文は「読む人に伝える」ものですから、自分の耳でもしっかり確認しましょう。
推敲で読みやすくしよう
文章を書いたあとにやるべき大切な作業が「推敲(すいこう)」です。推敲とは、文章を読み直して、より良い表現や構成に直すことです。一度で完璧な文章を書くのは難しいので、何度か読み返して手直しを重ねましょう。
推敲のときに注目するポイントは、「同じ言葉のくり返し」「長すぎる文章」「話の流れが飛んでいないか」などです。また、「でも」「そして」「だから」などの接続詞を使いすぎていないかも見直しましょう。読みやすくするためには、文のリズムも意識することが大切です。
段落ごとに意味が分かれているか、主語と述語が対応しているかなど、基本的な文法にも気をつけると、さらに良い文章になります。何度も読み返して、読んだ人に伝わるかどうかを考えながら仕上げましょう。
印象に残るタイトルの工夫
感想文にも「タイトル」をつけることがありますが、このタイトルも意外と大切です。印象に残るタイトルがあると、「どんな内容なんだろう?」と読み手の興味を引くことができます。
たとえば、単に「銀河鉄道の夜の感想」ではなく、「星のきらめきの中で感じた本当の幸せ」や「カンパネルラと旅した心の銀河」など、作品の印象的な要素や自分の感動を表現したタイトルにすると、個性が出て魅力的になります。
タイトルを考えるときは、本文の中で特に心に残った言葉やテーマを思い出して、それにちょっとした工夫を加えてみましょう。難しい言葉を使う必要はありません。自分らしい言葉で、感想の核を伝えるタイトルがベストです。
最後に「自分らしさ」を足そう
どんなにうまく文章が書けても、それが「自分らしい」ものでなければ意味がありません。読書感想文は、決して正解のある作文ではなく、自分の感じたことを、自分の言葉で表すことが大切です。
たとえば、「みんながこう書いているから自分も…」ではなく、「私はこう感じた」「私はこの場面が好きだった」と、自分だけの視点や経験を大切にしましょう。他の人と違っていてもいいのです。むしろ、その違いこそが個性であり、感想文の価値になります。
文章の最後や冒頭に、「私はこの本に出会って…」というように、自分自身の言葉でメッセージを込めると、より心のこもった感想文になります。最後のひと工夫として、ぜひ「自分らしさ」を加えてみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「銀河鉄道の夜」の読書感想文はどんな構成で書けばいいですか?
A. 一般的には「導入(本を選んだ理由)→あらすじの簡単な紹介→感動した場面→自分の感想や気づき→まとめ」という5段構成が基本です。感情と体験を具体的に書くことで、読み手に伝わる感想文になります。
Q2. 中学生でも理解できる内容ですか?
A. はい、宮沢賢治の独特な文体や表現はやや難しい部分もありますが、物語のテーマは「友情」「命」「幸せ」など、中学生でも深く共感できる内容です。読書感想文のテーマとしても非常におすすめです。
Q3. 感想文に名言やセリフを使ってもいいですか?
A. はい、印象的なセリフや場面を引用することで、感情や意見に説得力が増します。ただし、引用部分は短くし、出典を明確にして、その後に必ず自分の感想や解釈を書くようにしましょう。
Q4. 感想文に自分の体験を入れてもいいですか?
A. むしろ入れたほうが良いです。作品と自分の経験をつなげることで、オリジナリティが出て読みごたえのある感想文になります。たとえば「大切な人を失った経験」と物語を重ねるなどがおすすめです。
Q5. 「銀河鉄道の夜」の読書感想文で賞を取るには?
A. 感情を丁寧に書くだけでなく、「本当の幸せとは何か?」「死とは?」など、物語のテーマに自分なりの答えを見つけて言葉にすることがカギです。形式的にならず、素直な言葉で書くことも重要です。
まとめ
「銀河鉄道の夜」は、単なる空想の物語ではありません。ジョバンニとカンパネルラの銀河鉄道の旅は、生と死、友情、そして「ほんとうの幸せ」について深く問いかけてくれる、大人になっても心に残る名作です。この物語を通じて、読者は自分の人生や大切な人との関係を見つめ直す機会を得ることができます。
読書感想文を書くうえでは、あらすじの説明に偏らず、自分の感情や体験を具体的に書くことが大切です。そして、推敲や声読み、他人の意見を取り入れることで、さらに深みのある文章に仕上げることができます。感想文とは、「本を読んで自分がどう変わったか」を伝える作文です。この記事で紹介したコツを活かして、あなたらしい感想文を書いてみてください。
読書感想文にピッタリな『銀河鉄道の夜』はこちらから購入する事が出来ます。