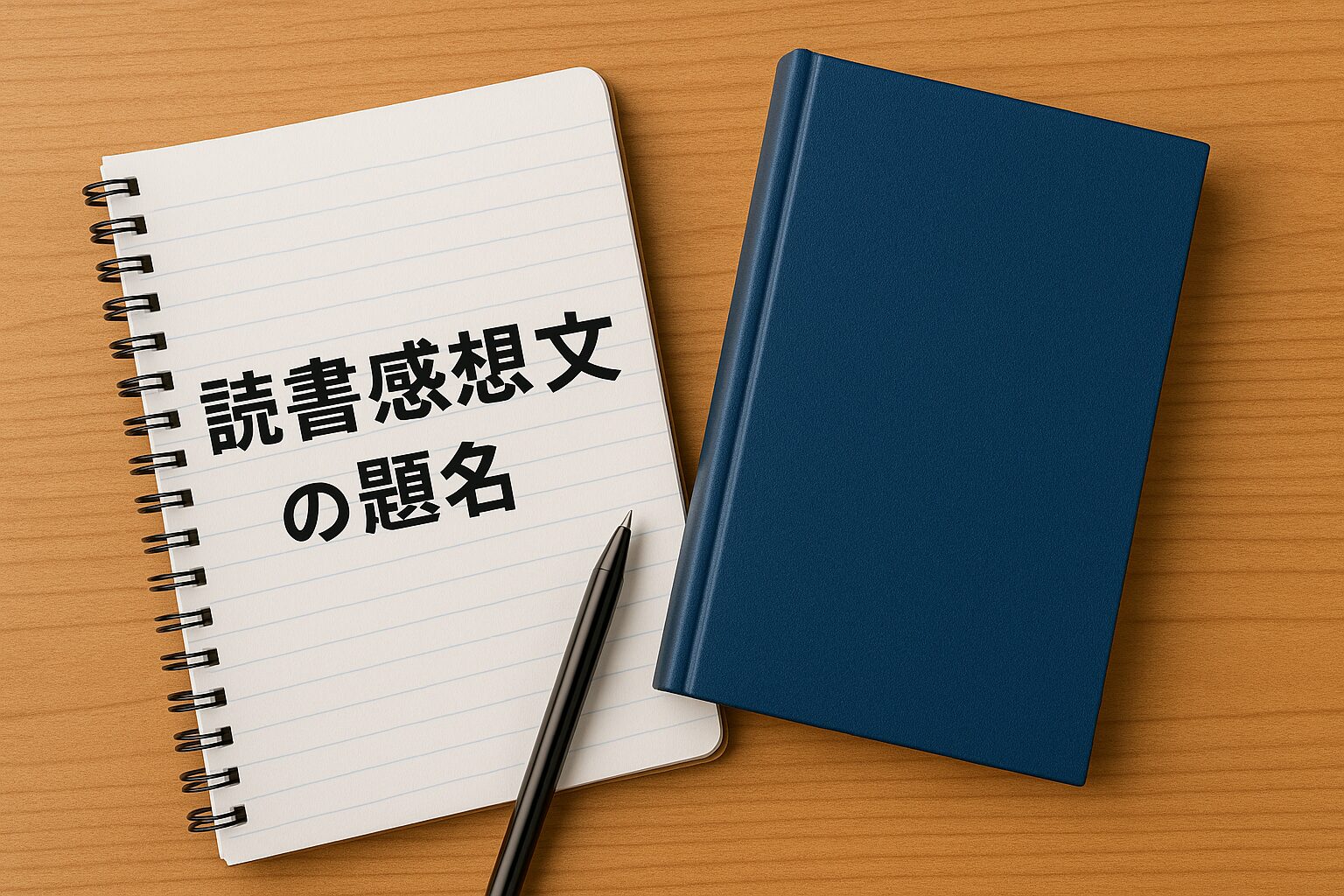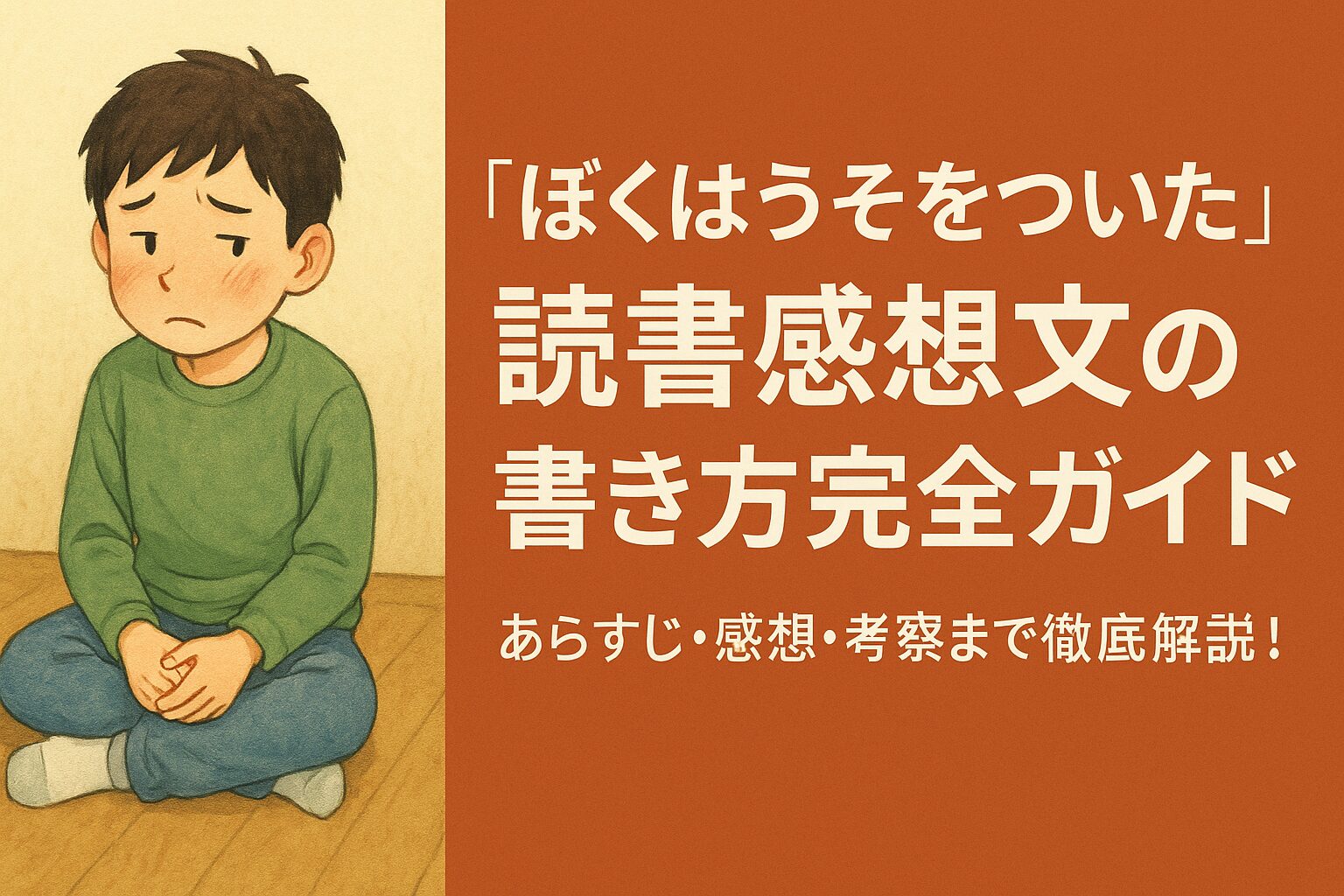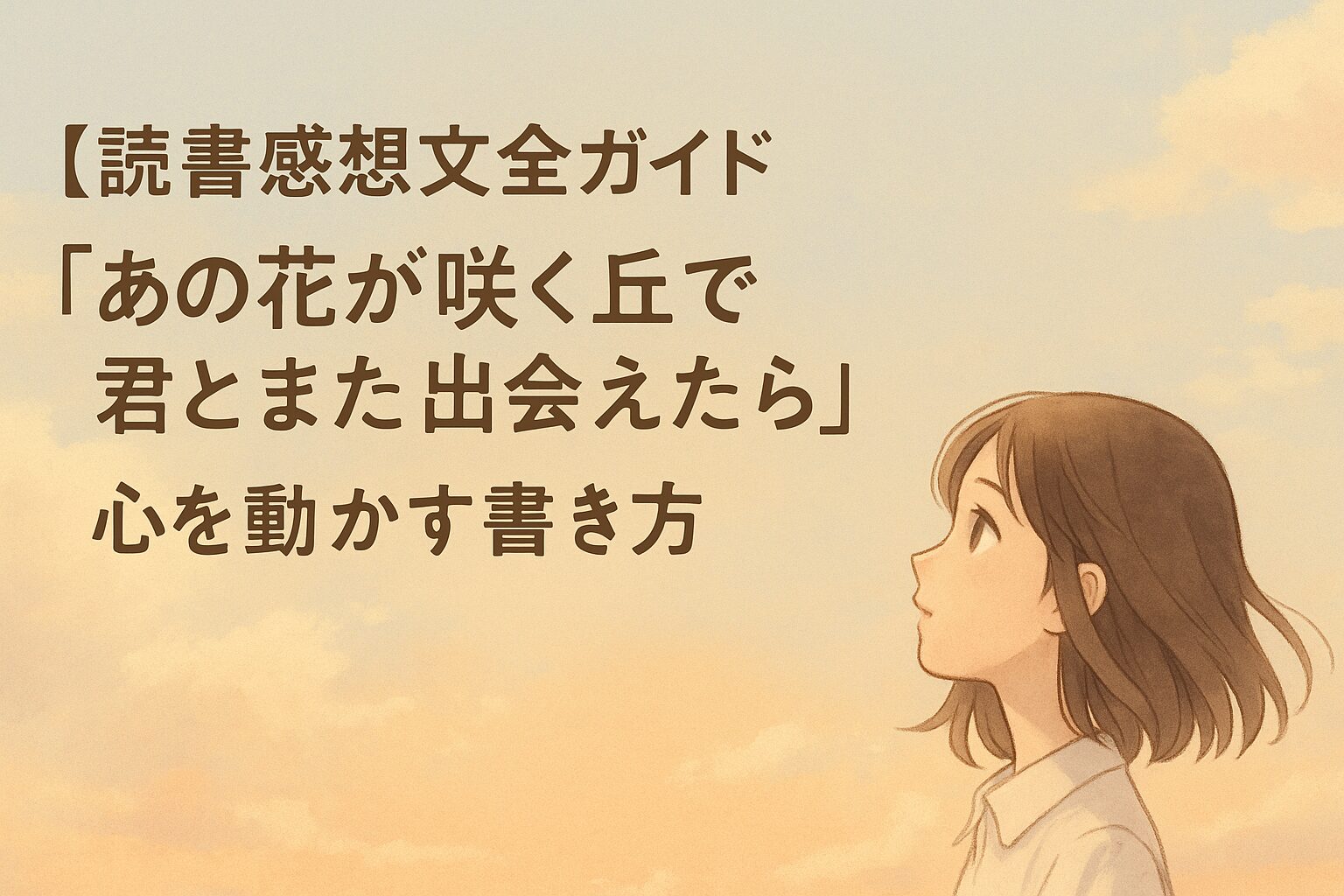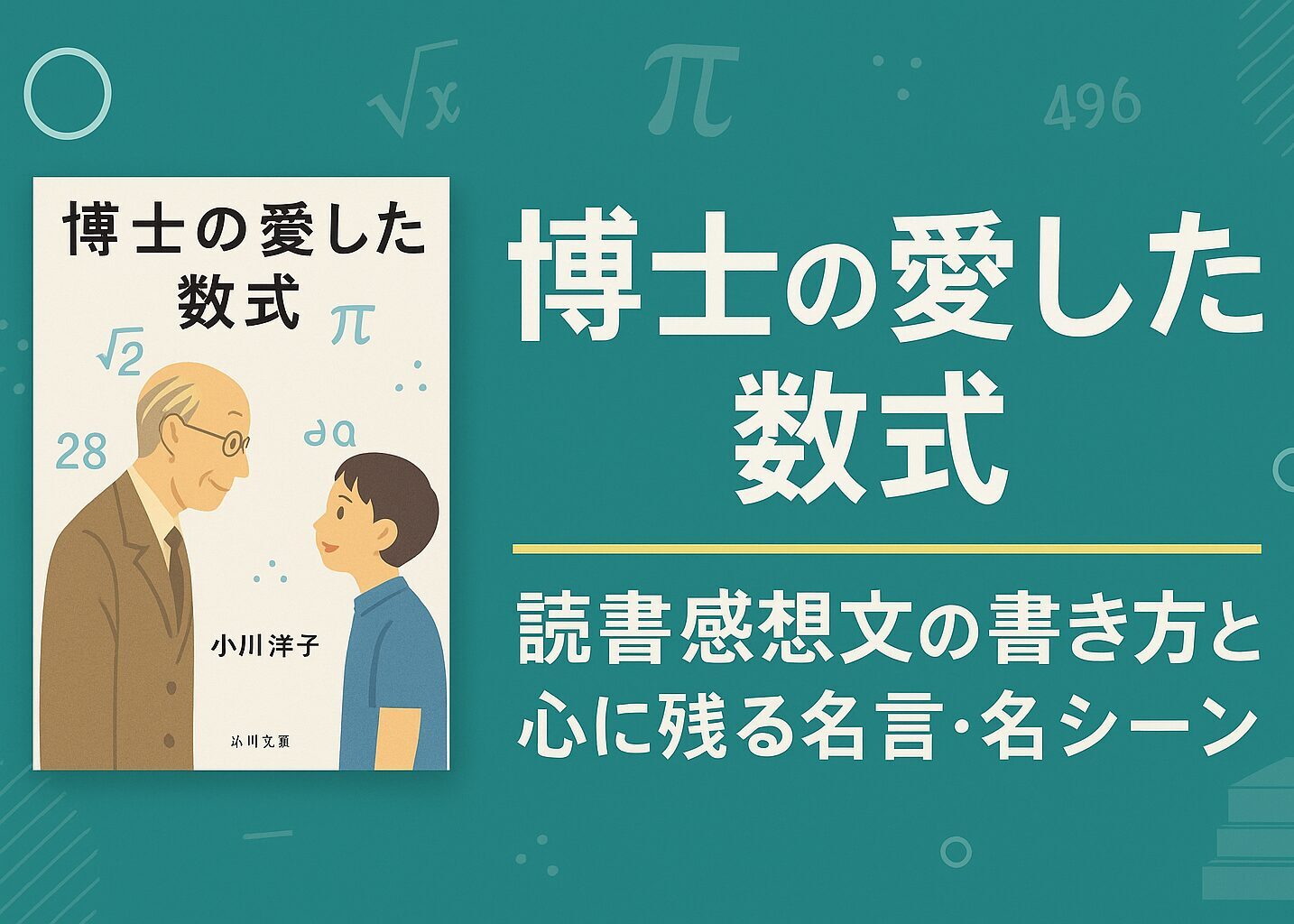「読書感想文の題名って、どうやって決めたらいいんだろう…」
そんなふうに悩んでいませんか?
実は、読書感想文の題名は「本文を書く前」にしっかり考えることで、感想文全体の完成度がぐんと上がります!
この記事では、小学生〜高校生まで使える題名の付け方をわかりやすく紹介しています。
迷ったときにすぐ使える題名アイデアや、NGパターンとその直し方、さらに読んだあとに「なるほど!」と思えるFAQまで盛り込んでいるので、ぜひ最後まで読んで、あなただけの素敵な題名を作ってくださいね!
スポンサーリンク
読書感想文の題名ってどう決める?基本を押さえよう
読書感想文に題名が必要な理由とは?
読書感想文を書くときに「題名って必要なの?」と疑問に思うかもしれません。でも、実は題名はとても大切な役割を持っています。
題名は、読者に「この感想文がどんな内容なのか」を伝える最初のサインです。まるでお店の看板のようなもの。看板が魅力的なら、中をのぞきたくなりますよね。
学校やコンクールでは、題名だけで第一印象が決まることもあります。実際に題名が魅力的な作品は、つい内容をじっくり読んでしまうことが多くある印象です。題名をしっかり考えることは、感想文をさらに魅力的にする第一歩なのです。
良い題名と悪い題名の違いって?
良い題名と悪い題名の違いは、とてもシンプルです。
- 良い題名:感情やテーマがわかりやすく伝わるもの
- 悪い題名:何について書いているか伝わらないもの
たとえば、「私の感想文」という題名では、内容が全く伝わりません。一方で、「友情に涙した『走れメロス』」のように、作品名と自分の感じたことが題名に入っていると、読む前からワクワクします。
題名は「どんな気持ちで読んだか」「何を伝えたいか」を短くまとめるのがコツです!
本のタイトルそのままはアリ?ナシ?
結論から言うと、「本のタイトルそのまま」はおすすめしません。
理由は簡単で、オリジナリティが感じられないからです。本のタイトルだけでは、あなた自身の感じたことや考えが見えません。
もちろん、どうしても思いつかないときは、本のタイトルに少し手を加えるだけでもOKです。たとえば、『二十四の瞳』を読んだ感想文なら、「小さな瞳に教えられた大切なこと」というように、自分の感じたテーマをプラスしてあげると、ぐっとオリジナリティを出す事が出来ます。
読書感想文のテーマを題名にするコツ
題名を決めるときは、まず自分の読書感想文の「テーマ」をはっきりさせましょう。テーマとは、「この本から何を感じたか」「何を伝えたいか」ということです。
たとえば、勇気をもらったなら「勇気をくれた一冊」、家族の大切さに気づいたなら「家族の絆を考えた日」というように、感じたテーマを一言にまとめると、そのまま題名にできます。テーマを明確にすると、読者も読みやすくなり、感想文の評価も高くなりやすいですよ!
読みたくなる題名にするための3つのポイント
読みたくなる題名にするためには、次の3つのポイントを意識しましょう。
- 感情を込める:「うれしい」「悲しい」などの感情を表現する
- キーワードを入れる:本の中で印象的だった言葉やテーマを入れる
- 読者を引きつける:問いかける形や意外性を持たせる
例えば、「なぜ僕は涙を流したのか?」のように、少し考えさせる題名にすると、自然と本文も読みたくなります。
【FAQ】読書感想文の題名ってどのくらいの長さがいい?
答え:短すぎず長すぎず、10〜20文字程度がおすすめ!
理由は、長すぎると読みにくくなり、短すぎると内容が伝わりにくいからです。だいたい1行に収まるくらいを目安にしましょう!
スポンサーリンク
すぐ使える!読書感想文の題名アイデア集【例文つき】
感動したときに使える題名例
読書して感動したときには、その感情を素直に題名に表すのがポイントです。たとえば、
- 「心が震えた最後のページ」
- 「涙と一緒に読んだ物語」
- 「一歩を踏み出す勇気」
など、感動の瞬間を題名にすることで、読む人にもその気持ちが伝わりやすくなります。
感動はとても個人的な体験なので、無理にかっこよくまとめようとせず、自分らしい言葉を選ぶと、ぐっと魅力的になります。
自分の成長を感じたときに使える題名例
本を読んで「自分ってちょっと成長できたな」と感じたときは、その成長を題名に表すと、とても深みのある読書感想文になります。たとえば、こんな感じです。
- 「弱虫だった僕が強くなった日」
- 「勇気を知った小さな冒険」
- 「一歩を踏み出す決心」
- 「小さな気づきがくれた大きな変化」
- 「心が大人になった瞬間」
本の中の登場人物や物語を通じて、自分自身がどう変わったかを考えると、オリジナルの題名が自然に浮かんできます。成長はとても個人的な体験なので、誰かのマネではなく、自分の言葉で表現することが大切です。
特に中学生や高校生になると、感想文では「自分自身の成長や考えの変化」をしっかりアピールすることが求められることが多いです。題名でその成長を匂わせることができれば、内容に深みを持たせることができますよ!
登場人物に共感したときに使える題名例
本を読んで「この登場人物に共感した!」という経験はありませんか? そんなときは、共感した気持ちを題名に込めると、読む人にも伝わりやすくなります。例えば、
- 「あのときの君に自分を重ねて」
- 「ぼくにもできると教えてくれた君」
- 「涙の理由がわかった日」
- 「夢に向かう背中を追いかけて」
- 「不器用だけどまっすぐな心」
登場人物のどの部分に共感したか、どんな場面で自分と重なったかを考えると、自然な題名が浮かびます。読書感想文では「このキャラクターが好き」というだけで終わらせず、自分と重ね合わせて書くと、評価も高くなりやすいですよ。
本を通して他人の気持ちを理解することは、まさに読書の醍醐味。題名にもその温かい視点を込めましょう。
問題提起型の題名例【考えさせたいとき】
ちょっと大人っぽい読書感想文を書きたいなら、「問題提起型」の題名がおすすめです。読者に「なんだろう?」と思わせることで、注目を集められます。例を紹介しますね。
- 「本当の正義とは何か」
- 「幸せってなんだろう」
- 「生きる意味を考えた夜」
- 「なぜ僕たちは争うのか」
- 「本当に大切なものを見つけるために」
こんなふうに、ちょっと深く考えさせる問いを題名にすると、高校生の読書感想文にもピッタリです。もちろん、小学生や中学生でも「なぜ」「どうして」という視点を入れれば、すごく深い作品になります。
問題提起型の題名を書くときは、答えを出すことよりも、「考え続けること」が大事だというスタンスで書くと自然になりますよ!
ひとひねりある面白い題名例
少しユニークで、人と違う題名にしたい人には、ひとひねりした題名がおすすめです。例えばこんな感じ。
- 「僕の心に住みついたネコ」
- 「勇者になれなかった僕の冒険」
- 「感想文じゃなく、手紙を書いてみた」
- 「物語の外に広がる世界」
- 「先生にはナイショだけど本音で書きます」
「え、どんな話?」と気になるようなタイトルをつけると、読む人の興味を引きます。少し遊び心を入れることで、読書感想文が一気に生き生きとしたものになりますよ。
もちろん、ふざけすぎないことが大事ですが、読書感想文は「真面目にだけ」じゃなく、「自分らしさ」を出す場所でもあります。楽しく工夫してみましょう!
【FAQ】本の内容と違う感想でもいい?
答え:もちろんOKです!
読書感想文は、「あなたがどう感じたか」が大事です。内容そのものよりも、自分の考えや感情をしっかり書けば問題ありません。ただし、あまりにも本の内容とズレすぎると読者に違和感を与えるので、ある程度は作品に寄り添った内容にしましょう。
スポンサーリンク
小学生・中学生・高校生別!読書感想文の題名のつけ方
小学生向け:わかりやすくて親しみやすい題名のコツ
小学生の読書感想文の題名は、とにかくわかりやすくすることが一番大切です。難しい言葉や漢字を無理に使おうとせず、自分の感じたことをそのまま素直に言葉にするのがポイントです。
例えば、
- 「うれしかったぼくの一日」
- 「友だちってすごい!」
- 「はじめてわかったやさしさ」
このように、短い言葉で感情をストレートに伝えると、読む人にもすぐに気持ちが伝わります。また、登場人物の名前を入れるのも効果的です。たとえば「けんたくんとぼくの冒険」など、親しみやすい雰囲気が出せます。
小学生の感想文は、先生や家族が読むことが多いので、できるだけ読み手を意識して、元気で明るい印象を与える題名を目指しましょう!
中学生向け:感情を表現する題名の工夫
中学生になると、少し大人っぽい題名が求められるようになります。感情を表現するのは大切ですが、ただ「楽しかった」「すごかった」だけでは物足りないことも。ここで一歩深く、自分の感じた感情を掘り下げる工夫をしましょう。
例えば、
- 「希望をくれた小さな手紙」
- 「心に残った、あの日の約束」
- 「未来へつながる一歩」
こんなふうに、具体的な場面やイメージを加えると、一気に深みが増します。また、比喩表現を使うのもおすすめです。「心に咲いた一輪の花」など、少し文学的な言葉を使うと、大人びた印象を持たせることができます。
中学生は、ちょうど思春期に入り、自分の内面と向き合う時期。感情を素直に、でも少し洗練された言葉で表現できると、素敵な題名になりますよ!
高校生向け:深みと視点を盛り込む題名の作り方
高校生になると、読書感想文もより考察力やオリジナリティが重視されます。題名も、単なる感想ではなく、自分なりの視点や問題意識を反映させることが大切です。
例えば、
- 「自由とは何かを問うた『夜間飛行』」
- 「孤独とともに歩む勇気」
- 「世界の片隅で見つけた希望」
このように、本のテーマに対する自分なりの考えや感じた問題意識を、短く鋭く表現するのがポイントです。単に「感動した」だけではなく、「なぜ感動したのか」「その感動が自分に何をもたらしたのか」まで題名に込めると、高い評価につながります。
また、題名の作り方一つで、本文全体の「説得力」も変わってきます。高校生は特に、題名=論点の提示と考えて作ると、ぐっとレベルの高い感想文になりますよ。
年代別おすすめワード集
ここで、小学生・中学生・高校生向けに、それぞれおすすめのワードを一覧で紹介します!
| 年代 | おすすめワード例 |
|---|---|
| 小学生 | うれしい、たのしい、びっくり、ぼく、わたし、なかよし |
| 中学生 | 希望、未来、友情、約束、涙、心の変化 |
| 高校生 | 問題提起、自由、孤独、社会、挑戦、葛藤、選択 |
年代ごとに使いやすい言葉を意識すると、自然と題名もその学年らしいものに仕上がります。
ワードを組み合わせて、自分だけの題名を作ってみましょう!
学年ごとの注意点と成功パターン
それぞれの学年ごとに、題名を考えるときの注意点と、うまくいきやすいパターンをまとめました。
小学生の注意点と成功パターン
- 難しい言葉を無理に使わない
- 感じたことを素直に表現する
- 「○○がすごかった!」など元気な題名が◎
中学生の注意点と成功パターン
- 感情だけでなく「なぜそう感じたか」も意識する
- 比喩やイメージを取り入れると大人っぽくなる
- 「希望」や「未来」など広がりを感じさせるワードを使う
高校生の注意点と成功パターン
- 問題意識を持った題名にする
- 本のテーマ+自分の考えを掛け合わせる
- 「問いかける題名」で読者の興味を引く
学年によって求められるレベルが違うので、自分の学年に合わせた題名づくりを意識してみてくださいね!
【FAQ】題名はカッコよくした方がいい?
答え:カッコよさよりも「伝わるか」が大事!
もちろん、かっこいい題名も素敵ですが、一番大切なのは「読者に内容や気持ちが伝わるかどうか」です。見た目だけを意識して意味がわからない題名にならないように注意しましょう!
スポンサーリンク
NG題名に要注意!よくある失敗例とその直し方
ありがちすぎる題名とは?
読書感想文でよく見かけるのが、「ありがちすぎる題名」です。たとえば、
- 「○○を読んで」
- 「感動しました」
- 「○○について思ったこと」
このような題名は、とても一般的でオリジナリティがありません。読む側としては、「またこのパターンか」と思ってしまい、印象に残りにくくなってしまいます。
ありがちすぎる題名にならないためには、自分の感想を一歩深く掘り下げてみることが大切です。「何に感動したのか」「どの場面が心に残ったのか」など、具体的な気持ちを題名に入れ込んでみましょう。
たとえば、「感動しました」だけではなく、「家族の絆に心がふるえた瞬間」というように、具体性を持たせると、グッと魅力的な題名になります。
長すぎる題名・短すぎる題名の問題点
題名が長すぎても、逆に短すぎても、読書感想文の魅力が伝わりにくくなります。
長すぎる題名の問題点
- 読みにくい
- 内容がぼやけてしまう
- 覚えにくい
例:「○○という本を読んで私はとても感動して、そこから自分の生き方について考え直すきっかけになった」
→ 長すぎて何が言いたいかわかりません!
短すぎる題名の問題点
- 何について書かれているか伝わらない
- 読者の興味を引けない
例:「感想文」
→ 内容が全くわかりません!
目安は10~20文字くらい。長すぎず、短すぎず、内容がコンパクトに伝わる長さを意識しましょう。
書いた内容とズレてしまう題名
これもよくある失敗の一つ。感想文を書き終わった後に、題名と内容がズレてしまっているケースです。たとえば、題名では「友情の大切さ」について書くと予告しているのに、本文では家族愛についてばかり語っている……なんてことも。
こうなると、読者は「え、題名と違うじゃん」と違和感を持ってしまい、評価が下がる原因になります。
なのでズレを防ぐには、感想文を書く前に
- 題名を先に決め、そのテーマに沿って書く
- 書き終わったら、題名と本文が一致しているか確認する
この2つを必ず行うようにしましょう。
かっこつけすぎて伝わらない題名
かっこいい言葉を並べたい気持ちはわかります。でも、難しい言葉をたくさん使ったり、外国語を無理に使ったりすると、かえって伝わらなくなります。
たとえば、
- 「エモーショナルな自我の覚醒」
- 「イデアとエゴの狭間で」
こんなタイトルだと、読む前から「難しそう」「何の話?」と思われてしまいます。読書感想文は、自己満足のためではなく、読む人に伝わることが一番大切です。
わかりやすく、素直な言葉で題名をつけることを心がけましょう!
直し方!プロっぽく題名をブラッシュアップする方法
もし「題名がイマイチかも…」と思ったら、次のステップで直してみましょう。
- テーマを明確にする
→ この感想文で一番伝えたいことは何か? - 具体的な言葉を選ぶ
→ 「感動」ではなく「家族に会いたくなった」など、具体的に! - 短くシンプルにまとめる
→ 長い文章ではなく、短い言葉でキュッと! - 声に出して読んでみる
→ 不自然なところがあればすぐに気づきます!
この方法を使えば、題名をプロっぽくブラッシュアップでき、読書感想文の完成度がぐっと上がりますよ。
【FAQ】題名と本文のズレを直すにはどうすればいい?
答え:本文を書き直すのではなく、題名を本文に合わせて調整するのが基本です!
感想文を書き終えたあとにズレに気づいたら、本文の主張に合わせて題名を微調整しましょう。題名の方が短く直せるので、効率的です!
スポンサーリンク
まとめ:読書感想文の題名をサクッと決めるために大事なこと
最初にテーマを決めるべし
読書感想文の題名をスムーズに決めるために、最初に「テーマ」をはっきりさせることがとても大事です。
テーマとは、「この本を通して自分が一番感じたこと」「読んだ後に心に残ったこと」です。
例えば、「友情の大切さ」「自分を信じる勇気」「家族との絆」など、自分の心に響いたことをテーマにしましょう。このテーマさえ決まれば、題名も自然とテーマに沿ったものが作りやすくなります。
最初にテーマを決めずに書き始めると、感想文の内容もぼんやりしてしまい、題名もなかなか決まりません。
まずは深呼吸して、「この本から何を一番伝えたいか?」を考えてみてくださいね。
題名は「読む人目線」で考えよう
題名を考えるときは、「読む人はどんな気持ちになるだろう?」と想像してみましょう。
たとえば、自分の気持ちだけを押し付けるのではなく、読む人が「読みたい!」と思えるような題名にすることがポイントです。
読み手の興味を引くためには、
- 驚き
- 感動
- 疑問
このどれかを題名に込めると効果的です。
例:「なぜ僕は立ち上がれたのか」
このように問いかける形にすると、読む人も自然と本文に興味を持ちやすくなります。
「自分が読み手だったらどんな題名に惹かれるか」を考えながら作ると、素敵な題名になりますよ!
迷ったら「キーワード」を盛り込もう
題名に迷ったときは、「キーワード」を入れるとまとめやすいです。
キーワードとは、その本や感想文の中で特に大事な単語のこと。
例えば、
- 本のテーマ(友情、自由、成長など)
- 登場人物の名前
- 印象に残った言葉
これらを題名に組み込むだけで、ぐっとわかりやすくなります。
例:「友情に勇気をもらった日」
→ 「友情」と「勇気」というキーワードをしっかり盛り込んでいますね。
キーワードを使うと、題名が内容としっかりリンクするので、読む人にも伝わりやすくなります!
シンプルにしてインパクトを出す方法
題名を考えるとき、つい色々詰め込みたくなりますが、シンプルが一番強いです。
シンプルにすると、逆にインパクトが出て、記憶にも残りやすくなります。
インパクトを出すためには、
- 強い言葉を使う(勇気、涙、絆など)
- 具体的な場面を想像させる
- 少し意外性を持たせる
この3つを意識しましょう。
たとえば、「涙の理由を探して」や「一歩を踏み出す勇気」などは、短いけれど印象に残る題名ですよね。
無理に長い題名にしようとせず、「短く、強く」を意識して作ると、説得力がぐんとアップします。
最後に声に出して読んでみるチェック法
題名が決まったら、最後に声に出して読んでみるのをおすすめします。
声に出すことで、
- 読みやすいか
- 変なリズムになっていないか
- 意味が自然に伝わるか
をチェックできます。
もし声に出して違和感を感じたら、言葉を少し変えたり、順番を入れ替えたりしてみましょう。
特にコンクールや学校提出用の場合、自然な日本語になっているかどうかはとても大事です。
「題名を声に出して確認する」という一手間をかけることで、完成度の高い読書感想文に仕上がります!
【FAQ】最後にチェックするコツは?
答え:声に出して読む+第三者に聞いてもらうのがおすすめ!
自分では完璧と思っても、他の人に聞いてもらうと気づくことがあります。家族や友だちに題名を聞かせて、「どんな内容だと思う?」と感想を聞くと、修正ポイントが見つかるかもしれません。
本記事のまとめ
この記事では、「読書感想文の題名をどう決めたらいいのか」という悩みに対して、小学生から高校生まで使える具体的なコツやアイデアを紹介しました。
読書感想文の題名は、ただの「タイトル」ではありません。読む人に「どんな感想文なのか」を伝える大切な入り口です。
テーマをはっきりさせ、読む人目線で考え、キーワードを取り入れ、シンプルかつインパクトのある言葉選びをすることで、誰でも素敵な題名をつけることができます。
この記事を参考にして、ぜひあなたも世界に一つだけの素敵な読書感想文の題名を作ってくださいね!