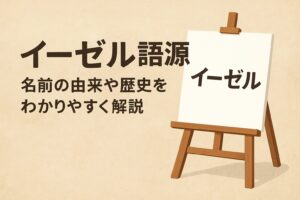干支飾りは、お正月の縁起物として飾られることが一般的ですが、具体的に「いつまで飾るべきか?」と迷う方も多いでしょう。
ここでは、干支飾りを飾る期間や片付けるタイミングについて詳しく解説します。
スポンサーリンク
干支飾りを飾る期間
干支飾りの飾る期間には特に厳密な決まりはありませんが、以下の時期が一般的です。
① 飾り始めの時期
- 12月中旬~大晦日
→ お正月飾りの一環として、12月の中旬頃から飾る方が多いです。 - 12月28日までがベスト
→ 29日は「二重苦(にじゅうく)」を連想させるため避ける風習があります。
→ 31日は「一夜飾り」となり、縁起が悪いとされるため、できれば避けた方がよいでしょう。
② 片付ける時期
- 松の内が終わる1月7日 or 1月15日
→ 一般的に、正月飾りは「松の内」の期間が終わると片付けます。
→ 地域によって異なり、関東は 1月7日、関西は 1月15日 まで飾ることが多いです。 - 節分(2月3日頃)まで飾る人も
→ 「年の厄を祓う」という意味で節分まで飾る家庭もあります。 - 旧正月(2月初旬~中旬)まで飾る場合も
→ 旧暦にこだわる家庭や地域では、旧正月まで飾ることもあります。
片付ける際のポイント
干支飾りを片付ける際には、以下の点に注意しましょう。
① 感謝の気持ちを込める
干支飾りは縁起物なので、処分する際には「一年の無事を守ってくれたこと」に感謝をしましょう。
② 処分方法
- 神社の「どんど焼き」で焼く
→ お正月飾りやしめ縄と一緒に、神社でお焚き上げしてもらうのが理想的です。 - 白い紙に包んで処分
→ 燃やせない場合は、白い紙に包み「ありがとう」と声をかけて処分しましょう。 - 来年も使うなら丁寧に保管
→ 陶器や木製の干支飾りなら、箱に入れて丁寧に保管し、翌年の年末にまた飾るのもOK。
まとめ
| 飾り始め | 片付け時期 | 注意点 |
|---|---|---|
| 12月中旬~28日までがベスト | 1月7日(関東) or 1月15日(関西) | 29日・31日は避ける |
| 節分(2月3日)まで飾る人も | どんど焼きで処分するのが理想 | |
| 旧正月(2月初旬~中旬)まで飾る場合も | 白い紙に包んで捨てるのもOK |
干支飾りを飾ることで、新年の福を呼び込み、一年の幸運を願いましょう!
地域別の干支飾りの飾る期間と風習
1. 関東地方
- 飾り始め:12月13日の「正月事始め」以降、またはクリスマス後の12月26日頃から飾ることが一般的です。
- 片付け時期:「松の内」が1月7日までとされており、1月7日を過ぎてから片付けるのが一般的です。
2. 関西地方
- 飾り始め:関東と同様に、12月13日以降、または12月26日頃から飾り始めます。
- 片付け時期:「松の内」が1月15日までとされており、1月15日を過ぎてから片付けるのが一般的です。
3. 沖縄県
- 飾り始め:沖縄では旧暦の行事が根付いており、旧正月に合わせて飾り始めることが多いです。
- 片付け時期:旧暦1月14日の「十四日正月(トゥカユッカー)」にお供え物を下げて飾りを片付ける風習があります。
4. 三重県伊勢地方
- 飾り始め:伊勢地方では、しめ縄を年中飾る風習があります。
- 片付け時期:特に片付ける時期を設けず、一年中しめ縄を飾り続けます。
このように、干支飾りの飾る期間や片付け時期は地域や風習によってさまざまです。お住まいの地域の伝統や習慣に合わせて、適切な時期に飾り、片付けることをおすすめします。
出典情報:
干支飾りの種類とその意味
1. 置物
干支の動物をかたどった置物は、家内安全や無病息災などの願いを込めて飾られます。素材やデザインは多岐にわたり、陶磁器や木製、金属製などがあります。玄関やリビングなど、人目につく場所に飾ることで、その年の福を招くとされています。
2. 根付(ねつけ)
根付は、江戸時代から伝わる小さな装飾品で、携帯品を帯に固定するための留め具として使われてきました。干支をモチーフにした根付は、厄除けや無病息災のお守りとして人気があり、携帯しやすいため、日常生活のアクセサリーとしても重宝されています。
3. 掛け軸や絵画
干支を描いた掛け軸や絵画は、室内の装飾としてだけでなく、縁起物としても用いられます。新年の初めに掛け替えることで、清新な気持ちで一年を始めることができます。
4. 張り子
紙を素材にした張り子の干支飾りは、素朴で温かみのある風合いが特徴です。地域ごとの伝統工芸としても親しまれ、魔除けや子供の健やかな成長を願って飾られます。
5. 土鈴(どれい)
陶器や土で作られた鈴で、干支の形をしたものが多く見られます。音色が邪気を払うとされ、縁起物として新年に飾られます。
干支飾りを選ぶ際は、そのデザインや素材だけでなく、込められた意味や願いにも注目すると良いでしょう。適切な場所に飾ることで、一年の幸運や繁栄を祈ることができます。
出典情報:
干支飾りを飾る際のポイントと注意点
1. 飾る場所の選定
- 家族が集まる場所に飾る:干支の置物は縁起物として扱われるため、基本的に家族が集まるリビングや玄関に飾るのが良いとされています。
- 床に直接置かない:縁起物を床に直接置くのは避け、棚や台の上など、目線より少し高い位置に飾ると良いでしょう。
2. 干支ごとの注意点
- 戌(いぬ)の置物:玄関に飾ると運気が安定しないとされているため、リビングなどの人が集まる場所に飾るのがおすすめです。
- 寅(とら)と龍(りゅう)の置物:玄関に飾る場合、寅は玄関を背にして左側に、龍は右側に配置し、それぞれの顔が適切な方向を向くようにすると良いとされています。
3. 置物の向きと配置
- 方角を意識する:干支にはそれぞれ相性の良い方角があります。例えば、辰(龍)は東、酉(鶏)は西が良いとされています。
- 清潔な場所に飾る:埃や汚れが溜まらないよう、定期的に掃除を行い、清潔な状態を保ちましょう。
干支飾りを適切に飾ることで、より良い運気を呼び込むとされています。各干支の特徴や意味を理解し、適切な場所や向きに配置することで、その効果を最大限に引き出しましょう。
出典情報:
干支飾りの処分方法
1. 神社やお寺でのお焚き上げ
一年間の感謝を込めて、神社やお寺でお焚き上げをしてもらう方法です。多くの神社やお寺では、古いお守りや縁起物を受け付けており、境内の「納札所」や「古札納所」に納めることで供養してもらえます。事前に受け入れ可能か、費用がかかるかを確認すると良いでしょう。
2. 自治体のゴミ収集での処分
お焚き上げが難しい場合、自治体のゴミ収集ルールに従って処分することも可能です。素材に応じて、可燃ゴミや不燃ゴミとして分別し、白い紙に包んで「ありがとうございました」と感謝の気持ちを込めて処分すると良いでしょう。
3. リサイクルショップやフリマアプリでの譲渡
状態の良い干支飾りは、リサイクルショップやフリマアプリ、ネットオークションでの売却や、地域の掲示板での譲渡を検討することもできます。特に希少価値の高いものや高価な素材で作られたものは、高値で取引される可能性があります。
干支飾りの来年への活用法
干支飾りは12年周期で同じ干支が巡ってくるため、丁寧に保管しておくことで再利用が可能です。陶器や木製のしっかりとした作りのものは、箱に入れて湿気や直射日光を避けて保管しましょう。また、毎年の干支飾りをコレクションとして飾ることで、インテリアとして楽しむこともできます。
干支飾りを適切に処分・活用することで、縁起物としての役割を全うさせ、次の年も良い運気を迎えることができます。感謝の気持ちを持って対応しましょう。
出典情報:
まとめ:干支飾りを正しく飾り、福を呼び込もう
干支飾りは、新年の福を呼び込み、良い運気をもたらす大切な縁起物です。正しいタイミングで飾り、適切な時期に片付けることで、その効果を最大限に活かすことができます。
本記事のポイント
- 干支飾りは12月中旬~28日までに飾るのがベスト
- 片付けは松の内(1月7日 or 15日)が一般的
- 関東と関西では松の内の期間が異なる
- 干支飾りにはさまざまな種類があり、置く場所にも意味がある
- 処分する際はお焚き上げや白い紙に包む方法が適切
- 再利用する場合は、翌年のインテリアや縁起物として活用するのも◎
干支飾りを正しく扱うことで、新しい年の運気が向上し、幸せな一年を迎えることができます。ぜひ、ご自宅に合った方法で飾り、片付けてみてください!